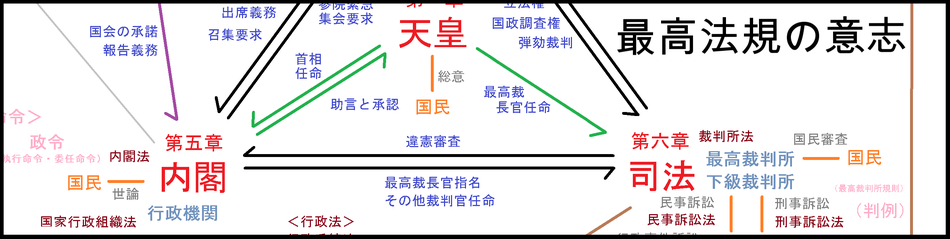同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 「同性婚」は法律用語ではない
〇 「同性婚」の多義性の混乱
〇 「婚姻の本質」の誤用
〇 「目的」の意味の混同
〇 主要な論点
福岡地裁判決の内容
判決の誤りを継承する解説
はじめに
「同性婚訴訟 福岡地裁判決」の内容を分析する。
判決
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日 (PDF)
【九州(福岡)】判決全文 PDF
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日
判決要旨
【九州(福岡)】判決要旨 PDF
【判決要旨全文】「同性カップルの結婚を認めないのは『個人の尊厳』に反する」。福岡地裁は「違憲状態」と判断、その内容は? 2023年06月08日
この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
「同性婚」は法律用語ではない
この判決では、「同性婚」という言葉が使われている。
しかし、これは法律用語ではないし、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。
もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるのであれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。
このような考えは妥当でないため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができることにはならない。
仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする理由を示すものではない。
そのため、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。
よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。
そこで、「婚姻」という概念に内在的に含まれている限界について下記で検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合をが発生する。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。
このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。
また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。
この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。
そのため、法律論として論じる際には、この点を考えないままに「~~婚」のように、あたかも「~~」の部分を「婚姻」とすることができるかのような前提を含む形で論じることは適切ではない。
この判決では「同性婚」という言葉を使っているが、「同性間の人的結合関係」についても、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
「同性婚」のように、あたかも「婚姻」として扱うことができるかのような誤解を生む表現を用いていることは妥当であるとはいえない。
「~~婚」という言葉は法律用語として通用するものではないことを押さえ、このような言葉のトリックに惑わされることがないように注意する必要がある。
「同性婚」の多義性の混乱
この判決は、「同性婚」という文言を用いているが、この言葉を多義的に用いており、意味が安定していない。
また、「同性間の婚姻」という言葉も用いているため、同一の意味を指しているのかも検討する必要がある。
ここで「同性婚」の意味をABCDの四つに分類する。
A 「同性間の人的結合関係」を指す場合
B 「婚姻類似の制度」を指す場合
C 「婚姻制度の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度」を指す場合
国(行政府)は訴訟の中で「同性婚」の文言の意味を「同性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより,本件規定が定める権利義務等の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度」を指すものとして使っている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお,「同性婚」という用語は,多義的な概念であるところ,被告は,従前,「同性婚」を「当事者双方の性別が同一である婚姻」と定義していたが(被告第1準備書面第2・11ページ),原告らの主張の趣旨に鑑み,以下においては,同性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより,本件規定が定める権利義務等の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度という意味で使用する。また,これに対する形で,「異性婚」という用語を,異性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより本件規定が定める権利義務等の法的効果を異性間の人的結合関係に及ぼす法制度という意味で使用する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 PDF
D 「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とすることを指す場合
〇 「同性婚」の意味の可能性
この判決で使われている「同性婚」の意味が、どれに当たるのかを検討する。
【 (2) 本件諸規定は憲法24条1項に違反するか 】の項目
「同性婚について議論が行われておらず、」
→ ABCDいずれの可能性もある。
「国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められない」
→ ABCDいずれの可能性もある。
「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかった」
→ BCDの可能性がある。
「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」
→ Aを禁止していないことは確かだが、BCDを禁止しているかは論点となる。
「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではない」
→ Aで読むことが自然だが、BCDについて述べているのかもしれない。
「同条項の拡張解釈ないし類推適用により同性婚を含むものと解されると主張する。」
→ Aで読むことが自然だが、文脈全体ではDを目指している意味と思われる。
「同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」
→ Aで読むことが自然であるが、文脈全体ではDを目指している意味と思われる。
「諸外国において同性婚を法制度化している国が」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「パートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動き」
→ 法的保護を与えるか否かの視点なので、Aで読むことが妥当と思われる。
「世論調査の結果等によれば、同性婚の導入に反対の意見を有する者が」
→ 何らかの制度の導入が論点なのでAではないが、BCDのどれかは分からない。
「同性婚に対する価値観の対立が存する」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難い」
→ ACDの可能性が考えられる。
「同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含むと解釈することは少なくとも現時点においては困難」
→ Aで読むことが自然であるが、BCを指しているのかもしれない。文全体ではDを目指しているようにも見える。
【 (5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか 】の項目
「平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚の可否に関する質疑が度々行われている」
→ BCDの可能性がある。
「同性婚に賛成する者の数は」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚の実現への支持」
→ BCDの可能性がある。
「同性婚に対する国民の理解も」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていない」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否か」
→ Aと思われる。
「国会で同性婚に関する質疑が行われ、」
→ BCDの可能性がある。
「同性婚に関する各種意識調査が」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「初めて同性婚に関する問題が」
→ ABCDのいずれの可能性もある。
「同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が」
→ 法的保護をするかが論点なので、Aと思われる。
「同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が」
→ 法的保護をするかが論点なので、Aと思われる。
このように、「同性婚」は法律用語ではないし、上記のような混乱を招くため、いずれの意味でもこの文言を用いるべきではないと考える。
〇 「同性間の婚姻」の意味の可能性
上記と関連するものとして、下記ではこの判決で使われている「同性間の婚姻」の文言について検討する。
【 (4) 本件諸規定は憲法14条1項に反するか 】の項目
「本件諸規定の下では同性間の婚姻は認められておらず、」
→ Dと思われる。
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが」
→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。
「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されない」
→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが」
→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。
【 (5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか 】の項目
「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が」
→ Dと思われる。
このように、「同性間の婚姻」の意味は安定していないし、上記の「同性婚」の文言とも合わせて、非常に混乱を招くものとなっている。
この問題が生じているのは、この判決を書いている裁判官自身も、自分の用いている言葉がどのような意味を有しているのか明確に思い描くことができていないことに原因があると思われる。
下記に記載したこの判決に対する【筆者】の解説では、この「同性婚」や「同性間の婚姻」の文言が使われている部分について、基本的にはDの「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とすることについて述べようとしているものと捉えた上で、それに対する解説を行うものとしている。
「婚姻の本質」の誤用
この判決は、最高裁判決(昭和62年9月2日・PDF)が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明したことを基に論じるものとなっている。
ただ、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。
◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
このように、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について、「婚姻の本質」と称する説明として示されているものである。
そのことから、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して導かれているものであり、「婚姻」という概念そのものから根拠もなく直ちに導き出されるという性質のものではない。
また、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するものではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。
そのことから、具体的な法制度として示されている婚姻制度の枠組みを離れて、「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かを基準とすることによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と、含めることができない人的結合関係とを区別することができるということにはならない。
そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできない。
当然、この「婚姻の本質」と称する説明を、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準として用いることができることにもならない。
この福岡地裁判決は、この「婚姻の本質」と称する説明を具体的な婚姻制度の枠組みに基づかずに根拠なく切り取り、婚姻制度を利用する者の権利・義務による法律関係の状態を示す意味から離れて、別の意味として用いているため、誤っている。
「目的」の意味の混同
「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。
① 「国の立法目的」の意味
概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。
例
・「会社法」の立法目的
・「宗教法人法」の立法目的
・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること
② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味
ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。
制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)
例
・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】
→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。
・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。
→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。
・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。
→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。
この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。
これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。
そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。
③ 「個々人の利用目的」の意味
個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。
例
・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。
・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。
・私は子供をつくることを目的として婚姻する。
下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。
この判決では、②の「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味や、③の「個々人の利用目的」の意味で用いられている「目的」の文言を拾って、これがあたかも①の「国の立法目的」の意味であるかのように「目的」の意味を変更した上で論じようとしている部分があり、誤っている。
主要な論点
主要な論点を下図にまとめた。
福岡地裁判決の内容
具体的に、判決の誤りを確認する。
〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。
〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「両性愛」「同性愛等」「異性愛者」「同性愛者」に色付けをした。
〇 「カップル信仰論」を前提とした「カップル」「異性カップル」「同性カップル」という言葉に色付けした。
〇 「同性間の婚姻」に色付けした。
〇 「同性婚」に色付けした。
〇 「社会通念」に色付けした。
〇 「社会的承認」に色付けした。
〇 「法的に家族として承認」と「法的に家族と承認」の「承認」に色付けした。
「同性カップルの承認及び保護」と「多様な生き方の承認」の二か所は、「承認」の文言があるが、意味を分類できないので色付けしていない。
〇 「不利益」に色付けした。
〇 「公証の利益」に色付けした。
〇 「人格的利益」に色付けした。
〇 「個人の尊厳」に色付けした。
〇 「婚姻及び家族」「婚姻及び家族に関する事項」「婚姻及び家族に関するその他の事項」「家族に関するその他の事項」を太字にした。
〇 主要な文に色付けしているところがある。
〇 リンクを加えた。
【筆者】
インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告1及び原告2に対し、各100万円及びこれに対する令和元年10月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告3、原告4、原告5及び原告6に対し、各100万円及びこれに対する令和3年3月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事案の概要
本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった原告らが、同性同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、同性同士の婚姻が認められない法的状態を生じさせており、憲法13条、14条1項及び24条に違反するにも関わらず、被告が必要な立法措置を怠ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、被告に対し、慰謝料100万円及びこれに対する各訴状送達の日(原告1及び2は令和元年10月9日、原告3ないし6は令和3年3月8日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 性的指向
性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいい、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。また、性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティを自分の感覚として持っているかを示す概念であり、身体の性と性自認が一致しない者をトランスジェンダーという。
【筆者】
法律論としては、このような内心に基づいた分類を用いてはならない。
詳しくは、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」の同様の項目で解説している。
(2)ア 原告1及び原告2は、いずれも男性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告1及び原告2は、平成30年6月、福岡市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲B1、2の1・2)。
原告1及び原告2は、令和元年7月5日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲B3)。
イ 原告3及び原告4は、いずれも男性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告3及び原告4は、令和2年3月、熊本市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲C1)。
原告3及び原告4は、令和2年3月4日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲C2)。
ウ 原告5及び原告6は、いずれも女性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告5及び原告6は、令和2年3月、福岡市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲D4)。
原告5及び原告6は、同年8月12日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲D5)。
【筆者】
上記は、「同性愛者」であることが何度も認定されているが、自己の思想、信条、信仰、感情を告白するものに過ぎず、このような事柄は法律論として区別して取扱うことのできる性質のものではない。
これは「同性愛者」に限られるものではなく、「異性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、それ以外の「性愛」を持つと称する者も同じである。
そもそも「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、考えたことない者もいるのであり、「性愛」の存否や傾向を述べること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものである。
それを公の機関が安易に受け入れて推進しようとしている状態となっているのであり、極めて不適切である。
(3) 法律の定め民法は婚姻届の受理要件として、婚姻成立の実質的要件(民法731条~736条)を満たしていること、民法739条2項やその他の法令の規定(戸籍法や戸籍法施行規則等)に違反していないことを定めており、民法及び戸籍法には、婚姻当事者が異性同士でなければならないという規定は明示的には存在しない。
他方で、民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるとし、戸籍法74条1号は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定していること等に照らし、現在の婚姻制度として、同性同士の婚姻の届出は、不適法とされる。(以下、同性同士の婚姻を不適法とする民法及び戸籍法の諸規定を総称して、「本件諸規定」という。)
2 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨
本件の争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙2のとおりである。なお、同別紙で定義した用語は、本文においても用いる。
(1) 本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反しているか。
(2) 本件諸規定を改廃しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。
(3) 原告らの損害の発生及び数額
(4) 原告6につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実等
当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見
ア 現在の性的指向に関する知見
性的指向の形成原因については不明確であるものの、精神衛生に関わる専門家の間では、ほとんどの場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないと考えられている。また、精神疾患と性的指向は無関係であり、自己の意思や精神医学的な療法によって性的指向が変わることはないとされている(甲A2、3、466の1・2、542、弁論の全趣旨)。
【筆者】
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。
「自己の意思や精神医学的な療法によって性的指向が変わることはないとされている」との部分であるが、「自己の意思」で「性的指向」を変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「変わることはない」と示すことは控えるべきものである。
たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「自己の意思」で変えたいと望む者が存在する。
それに対して、「変わることはない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。
もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。
しかし、この判決が人の内心そのものを「変わることはない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。
イ 同性愛に関する知見の変遷
(ア) 欧米には、キリスト教的価値観の下、同性愛的関係を否定する考え方があり、19世紀後半に自らを同性愛者と考える人々が現れるようになると、これを処罰する又は病気として医療の対象とするようになった。この頃、ドイツの精神科医らにより同性愛の病理化を提唱する文献が執筆された。(甲A358・78~84頁)
アメリカ精神医学会が公刊した精神疾患の診断マニュアル(Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders、以下「DSM」という。)のうち、1952年(昭和27年)に公刊したDSM-Ⅰでは、「同性愛」を「性的逸脱」の一つの診断名と位置づけ、「社会病質パーソナリティ障害」の大分類の下に分類した。1968年(昭和43年)に公刊したDSM-Ⅱでは、「パーソナリティ障害及びその他の非精神病性精神障害」という大分類の下に「性的逸脱」という小分類があり、その中に「同性愛」という項目が分類されている。世界保健機関(以下「WHO」という。)が1975年(昭和50年)に出した疾病分類(International Classification of Diseases、以下「ICD」という。)の第9版(ICD-9)では「性的逸脱及び障害」の項の1つに「同性愛」という分類名が挙げられていた。(甲A377)
(イ) 1970年代初頭から、同性愛の病理化に対する実証的研究による疑義及びこれを根拠とした同性愛者らの運動により、同性愛の脱病理化が進められた。アメリカ精神医学会は、1973年(昭和48年)、DSMの同性愛の項目を削除することを決定したものの、DSM-Ⅱでは新たに「性指向障害」という診断名が掲載され、1980年(昭和55年)に公刊したDSM-Ⅲにおいて、「性指向障害」を自我違和性(異質性)同性愛という限定的な概念に改め、1987年(昭和62年)に公刊したDSM-Ⅲ-Rにおいて、「自我違和性(異質性)同性愛」という名称も削除され、同性愛を「正常範囲内の差異」だとする見方をとるようになった。WHOは、1992年(平成4年)、ICD-10以降において、「同性愛」の分類名を削除し、自我違和的性指向という分類名が用いられ、「性指向自体は障害と考えられるべきではない」と明記された。
今日、同性愛それ自体は病気ではないという見方は、精神医学及び心理学の専門家の一般的見解である。
(以上につき、甲A359、377、379の1・2、382の1・2、383の1・2、384、385の1・2)
ウ 我が国における同性愛に関する知見
(ア) 明治時代以前
我が国においては、明治以前より、男色又は衆道と呼ばれる男性同士の性的な結びつきが行われ、江戸時代には少年による売春が広がり当時の幕府が男色を規制したが、欧米と異なり、男性間の性的接触そのものを違法なものとして取り締まることを目的とするものではなかった(甲A358・94~96頁)。
(イ) 明治初頭
明治政府は、明治維新後、文明開化を掲げ、社会の変革に取り組み、文明にふさわしい性の価値観が示された。この価値観はすぐに浸透したわけではなかったが、明治5年、日本では中世から鶏姦(男性同士の性行為を指す。)が行われてきたが、西洋においては鶏姦が不自然の罪と呼ばれていることからこれを禁止する鶏姦条例が制定され、翌年には法律で禁止された(明治15年に刑罰ではなく慣習によって処すべきといった意見から鶏姦を罪とする法律は廃止された。)。(甲A205・5頁、358・97~99頁)
明治24年、同性愛の病理化を提唱するドイツの精神学者の文献(前記イ(ア))の翻訳が『裁判医学会雑誌』に翻訳連載され始め、明治27年には、この連載をもとに『色情狂編』として翻訳本が出版された(甲A360、361)。また、明治39年、同性愛を精神病とした『新撰精神病學』が出版された(甲A362)。これらの文献では、同性愛が病理的な色情として紹介され、その治療法として、催眠術、臭素剤の投与、身体的労働、冷水浴及び境遇の変化等が挙げられた(甲A361、362)。
(ウ) 大正から平成まで
大正時代には、西洋の性科学が翻訳書を通して浸透するとともに、性欲学についての書籍が執筆されるようになった。大正2年、『色情狂編』は、『変態性欲心理』というタイトルで一般大衆向けに出版され、我が国でも大きな影響力を有するようになり、同性愛を変態性欲として精神病とみなす性雑誌が多く発刊された。(甲A205)
同性愛を変態性欲とする知見は我が国でも定着し、広辞苑は昭和44年出版の第2版から昭和58年出版の第3版まで同性愛を「同性を愛し、同性に性欲を感ずる異常性欲の一種」と記述した(甲A358・105頁、370の1)。
(エ) 平成以降
前記イ(イ)の欧米の脱病理化の動きを経て、厚生省(当時)は、平成7年、前記ア(イ)の性的指向単独では障害とはみなされないものとするWHOのICD-10を採用した。これを受けた日本精神神経学会も、同年、ICD-10を採用することを明らかにした。(甲A205・46頁、385の1・2)
【筆者】
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、ここで「(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見」と項目を立て、「ア 現在の性的指向に関する知見」、「イ 同性愛に関する知見の変遷」、「ウ 我が国における同性愛に関する知見」のように述べる必要そのものがないものである。
また、現在の婚姻制度についても、それは「異性愛」を保護することを目的とするものではないし、「異性愛者」を称する者を対象とするものでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
現在の婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象とするものとなっている場合には、それ自体で憲法違反となる。
よって、ここで「同性愛」の知見を述べたところで、婚姻制度に影響を及ぼすようなことはないし、影響を及ぼすようなことがあれば、その時点でその制度は憲法違反となることを押さえる必要がある。
(2) 婚姻制度の変遷と同性婚についての検討の有無
ア 婚姻制度は、男女の性的結合関係による種の保存を規範によって統制しようとするところに生まれ、それぞれの時代、社会には、それぞれの要請を実現するための婚姻制度があった。
【筆者】
「婚姻制度は、男女の性的結合関係による種の保存を規範によって統制しようとするところに生まれ、」との部分であるが、その通りである。
ただ、その「統制しようとするところに生まれ」るという背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。
もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制しようとする」ことも必要ないはずだからである。
よって、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。
「それぞれの時代、社会には、それぞれの要請を実現するための婚姻制度があった。」との部分であるが、おおよそその通りである。
「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で、夫婦の財産関係や相続関係を定めるなどしているが、そのあり方は「それぞれの時代、社会」によって方法が異なる場合がある。
欧米の婚姻制度の前提には聖書の婚姻観があり、10世紀以降教会が婚姻をサクラメントとして独占していたが、宗教改革と絶対王権の整備に伴い、国家が婚姻の成立を把握する民事婚思想が台頭し、以降民事婚が婚姻の方式の中核を占めるようになった。近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ、人間の社会的関係は、自由な意思主体者間の契約的関係となったことから、婚姻も当事者の合意という契約的成立要件が与えられる一方で、婚姻の内容はあらかじめ法によって定められるという制度としての婚姻は残存した。
(以上につき、乙2)
【筆者】
「近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ、人間の社会的関係は、自由な意思主体者間の契約的関係となったことから、」との部分から、この判決を考える際に必要となる論点を抜き出すことにする。
「すべての人は平等な資格が与えられ、」の部分であるが、これは日本法の中でも用いられている「権利能力」にあたるものである。
つまり、ここでいう「人」という個々の自然人が「権利能力」の主体となっているということである。
また、「自由な意思主体者間の契約的関係」の部分であるが、「自由な意思主体者間」とあるように、「意思主体者」となっているのは「権利能力」を有する個々の自然人である。
これに対して、この判決では、後程「カップル」という「二人一組」の人的結合関係を取り上げて、何らかの比較を試みようとする記述が見られる。
しかし、法律関係を形成する主体となるものは、「権利能力」を有する個々の自然人が単位となるのであり、「カップル」という「二人一組」を単位として論じようとしている部分は誤りである。
この判決の内容は、この判決がここで述べている「近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ」ており、「自由な意思主体者」によって法律関係が形成されるという前提となる認識を十分に持つことができていないのである。
イ 日本における婚姻制度とその要件
(ア) 民法制定以前
明治初年頃、婚姻の実質的要件は、慣習に委ねられ、統一的な実体法は存在しなかったところ、我が国最初の民法典として公布された明治23年法律第98号(旧民法)の人事編において初めて統一的な実質的要件が定められ、旧民法は施行に至らなかったものの、明治31年法律第9号の民法(以下「明治民法」という。)に受け継がれた。旧民法人事編の草案段階では、イタリア民法に倣い、「身体ノ不能力」を婚姻の目的である子孫を生殖する結果を得ないものとして婚姻の無効原因に加えようとする意見もあったが、結局そのような意見は採用に至らなかった。(甲A209、乙1)
【筆者】
「「身体ノ不能力」を婚姻の目的である子孫を生殖する結果を得ないものとして婚姻の無効原因に加えようとする意見もあったが、結局そのような意見は採用に至らなかった。」の部分について検討する。
ここでいう「婚姻の目的」の意味は、「③ 個々人の利用目的」にあたるものと捉えることが妥当と思われる。
これは、一旦、婚姻制度を利用する者は「子孫を生殖する結果」を求めているという仮定を置き、「身体ノ不能力」によってその「③ 個々人の利用目的」を達成できないことが分かった場合には「婚姻の無効原因」としてもよいのではないかとの議論である。
しかし、「結局そのような意見は採用に至らなかった。」との結論が導かれたことは、国は「③ 個々人の利用目的」には関与しないとのスタンスによるものと思われる。
また、これは個別の事例において「婚姻」を有効に成立させるか否かの論点であり、そもそも「婚姻」の枠組みが「① 国の立法目的」に従う形でどのような人的結合関係を対象としているかに関する論点を述べるものとは異なる。
そのため、「結局そのような意見は採用に至らなかった。」との結論が導かれたものと思われる。
また、当時の学説においては、婚姻の目的は心の和合や夫婦の共同生活であり、必ずしも子を得ることを目的としないという考えがあった(甲A211、213)。
【筆者】
ここには「心の和合」との記載がある。
これについて、国(行政府)は、それが記載された文献の記述は「婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているもの」であることを指摘している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,我が国の婚姻制度が伝統的に生殖と結びついて理解されてきたことは,被告第2準備書面第1の2(1)及び(2)(5ないし8ページ)において引用した文献の記載等からも明らかである。
イ この点,原告らは,「婚姻ハ兩心ノ和合ヲ以テ性質ト為スモノニシテ産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ條件ナレドモ,必要欠ク可ラサル條件三アラズ」と説明する文献(熊野敏三ほか「民法正義入事編巻之壹(上下)」193ページ・甲A第186号証)を引用し,「我が国の婚姻制度は,必ずしも生殖を目的どしない親密な人格的結合(『両心ノ和合』)に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきたものであり,現在においてもそのような前提に変更はないものと解するのが適切である」と主張する(原告ら第6準備書面 22,40ページ)。
しかし,上記文献は,上記の引用部分の前に「産子ノ能力ヲ有セサル男女ト雖モ婚姻ヲ為スヲ得ヘキカ」という問いが設けられているとおり(同号証192ページ),生殖能力が婚姻の必要条件か否かについて論じているのであって,我が国の婚姻制度が,伝統的に,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきた旨を述べるものではない。むしろ,「産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ侠件」と明記されているととからすれば,上記文献は,婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているものと解するのが自然であって,同文献は原告らの上記主張を補強するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P6)
恣意的な引用 Wikipedia
よって、具体的な婚姻制度の存在を前提として、その婚姻制度の効力が及ぶか否かを論じるものであり、この「心の和合」というものが「国の立法目的」となっているわけではないし、この「心の和合」というものによって、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
また、「心の和合」という精神的な事柄については、個々人が自由に人的結合関係を形成する中で価値観として営むことは可能であるし、「組合」「会社」「宗教団体」「政党」など、様々な人的結合関係についても「心の和合」を述べることが可能であり、このような事柄を基にして婚姻制度の枠組みを決めることができるとする理由とはならないことは明らかである。
「夫婦の共同生活であり、」との部分についても、「夫婦」とは適法な婚姻関係にある男女のことであるから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その枠組みを利用する者をいうものである。
そのため、その「婚姻制度を利用する者」の「共同生活」について述べているだけであり、そこに法的効果や一定の優遇措置が与えられることに関して述べるものということができる。
そのことから、この「共同生活」の部分だけに着目して、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
「必ずしも子を得ることを目的としない」との部分についても、これは婚姻制度を利用する者としての地位が適法に成立するか否かについて論じるものとして述べられているものであり、婚姻制度の枠組みが導かれる際の「国の立法目的」を示すものではない。
よって、このことを理由として婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
これらの点は、この判決がその後、特定の結論を導き出すために意図的に意味を読み替えて論じようとしていないか注意して読み解く必要がある。
(イ) 明治民法制定時
明治民法「第4編 親族」は、明治31年7月16日に施行された(甲A209)。
明治民法における婚姻は、我が国の従来の婚姻に関する慣習を前提としつつ、弊害や不明瞭な部分を法律によって補正することを目的とした(乙3)。明治政府は、婚姻制度の近代化のために妾制度や封建的身分制度を廃止したものの、国民の把握と統制の手段である戸籍制度を民法上の家族として構成し、婚姻に戸主や親の同意を必要とするなど家による統制を維持した(甲A214)。この際の婚姻は男女間のものであることが前提とされていた(乙4、5)。
当時の学説においても、婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、必ずしも子を得ることを目的としないという考えがあった(乙4)。また、律令制度以来の離婚法では「無子」が棄妻の一事由とされていたが、明治民法においては、生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった(甲A209、210、553)。
【筆者】
「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、」との部分について、「婚姻」や「夫婦」の文言があることから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その「婚姻制度を利用する者」の「共同生活」について述べるものである。
この「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、」の部分は、「必ずしも子を得ることを目的としない」との部分と繋がっており、これは婚姻制度を利用する者としての地位が適法に成立するか否かに関して述べているものである。
よって、ここでいう「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味である。
そのため、この「目的」の意味は、婚姻制度の枠組みが導かれる際の「① 国の立法目的」を示すものではないことから、この「共同生活」や「共同生活を目的とする」や「必ずしも子を得ることを目的としない」の部分だけに着目して、これがあたかも「① 国の立法目的」であるかのように考えることはできず、これを理由として婚姻制度の枠組みを変更することができるということにはならない。
その後の「明治民法においては、生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった」と述べている部分についても、婚姻制度の効力の問題を述べているものであり、「① 国の立法目的」を述べるものではない。
「目的」の意味を取り違えることがないように注意する必要がある。
(ウ) 日本国憲法(昭和22年5月3日施行)制定時
明治23年施行の大日本帝国憲法は、婚姻に関する規定を置いていなかったが、これを改正する形で制定された現行の憲法(日本国憲法)では、日本軍国主義の温床とみなされた「家」制度を解体して、家族関係に個人の尊厳(自由)と平等を確立するため、婚姻に関する憲法24条の規定が置かれた(甲A136)。
憲法24条の起草過程において、その原案を作成した連合軍総司令部(GHQ)民生部のベアテ・シロタ・ゴードンは、女性の地位向上と家族の保護のために詳細な条文を起草し、その草案には、「・・・婚姻と家庭とは、両性(原文ではboth sexes)が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配(原文ではmale domination)ではなく、両性の協力(原文ではcooperation)に基づくべきことを、ここに定める。・・」という文言があった(甲A135、136)。日本政府は、家族関係についての条項を憲法に規定することに消極的な姿勢を示し、一旦は婚姻に関する条項に限定しようとしたが、最終的に現在の憲法24条2項に当たる条項が復活された(甲A136)。その後の修正過程における日本側の「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」という文言を経て、最終的に大日本帝国憲法改正案22条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされ、帝国議会の議論を経て、現在の憲法24条として制定された。
当該改正の目的は、婚姻の自由と夫婦関係における平等の確保を目指したものとされ、その起草過程や帝国議会での審議において、同性婚について何らの議論がなされた形跡はない。
(以上につき、前掲証拠のほか、甲A137、214、乙21、弁論の全趣旨)
(エ) 昭和22年の民法改正時
日本国憲法の制定に伴い、明治民法は、昭和22年に全面的に改正された(昭和22年法律第222号)。当該改正の提案理由は、日本国憲法13条、14条及び24条の制定に対し、明治民法の特に親族編、相続編において、当該基本原則に抵触する幾多の規定があるので、これを改正する必要があることと説明され、上記基本原則に反する戸主制度等が撤廃された。同改正に係る国会審議において、同性婚について言及された形跡はない。(乙6、7)
また、当時の学説では、婚姻意思は、その社会の通念において婚姻とみられる生活共同体を形成しようとする意思という意味で、同性婚に向けられた意思は婚姻意思に当たらず、同性婚は無効であるという考えがあった(乙9、10)。
(3) 諸外国及び地域における同性婚等に関する状況
ア 同性間の人的結合関係に関する諸制度(甲A10)
(ア) 登録パートナーシップ制度
欧米でも、前記(1)のとおり、キリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていたが、知見の変化により制度にも変化が生じた。1989年(平成元年)、デンマークにおいて登録パートナーシップ制度が誕生し、同様に同性カップルを法的に保護するための法制度(国により名称や具体的な内容は異なるものの、以下総称して「登録パートナーシップ制度」と呼ぶことがある。)の整備がヨーロッパ諸国を中心に広がった。
登録パートナーシップ制度は、一般的に、婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与えるものであるが、あくまで婚姻とは別のものと整理され、異性カップルにも利用を認める国もあるものの、多くの国は同性カップルのみを対象としている。また、当該制度は独立した規定によるもの、婚姻の規定を準用するもの又はその中間に分類でき、独立した規定による制度は婚姻に比べると保護の範囲が限定されており、国によって、保護の範囲が異なっている。
(イ) 法定同棲・PACS等
婚姻や登録パートナーシップ制度では、財産法・身分法・社会保障法・税法等の広範囲にわたる法的な権利及び義務がパッケージとなっているが、このような強力な法的効果を望まないカップルについて、一定の同棲関係に対して、主に財産法上の法的効果を与える法定同棲(ベルギー、スウェーデン)、当事者の契約によって権利及び義務を設定し公的機関に登録することで、第三者や国に対してカップルであることを対抗することができるようになるPACS(フランス)等の法制度を用意する国もあり、これらの諸制度は、異性カップルか同性カップルかを問わず利用することができる。
(ウ) 同性婚
婚姻は、従来異性間においてなされるものであったが、2000年(平成12年)にオランダが同性間の婚姻を容認して以来、同性間の婚姻を容認する国は着実に増加している。ただし、国によっては同性婚カップルと異性婚カップルとで一部異なる法的取扱いを行っており、その主なものとして嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられる。
イ 同性間の人的結合、特に同性婚に関する各国・地域の対応
(ア) 次の各国・地域は、次に掲げる年(断りのない限り法律の制定年又は裁判所がこれを容認する判断をした年)に同性婚の制度を導入した。2022年(令和4年)10月時点における世界人口に占める同性婚を認める国の割合は約17%、世界GDPに占める同性婚を認める国の割合は約52%である。(甲A10~13、109、300、453~455、557~559)
2000年(平成12年) オランダ
2003年(平成15年) ベルギー
2005年(平成17年) スペイン及びカナダ
2006年(平成18年) 南アフリカ
2008年(平成20年) ノルウェー
2009年(平成21年) スウェーデン
2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド及びアルゼンチン
2012年(平成24年) デンマーク
2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル及び英国(イングランド及びウェールズ)
2014年(平成26年) ルクセンブルク
2015年(平成27年) 米国、アイルランド及びフィンランド
2016年(平成28年) コロンビア(ただし施行年)
2017年(平成29年) マルタ、ドイツ、オーストリア及びオーストラリア
2018年(平成30年) コスタリカ
2019年(令和1年) 英国(北アイルランド)及びエクアドル(ただし施行年)、台湾
2021年(令和3年) スイス及びチリ
2022年(令和4年) スロベニア及びキューバ
(イ) 以下の各国・地域の最高裁判所に当たる司法機関で、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判断等又は同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等が示された。
カナダ(平成16年)及びスペイン(平成24年)で、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判断等が示された(甲A11)。
南アフリカ(平成18年)、米国(平成27年)、コロンビア(平成28年)、オーストリア(平成29年)、台湾(平成29年)、コスタリカ(平成30年)及びスロベニア(令和4年)で、同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等が示された。(甲A11、12、14、16の1・2、327、558)
(ウ) 他方、ロシアでは、1993年(平成5年)の刑法典改正によって同性愛行為が処罰対象から外されたが、2013年(平成25年)、連邦レベルの規制として「伝統的な家族関係を否定する情報から未成年者を保護するために連邦法「健康及び発達に害を及ぼし得る情報から未成年者を保護する法律」第5条及びその他個別の連邦法を改正する法律」が成立し、未成年者に対する同性愛の宣伝行為が禁止された。憲法裁判所は、2014年(平成26年)、非伝統的な性的関係の宣伝行為の禁止は憲法に違反しないと判断した。
ベトナムでは、2014年(平成26年)に改正婚姻家族法が成立し、婚姻の禁止事項から同性婚が除かれる一方で、「国家は同性者同士の婚姻を認めない。」と明記した。
イタリアでは、憲法裁判所が、2010年(平成22年)に、同性婚を認めていない民法の規定は憲法に違反しないと判断する一方で、2014年(平成26年)、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国に存在しないことは違憲であると判断した。また、ヨーロッパ人権裁判所は、同性カップルの承認及び保護のための法的枠組みを提供しないことはヨーロッパ人権条約8条違反に当たると判断した。このような判断を受けて、2016年(平成28年)にイタリアにおける登録パートナーシップ制度が法制化された。当該制度の利用による法的権利義務は、基本的に婚姻に関する規定が準用されているが、貞操義務の有無や養子縁組に関する規定の有無といった違いもある。
韓国では、2016年(平成28年)、ソウル西部地方法院が、同性婚の可否について、一般国民の意見の収斂等を経て国会の立法的決断によって解決されるべきであって、司法による新しい解釈又は類推解釈を通じて解決できる問題ではないと判断した。
(以上につき、甲A10)
【筆者】
上記では、「同性間の人的結合関係」をその国の法制度によって位置付けているものが取り上げられている。
(それぞれの国は、それぞれの国の社会事情に応じて、そこで生じる問題を解決することを目的として法制度を定めているだけであるから、ここで日本法のいう『婚姻』という概念と完全な対応関係にあるわけではない。そのため、『婚姻』という言葉を使って同一の概念であるかのように扱うことには抵抗がある。)
しかし、外国では、「一夫多妻型」の制度を立法している場合もあるのであり、「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて論じようとすることは、特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなるため妥当ではない。
【参考】「一夫多妻制が認められているところが世界にはあるって言ったらどうなる」 Twitter
【参考】一夫多妻制 Wikipedia
ウ 国連等の動きについて(甲A467)
ヨーロッパ人権裁判所が、1981年(昭和56年)に北アイルランドのソドミー法(同性愛者の性行為を刑罰で禁止する法律)がヨーロッパ人権条約第8条の私生活の尊重を受ける権利に反すると判断した後、同裁判所でソドミー法が同条を侵害するという判例が確立された。国連自由権規約人権委員会は、1994年(平成6年)、ソドミー法の自由権規約適合性の判断において、自由権規約2条1項(差別なき権利の享有)及び26条(法の下の平等)の差別禁止分類としての「性(sex)」又は「その他の地位(other
status)」に性的指向の概念が含まれるとの解釈を示し、2003年(平成15年)や2007年(平成19年)には同性同士のパートナー関係に、少なくとも事実婚と同等の保障をしないことは、性的指向に基づく差別という解釈を示した。
このようなヨーロッパ人権条約の解釈、その後の国際人権の専門家による同性愛の権利内容の定式化や各国による同性愛を人権課題とする共同声明等の動きも受けて、国連人権理事会は、2011年(平成23年)、「人権、性的指向及び性自認」の決議を採択した(甲A392の1・2)。同決議は、世界のあらゆる地域での、性的指向及び性自認を理由とした暴力や差別に重大な懸念を表明し、人権高等弁務官に対し、差別的な法律や法の運用、性的指向や性自認を理由とする個人に対する暴力について、同年12月までに、全世界的な調査を行うことを要請し、その報告を受け討議するためのパネルを開催すること、この問題に引き続き取り組むことを謳っている。
(4) 我が国における同性愛者への対応等に関する状況
ア 政府・地方公共団体の対応
(ア) 政府の対応
平成12年、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が成立し、同法に基づく基本計画や啓発活動強調事項の中には、性的指向を理由とする偏見と差別を無くすことが掲げられた(甲A17、18)。それ以降、政府は、男女共同参画社会法に基づく基本計画(平成22年、27年、令和2年)、自殺対策基本法に基づく自殺総合対策大綱等(平成24年、29年、令和4年)、文部科学省発出の教育に係る通知(平成27年、28年)、男女雇用機会均等法に基づく指針(平成28年)、労働施策総合推進法に基づく告示(令和2年)等において、性的指向・性自認に関する理解とこれに基づく差別等の禁止を推奨してきた(甲A184、395、397、398、400、555、弁論の全趣旨)。また、政府は、平成23年、前記(3)ウの「人権、性的指向及び性自認」の決議に賛成している(甲A392の1・2)。
(イ) 地方自治体の対応
諸外国の動向を受けて、地方自治体の中で同性婚の容認を求める声が揚がり、平成27年の東京都渋谷区での導入を皮切りにパートナーシップ認定制度(以下、各種違いはあるものの、我が国の地方自治体が導入する同制度を総称して、「パートナーシップ制度」と呼ぶ。)の導入が広がった。同制度は、各地方自治体により目的、効果、形式等が異なるものであるが、人権や個人の尊厳の尊重、多様な生き方の承認及び安心して暮らせる社会やまちづくりを主な目的として、同性カップルを公的に認定するための制度であり、登録パートナーシップ制度とは異なり、法的効果を生じさせるものではない。地方自治体によっては、地方公共団体間での相互利用を可能とする例や同性パートナーの子を含めたファミリーシップ証明も可能とする例もあり、制度を利用することで市営住宅の申込み等一部の行政サービスの対象となるところもある。(甲A10、164、393、394、601、602、604)
令和4年11月1日時点で、パートナーシップ制度を導入した地方自治体の累計数は242、日本の総人口に対する導入自治体の人口カバー率は62.1%である(弁論の全趣旨)。
全国20の指定都市の市長による指定都市市長会は、平成30年、各公共団体のパートナーシップ制度の広がりの状況も踏まえて、国がパートナーシップ制度を含めた性的少数者への理解促進や自治体の取組を促進するような支援を行うことが必要といった内容の国への要請を採択した(甲A44、45)。
【筆者】
地方自治体のパートナーシップ制度について述べられている。
しかし、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などは、国会の制定する法律に違反してはならないため、民法に定められた婚姻制度に抵触するものとなっている場合には違法となる。
下記で条例制定権の限界に関する判例を読み取る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)
この判例によれば、下記の場合には、「地方公共団体」において「パートナーシップ制度」を導入していることは、違法となる。
◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」
◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合
そこで、民法上の婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると婚姻制度の立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)
〇 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること
(→ 達成手段:貞操義務と嫡出推定、再婚禁止期間によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢を設定)
「パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その者にも子に対する養育の責任を担わせることによって、「子の福祉」を実現しようとするものとなっていることから、父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、この目的を達成することを阻害することになるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
また、「パートナーシップ制度」の内容が「男女二人一組」の形であるとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、結局は制度の内容に従って適法な行動をしていたとしても、子の母親となる者は「パートナーシップ制度」を利用する相手方とは異なる他の男性との間で生殖を行っている可能性を排除することができないことから、父親を特定することができなくなるため、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その父親にも子に対する養育の責任を担わせることによって「子の福祉」を実現しようとするものであるから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を与えないことにより、「生殖」によって子供をつくる者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定できる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。しかし、国民が「パートナーシップ制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「パートナーシップ制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害することになる。よって、婚姻制度とは異なる選択肢として「パートナーシップ制度」を設け、婚姻制度と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
(ここで『婚姻制度とは異なる選択肢として』と記載している意味は、『企業間パートナーシップ』『商工業パートナーシップ』『貿易におけるパートナーシップ』など、婚姻とはまったく関わらない制度については、婚姻制度には抵触しないことを意味するものである。単に地方公共団体の政策担当者が『パートナーシップ制度』について『婚姻制度とは異なる制度である』と言い張るだけで、その『パートナーシップ制度』が民法の婚姻制度に違反しなくなって適法となるわけではなく、その『趣旨、目的、内容及び効果』が実質的に婚姻制度と競合したり、影響を与えることになるかどうかを判断することが必要である。)
婚姻制度には、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、それらの者との間で婚姻制度を利用できないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ぐ目的がある。この観点から、「女性同士の組み合わせ」に対して優遇措置を与えることは、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用を持つものとなるから、遺伝的な近親者の範囲を把握することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。そうなれば、婚姻制度が潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。よって、「パートナーシップ制度」の内容が、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)に対して婚姻制度と同様の、あるいは類似する優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「パートナーシップ制度」においても婚姻制度と同様の、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間の人的結合関係を結んで「パートナーシップ制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数の不均衡が生じることにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「パートナーシップ制度」の中には、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的としているものがあり、このような目的をもって制度を立法することは憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、ある特定の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」を制度の対象としていないことは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、そのような区別取扱いは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
加えて、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、24条の規定が骨抜きとなるからである。
よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、ここでいう「パートナーシップ制度」の内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
その他、「パートナーシップ制度」は「二人一組」を前提とするものとなっているが、婚姻制度のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象としてその目的の実現を目指すものとは異なるものであるから、そのような目的を有しない「二人一組」の間に何らかの制度を設けることは、「三人一組」や「四人一組」などの他の様々な人的結合関係との間で異なる取扱いをすることを正当化することのできる理由はないし、何らの制度も利用していない者との間でも合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになる。
そのため、「二人一組」の人的結合関係のみを「パートナーシップ制度」の対象としていることについても、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、このように「パートナーシップ制度」が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触するか否かの論点が存在するにもかかわらず、あたかも「パートナーシップ制度」が適法な制度であるかのような前提に基づいて論じていることは妥当でない。
「パートナーシップ制度」が法律に違反するか否かそのものが、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題に直接的に関わっているにもかかわらず、これを論じずに「パートナーシップ制度」が適法に成立することができることを前提に話を進めている点で、十分な検討を行っているとはいえない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
(ウ) 国会での議論
平成21年、衆議院法務委員会において、外国で同性婚を可能とする証明書を法務省が発行することについて質問が行われ(甲A55)、平成25年に同性パートナーの在留資格について質問が行われ(甲A56)、平成27年には、参議院本会議において同性婚と憲法の関係についての質問が行われた(甲A57)。このうち、平成27年の質問に対し、当時の内閣総理大臣は、憲法24条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていないこと、同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要すると答弁した(甲A57)。
野党は、令和元年6月3日、同性婚を可能とするために必要な法整備を行い婚姻の平等を実現するための民法の一部を改正する法律案を国会に提出したが、審議がされないまま令和3年10月14日、衆議院の解散により廃案となった。上記以降、国会の委員会又は本会議において、同性婚及び同性愛カップルの法的保護に関する質疑は行われているものの、これらに対する政府の答弁は概要上記のものから変わっていない(甲A58~63、69~71、83~88、110~112、267~291、405、424~426、636、637、639~653)。
イ 同性婚に関する意識調査
(ア) 平成27年
河口和也広島修道大学教授(以下「河口教授」という。)を研究代表者とするグループが、全国の20歳から79歳の男女に対して行った調査(有効回答者1259名)によれば、「同性どうしの結婚を法で認めること」について、賛成が14.8%、やや賛成が36.4%、やや反対が25.3%、反対が16.0%、無回答が7.5%であった。このうち、20~30代の72.3%、40~50代の55.1%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代は32.3%が賛成又はやや賛成と回答し、56.2%は反対又はやや反対と回答した。(甲A74・152、155頁)。
毎日新聞社が、有権者に対して行った世論調査(有効回答者1018名)では「同性婚」について「賛成」が44%、「反対」が39%、「無回答」が17%であった(甲A75)。
朝日新聞社が行った世論調査では、「男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだと思いますか」について、「認めるべきだ」が41%、「認めるべきではない」が37%であった(甲A266)。
(イ) 平成29年
NHKが、全国18歳以上の国民に対して行った世論調査(有効回答者2643名)では、「男性どうし、女性どうしが結婚することを認めるべきだ」について、「そう思う」が50.9%、「そうは思わない」が40.7%、「わからない、無回答」が8.4%であった(甲A76、77)。
朝日新聞社が、有権者に対して行った世論調査では、同性婚を法律で認めるべきが49%、認めるべきでないが39%であった。このうち、18~29歳、30代では「認めるべきだ」が7割を超えているのに対し、60代では「認めるべきだ」「認めるべきではない」がともに42%と拮抗、70歳以上では「認めるべきだ」が24%、「認めるべきではない」が63%となった。(甲A78、79)
(ウ) 平成30年
国立社会保障・人口問題研究所が、全国の配偶者のいる女性に対して行った全国家庭動向調査(有効回答者6142名)によれば、「男性どうしや、女性どうしの結婚(同性婚)を法律で認めるべきだ」について「まったく賛成」が20.3%、「どちらかといえば賛成」が49.2%、「どちらかといえば反対」が22.2%、「まったく反対」が8.3%であった(甲A104・72頁)。
(エ) 令和元年
河口教授を研究代表者とするグループが、全国の20歳から79歳の男女に対して行った調査(有効回答者2632名)によれば、「同性どうしの結婚を法で認めること」について((ア)と同様の質問)、賛成が25.8%、やや賛成が39.0%、やや反対が19.4%、反対が10.6%、無回答が5.2%であった。このうち、20~30代の81%、40~50代の74%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代は47.2%が賛成又はやや賛成と回答し、43.4%は反対又はやや反対と回答した。(甲A170)
日高庸晴宝塚大学看護学部教授が、性的少数者に対して行ったオンライン調査(有効回答者1万769名)によれば、対象者全体の60.4%が異性婚と同じ法律婚の同性間への適用を望んでいると回答した(甲A172)。
「働き方と暮らしの多様性と共生」研究チームが、18~59歳の大阪市民に対して行ったアンケート(有効回答者4285名)によれば、「同性カップルが法的に結婚できる制度」に「賛成」が51.5%、「やや賛成」が31.3%、「やや反対」が8.9%、「反対」が6.8%であった(甲A105・54頁)。
(オ) 令和2年
朝日新聞社が、全国の有権者に対して行った調査(有効回答者2053名)によれば、同性婚について、「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」が46%、「どちらとも言えない」が31%、「反対」又は「どちらかと言えば反対」が23%であり、平成17年の有権者を対象として行った調査と比較すると賛成意見が14%増加した。このうち、与党である自由民主党支持層でも「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」が41%、「反対」又は「どちらかと言えば反対」が29%であった。(甲A171)
(カ) 令和3年
朝日新聞社が、全国の有権者に対して行った世論調査(有効回答者1564名)では、「男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだと思いますか」について((ア)と同様の質問)、「認めるべきだ」が65%、「認めるべきでない」が22%であった。このうち、18~29歳、30代では「認めるべきだ」が8割を超え、60代では「認めるべきだ」が66%、70歳以上では「認めるべきだ」が37%、「認めるべきではない」が41%となった。(甲A266、409)
NHKが、全国18歳以上の者に対して行った世論調査(有効回答者1508名)では、男性同士、女性同士の結婚も認めるべきだという意見について、「賛成」が27.9%、「どちらかといえば、賛成」が28.8%、「どちらかといえば、反対」が18.6%、「反対」が18%であった(甲A624の1・2)。
(キ) 令和4年
毎日新聞社が、全国の有権者に対して行った世論調査(有効回答者1315名)では、同性婚を法的に認めるべきかどうかについて、「認めるべきだ」が46%、「どちらともいえない」が37%、「認める必要はない」が16%であった(甲A625の1・2)。
ウ 性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律
性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号、平成16年7月16日施行)3条1項は,性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として、「現に婚姻をしていないこと(同項2号)を定めているところ、最高裁判所は、同規定について、現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項、24条に反するものとはいえないと判断した(同裁判所令和元年(ク)第791号同2年3月11日第二小法廷決定)。
【筆者】
この段落と関連する内容について、当サイト「性別と思想」で解説している。
国(行政府)の主張でも少し記載がある。
【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P7)
エ 婚姻に関する意識調査
(ア) 内閣府の平成17年版国民生活白書によれば、18~40歳の未婚者に対しての「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちどちらですか」という質問に対し、「いずれ結婚するつもり」と回答した割合は、昭和57年から平成14年までの毎年全ての調査で9割を超えており、同年の調査では、「結婚している友人は幸せそうだと思うか」という質問に対し、「当てはまる」と回答した割合はいずれの世代でも5割を超えていた(甲A301・16頁)。
(イ) 厚生労働省の平成25年版厚生労働白書によれば、世論調査において、「人は結婚するのが当たり前だ」と回答した割合は平成20年時点で約35%であり、平成3年と比較すると約10%低下しており、「必ずしも結婚する必要はない」という考え方への賛成が増加する一方で、未婚者に対しての生涯の結婚意思の質問に対し、「いずれ結婚するつもり」と回答した割合は、昭和57年から平成22年までの毎年全ての調査で90%を超えていた(甲A303・59、66頁)。
(ウ) 内閣府の平成26年度結婚・家族形成に関する意識調査によれば、20歳~39歳の未婚・既婚の男女に対しての「あなたは結婚についてどのようにお考えですか」という質問について、「必ずした方が良い」が14%、「できればした方が良い」が54.1%、「無理してしなくても良い」が29.3%、「しなくて良い」が1.7%、「無回答」が0.9%であった(甲A304・35頁)。
このうち、結婚を希望する未婚の者に対する「結婚したい理由」は、「家族を持ちたい」、「子供が欲しい」がいずれも70.0%、「好きな人と一緒にいたい」が68.9%、「老後に一人でいたくない」が49.3%、「両親や親戚を安心させたい」が49%であった(甲A304・43頁)。
(エ) 国立社会保障・人口問題研究所の平成27年社会保障・人口問題基本調査(結婚と出産に関する全国調査)によれば、18~34歳の未婚者に対しての、「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちどちらですか」について、「いずれ結婚するつもり」が男性85.7%、女性89.3%であった。また、「結婚に利点がある」と回答したものは、男性が64.3%、女性が77.8%であり、具体的な利点としては「自分の子どもや家族をもてる」と回答した者が男性35.8%、女性49.8%で最も多かった(甲A305)。
オ 令和元年の婚姻に関する統計
政府の調査、国立社会保障・人口問題研究所の資料等によれば、令和元年の我が国の婚姻に関する状況として、以下の事実が認められる。
(ア) 婚姻件数は59万9007組、婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は4.8%であり、婚姻件数100万組以上、婚姻率10%以上であった昭和47年をピークに減少傾向にある(甲A306、309の4)。
(イ) 合計特殊出生率(15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は、1.36%となり、昭和48年の2.14%から低下傾向にある(甲A308)。
全世帯のうち、児童のいる世帯が占める割合は21.7%であり、昭和61年の46.2%から年々減少している(甲A307・7頁)。
また、嫡出でない子の出生割合は約2.3%である(甲A309の3)。
【筆者】
日本国の「嫡出でない子の出生割合」は他国とは大きく異なっており、婚姻制度の内容や機能が他国とは異なることは明らかである。
【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05
【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年
外国の法制度と比較する際には、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という同一の言葉を充てて説明しているからといって、それぞれの国の間でまったく同一の制度を指していることにはならないことに注意する必要がある。
カ 各国、各団体の動向等
(ア) 国連自由権規約委員会又は社会権規約委員会は、平成20年10月、平成25年5月、平成26年8月及び令和4年11月、日本に対して発出した総括所見等において、同性カップルの人権状況について懸念を示し、同性カップルの権利保障について具体的施策を求める趣旨の勧告を行った。うち、令和4年11月に国連自由権規約委員会が発出した総括所見では、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル及びトランスジェンダーの人々が、特に公営住宅、戸籍の性別変更、法律的な結婚へのアクセス及び矯正施設での処遇において、差別的な扱いに直面していることを示す報告に懸念を抱いている(自由権規約第2条及び26条)と述べ、締結国が行うべきことの1つとして同性カップルが公営住宅へのアクセスや同性婚を含め、規約に規定された全ての権利を締約国の領域の全てで享受できるようにすると述べている(甲A80の1~82の2、560の1・2)。
(イ) 在日アメリカ商工会議所は、2018年(平成30年)9月、日本政府に対し、同性カップルにも婚姻の権利を認めるように提言し、同意見書について、令和4年11月までに、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商工会議所、在日カナダ商工会議所、在日デンマーク商工会議所、在日アイルランド商工会議所、在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所、欧州ビジネス協会及び多数の日本企業、法律事務所等が賛同している(甲A53、54、614)。
(ウ) 日本弁護士連合会は、令和元年、国は同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきであるとの内容の意見書を取りまとめ、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び法務大臣に提出した(甲A48、49)。各地の弁護士会連合会、弁護士会でも令和4年11月までに5弁護士会連合会、15弁護士会等から同性婚の実現を要請する意見書、会長声明、宣言等が発出されている(甲A46、47、103、226~232、292~296、450~452、541、621、622)。
2 争点(1)(本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反しているか。)について
(1) 婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ(最高裁判所昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)、婚姻は、①両当事者が上記意思を持って共同生活を開始することを、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)、②民法は、親族関係(725条)、共同親権(818条)、配偶者の遺留分を含む相続権(890条、900条1号ないし3号及び1042条)、離婚時の財産分与(768条)、配偶者居住権(1028条)のほか、夫婦同氏の原則(750条)、夫婦の同居、協力及び扶助の義務(752条)、夫婦間の契約の取消権(754条)、夫婦の財産関係(755条)、夫婦財産契約の対抗要件(756条)、婚姻費用の分担(760条)、日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)、夫婦間における財産の帰属(762条)等の夫婦間の権利義務を発生させる。また、婚姻により、③戸籍制度による家族関係の公的認証(戸籍法6条)が与えられるとともに、これを基礎として、④所得税・住民税の配偶者控除(所得税法2条、83条、83条の2、地方税法34条)、相続税の軽減(相続税法19条の2)、配偶者としての在留資格の付与(出入国管理及び難民認定法2条の2)、遺族年金の付与(国民年金法37条、厚生年金保険法59条)、犯罪被害者給付制度における遺族給付金の支給(犯罪被害者等の給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号)等の利益、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護、裁判における証言拒否特権(民事訴訟法196条、刑事訴訟法147条)等の各種権利が与えられる。
【筆者】
「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」との記載があるが、文言上の誤りと、法的な意味における用い方の誤りがある。
■ 文言上の誤り
この「婚姻の本質」と称する説明は、下記の最高裁判決を参考としているものであるが、最高裁判決をそのまま抜き出したものとはなっていないことに注意が必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず、最高裁判決においては明確に「両性」と書かれているが、この福岡地裁判決では「両当事者」に変えられている。
この福岡地裁判決が最高裁判決に示された文面を正確に引用していない背景には、この裁判官が「婚姻」の内容について「両性」という「男女」を意味する言葉を用いてその範囲が確定されている事実を意図的に排除することによって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであることを原因とした「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を考慮することなく、それを超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めるという特定の結論を導き出すために、恣意的に文言を変更している可能性が考えられる。
これは、そのような意図に基づいて最高裁判決に示された「両性」の文言を「当事者」という文言に変更しているのであれば、「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を何ら考慮することなく恣意的な形で結論を導き出そうとする不正であるし、最高裁判決で用いられた文面の意味を改竄するものということができ、解釈の過程を誤った違法なものというべきである。
法解釈は、論理的整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となるのであり、解釈の過程で根拠となっている判例の文章の意味を読み替えたり、文言を勝手に変更したり、文章の内容を改竄することは、不正であり、違法な手続きということができる。
このような解釈の過程に不正、違法が含まれている場合には、根拠となっているもともとの条文や判例との間で完全に断絶するものとなるのであり、その結論は正当化することはできないことになる。
よって、この判決が「婚姻の本質」と称している説明を根拠として、何らかの解釈を行おうとしても、もともとの「婚姻の本質」と称している説明そのものが、具体的な条文やそれを基にして示された最高裁判決の文面の意味や内容から切り離された不当な内容であることになるから、それを根拠とした解釈や判断の枠組みについても、正当化することができないことになる。
下記の記事でも、最高裁判決では「両性」と示されていることや、「夫婦」の文言を前提としているものであることが説明されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もっとも昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」としているが、この定義に続いて「夫婦」の言葉も見え、最高裁は、男女のカップルの共同生活を「婚姻」としているように読める〔最高裁判所大法廷 昭和61年(オ)260号 判決〕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
国(行政府)の主張においても「両性」と示されていることが述べられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、控訴人らは、前記④のとおり、有責配偶者からの離婚請求の可否が争点となった事案において、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423ページ)が、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」と判示している点をとらえて、「カップル間の自然生殖可能性の有無は問題とされていない」旨主張するところ、同判決は、「両性」すなわち「一人の男性と一人の女性」を前提として判示しているものであることからすれば、控訴人らの主張のようには解されないところである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P27)
最高裁判決には、明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものである。
■ 法的な意味における用い方の誤り
次に、この最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している根拠を検討する。
なぜならば、もし最高裁判所の裁判官が何らの根拠もなく独断で決めているとすれば、その時々の気分によって「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、法の支配、法治主義を逸脱することになって妥当でないからである。
・ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
・ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
・ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
憲法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
・ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について示されているものである。
立法目的:国の立法目的
↓
達成手段:婚姻制度の枠組み
↓
法律関係:「婚姻の本質」と称する説明
この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を説明したものとは異なる。
よって、「婚姻の本質」と称する説明が、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するわけではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。
そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできず、同性間の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準とすることができる性質のものではない。
また、この最高裁判決の「婚姻の本質」と称する説明では「真摯な意思をもって」との記述がある。
これは、法律上において具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で法的拘束力を発生させることが妥当であるかどうかという問題において、「婚姻意思」を満たすものとして有効性を保つべきであるか否かに関係して論じられているものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「婚姻意思」に関する別の判例も見る必要がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
婚姻無効確認本訴並びに反訴請求 最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月31日 (PDF)
このように、この最高裁判決で「婚姻の本質」として説明されている内容は、法律上の具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度の法的な効果を発生させることが妥当であるか否かの「婚姻意思」の存否に関係する場面で論じられている説明である。
そのため、ここで「婚姻の本質」として説明されている「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」という説明についても、具体的な法制度が存在することを前提として、その制度の要件に従う形で制度を利用する者について、その制度による法的な効果を及ぼすべきであるか否かが論点となって説明されているものである。
このような具体的な婚姻制度の適用の当否を論じる意味を超えて、その法律関係の意味を離れて「永続的な精神的及び肉体的結合」や「真摯な意思」、「共同生活を営む」という文字を見て、その日本語としての語感を文学的な意味で捉えて、「それが婚姻である」「婚姻の本質である」などと考えることは誤りである。
◇ 法学的な意味
・「両性」 ⇒ 「男性」と「女性」の要件を満たすこと。
・「永続的な」 ⇒ 有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができること。
・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 「相互の協力」が求められること
・「肉体的結合を目的として」 ⇒ 「貞操義務」があること。
・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 「婚姻意思」があること。
・「共同生活を営む」 ⇒ 「同居義務」を定めていること。
◇ 文学的な語感で考える誤り
・「両性」 ⇒ 「両当事者」でもいいよね?(誤り)
・「永続的な」 ⇒ 「永遠」って何かロマンチックね!(誤り)
・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 愛し合うことだよね!ロマンチック・ラブだ!(誤り)
・「肉体的結合を目的として」 ⇒ セックスのことだよね!(誤り)
・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 真剣に考えてます!(誤り)
・「共同生活を営む」 ⇒ いつも一緒に居ようね!(誤り)
もう一つ、この「婚姻の本質」について説明している最高裁判決では「裁判官佐藤哲郎の意見」の中で「離婚の本質」についても取り上げていることを見逃してはならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 民法七七〇条一項五号は、同条の規定の文言及び体裁、我が国の離婚制度、離婚の本質などに照らすと、同号所定の事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者からされた離婚請求を原則として許さないことを規定するものと解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この「離婚の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度があることを前提として、「離婚」という法律行為をしようとする者に対して法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合を区別する際の意味合いで用いられているものである。
同様に、「婚姻の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度の存在を前提として、その法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合について論じる中で説明された文面であり、このような法律関係の意味を離れて、文学的な語感に基づいて説明を試みることは誤りである。
その他、この判決は、2(4)イの第三段落の第二文で「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので前記精神的及び肉体的結合の対象を定めるものである」と述べていることから、「精神的及び肉体的結合」の部分が「恋愛・性愛」に対応するものと考えているように見受けられる。
しかし、そもそも国が法制度として「恋愛・性愛」を保護する必要そのものがないのであり、婚姻制度の立法目的として「恋愛・性愛」を保護することが含まれているかのように考えている点で誤りである。
また、もし「恋愛・性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在する場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなるから、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、国が保護する「恋愛・性愛」と、保護しない「恋愛・性愛」、あるいは、「恋愛・性愛」以外の思想、信条、信仰、感情の間で差異を設けることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「恋愛・性愛」を保護することを立法目的としているかのように考えて、「婚姻」という制度と「恋愛・性愛」を結び付けて考えている部分が誤っている。
婚姻制度と「恋愛・性愛」を結び付けて考えていることは、この判決を書いた裁判官の抱く婚姻制度を利用する場合における個人的な理想像や結婚観について述べているだけであり、法制度上の婚姻制度そのものを論じるものではない。
そのため、婚姻制度と「恋愛・性愛」を結び付けて論じるものは、法解釈を行ったものとはいえない。
「婚姻は、①両当事者が上記意思を持って共同生活を開始することを、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)」との記載がある。
まず、ここでいう「上記意思」とは何を指しているかが問題となる。
「上記」とは、「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」と記載されている文を指していると思われる。
しかし、その「上記意思」とは、「両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」という部分のすべてを指しているのだろうか。
そのように考えた場合には、この文は「両当事者が(両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む)意思を持って共同生活を開始すること」と述べていることになる。
これは、「真摯な意思をもって」と「意思を持って」が二回重なるため、適切ではない。
また、「共同生活を営む」と「共同生活を開始する」が二回重なるため、不自然である。
よって、「両当事者が」の部分や「意思を持って共同生活を開始すること」は不要であり、法律の定めにある通り、単に「婚姻は、」「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)」と説明すればそれで足りるものである。
ここで敢えて最高裁判決の示した「婚姻の本質」と称する説明をする必要はない。
その他、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に示すものとして用いられた文である。
そのことから、これは「婚姻」という法律関係に入るための法律上の要件を示したものではない。
この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度を利用する意思に関わるものであり、婚姻の形式を定めるものではないのである。
また、「婚姻の本質」と称する説明の文面だけを見て、これが心得や格言、スピリット、ライフスタイルの基準か何かだと勘違いして、その気持ちを持っているか否かを問うような書き方をしていることについても不適切である。
「②民法は、親族関係(…)、共同親権(…)、配偶者の遺留分を含む相続権(…)、離婚時の財産分与(…)、配偶者居住権(…)のほか、夫婦同氏の原則(…)、夫婦の同居、協力及び扶助の義務(…)、夫婦間の契約の取消権(…)、夫婦の財産関係(…)、夫婦財産契約の対抗要件(…)、婚姻費用の分担(…)、日常の家事に関する債務の連帯責任(…)、夫婦間における財産の帰属(…)等の夫婦間の権利義務を発生させる。」(カッコ内省略)との記載がある。
この民法上の婚姻制度の内容について、国(行政府)は下記のように説明している。
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF
国(行政府)は、「婚姻をした夫婦間に生まれた子について,嫡出の推定(772 条),父母の氏を称すること (790 条)等」も挙げ、これが「生殖に結びついて理解される異性間の人的関係を前提とした制度」と評価している。
この判決が示しているこれらの法的効果の内容を読み取る際に、単に法的効果が得られる人と得られない人がいるという問題として考えるのではなく、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段としてどのような枠組みが定められ、どのような法的効果が設定されているかという視点で考えることが必要である。
また、「婚姻している者(既婚者)」が、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのような視点で個々の法的効果を検討することが必要である。
「③戸籍制度による家族関係の公的認証(戸籍法6条)が与えられるとともに、」との記載がある。
ここでいう「戸籍制度による家族関係の公的認証」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「婚姻及び家族」の制度に対して設けているものである。
そのため、この目的に沿わない関係に対してはもともと設けていないものである。
よって、もともと「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない関係については「戸籍制度による家族関係の公的認証」が与えられないことは当然に予定されている。
そのことから、「戸籍制度による家族関係の公的認証」を与えられている者がいるとしても、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない者に対しても同様の制度を設けなければならないということにはならない。
この点を押さえておく必要がある。
「④所得税・住民税の配偶者控除(…)、相続税の軽減(…)、配偶者としての在留資格の付与(…)、遺族年金の付与(…)、犯罪被害者給付制度における遺族給付金の支給(…)等の利益、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護、裁判における証言拒否特権(…)等の各種権利が与えられる。」(カッコ内省略)との記載がある。
これについて、国(行政府)は、民法や戸籍法における「婚姻」の問題ではなく、具体的な一つ一つの政策の当否の問題であると述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
当サイトもこの訴訟で論点となっている民法や戸籍法上の「婚姻」の問題と、これらの別の法的地位の問題は切り分けて論じるべきであると考える。
なぜならば、現在の制度において政策的に「婚姻している者(既婚者)」に対して④のような「各種権利」を与えることが妥当であると判断されているだけであり、婚姻制度の枠組みを変更した場合には、それらの内容を「婚姻している者(既婚者)」に対して与えることが政策的に妥当でないと判断され、結果としてそれらの内容が与えられなくなる場合も考えられるからである。
以上によれば、現行法上、婚姻とは、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを市町村長に届け出(上記①)、市町村長がこれを受理することで、当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ(上記②)、身分関係を公証し(上記③)、これに公的な保護が与えられる(上記④)制度であると認められる。
【筆者】
「現行法上、婚姻とは、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを市町村長に届け出(上記①)」との記載がある。
しかし、一つ上の段落で説明したように、最高裁判決は「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明しており、そこには明確に「両性」と書かれている。
この「両性」の文言を「当事者」の文言に変えていることは、最高裁判決で前提となっている事柄を意図的に無視することで、この福岡地裁判決が特定の結論を導き出そうとする恣意的な判断があると考えられる。
このような文言上の操作を行った場合には、最高裁判決が前提としている憲法や法律などの具体的な条文や、その背景にある立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとの関係から切り離されたものとなるのであり、そのような前提となる条文などから切り離された単なる文面を利用して何らかの結論を導き出そうとしても、その文面そのものが根拠となる法源から論理的な過程の積み重ねによって導き出されたものではなくなっていることから、既に法的に正当化することのできる根拠を失っており、法的な効力を有することにはならない。
これとは別に、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
ここでは「現行法上、婚姻とは、」と説明しているのであるが、これは、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みに従う形で「婚姻」した場合に、その「婚姻制度を利用する者」の間で生じる法律関係を示す意味としてはその通りということができるが、この「婚姻の本質」と称する文面は、婚姻制度を利用するための条件を示しているわけではないし、法的な制度として整備する場合の対象者を示すものとして述べられているものではないし、婚姻制度についての「国の立法目的」を示したものというわけでもない。
そのため、この「婚姻の本質」と称する説明に示されている文面が何らかの基準となるかのように考えて、この文面に当てはまるか否かという視点を根拠として、婚姻制度の対象となる人的結合関係の範囲を拡大することができることにはならない。
「市町村長がこれを受理することで、当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ(上記②)」との記載がある。
ここで「当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ」とあるが、このような法律関係に入ることで「婚姻の本質」と称する説明の状態に入ることになる。
そのため、「婚姻の本質」と称する説明そのものがこのような具体的な婚姻制度の内容を離れて何らかの意味を持っているというわけではないことに注意が必要である。
具体的な婚姻制度を離れて、何らかの思想、信条、信仰、感情に基づいて人的結合関係を形成したり、共同生活を行うことは、個々人の価値観やライフスタイルにすぎず、法律関係とは関係のないものである。
よって、具体的な婚姻制度におけるこのような「各種の法的権利義務」による法律関係を離れて、「婚姻の本質」と称する観念が別に存在しているかのような考え方をしている部分は、法制度とは離れた何らかの価値観や信仰心が現れたものに過ぎないことに注意が必要である。
「身分関係を公証し(上記③)」との記載がある。
ここでいう「身分関係」とは、「婚姻」という制度を利用する者としての「身分関係」を指すものである。
つまり、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた制度を利用する者としての「身分関係」を明らかにしているだけである。
そのため、例えば「公務員」としての身分など、「婚姻」とは別の制度についての身分関係とは全く関係がない。
そして、その「婚姻」という制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ制度の利用を認めることによって、その目的の実現を目指すものであるから、その制度の目的に沿わない場合には、「婚姻」という制度による「身分関係」を形成することができないことは当然のことである。
この点を押さえておく必要がある。
「これに公的な保護が与えられる(上記④)制度であると認められる。」との記載がある。
これについて、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形でのみ正当化される「保護」である。
そのため、もし「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻」の目的を達成するための手段としては不必要に過大な「保護」を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な「保護」に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
(2) 本件諸規定は憲法24条1項に違反するか
ア 原告らは、今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障されるから、同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、婚姻の自由を侵害するものであり、同項に違反すると主張する。
【筆者】
「今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障されるから、」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「婚姻」という概念には、下記の目的が存在する。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そして、これらの目的を達成するための手段として整合的な要素によって「婚姻」の概念が有する内在的な限界が画されることになる。
それは、下記の要素である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素は、「婚姻」という概念そのものが、他の様々な人的結合関係との間で区別されるものとして成り立つための境界線となるものである。
これによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と含めることができない人的結合関係が区別されることになる。
これに加えて、憲法24条1項には「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これらの目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みと対応するものとなっている。
その上で、24条1項を前提として、24条2項の要請に従った形で定められた法律上の具体的な婚姻制度の要件に従う形で、制度を利用する意思があるのであれば、誰でも適法に「婚姻」することが可能である。
この意味で、ここでいう「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の要件を満たす形で婚姻制度を利用する意思を有しているのであれば、適法に婚姻制度を利用することは可能であり、24条1項の「婚姻をするについての自由」(ここで『婚姻の自由』と述べられているものにあたる)についても保障されていることになる。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもないため、「同性愛者」を称する者であるとしても、何ら分け隔てなく制度の利用を認めているのである。
そのため、ここでは「今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障される」と述べているが、そもそも24条1項が制定された時点からずっと「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用する自由は保障されていることになる。
「同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、婚姻の自由を侵害するものであり、同項に違反すると主張する。」との部分について検討する。
これは、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」が「婚姻」の対象となっていないことについて、「同性愛者」を称する者の「婚姻の自由」(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたると思われる)に違反すると述べるものである。
しかし、ここでいう「婚姻」とは何なのかということを検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。
そのため、その目的を達成するための手段として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付けるものとして概念が形成されている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たしておらず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に沿うものではないことから、「婚姻」という概念の中に含まれない。
そして、24条1項の「婚姻」についても、このことを前提としており、24条1項の「婚姻をするについての自由」についても、「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付ける制度を利用することについての「自由」をいう。
そのことから、「同性愛者」を称する者についても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用することについて、「婚姻をするについての自由」(ここでいう『婚姻の自由』)は保障されており、これが「侵害」されているという事実はない。
そのため、「婚姻の自由を侵害するもので」と述べていることは誤りとなる。
これとは別に、24条1項の「婚姻をするについての自由」を根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるかであるが、そもそも「婚姻」いう概念そのものが一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付ける概念として形成されており、「同性間の人的結合関係」は「婚姻」の中に含まれないことから、24条1項の「婚姻をするについての自由」を基にして、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができることにはならない。
婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻により与えられる重要な法律上の効果や国民の法律婚尊重の意識等を考慮すると、憲法24条1項の規定の趣旨に照らして尊重されるべき利益であることが認められる(最高裁判所平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)。
【筆者】
この段落の文について、参照として最高裁判決の文面を示している。
しかし、最高裁判決の文面と同様の文面で引用しているわけではなく、その内容を大幅に削るものとなっている。
下記で、最高裁判決の文面との対応関係を確認する。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF) (目印とするために太字にしている部分がある。)
最高裁判決の文面を大幅に短くしていることを見て取ることができるが、「婚姻をするについての自由」の文言が削られている点には、注意が必要である。
また、最高裁判決では「尊重に値するもの」としている部分を、この判決では「尊重されるべき利益である」としているが、意味を変更するものとなっていないか注意する必要がある。
そこで、憲法24条1項が同性愛者間の婚姻の自由を保障するものといえるか否かについて検討すると、憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。その制定過程を検討しても、前記1(2)のとおり、日本国憲法制定時の憲法24条の主な目的は、家族関係における自由と平等の実現、その中でも戸主制度の廃止による女性の地位向上と家族の保護であり、同性婚について議論が行われておらず、その起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れていること、これを受けた昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。そして、前記のとおり、婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するものであり、上記②~④のとおり、当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度であり、当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではないことからすれば、婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。
【筆者】
「憲法24条1項が同性愛者間の婚姻の自由を保障するものといえるか否かについて検討すると、憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との記載がある。
まず、婚姻制度は個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないことから、ここでいう「同性愛者」であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を適法に利用することが可能である。
よって、ここでいう24条1項についての「婚姻の自由」と称するもの(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたるものと思われる)は「同性愛者」を称する者についても当然に保障されている。
ここでは、「同性愛者間」との文言があることから、「同性愛者」を称する者と、別の「同性愛者」を称する者の間で「婚姻」することを、24条1項についての「婚姻の自由」と称するもの(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたるものと思われる)によって保障されているかを述べようとしていると思われる。
このような視点で見るとしても、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもないことから、「男女二人一組」などの要件を満たしているのであれば、婚姻制度を利用することができる。
その意味で、それがたとえ「同性愛者」(男性の同性愛者)を称する者と「同性愛者」(女性の同性愛者)を称する者の組み合わせであるとしても、ここでは「男女二人一組」の要件を満たしていることから、適法に婚姻制度を利用することができる。
この意味で、「保障するものといえるか否かについて検討する」の部分について、「男女二人一組」の要件を満たすのであれば、それらの個々人に対して24条1項の「婚姻をするについての自由」を保障しているということができる。
これとは別に、「同性愛者」を称する者はすべて「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めているとの前提(因果関係がなく誤った認識であるが)の下に、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを、24条1項の「婚姻をするについての自由」によって求めることができるか否かを論じている可能性がある。
これについては、そもそも「婚姻」とは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができないため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
また、「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との部分で説明しているように、憲法24条1項では「両性」「夫婦」の文言を用いており、「男女」の関係を定めている。
これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みについて、具体的な基準を定めているものであるから、この意味を離れて法律を立法することはできないし、24条1項の「婚姻をするについての自由」が保障する範囲もこの範囲に限られる。
よって、24条1項の「婚姻をするについての自由」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることはできない。
次に、「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との部分であるが、その通りということができる。
この点は、「婚姻」という概念そのものが「男女」を法的に結び付けるものとして成立していることを裏付けるものでもある。
ただ注意したいのは、法的には「婚姻」の枠組みが「男女」であることと、それを利用する者が「同性愛者」を称する者であるかどうがは、まったく別の次元の問題ということである。
この点を区別しないままに論じることは、議論を混乱させる原因となる。
「その制定過程を検討しても、前記1(2)のとおり、日本国憲法制定時の憲法24条の主な目的は、家族関係における自由と平等の実現、その中でも戸主制度の廃止による女性の地位向上と家族の保護であり、同性婚について議論が行われておらず、その起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れていること、これを受けた昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」との記載がある。
この一文は長すぎるため、意味を整理して読み取ることが難しくなっている。
この文の意味の流れをまとめると下記のような意味である。
(憲法24条の)「起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れている」
↓ ↓
「日本国憲法制定時」「同性婚について議論が行われておらず、」
↓ ↓
「昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められない」
↓ ↓
「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかった」
↓ ↓
「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではない」
この流れとなっていることを押さえた上で、詳しく検討する。
「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」との部分について検討する。
ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で枠組みを形成する際に、「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それを一定の形式で法的に結び付ける概念を「婚姻」と呼んでいる。
この一文の中で登場する24条1項の「両性」や「夫婦」の文言についても、すべてこの意味に対応するものとして用いられている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、この判決が述べるような「異性間の婚姻を指し、」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念と、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。
「同語(同義)反復」の例を下記に挙げる。
・「金持ち富裕層」 トートロジーに陥ってはいけない
・「やる気に満ちたモチベーション」 (〃)
・「実際にあったノンフィクション」 (〃)
・「未成年の小学生」 同語反復
・「私の親は男の父だ。」 トートロジー Wikipedia
・「頭痛が痛い。」 (〃)
・「馬から落馬した。」 (〃)
上記の「金持ち富裕層」の例を取り上げれば、「富裕層」であれば「金持ち」しか存在しないのであり、「金持ち」と「富裕層」を組み合わせることは、「同義反復」となる。
同じように、この判決が「異性間の婚姻」という言葉を使っていることについても、「婚姻」であることそれ自体において「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、「異性間」と「婚姻」を組み合わせることは、「同義反復」となる。
また、「同義反復」となることを無視して、「金持ち富裕層」という言葉を使ったとしても、「富裕層」であることそれ自体で「金持ち」しか存在しないのであり、それに対する形で「貧乏な富裕層」というものが存在することにはならない。
同じように、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、それに対する形で「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。
そのため、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。
「婚姻」であることそれ自体で「男性」と「女性」(異性間)の組み合わせを指す意味しか存在しないということである。
よって、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないのであり、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。
◇ 本来の意味
「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする
◇ この判決の言葉の使い方
「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる
そのことから、「異性間の婚姻」という言葉の表現は適切であるとはいえず、このような「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じるべきではない。
この一文の中には、「同性婚」という文言が5回登場する。
・「同性婚について議論が行われておらず、」
・「同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、」
・「同性婚は想定されていなかったものと認められ、」
・「同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、」
・「同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」
この判決が用いる「同性婚」の意味は多義的なものであるため、その意味を確定することは難しい。
詳しくは、このページの冒頭の「ポイント」の所で解説している。
「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」との記載がある。
まず、「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、」との部分を検討する。
「想定されていなかった」ことには、それが「想定されていなかった」なりの事情が存在するはずである。
その理由を遡って検討しなければ、「婚姻」という概念そのものや、24条の「婚姻」の文言や「両性」「夫婦」の文言が、「同性間の人的結合関係」をどのように扱っているのかを理解することはできないし、24条の下で「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるか否かも判断することはできない。
そこで、その理由を下記で検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された枠組みである。
このような経緯から、「婚姻」は「生殖と子の養育」の趣旨を含む制度となっている。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を観念できないことから「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものとはいえず、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。
つまり、制度の趣旨に沿わない関係であれば、もともと「婚姻」ではないことから、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。
また、「婚姻」の目的を達成するためには、下記の要素を満たす人的結合関係を対象とする必要がある。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
「同性間の人的結合関係」については、これらの要素を満たすものではない。
そのため、そもそも「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。
このように、「想定されていなかった」ことには、「想定されていなかった」だけの理由があると考えられる。
この「想定されていなかった」との文言だけを見て、それを単に立法者がうっかり忘れていたかのような安易な発想によるものであると意味を限定して認識し、それを反対解釈すれば「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるということにはならないことに注意が必要である。
【参考】「想定していないということは、同性婚は24条の【婚姻】と認められないということ」 Twitter
【参考】「想定してないモノはそもそも【婚姻】じゃない」 Twitter
【参考】「想定していないことは禁じてることにはならないが、想定していなければ認められない。」 Twitter
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「24条は同性婚を想定していない」
①だから同性婚を禁止していない
②だから同性婚を許可していない
どちらも正解。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「想定してない」「触れてない」「定めてない」
そんなモノがどうして【婚姻】と言えるのだ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【参考】「同性婚を想定したものじゃないから関係ない。 これ言い始めたら憲法条文に意味がなくなる。」 Twitter
次に、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、」の部分を検討する。
この判決の「同性婚」の意味は多義的なものとなっている。
ここで「同性婚」の意味が、「同性間の人的結合関係」そのものを指している場合には、それを「禁止」するようなものではないことはその通りである。
ただ、これより以下はこの文が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて「禁止する趣旨であるとはいえない」と述べているものであると捉えた上で検討する。
■ 「禁止」の意味
この「禁止する」という言葉は、様々な意味で用いられる。
そのため、その「禁止する」の文言がどのような意味で使われているのかを更に検討する必要がある。
① 義務文・否定文による禁止
「義務文・否定文による禁止」とは、条文中に「禁止する」や「禁ずる」、「~~してはならない」、「~~しなければならない」のように記載されている場合のことをいう。
② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)
「防ぐ意図の禁止」とは、何らかの対象を認識した上で、それを意図的に防ぐ意思を持って規定が設けられている場合のことをいう。
これは、何かを制限する意味、対象者を限定する意味、対象者専用とする意味も含まれる。
③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)
「上位法に反する禁止」とは、下位の法令で制度を構築した場合に憲法に違反する場合のことをいう。
この判決は、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べているが、これら、①「義務文・否定文による禁止」、②「防ぐ意図の禁止」、③「上位法に反する禁止」のどれを指して「禁止する趣旨であるとはいえない」と判断したかを検討する必要がある。
また、その「禁止する趣旨であるとはいえない」との判断が24条1項を解釈したものとして妥当な内容であるかも検討することが必要である。
■ 「婚姻」の中に含めることができるもの
この判決は、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べ、その結果として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように理解しているようである。
しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかどうかという部分から検討することが必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。
憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
そこで、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるかどうかを検討する。
■ いくつかの立場との関係性
24条を解釈する際に、いくつかの立場がある。それらを検討する。
▼ 「婚姻」の由来
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。
「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。
これについて、後ほど「『婚姻』の概念による制約」の項目でも解説する。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。
「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。
◇ 成立条件説
この立場は、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。
「婚姻」を成立させるためには「両性」である「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。
◇ 想定していない説
この立場は、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。
上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。
24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、これを満たさないため「婚姻」とすることはできないことになる。
◇ 禁止説
この立場は、24条の規定は、何かを認知した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。
「同性間の人的結合関係」についても、24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。
◇ 義務文・否定文による禁止説
この立場は、24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。
これによれば、24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。
「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。
どの説で考えることが妥当であるかを検討するためにも、「婚姻」という概念が形成されている由来を検討することが必要である。
そこで、下記ではさらに「婚姻」という概念が形成されている由来や、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。
■ 「婚姻」の概念による制約
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。
このことから、これらの要素は、「婚姻」という概念が他の様々な人的結合関係とは区別する形で成り立つための境界線となるものである。
そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合(国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題)を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
よって、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが求められ、その目的を達成するための手段となる枠組みを「婚姻」という概念が担っている以上は、「婚姻」はそれを解消するものとして機能することが求められている。
そのため、「婚姻」の文言の中には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、これらの要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。
このような差異が生じることは、「婚姻」という概念そのものが、目的を達成するための手段として形成されている枠組みである以上は当然のことである。
「同性間の人的結合関係」(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、上記の要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。
▼ 24条の「婚姻」による限界
憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
24条が定めているものが「婚姻」である以上は、その「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、そこには「婚姻」の立法目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。
よって、24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
また、24条は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たすからである。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。
「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないし、これらの要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
よって、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▼ 言葉の置き換えを繰り返すことはできないこと
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このように、「婚姻」という枠組みが形成されている立法目的がある以上は、その「婚姻」という概念の中には、他の人的結合関係との間で区別するための要素が存在する。
それは、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な要素であり、下記が不可欠である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。
すると、そもそもそのような制度に対して法的効果や優遇措置を行う意味も失われ、制度を継続する必要性がなくなり、その「婚姻」と呼んでいる制度を廃止することに行き着く。
また、その「婚姻」と呼んでいる枠組みによっては、既に立法目的を達成することができなくなっていることから、その目的を達成するために「婚姻」以外の新たな制度を立法することが求められることになる。
しかし、それは結局、それまで機能していた本来の「婚姻」とまったく同様の目的を達成することを意図して立法されることになるから、上記の要素を満たす人的結合関係を新たな枠組みとして他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けることになるものである。
こうなると、それはもともと「婚姻」が有していた機能を、新たな枠組みの制度が担おうとするものとなることから、そもそも「婚姻」から新たな枠組みの制度へと言葉の入れ替えを行っているだけの状態となるのである。
このような言葉の置き換えという無意味なループを繰り返すことを防ぐためには、「婚姻」という枠組みが存在する時点で、そこには「婚姻」という枠組みを形成している立法目的が存在しており、その「婚姻」という枠組みそのものにその立法目的との間で整合性を保つことができる内在的な限界が含まれていることを捉える必要がある。
そして、その内在的な限界となる要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとする試みは、「婚姻」という概念そのものが有している本来の意味、内在的な機能を改変し、消失させようとするものとして排斥することが必要となる。
これによって、「婚姻」という概念そのものの枠組みを維持し、「婚姻」という概念そのものが消失することを防ぎ、「婚姻」という言葉の意味が成立する状態を保つことができるからである。
そのことから、「婚姻」という枠組みが形成されている背景にある立法目的が正当である以上は、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができ、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。
このような差異が生じることは「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。
この差異を否定するのであれば、それはそもそも「婚姻」の立法目的を否定することになることを意味する。
「婚姻」の立法目的が正当と認められる以上は、その立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みによって生じる差異は、法制度が政策的なものであることからくる誰もが甘受しなければならないものである。
そして、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」の目的を達成するための手段として必要となる上記の要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
▼ 主張の基盤を失わせる主張であること
24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるはずであるとの主張がある。
しかし、この主張に従って「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めた場合には、24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることになる。
こうなると、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有していないことになる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
その「生殖と子の養育」に関わる制度は、「婚姻」ではないことから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさなくとも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
そして、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備するようになった場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
この影響で、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
すると、実質的に24条の規定が無意味なものとなり、24条が「婚姻」に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように立法裁量の限界を画している意味が希薄化してしまう。
そうなると、もともと24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を24条の「婚姻」の中に含めることができると主張し、それによって「同性間の人的結合関係」についても優遇措置を得られると期待していたにもかかわらず、それをした場合には、そもそも「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることから、結果として「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」とは別の制度として立法することを許すことに繋がり、その別の制度の優遇措置が増えるなどしてその制度が主流化し、もともと「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることによって得られると期待していただけの優遇措置を「婚姻」という制度からは得られない状態に陥ることになるのである。
そのため、24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についても「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張は、結果として、自己の主張の基盤さえも失わせる主張となっているということができる。
よって、24条の定める「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を含めることができるとの主張は成り立たない。
もし「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、24条の「婚姻」の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
これらを前提として、この判決が「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べている部分を改めて検討する。
「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。
そのため、「婚姻」という概念に含めることができる人的結合関係には、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。
そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。
また、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。
「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
また、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨にも当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
結果として、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを認めていないことになる。
他にも、24条は「婚姻」を定めていることから、この24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。
そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする法律を立法することを、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言はそれを許容していない。
よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
このことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。
これらの観点から、この判決が「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じていることは、「婚姻」という概念そのものに含まれている内在的な限界や、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨を考慮しないものであり、誤りとなる。
■ 「禁止」の意味との関係性
この判決は「禁止する趣旨であるとはいえない」と述べるが、これは下記のように考えることになる。
① 義務文・否定文による禁止
24条1項の条文を確認すると、最後に「~なければならない。」と記載されている。
また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英文契約書における権利義務の定め方
そのことから、24条1項は「義務文・否定文による禁止」の意味を有していると考えることができる。
「同性間の人的結合関係」については、24条が「婚姻は、両性~に基いて成立し~なければならない。」(shall)と定めていることの「両性」の部分を満たさないことから禁止する趣旨である。
② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)
24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と記載されている。
憲法上に具体的な基準を示しており、また、いくつかの事項を満たすことを求めるものとなっている。
そのことから、24条1項は「防ぐ意図の禁止」の意味を有していると考えることができる。
24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって規定されていることから禁止する趣旨である。
【参考】「24条は『両性の合意』に基づかない婚姻の成立を制限している。」 Twitter
【参考】「24条は『婚姻の自由の及ぶ範囲を規定している』」 Twitter
【参考】「範囲を規定している以上、その効果は範囲内に制限され、それ以外が除外される」 Twitter
【参考】「【男性禁止】だと不必要に攻撃的で印象が悪いので普通は【女性専用】を使うわな。」 Twitter
【参考】「24条は婚姻の成立条件を異性婚に限定しようという意図が含まれていると解するほうが、よほど論理的つながりがスムーズ」 Twitter
【参考】「『~せねばならない』なんて物言いは全く不要です。」 Twitter
【参考】「憲法で『禁ずる』と述べているのは36条のみ」 Twitter (憲法36条)
【参考】「【禁止】と銘打たなくても、対象を限定したり、それ以外を排除することは可能」 Twitter
【参考】「『禁止じゃなきゃ制限できない』なら、24条は『戸主による強制的な婚姻』すら制限できないことになるよね。」 Twitter
【参考】「24条は【戸主による婚姻の強制】を【制限】しているわけだし、」 Twitter
【参考】「ま、取り敢えず、『24条は一定の制限を画している』事実を認めたわけで、」 Twitter
【参考】「『24条は戸主による強制的な婚姻を制限している』を目的の一つと認めた時点で『禁止してないのに制限してる』事実を認めたことに他ならない。」 Twitter
【参考】「『禁止していない』だけ大声で叫んでも『許容している』ことにはならない」 Twitter
【参考】「『禁止を明示していなければ一切の制限は不可能』という公的な解釈を出して御覧なさい。」 Twitter
【参考】「例えば学校教育法2条で学校設置者が国、地方、学校法人のみとされてますが、禁止の文ではないのだから個人もOKと読んでいいのですか?」 Twitter (学校教育法2条)
③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)
24条1項には「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言があり、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
これらの文言の趣旨を満たさない形で法律を立法した場合には、上位法である憲法と下位法である法律の間に矛盾・衝突が生じることになる。
この場合、上位法である憲法を基準として、下位法である法律の内容の齟齬がある部分を是正することになる。
このため、24条1項は「上位法に反する禁止」の意味を有していると考えることができる。
24条の下で婚姻制度を「同性間の人的結合関係」を含む形で立法しようとした場合には24条に違反するため、結果としてこれは禁止する趣旨である。
【参考】「婚姻の成立条件は両性の合意【のみ】だということです。」 Twitter
【参考】「「のみ」で「成立」なので反対解釈すると「両性の合意以外は不成立」になります。」 Twitter
【参考】「同性婚を婚姻の成立と認めていない」 Twitter
【参考】「そもそも同性は婚姻の対象にならない。」 Twitter
【参考】「結婚は異性同士でするもので差別とは全く関係ない」 Twitter
【参考】「そもそも婚姻は男女が一緒になることを意味していて、同性が一緒に暮らすことを婚姻とは言わないから。排除も禁止も必要もない。」 Twitter
【参考】「同性婚の概念が無く、従って同性婚を否定するネガティブ規定は、それを明文化する必要が無かった。」 Twitter
【参考】「違憲の条件は『禁止していること』ではなく『反していること』だからね。」 Twitter
【参考】「24条は禁じていないが、98条が『憲法に反した立法行為』を否定」 Twitter
24条の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
そのため、24条がそれを「禁止する趣旨」であるかどうかという点については、上記の①「義務文・否定文による禁止」、②「防ぐ意図の禁止」、③「上位法に反する禁止」のいずれの立場によって説明するものであるかという問題に過ぎないものとなる。
そして、これは➀②③が同時に成り立つ場合、②と③が同時に成り立つ場合、③だけに該当する場合の3つのパターンによって説明することが可能である。
この判決の「禁止する趣旨であるとはいえない」の文についても、①ではない、①と②ではないという部分までは何とか意味が成り立つとしても、③ではないという意味までは成り立たない。
■ 結論
この判決は、「禁止する趣旨であるとはいえない」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じようとしている。
しかし、上記の点を考慮しておらず、その結論は正当化することができない。
憲法上の文言に従う解釈を行った場合に、そこに目的を達成するための手段として整合的な枠組みとなっていることを確認することができ、憲法上の規範としての意義を見出すことができる以上は、そこに規範的な力を認めることによって、憲法の規範性を保つことが求められる。
社会の根幹に関わる制度について、安易に憲法の規範力を損なわせる方向で考え、その制度の枠組みそのものを、その時々の政治的な事情や、国民のその時々の一時的な感情の振れ幅に委ねることができるかのように述べていることは適切ではない。
これら点を考慮せずに、「禁止する趣旨であるとはいえない」というように憲法の規範力を損なわせるような説明を行っていることは、内容が不適切であるばかりか、法秩序の安定性まで損なわせるものとなっており、妥当であるとはいえない。
■ 論じる必要のない論点であること
この判決は、24条1項について「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じている。
しかし、今回の事例は、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律が存在していないことが24条1項に違反するか否かが問われているのであって、24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法した場合に24条に違反するか否かという意味において「禁止」しているか否かが問われているわけではない。
そのため、24条の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法した場合に、その法律が24条に違反するか否かについてまで判断を示す必要がないものである。
解釈の方法について様々な論点が存在し、様々な立場から対立が見られるテーマについて、今回の事件の論点を超える形で裁判所が独断で方向性を示すことは控えるべきであると考える。
今回の事件の論点を超える形で判断を示すことは、別の事件が生じたときに、改めて別の角度から検討した結果、別の判断が下されることも起こり得る。
そのことから、他の立場の意見を網羅的に検討した上で異論が出ないほどまでに確立しているような十分な理由を示すこともなく、24条の「婚姻」の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるという意味において「禁止する趣旨であるとはいえない」などと一方の意見のみを述べて何らかの方向性を与えようとすることは、この事例を解決するにあたって求められている法解釈の範囲を超える形で政治部門の特定の政策に対して支持、不支持、適当、不当を表明するものと受け止められかねないものとなっており、司法権の行使として適切な範囲を超えることになると考えられる。
国(行政府)の主張でも、この論点は今回の事例の争点ではないことについて指摘されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、被控訴人原審第 2準備書面26ページにおいて述べたとおり、そもそも、憲法 24条との関係で木件立法不作為が違憲であることが明白であるといえるためには、同条が同性問の婚姻を法制化するととを国会に対して要請しているといえなければならず、同性婚が憲法上禁止されているか、又は許容されているのかという点は、原告らの憲法24条に関する主張の当否の判断において争点とはならないため、この点に関する回答は差し控える。また、憲法が同性問の婚姻を法制化することを国会に対して要請していないことは、控訴答弁書7ないし10ページにおいて述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第2回】被控訴人回答書 令和4年3月4日 PDF
司法の謙抑性の観点からも、様々な論点が存在し、異論がないほどまでに解釈の方法が確立しているわけではない問題について、一定の方向性を与えるようなことを述べることは不適切ということができる。
司法権を行使する裁判所は、その事件を受け持った裁判官や裁判体の政治的な意見表明を行う場ではないことを心得る必要がある。
「婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するものであり、上記②~④のとおり、当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度であり、当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではないことからすれば、婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。」との記載がある。
この一文が読み取りづらい理由は、下記の四つの説明が混在しているからである。
① 「婚姻」とはどのような制度かについての説明
② 「婚姻」の要件と効果を当事者の意思のみで決定できるかどうかの説明
③ 「婚姻」する自由が憲法上尊重すべき利益であることの説明
④ 「男女」の枠に当てはまらない関係で「婚姻」することが憲法上の権利を構成するかの説明
他にも、「これ」が三回出てくるが、最後の「これ」は何を指しているのかはっきりせず、理解がスムーズにいかないものとなっている。
三回目の「これ」の可能性
◇ 一文前の「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻」の部分
◇ この文の「各種法律によりその要件が定められ、」や「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではないこと」の部分
◇ 「婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益である」の部分
このよう悪文となることを防ぐためには、文を短く区切ることを心掛けるべきである。
この一文は分かりにくいので、下記で並べ替えてまとめる。
「婚姻は、」「上記②~④のとおり、当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度」
「自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するもの」
↓ ↓
「婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、」
↓ ↓
「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではないことからすれば、」
↓ ↓
「これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。」
これでも長いので、短くまとめると下記のような意味である。
「婚姻は、」「法律上の制度」であり、「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではな」く、「これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。」
しかし、このようにまとめても「これ」の意味をはっきりと理解することができない。
「婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、」との部分であるが、ここでいう「婚姻」については、この段落内で下記のように述べられているように、「男女」であることを前提としている。
◇ 「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているもの」
◇ 「起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れている」
◇ 「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」
そのため「婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益である」という部分についても、「男女」の枠組みの婚姻制度を利用することについての「自由」が「憲法上尊重すべき利益である」と述べているだけである点を押さえる必要がある。
イ 原告らは、憲法24条1項の「婚姻」には同条項の拡張解釈ないし類推適用により同性婚を含むものと解されると主張する。
【筆者】
ここでは「憲法24条1項の「婚姻」」の中に「同性婚」を含めることができるかを論じるものとなっている。
しかし、憲法24条は「婚姻」を規定しており、日本法における「婚姻」という概念はすべて24条の「婚姻」を意味するものであるから、この24条を離れて「婚姻」を立法することはできない。
また、憲法24条は「婚姻」の内容を24条の統制が及ぶように求める規定であるから、もし法律上で24条の「婚姻」が及ばない形で「婚姻」と称する制度を定めようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「憲法24条1項の「婚姻」」と、憲法24条に基づかない別の「婚姻」(あるいは『~~婚』と称する制度)が併存するということはあり得ない。
このことから、「憲法24条1項の「婚姻」」の中に「同性婚を含むもの」か否かという文からは、あたかも憲法24条を離れた別の形式として存在する「同性婚」という制度を、「憲法24条1項の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点から論じているように見受けられるが、そもそも「憲法24条1項の「婚姻」」が男女間(異性間)に限られている以上は、それ以外の形式の「婚姻」と称する制度が「憲法24条1項の「婚姻」」の下で存在することはできない。
よって、「憲法24条1項の「婚姻」」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かという視点の議論をしようとしているということであれば文の意味としては理解することが可能であるが、「憲法24条1項の「婚姻」」を離れて別の法形式として「婚姻」(あるいは~~婚)と称する制度が存在することを前提として、その中の一つである「同性婚」という制度を「憲法24条1項の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点で論じているのであれば、誤りである。
次に、「憲法24条1項の「婚姻」」を「拡張解釈」することによって、その「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含むと考えることができるかを検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で結び付けるものとして形成されている。
この制度の根幹部分は、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることで産まれてくる子供の父親を特定することができるというところにあり、この仕組みを離れて「婚姻」を観念することはできない。
よって、この仕組みに当てはまらないものを「婚姻」という概念に含めることはできない。
もしこの仕組みを損なった場合には、そもそも「婚姻」という枠組みが有している目的を達成することができない影響が生じることになるから、その仕組みを満たさないものを「婚姻」として扱うことはできない。
そのため、その間で自然生殖を想定することができない「同性間の人的結合関係」についても「婚姻」の中に含めることができない。
これにより、「憲法24条1項の「婚姻」」を「拡張解釈」することによって、その「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かについては、「婚姻」という概念そのものが成り立つために必要となる内在的な限界を超えるものであるから「拡張解釈」を採用することができる事例であるとはいえず、含めることはできないことになる。
もう一つ、「憲法24条1項の「婚姻」」を「類推適用」する余地があるかを検討する。
憲法は「個人の尊重(13条)」、「個人の尊厳(24条)」の原理に基づいていることから、条文の適用の可否を考える際には、個人を単位とする必要がある。
そのため、「類推適用」の可否を考える際にも、個々人が婚姻制度を利用することができるか否かという視点によって論じることが必要である。
そして、一人一人の個人は「男女二人一組」の婚姻制度を利用することは可能であり、その個人に対して「直接適用」されることになるから、「類推適用」を論じる余地はない。
確かに婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得るものであり、こうした社会通念等の変遷により同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。上記認定事実によれば、諸外国において同性婚を法制度化している国が相当数あり、わが国においても多くの地方自治体においてパートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動きや同性愛に対する偏見を除去しようとする動きがあることが認められる。しかし、我が国における世論調査の結果等によれば、同性婚の導入に反対の意見を有する者が60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と拮抗していることをはじめ、全体的に依然相当数おり、同性婚に対する価値観の対立が存するところである。そして、このような反対の意見の中には婚姻は依然として男女間の人的結合であるとのこれまでの伝統的な理解に基づくものと考えられるのであって、婚姻についての社会通念や価値観が変遷しつつあるとは言い得るものの、同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難いところである。
【筆者】
「婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得るものであり、こうした社会通念等の変遷により同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」との記載がある。
まず、「婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得るものであり、」の部分について検討する。
「婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観」という場合、それは「婚姻制度を利用する者の利用方法」について述べられているのか、「婚姻制度の枠組みそのもの」について述べられているものであるのかを区別して考える必要がある。
◇ 「婚姻制度を利用する者の利用方法」についての「社会通念や国民の意識、価値観」
例
・ 子供をつくる前に婚姻したいと思う者の割合
・ 25歳までに婚姻したいと思う者の割合
・ 昔は離婚するには勇気が必要だったが今の時代はそうでもない
・ 婚姻したいと思わない者の割合 など
◇ 「婚姻制度の枠組みそのもの」についての「社会通念や国民の意識、価値観」
例
・ 婚姻適齢が12歳だと低すぎるのではないか
・ 「いとこ」とも婚姻できないようにしたほうがいいのではないか
・ 姻族との扶養関係を強化した方がいいのではないか
・ 再婚は2回までに制限した方がいいのではないか など
「婚姻制度を利用する者の利用方法」については、婚姻制度を利用する者がどのような理由で利用しているのか、また、婚姻制度を利用しない者がどのような理由で利用しないのかを検討するものである。
これは、婚姻制度を個々人がどのような価値観に従って活用するかという個々人の利用目的に基づくものであり、法律論として論じることのできる対象ではない。
これに対して、「婚姻制度の枠組みそのもの」については、国民が婚姻制度の枠組みをどのようなものと考えているかを検討するものである。
ただ、これが法学的な意味の「婚姻」である以上は、どのような人的結合関係でも「婚姻」として扱うことができるという性質のものではないため、「婚姻」という概念であることそのものによって、「変遷」の範囲には内在的な限界がある。
その理由は、下記の通りである。
「婚姻」とは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている枠組みである。
そのことから、「婚姻」という概念そのものの中に、その「婚姻」という概念が形成されている立法目的との関係で、他の様々な人的結合関係との間で区別することを可能とするための要素が含まれていることになる。
そのため、それらの要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができるが、それらの要素を満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。
これは、「婚姻」という概念そのものが成り立つために必要となる境界線であり、内在的な限界である。
そのため、それらの要素を満たすことによって、その「婚姻」という枠組みを維持することのできる人的結合関係の範囲内で、「婚姻適齢」が多少変わるとか、「法定相続分」が変更されるとかいうことは考えられる。
このような内容については、「社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得る」ことは考えられる。
しかし、法学的な意味の「婚姻」の概念を用いて説明しているにもかかわらず、それをその内在的な限界を取り払うことを意味する形で「婚姻」の文言を用いることができることにはならない。
それは、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた枠組みである「婚姻」ではなく、その概念を廃止し、21条1項の「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係と同化し、混同させることになるからである。
そのため、「婚姻」という言葉を用いている時点で、そこには内在的な限界が含まれているのであり、「社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得る」という場合においても、その限界の範囲内の「変遷」であることが前提である。
その枠組みを形成していることによる内在的な限界を超える形で、あらゆる人的結合関係を「婚姻」の中に含めることができるということにはならない。
次に、「こうした社会通念等の変遷により同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」の部分について検討する。
上記で述べたように、「婚姻」という概念には、その概念が有する目的の関係で内在的な限界がある。
そのため、どのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができるということにはならない。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを選び出し、一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている。
そして、このような目的を離れて「婚姻」という概念を観念することはできない。
そのため、「婚姻」という言葉を用いている時点で、それは「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている概念を指していることになる。
この範囲を超える人的結合関係を「婚姻」とすることはそもそもできない。
ここでは、「社会通念等の変遷」や「国民の社会的承認」を述べるのであるが、「婚姻」という概念そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成された枠組みであるから、その枠を離れて「婚姻」という言葉を用いることができることにはならない。
これは法解釈を行うものであることから、国民のその時々の支持・不支持の割合が多いか少ないかによって言葉の意味が変わるというものではない。
よって、「社会通念等の変遷」や「国民の社会的承認」が有るとか無いとか述べるだけで、「婚姻」という概念に内在する「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを変更することができることにはならない。
そのため、「同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」と述べていることについても、妥当でない。
また、そもそも24条1項には「婚姻」の文言だけでなく、「両性」「夫婦」「相互」の文言が存在し、一夫一婦制(男女二人一組)が定められている。
24条1項の下で、この趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」についても、これを満たしていないことから、「婚姻」とすることはできない。
「諸外国において同性婚を法制度化している国が相当数あり、わが国においても多くの地方自治体においてパートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動きや同性愛に対する偏見を除去しようとする動きがあることが認められる。」との記載がある。
「諸外国において同性婚を法制度化している国が相当数あり、」との部分について検討する。
諸外国の法制度は、その国の社会事情の中で発生している不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として定められているものである。
そのため、その諸外国の法制度と日本の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
そして、ここでは「同性婚を法制化している国」との記載があるが、その国の法制度について外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という言葉をあてて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一の制度を指していることにはならない。
それぞれの国の制度は、それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを目的として制度が設けられているだけであり、その目的や目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
そのため、「同性婚を法制度化している国が相当数あ」ると述べたところで、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠とはならない。
また、ここでは「諸外国」として「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度を設けている国を取り上げるのであるが、「諸外国」の中には「一人の男性と四人の女性まで」の「一夫多妻制」を採用している国もあるのであり、それらを出すことなく、「同性間の人的結合関係」を対象とした法制度を設けている国だけを持ち出して論じるものとなっていることも妥当でない。
「わが国においても多くの地方自治体においてパートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動きや同性愛に対する偏見を除去しようとする動きがあることが認められる。」との部分について検討する。
これについて、「地方公共団体」の「パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、その制度は違法となる。
また、ここでは「パートナーシップ制度」と「同性愛に対する偏見を除去しようとする動き」を一つの文の中で説明していることから、「同性愛」と「パートナーシップ制度」を関係するものと考えているように見受けられる。
しかし、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として「パートナーシップ制度」を設けている場合には、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することは、他の思想、信条、信仰、感情との間で区別するものであるから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
他にも、個々人の抱く思想、信条、信仰、感情によって区別取扱いをすることになるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
そのため、「地方公共団体」の「パートナーシップ制度」の内容が「同性愛」という思想や信条に着目して分類された「同性愛者」にあたる者を対象とした制度となっていれば、そのこと自体で違憲となる。
法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならず、特定の思想や信条を取り上げて制度化したり、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置を設けていること自体が違憲となるからである。
そのような制度を行政主体が運用していることを正当化できるかのように論じているのであれば、誤りなる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「我が国における世論調査の結果等によれば、同性婚の導入に反対の意見を有する者が60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と拮抗していることをはじめ、全体的に依然相当数おり、同性婚に対する価値観の対立が存するところである。」との記載がある。
この文は、「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みからどのような人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかという観点から論じるのではなく、「世論調査の結果等」における「価値観の対立」によって、「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かが変わるかのように論じようとするものとなっている。
しかし、ここでは法解釈が問われているのであるから、「世論調査の結果等」における「価値観の対立」によって、「婚姻」として扱うことができる人的結合関係の範囲が広がったり狭まったりするような論じ方をすることは妥当でない。
そのような「世論調査の結果等」における「価値観の対立」を反映することによって規範を変更することができる場合とは、国会によって法律の規定を改廃するか、憲法改正によって憲法上の規定を改廃する場合のことである。
裁判所が法解釈を行う際には、国民意識などという漠然とした説明や、「世論調査の結果等」などというその時々の調査によって結論が変わるような資料を根拠として規範の意味を論じるべきではない。
立法府の国会が担うべき問題と、司法府の裁判所が担うべき問題を区別することが必要である。
「このような反対の意見の中には婚姻は依然として男女間の人的結合であるとのこれまでの伝統的な理解に基づくものと考えられるのであって、婚姻についての社会通念や価値観が変遷しつつあるとは言い得るものの、同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難いところである。」との記載がある。
ここでは「社会通念」や「価値観」、「社会的承認」があれば、24条1項の「婚姻」の意味が変わるかのような説明となっている。
しかし、ここでは法解釈が問われているのであり、法の条文に記された文言の意味そのものを国民の賛成・反対の意見の数に委ねるような判断を行うことは適切ではない。
ここで「伝統的な理解」としている「婚姻は」「男女間の人的結合である」という枠組みは、「婚姻」という概念に含まれている目的とその目的を達成するための手段となる要素によるものであり、そこを検討せずに、賛成派の個人的な価値観や反対派の個人的な価値観の対立によって結論が変わるものであるかのように理解していることは妥当なものではない。
したがって、同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含むと解釈することは少なくとも現時点においては困難であり、原告らの上記主張を採用することができない。
【筆者】
まず、ここで使われている「同性婚」との文言は、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるかのような前提で論じるものとなっている。
しかし、「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で、「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている。
そのため、その間で「生殖」を想定することができない「同性間の人的結合関係」については、もともと「婚姻」として扱うことはできない。
これは、「婚姻」という概念に含まれている内在的な限界によるものである。
次に、ここでは「憲法24条1項の「婚姻」」の中に「同性婚」を「含む」か否かという視点となっている。
しかし、憲法24条は「婚姻」を規定しており、日本法における「婚姻」という概念はすべて24条の「婚姻」を意味するものであるから、この24条を離れて「婚姻」を立法することはできない。
そして、憲法24条は「婚姻」の内容を24条の統制が及ぶように求める規定であり、もし法律上で24条の「婚姻」が及ばない形で「婚姻」と称する制度を定めようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
そのため、「憲法24条1項の「婚姻」」と、憲法24条に基づかない別の「婚姻」(あるいは『~~婚』と称する制度)が併存するということはあり得ない。
このことから、「同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含むと解釈すること」との部分については、あたかも憲法24条を離れた別の形式として存在する「同性婚」という制度を、「憲法24条1項の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点から論じているように見受けられるが、そもそも「憲法24条1項の「婚姻」」が男女間(異性間)に限られている以上は、それ以外の形式の「婚姻」と称する制度が「憲法24条1項の「婚姻」」の下で存在することはできない。
よって、「憲法24条1項の「婚姻」」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かという視点の議論をしようとしているのであればこの文の意味としては理解することが可能であるが、「憲法24条1項の「婚姻」」を離れて別の法形式として「婚姻」(あるいは~~婚)と称する制度が存在することを前提として、その中の一つである「同性婚」という制度を「憲法24条1項の「婚姻」」の中に含めることができるか否かという視点で論じているのであれば、誤りである。
この文は、一段落前の文の「世論調査の結果等」における「価値観の対立」によって、24条1項の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かが変わるかのように論じるものとなっている。
しかし、ここでは法解釈が問われているのであるから、「世論調査の結果等」における「価値観の対立」によって、「婚姻」として扱うことができる人的結合関係の範囲が広がったり狭まったりするような論じ方をすることは妥当でない。
そのような「世論調査の結果等」における「価値観の対立」を反映することによって規範を変更することができる場合とは、国会によって法律の規定を改廃するか、憲法改正によって憲法上の規定を改廃する場合のことである。
裁判所が法解釈を行う際には、国民意識などという漠然とした説明や、「世論調査の結果等」などというその時々の調査によって結論が変わるような資料を根拠として規範の意味を論じるべきではない。
立法府の国会が担うべき問題と、司法府の裁判所が担うべき問題を区別することが必要である。
ウ 以上により、憲法制定当時と比べて、同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況が変化していること(前記1(1)、(3)及び(4))を考慮しても、前記文理を越えて、憲法24条1項が同性愛者の婚姻の自由を保障していると解することはできない。
【筆者】
「憲法制定当時と比べて、同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況が変化していること(…)を考慮しても、」(カッコ内省略)との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、ここで「同性愛者」を取り上げるのであるが、婚姻制度と「性愛」との間に関係性を認めることができないことに注意が必要である。
また、もし「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には、20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
制度を利用する者に対して「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有することを求めることがあれば、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
さらに、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を有する者に対して制度を設け、それ以外の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で差異を設けるものとなるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、もし「同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況が変化していること(…)を考慮して」法制度を設けた場合には、法制度が「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に着目して、それを保護するものとなることから、20条1項後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、そのような制度は、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する者に対して制度を設け、それ以外の「性愛」の思想、信条、信仰、感情や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で差異を設けるものであることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「憲法制定当時と比べて、同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況が変化していること(…)を考慮しても、」などと、特定の「性愛」に着目して法制度を立法することができるかのような前提で論じている点で誤りである。
もう一つ、婚姻制度の内容が「男女二人一組」となっているとしても、それは「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とすることを意味しないし、「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する者を対象とすることを意味しないし、個々人に対して「異性愛」の思想、信条、信仰、感情を持つように求めたり勧めることを意味するものでもない。
もし法制度が「異性愛」という思想、信条、信仰、感情に着目して立法されていた場合には、そのこと自体で違憲となる。
「前記文理を越えて、憲法24条1項が同性愛者の婚姻の自由を保障していると解することはできない。」との部分について検討する。
婚姻制度(男女二人一組)は、個々人の内心に中立的な内容であり、「同性愛者」を称するものであっても婚姻制度の要件に従う形で制度を利用する意思があれば、婚姻制度を適法に利用することが可能である。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、その制度を利用することについて、24条1項の「婚姻をするについての自由」(ここでいう『婚姻の自由』にあたるもの)は保障されている。
よって、ここで「同性愛者」を称する者だけを取り上げて「憲法24条1項が同性愛者の婚姻の自由を保障していると解することはできない。」などと、24条1項の保障を否定していることは誤りである。
このように、個々人の内心を審査して、「同性愛者」を称する者に対してだけ法制度の適用を否定することは、法の支配、法治主義に基づくものではなく、誤っている。
よって、本件諸規定は憲法24条1項に違反するということはできない。
【筆者】
この結論は妥当であるが、判断の過程に上記のような誤りがある。
この「(2) 本件諸規定は憲法24条1項に違反するか」の項目は、全体として非常に理解しづらいものとなっている。
そこで、整理してまとめると、下記のようになる。
=======================================
「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻により与えられる重要な法律上の効果や国民の法律婚尊重の意識等を考慮すると、憲法24条1項の規定の趣旨に照らして尊重されるべき利益である」
↓ ↓
「原告らは、」
「今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障される」
「憲法24条1項の「婚姻」には同条項の拡張解釈ないし類推適用により同性婚を含むものと解される」
「同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、婚姻の自由を侵害するものであり、同項に違反する」
「と主張する。」
↓ ↓
「憲法24条1項が同性愛者間の婚姻の自由を保障するものといえるか否かについて検討する」
↓ ↓
「起草過程において」「「男女」及び「両性」という文言が現れている」
↓ ↓
「制定過程を検討しても、」「日本国憲法制定時の憲法24条の主な目的は、家族関係における自由と平等の実現、その中でも戸主制度の廃止による女性の地位向上と家族の保護であり、同性婚について議論が行われておらず、」
「昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められない」
↓ ↓
「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかった」
↓ ↓
「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているもの」
「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではない」
(当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない)
↓ ↓
「婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得るものであり、こうした社会通念等の変遷により同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」
↓ ↓
「同性婚に対する価値観の対立が存する」
↓ ↓
「諸外国において同性婚を法制度化している国が相当数あり、」
「わが国においても多くの地方自治体においてパートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動きや同性愛に対する偏見を除去しようとする動きがある」
↓ ↓
「反対の意見の中には婚姻は依然として男女間の人的結合であるとのこれまでの伝統的な理解に基づくものと考えられる」
「我が国における世論調査の結果等によれば、同性婚の導入に反対の意見を有する者が60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と拮抗していることをはじめ、全体的に依然相当数おり、」
↓ ↓
「婚姻についての社会通念や価値観が変遷しつつあるとは言い得るものの、同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難い」
↓ ↓
「憲法制定当時と比べて、同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況が変化していること」「を考慮しても、」
「文理を越えて、憲法24条1項が同性愛者の婚姻の自由を保障していると解することはできない。」
「少なくとも現時点においては」「憲法24条1項の「婚姻」に」「同性婚を」「含むと解釈することは」「困難」
↓ ↓
「婚姻は、」「当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度」(上記②~④)
(自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について)(国がこれを公証するもの)(上記①)
↓ ↓
「婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、」
「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではない」
↓ ↓
「これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。」
↓ ↓
「本件諸規定は憲法24条1項に違反するということはできない。」
↓ ↓
「原告らの上記主張を採用することができない。」
=======================================
しかし、この論旨には誤りがある。
婚姻制度(男女二人一組)は個々人の内心に中立的な内容であるから、「同性愛者」を称する者も等しく利用することができる。
よって、「憲法24条1項が同性愛者の婚姻の自由を保障していると解することはできない。」のように、24条1項が「同性愛者」を称する者に対してだけ婚姻制度(男女二人一組)を利用する自由を保障していないかのように述べていることは、誤りである。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的としておらず、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではなく、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度はそもそも「性愛」に関知していないのであり、「同性愛に対する偏見を除去しようとする動き」や「同性愛者に対する知見や国民の意識・社会状況」のように「同性愛」に対する理解が進めば、婚姻制度の内容を変えることができるかのように述べていることも誤りである。
24条1項の「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるか否かは、「社会通念」や「社会的承認」、「価値観」によって変わるかのように述べている。
しかし、法解釈は条文に記された文言の意味を検討することによって結論が導き出されるのであり、その時々の国民の意識を基準として「社会通念」や「社会的承認」があるとかないとか述べることによって、結論が変わるようなものではない。
そのような、国民の意識を基準として法令の改廃を行うことは、政治部門の役割であり、司法府が担う役割ではない。
まして、国民の意識によって条文の意味が左右されるようなことがあってはならないし、そのような形での法適用は「法の支配」、「立憲主義」、「法治主義」を損なわせるものであり、正当化することはできない。
(3) 本件諸規定は憲法13条1項に違反するか
原告らは、同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、同性カップルの婚姻の自由を侵害し、家族の形成という人格的自律権を侵害するものであり、憲法13条に違反すると主張する。
【筆者】
「同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、」との記載がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的して、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、その目的を達成するための手段として整合的な要素によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
そして、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
「同性カップルの婚姻の自由を侵害し、家族の形成という人格的自律権を侵害するものであり、憲法13条に違反すると主張する。」との記載がある。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を一つの単位として、その「婚姻の自由を侵害」としているが、憲法上の規定を適用できるか否かを論じるための前提となる理解に誤りがある。
憲法は「個人の尊厳」を定めており、自然人は「個人」として扱われる。
そのため、憲法上の権利の存否を検討するにあたっても、法主体としての地位を認められている「個人」を単位として、その者の「権利」や「自由」について検討することになる。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「個人」ではなく、法主体としての地位を有していないため、憲法上の権利の適用があるか否かを検討することのできる単位ではない。
そのことから、「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」を取り上げて、それを単位として考えて憲法上の権利の適用があるか否かを論じようとしている点が誤りである。
これとは別に、個々人が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めている場合について検討する。
「婚姻」は、生殖に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たす人的結合関係を対象としており、その趣旨を満たさない人的結合関係については「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
「家族の形成という人格的自律権を侵害するものであり、」の部分について、ここでいう「家族」の意味が社会学的な意味の「家族」を意味するのであれば、13条の「幸福追求権」や21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
しかし、法学的な意味の「家族」であれば、それは「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的によって形成されており、それと同一の目的を共有する形で、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で規律される枠組みであり、「夫婦」と、「親子」による「血縁関係者」を指すものである。
これは、立法目的を達成するための手段として予め枠組みを定めているものであることから、個人の意思によって自由に変更することができるというものではない。
そして、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」が「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、法学的な意味の「家族」には含まれない。
これに当てはまらない関係性については、そもそも「家族」ではないため、「家族の形成」という何らかの自由や権利を主張することはできない。
また、この「家族」の枠組みに含まれないとしても、それは単に優遇措置がないというだけであり、この「家族」の枠組みによって個々人に対して何らかの具体的な侵害を引き起こすというものではないため、「国家からの自由」という「自由権」によって侵害を排除しなければならないという場面とは性質が異なる。
よって、国家から個人に対する具体的な侵害行為がない事柄については、そもそも「人格的自律権」によって排除しなればならないとする侵害行為を見出すことはできず、「人格的自律権を侵害するもの」とはいえない。
その他、13条を根拠として特定の制度の創設を求めることはできない。
上記のとおり、婚姻は、相手方又は行政機関等との間で、有効となる種々の権利義務を発生させる(上記②、④)ものであり、婚姻の有無ひいては婚姻制度を利用できるか否かは、その者の権利義務に影響を与えるものである。また、婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するものであるが(上記③)、このように永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度しか存在しない。我が国では、家族を基本的な生活の単位として様々な制度が組み立てられており、上記②④で記載した公的な権利関係に留まらず、私的な関係においても家族であることが公証されることで種々の便益を得られる仕組みが多数存在する(例えば、医療における家族への説明や同意権、不動産購入、賃貸借又は保険等の各種契約の審査における家族状況の確認、家族を共同名義人や保険等の便益の受取人に指定できること、職場の異動等における家族の状況への配慮、同じ墓の利用の可否等の冠婚葬祭への参加。以上につき甲A554、原告ら本人)。このような公的にもたらされるわけではない事実上の利益も、公証(上記③)の効果として一律に発生するものであり、これを発生させる基本的な単位であるはずの婚姻ができず、その効果を自らの意思で発生させられないことは看過しがたい不利益であると認められる(以下、婚姻の効果である公証により受けられるようになる社会生活における各種便益を総称して「公証の利益」という。)。以上からすれば、婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益と認められる。
【筆者】
「婚姻は、相手方又は行政機関等との間で、有効となる種々の権利義務を発生させる(上記②、④)ものであり、婚姻の有無ひいては婚姻制度を利用できるか否かは、その者の権利義務に影響を与えるものである。」との記載がある。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
具体的には、「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という立法目的を達成するために、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して法的効果や一定の優遇措置を講じることにより、その目的の実現を目指すものである。
ここでいう「相手方又は行政機関等との間で、有効となる種々の権利義務を発生させる」という部分についても、これらの「種々の権利義務」は先ほど示した立法目的の実現に資することを理由として設定されているものであり、また、それらの「種々の権利義務」はその立法目的の実現に資する形でのみ設定することが正当化されるものである。
「婚姻の有無ひいては婚姻制度を利用できるか否かは、その者の権利義務に影響を与えるものである。」との部分であるが、そこでいう「婚姻」や「婚姻制度」とは、上記に示したように、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものを指していることになる。
この枠組みを利用しているか否かや利用できるか否かについて、「その者の権利義務に影響を与える」と述べている部分は、その通りであり、当然のことを説明するものということができる。
「婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するものであるが(上記③)、このように永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度しか存在しない。」との記載がある。
この「永続的な精神的及び肉体的結合」の部分は、最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明している部分から抜き出したようである。
しかし、この最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
これは、「両性」の部分は「男女」であること、「永続的な」の部分は死亡するまで有効期限がないこと、「精神的及び肉体的結合を目的」の部分は「相互の協力」や「貞操義務」を負うこと、「共同生活を営む」の部分は「同居義務」を負うことに対応するからである。
この判決は、2(4)イの第三段落の第二文で「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので前記精神的及び肉体的結合の対象を定めるものである」と述べていることから、「精神的及び肉体的結合」の部分が「恋愛・性愛」に対応するものと考えているようである。
しかし、そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人が「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かや、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に従って制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として一般的・抽象的にその間で自然生殖の可能性のある「一人の男性」と「一人の女性」を法的に結び付け、その関係に対して一定の優遇措置を行うことにより、立法目的の達成を目指すものとしており、この法的な枠組みには「相互の協力」、「貞操義務」、「同居義務」が設定されているが、個々人の「恋愛・性愛」の有無や、「恋愛・性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかなど、一切関知していない。
これは、そもそも国家権力が人の内面に存在する「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に対して干渉するものとして法制度を立法する必要そのものが存在しないからである。
また、もし個々人の内面である「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情に干渉する法律を立法した場合には、19条の「思想良心の自由」や、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
他にも、特定の「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的して法制度を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、この判決が「婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(…)、国がこれを公証するものである」(カッコ内省略)と述べている部分は、「精神的及び肉体的結合」の部分を「恋愛・性愛」の意味であるかのように考えて説明するものとなっているが、そもそも法制度が「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護するものとして存在しているとしてもそれが許されるかのような前提の下に論じていること自体が誤りとなる。
【参考】私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
よって、この判決は、「婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(…)、国がこれを公証するものである」と述べて、「婚姻」は「自己が永続的な」「恋愛・性愛」「の相手として選んだ者との間の共同生活について(…)、国がこれを公証するものである」と考えているようであるが、「婚姻」という概念に対する理解を誤ったものである。
「このように永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度しか存在しない。」との部分について検討する。
そもそも「婚姻制度」は、この判決がいう意味での「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度」ではない。
なぜならば、この判決のいう「精神的及び肉体的結合」は「恋愛・性愛」に対応するものと考えているようであるが、国が「恋愛・性愛」という個人の思想、信条、信仰、感情などの価値観に対して干渉するような制度を設ける必要はないし、個人の価値観に対して干渉するような制度を設けてはならないからである。
法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならず、「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度が存在した場合には、それ自体で憲法に違反することになる。
よって、「婚姻制度」をあたかも「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度であるかのような意味で、「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度」と論じていることは、誤りである。
「我が国では、家族を基本的な生活の単位として様々な制度が組み立てられており、上記②④で記載した公的な権利関係に留まらず、私的な関係においても家族であることが公証されることで種々の便益を得られる仕組みが多数存在する」との記載がある。
「②④で記載した公的な権利関係」の部分については、「婚姻及び家族」の枠組みについては、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象とするものとなっている。
その他の「権利関係」や「私的な関係」について、国(行政府)は民法や戸籍法における「婚姻」の問題ではなく、具体的な一つ一つの政策の当否の問題や、私人間の契約の問題であると述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
当サイトもこの訴訟で論点となっている民法や戸籍法上の「婚姻」の問題と、これらの別の法的地位の問題は切り分けて論じるべきであると考える。
なぜならば、現在の制度において政策的に「婚姻している者(既婚者)」に対して④のような「権利関係」を与えることが妥当であると判断されているだけであり、婚姻制度の枠組みを変更した場合には、それらの内容を「婚姻している者(既婚者)」に対して与えることが政策的に妥当でないと判断され、結果としてそれらの内容が与えられなくなる場合も考えられるからである。
また、「私的な関係においても家族であることが公証されることで種々の便益を得られる仕組みが多数存在する」との部分であるが、「私的な関係」における「種々の便益」と称するものについては、国の立法政策として感知できる範囲を超えているし、当然、これを婚姻制度の法的な効果として扱うことはできず、裁判所が審査できる範囲を超えるものである。
「例えば、医療における家族への説明や同意権、不動産購入、賃貸借又は保険等の各種契約の審査における家族状況の確認、家族を共同名義人や保険等の便益の受取人に指定できること、職場の異動等における家族の状況への配慮、同じ墓の利用の可否等の冠婚葬祭への参加。」との記載がある。
「医療における家族への説明や同意権」については、医療機関の「家族への説明」や「同意権」についての制度の目的と、その目的を達成するための手段としてどのような範囲の者に対してその制度の利用を認めるかの問題である。
その制度の定める枠組みが、たまたま法学的な意味の「婚姻」や「家族」を対象としていたからといって、その法学的な意味の「婚姻」や「家族」の制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みの当否の問題を超えて、「婚姻」や「家族」の制度の方を変更しなければならないとする理由にはならない。
単に、「医療における家族への説明や同意権」についての制度の目的に従って、どのような人物を対象とするかをその医療機関がその医療機関の事情に応じて決定すればよいものである。
【参考】「病院の面会等は面会制度の問題であって同性婚法制化と関係ないと思われます。」 Twitter
【参考】「それは手術の同意書のあり方の問題にすぎません。」 Twitter
「不動産購入、賃貸借又は保険等の各種契約の審査における家族状況の確認、家族を共同名義人や保険等の便益の受取人に指定できること、職場の異動等における家族の状況への配慮、同じ墓の利用の可否等の冠婚葬祭への参加。」についても、「契約の自由」の範囲の問題であり、国の制度としての「婚姻及び家族」の制度の問題とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
「このような公的にもたらされるわけではない事実上の利益も、公証(上記③)の効果として一律に発生するものであり、これを発生させる基本的な単位であるはずの婚姻ができず、その効果を自らの意思で発生させられないことは看過しがたい不利益であると認められる」との記載がある。
まず、「公的にもたらされるわけではない事実上の利益」と称するものは、婚姻制度の法的な効果を論じるものではないため、裁判所で審査することのできる対象ではない。
これについて論じようとしていることは、公権力によって介入できる範囲を逸脱するものである。
「公証(上記③)の効果として一律に発生するものであり、」との部分であるが、私人と私人の契約の問題については、それぞれの私人がどのようなサービスを展開し、どのような契約を行うかの問題であるし、そのようなサービスが行われることを国家によって強制されているものではないため、婚姻の効力の問題と共に論じることは不適切である。
「これを発生させる基本的な単位であるはずの婚姻ができず、」との部分であるが、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象としており、その枠組みを設けている趣旨に賛同する私人が、その婚姻制度に結び付ける形でサービスを展開しているだけであり、その私人が「婚姻していない者(独身者)」に対してはそのサービスを行っていないとしても、その事実をもって婚姻制度の枠組みの方を変えなければならないとする理由にはならない。
そのため、「これを発生させる基本的な単位であるはずの婚姻」と述べているが、そもそも婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられており、その趣旨に賛同する私人が勝手にその制度に結び付けたサービスを展開しているだけであり、公的な制度としての憲法上・法律上の「婚姻」は、「これを発生させる基本的な単位である」とはいえない。
そのため、私人が行っているサービスについて、あたかもそれが公的な国の制度と結び付いて切り離すことはできず、私人が行っているサービスまでもが、憲法上・法律上の婚姻制度の立法目的の中に含まれているかのような論じ方となっていることは誤っている。
「婚姻ができず、」との部分であるが、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従う形で、婚姻制度を適法に利用する意思があるのであれば、婚姻することは可能である。
よって、「婚姻ができず、」のように婚姻ができないことを前提としていることも妥当でない。
「その効果を自らの意思で発生させられないことは看過しがたい不利益であると認められる」との部分について検討する。
私人が行っているサービスについては、「契約自由の原則」の範疇であり、相手方の意思と合致しないのであれば、誰もが「その効果を自らの意思で発生させられない」ものである。
よって、「婚姻している者(既婚者)」であれば、必ず「その効果を自らの意思で発生」させることができることを前提として、それと比較して論じようとしていることは適当でない。
また、「その効果を自らの意思で発生させられない」というのは、制度は何らかの目的を達成するために存在するのであり、私人間の間でも、その目的の達成に沿わない場合には制度の対象としないということは当然のことである。
そのため、もともと「その効果を自らの意思で発生」させられることが保障されているというものではない。
よって、それがあたかも保障されているかのような前提で、それと比較して「その効果を自らの意思で発生させられないこと」について「不利益」を論じようとすることも妥当とはいえない。
「看過しがたい不利益であると認められる」の部分についても、そもそも「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であり、その状態に何らの「不利益」と称されるような状態も存在しないにもかかわらず、その「婚姻していない者(独身者)」の状態について「看過しがたい不利益である」などと「不利益」があるかのように論じている点も誤っている。
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益と認められる。」との記載がある。
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、」との部分について検討する。
ここに記載された「婚姻制度」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みのことである。
その「婚姻制度」の枠組みに従う形で制度を利用することを望むのであれば、誰でも婚姻することができる。
これについては、たとえ「同性愛者」を称する者であっても婚姻制度を利用することは可能である。
「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定すること」の部分についても、そこでいう「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みのことであり、この制度の枠組みに従う形で制度を利用するかしないか、この制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で誰と制度を利用するかを「自己の意思で決定すること」は可能である。
しかし、婚姻制度の枠組みに当てはまらない人的結合関係については「婚姻」とすることはできないのであり、それを「するかしないか」や「誰とするか」を「自己の意思で決定すること」のような形で、婚姻制度の枠組みを超える関係を「婚姻」として扱うように求めることができることにはならない。
それについて、「人格的利益と認められる。」と述べているのであれば誤りである。
「国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、」の部分について検討する。
この「(前記1(4)エ)」に記された内容は、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「男女二人一組」の形で設けられていることを前提としており、その枠組みの妥当性に基づく形で形成されている「国民の意識」である。
それが「重要」とされているとしても、それは「男女二人一組」の形であることの妥当性によって形成されているものであり、その「重要」と認識されていることを根拠として制度の枠組みを変えるべきことの理由になるわけではないことに注意が必要である。
「同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益と認められる。」との部分であるが、この「人格的利益」の文言が何を根拠として導かれているのか検討する必要がある。
24条2項の「個人の尊厳」から導かれているのであれば、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合には、「人格的利益」として尊重される場合が考えられる。
これは、たとえ「同性愛者」を称するものであるとしても、他の者と同様に扱われるものである。
しかし、これが「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない場合については、24条2項の「個人の尊厳」を適用することはできないため、「人格的利益」を検討することはできない。
ただ、24条2項の「個人の尊厳」の文言から「人格的利益」を述べようとしているのであれば、この13条について述べている項目で論じるのは不自然である。
この一段落の構成は非常に読み取りづらいものとなっている。
婚姻制度についての繰り返しになっている部分を省略するなどしてまとめると、下記のようになる。
「婚姻の有無ひいては婚姻制度を利用できるか否かは、その者の権利義務に影響を与える」
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項」
↓ ↓
「家族として公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度しか存在しない。」
↓ ↓
「公的にもたらされるわけではない事実上の利益も、」「発生させられないことは看過しがたい不利益であると認められる」
↓ ↓
「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益と認められる。」
このようにまとめると、論理的な誤りも見つけやすくなる。
まず、「同性愛者」を称する者でも、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たし、婚姻意思を有しているのであれば、適法に婚姻制度を利用することが可能である。
そのため、「婚姻制度を利用できるか否か」については、利用できるということができる。
「家族として公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度しか存在しない。」の部分についても、「家族」とは法学的には24条2項の「婚姻及び家族」の「家族」であり、これは「婚姻」と共に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成されている枠組みであるから、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象としたものである。
そのため、「家族」の中に含まれる場合と含まれない場合が存在することは「家族」の枠組みが定められている時点で初めから予定されていることであり、その「家族」の中に含まれず、「家族」として認められない関係があることも、それは当然のことである。
それは、「家族」とすることのできる範囲そのものが、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として形成された枠組みであることによるものである。
「公的にもたらされるわけではない事実上の利益も、」「発生させられないことは看過しがたい不利益であると認められる」との部分についても、そもそもこれは「婚姻」の法的な効力の問題ではなく、私的な関係におけるサービスの問題であるから、これを「立法目的」と「その立法目的を達成するための手段」として定められている公的な国の制度の方を変えなければならないとする理由にはならないし、そもそも憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、その状態に「不利益」がないにもかかわらず、その状態を「不利益であると認められる」と評価するしていること自体が誤りである。
「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益と認められる。」との部分について、そもそもそこでいう「婚姻」とは何かが問われることになる。
そして、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であるから、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものである。
そのことから、この「男女二人一組」の制度を「同性愛者」を称する者が利用することを望むのであれば、それが妨げられるということはない。
これとは別に、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかどうかについては、「同性間の人的結合関係」はその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて、ここでいう「人格的利益」などを主張することはできないことに注意が必要である。
しかしながら、上記②~④のとおり、婚姻とは当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度であり、当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではなく、婚姻を基礎とした家族の形成も当事者の意思によりその要件や効果が全て定まるものではない。このように婚姻に関して、法律により要件が定められている理由は、婚姻自体が国家によって一定の関係に権利義務を発生させる制度であることからの当然の帰結であって、同性愛者の婚姻の自由や婚姻による家族の形成という人格的自律権が憲法13条によって保障されている憲法上の権利とまで解することはできない。したがって本件諸規定は憲法13条に違反しない。
【筆者】
「上記②~④のとおり、婚姻とは当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度であり、」との記載がある。
おおむねその通りであるが、この説明の順番に注意が必要である。
法学的な視点からは、「婚姻」とは「各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度」であり、「当事者の意思」とは、その「法律上の制度」を利用するか否かの「意思」をいう。
しかし、この判決は「婚姻」の意味を、文学的な意味の「精神的及び肉体的結合」という価値観であるかのように述べている部分が見られ、法学的な意味を離れていることがある。
そのため、ここで「当事者の意思を前提に」という文を始めにもってきていることについても、その文学的な意味の「精神的及び肉体的結合」という価値観を持つように勧めるような意味を含めるものとなっていないか注意が必要である。
この判決の内容は、全体として婚姻制度を利用する者の価値観に対して介入することを前提とするような表現が見られることから、この部分についてもそのような意図を込めるものとなっている場合には、法律論として妥当なものではない。
「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではなく、婚姻を基礎とした家族の形成も当事者の意思によりその要件や効果が全て定まるものではない。」との記載がある。
この部分は、その通りということができる。
「婚姻」や「家族」の制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って形成された枠組みであり、「その要件や効果」はその目的を達成するための手段として整合的な形で定められるものである。
よって、「婚姻」や「家族」の制度は「当事者の意思」によって「その要件や効果」を決めることができるわけではない。
「このように婚姻に関して、法律により要件が定められている理由は、婚姻自体が国家によって一定の関係に権利義務を発生させる制度であることからの当然の帰結であって、」との記載がある。
この部分であるが、「婚姻」に「法律により要件が定められている」理由を、「婚姻自体が国家によって一定の関係に権利義務を発生させる制度である」と述べているだけであり、ほとんど説明にはなっていない。
また、この文は理解が難しいが、前後関係を逆にして考えると理解しやすくなる。
「婚姻自体が国家によって一定の関係に権利義務を発生させる制度であることから」、「当然の帰結」として「婚姻に関して、法律により要件が定められている」
ただ、この前後の文について「当然の帰結」などと表現しても、明確な意味のある文章にはならない。
「同性愛者の婚姻の自由や婚姻による家族の形成という人格的自律権が憲法13条によって保障されている憲法上の権利とまで解することはできない。」との記載がある。
まず、「同性愛者」の部分であるが、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」についても、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って制度を利用する意思があるのであれば、婚姻制度を利用することができる。
また、憲法24条1項の「婚姻をするについての自由」についても、「同性愛者」を称する者であるとしても尊重されることに違いはなく、婚姻制度(男女二人一組)を利用するための「婚姻をするについての自由」を有していることになる。
よって、ここで「婚姻の自由」としている部分についても、憲法24条1項の「婚姻をするについての自由」の意味であれば、「同性愛者」を称する者であるとしても憲法24条1項によって保障されているということができる。
これとは別に、「憲法13条」によって、ここでいう「婚姻の自由」が保障されているか否かであるが、これはすべての人に対して保障されていないということができる。
また、「憲法13条」によって、ここでいう「婚姻による家族の形成」が保障されているか否かについても、すべての人に対して保障されていないということができる。
ここでは「同性愛者」を称する者だけが、「憲法13条」によって保障されていないかのような文面となっているが、「同性愛者」を称する者だけでなく、すべての人が保障されてはいないことになる。
もし、法制度が個々人の内心を審査して、「同性愛者」を称する者にだけ何らかの権利や自由を保障しないことになれば、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
また、個々人の思想、信条、信仰、感情によって区別することになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのような措置は許されないのであり、ここで「同性愛者」を称する者を取り上げ、その者に対してだけ「憲法13条」によって保障されていないかのような説明となっていることは、不適切である。
もう一つ、「婚姻」や「家族」の制度によるものではなく、個々人が人的結合関係を形成することが「憲法13条によって保障されている」か否かであるが、「憲法13条」や憲法21条の「結社の自由」などの「自由権」(国家からの自由)によって保障されていると考えられる。
「したがって本件諸規定は憲法13条に違反しない。」との記載がある。
結論としてはその通りということができる。
しかし、上記のように判断の過程に妥当でない部分があるため、この結論部分だけを見て判断の内容が適正なものであったということにはならない。
その他、13条によって特定の制度を国家に対して求めることができるか否かについて、国(行政府)の主張が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……このように,被告は,現行の法制度が憲法の要請に従って構築されたものであることを前提に,かかる法制度を超える上記の新たな制度の創設を求める権利が憲法13条における自己決定権に含まれるものではないと主張しているのであって,国家の制度を前提にするか否かによって憲法上の保障に値するか否かが決定されると主張しているのではない。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。しかるところ,上記見解のいう「婚姻の自由」が,性別を問わず配偶者を選択する自由を含む権利であるとすると,それは,「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性の者を婚姻相手として選択できることを含む内容の法制度の創設を求めるものにほかならない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P9~12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。
そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。
(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13 条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)で述べたとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,人は,一般に,社会生活を送る中で,種々の かつ多様な人的結合関係を生成しつつ,生きていくものであり,当該人的結合関係の構築,維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが,そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと,そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは,少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。
前記2で述べたとおり,婚姻が一定の法制度を前提としている以上,「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し,故なくこれを妨げられないという「婚姻をするについての自由」は,法制度を離れた生来的,自然権的な自由権として憲法で保障されているものと解することはできない。前記1で述べたとおり,憲法24条1項は,婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とし,同性間の人的結合関係を対象とすることを想定しておらず,同条2項も,飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提としてこれを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり,これを受けて定められた本件規定も,婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするものであることを前提に定められている。
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
このように、13条を根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることはできない。
この段落は全体として非常に読み取りづらい内容となっているため、下記のように整理する。
「婚姻自体が国家によって一定の関係に権利義務を発生させる制度である」
↓ ↓ (当然の帰結) ↑ (理由)
「婚姻に関して、法律により要件が定められている」
↓ ↓
「婚姻とは」「各種法律によりその要件が定められ、」「当事者の意思を前提に」「これを満たしたときに一律に権利義務が発生する」「法律上の制度」
↓ ↓
「当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではなく、婚姻を基礎とした家族の形成も当事者の意思によりその要件や効果が全て定まるものではない。」
↓ ↓
「同性愛者の婚姻の自由や婚姻による家族の形成という人格的自律権が憲法13条によって保障されている憲法上の権利とまで解することはできない。」
↓ ↓
「したがって本件諸規定は憲法13条に違反しない。」
ここでいう「婚姻の自由」とは、最高裁判決の「婚姻をするについての自由」にあたるものと思われるが、これは24条1項によって保障されるものであり、13条で保障されるものではない。
ここでは、「同性愛者の婚姻の自由」のように「同性愛者」を称する者を取り上げるのであるが、これは「同性愛者」を称する者に限られるものではなく、すべての人についていえることである。
法的な意味おいては特に間違いとはいえないが、不必要に「同性愛者」を取り上げることは、「同性愛者」を称する者にだけ何らかの権利などを保障しないというものであったり、「同性愛者」を称する者にだけ法制度の適用を否定するものであるかのような誤解を生じさせることになるため、避けるべきである。
法律論としては、個々人の内心に立ち入って、「同性愛者」を称する者であるかどうかを論じる必要そのものがないことを押さえる必要がある。
(4) 本件諸規定は憲法14条1項に反するか
ア 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解される(最高裁判所判所昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、同裁判所昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁、同裁判所平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)。
【筆者】
まず、最高裁判決の例を挙げている(カッコ)内で「最高裁判所判所」と記載されており、「判所」の文字を二回繰り返してしまっている点は、記載する上でのミスと思われる。
次に、ここで示された判決は、下記の通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和39年5月27日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決 (PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決 (PDF) (再婚禁止期間大法廷判決)
この14条の「平等原則」を判断する際に必要となる視点は、下記の通りである。
◇ 「法適用の平等」と「法内容の平等」の違い
14条の「平等原則」における審査では、「法適用の平等」と「法内容の平等」を分けて考える必要がある。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues
vol.27】 2022/09/25
◇ 「法内容の平等」の審査
「法内容の平等」については、➀「区別(差別)」の存否と、②「区別(差別)」が存在した場合における「合理的な理由」の存否が問われることになる。
そして、②の「合理的な理由」の内容については、「立法目的」とその「達成手段」が問われることになる。
➀ 「区別(差別)」が存在するか否か
② 「区別(差別)」が存在する場合にその区別に「合理的な理由」が存在するか
「合理的な理由」の判断方法
・「立法目的」の合理性
・「立法目的を達成するための手段」の合理性
この判決の内容は、➀の「区別取扱い」が存在するか否かという判断から誤っているため、②の判断を行おうと試みている論旨についても、全面的に誤っている。
もう一つ、「婚姻及び家族に関する事項」について14条の「平等原則」によって区別の合理性が審査されることは考えられるが、そもそもそこでいう「婚姻」の枠組みそのものについては憲法上の規定である24条で具体的に「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言によって一夫一婦制(男女二人一組)が定められていることから、これに対しては14条の「平等原則」で審査することはできない。
憲法上で具体的な基準となる規範が定められている事柄である以上は、その枠そのものについては、一般に14条の「平等原則」によって審査できる対象ではないからである。
よって、これについて14条の「平等原則」の審査が及ぶかのような前提で論じ始めていることについても、妥当であるとはいえない。
そして、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるから、婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解される(最高裁判所平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)。
【筆者】
ここで示された判決は、下記の通りである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決 (PDF) (再婚禁止期間大法廷判決)
最高裁判決では「このような観点から,」との文言があるが、この判決では抜けている。
最高裁判決では「第一次的には国会」となっているが、この判決では「第一次的に国会」となっており、「は」が抜けている。
最高裁判決と対応するものは前半部分だけであり、その後、この東京福岡判決の「であるから、」の文言以下は、この判決に対応するものではない。
「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解される」との部分を検討する。
まず、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」とすることはできないし、「親子」や、「親子」を基本とした関係である「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば、「婚姻及び家族に関する事項」には含まれない。
そのため、「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱い」のように、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれることを前提として「区別取扱い」の合理性を判断できるかのように述べている部分から誤っている。
イ 本件諸規定による区別取扱いの有無について
前記第2の1(3)のとおり、本件諸規定の下では同性間の婚姻は認められておらず、その結果、同性愛者は婚姻制度を利用することができないのであるから、本件諸規定は、同性愛者と異性愛者の間において性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。
【筆者】
まず、「本件諸規定の下では同性間の婚姻は認められておらず、」との部分について検討する。
この「同性間の婚姻」という文言は、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができることが前提であるかのように見える。
しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるかどうかというところから検討する必要がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、その目的との関係で「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
これは、もしどのような人的結合関係でも「婚姻」の中に含めることができることになれば、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成できない状態に陥り、「婚姻」という枠組みを設けている意味そのものがなくなってしまうからである。
「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえない。
よって、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」とすることはできない。
そのことから、ここでは「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができることを前提として、「本件諸規定の下では」でそれが認められていないとの論じ方となっているように見えるが、そもそも「本件諸規定」で認められているか否かよりも以前の問題として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。
次に、「本件諸規定の下では同性間の婚姻は認められておらず、その結果、同性愛者は婚姻制度を利用することができない」との部分について検討する。
この「同性愛者は婚姻制度を利用することができない」の部分であるが、妥当でない。
婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従って、婚姻意思を有しているのであれば、「婚姻制度を利用すること」は可能である。
よって、「同性愛者は婚姻制度を利用することができない」との認識は誤りである。
実際に「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している事実は認められるのであり、「同性愛者」を称する者であることを理由として婚姻制度の利用が妨げられているという事実はない。
次に、「同性間の婚姻は認められておらず、その結果、同性愛者は婚姻制度を利用することができない」との文脈について検討する。
婚姻制度を利用する場合には「性愛」を抱いて利用しなければならないだとか、「性愛」に基づく形で利用するべきであるとか、「性愛」に基づく形で制度を利用することこそが正当であるという価値観によって、「同性愛者」を称する者は「男女二人一組」の婚姻制度を利用してはならないだとか、利用するべきではないだとか、利用することは正当でないと考え、「同性愛者は婚姻制度を利用することができない」と述べているのであれば、それは「同性愛者」を称する者に対して特定の価値観を押し付けるものであり、不当な主張である。
法制度は個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的でなければならないのであり、特定の価値観に基づいて制度を利用することを求めるようなことがあってはならないし、勧めるようなこともしてはならない。
その他、ここでは「婚姻」と「性愛」を結び付けて考えていることから、現在の「男女二人一組」の婚姻制度があたかも「異性愛」を保護することを目的としており、その内容も「異性愛者」を称する者を対象としているものであると考えた上で、それに対する形で「同性愛者」を称する者にも同様の制度を設けるべきであるとの主張をしていることが考えられる。
しかし、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その内容も一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものとして形成されているだけであり、それは「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とするものではないし、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であることを意味するものでもない。
また、法制度が「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的するものとなっていた場合には、そのこと自体で憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、個々人に「性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱くことを求めたり、勧めるようなものとなっている場合には、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、「性愛」以外の他の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で差異を設けることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、法制度が「性愛」というような特定の思想、信条、信仰、感情と結び付く形で立法されている場合には、そのこと自体で既に憲法違反となる。
よって、「同性愛者」のように、個々人を「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという視点で人を区別して論じるようなことはするべきではない。
また、その「性愛」に従う形で法制度を利用するべきであるとの特定の価値観を前提に論じてはならない。
さらに、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を満たすための制度が存在するか否かを問うことそのものが不適切である。
そのことから、「同性間の婚姻は認められておらず、その結果、同性愛者は婚姻制度を利用することができない」のように、個々人の内心に基づいて人を分類して「同性愛者」を称する者を取り上げたり、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情と法制度を結び付けて論じること自体が誤った前提に立った論じ方をするものということができ、そのような前提に立った認識そのものが誤りである。
「本件諸規定は、同性愛者と異性愛者の間において性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものとしており、「男女二人一組」が対象となっている。
また、これは「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とするものではないし、個々人が「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かや、「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合に、それがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、そもそも婚姻制度は「性愛」に着目して設けられたものではないし、個々人の「性愛」には関知していないのであり、「性愛」がどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものに基づいて「区別取扱い」をしているという事実はない。
そのため、「性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。」との理解は誤りである。
さらに、もし個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うような制度が存在していた場合には、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
また、「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して「性愛」に応じて人を区別し、その区別に従って法的な取り扱いを変えた場合には、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
他にも、もし「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在する場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、この判決は「性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。」と述べるのであるが、「性愛」に基づく形で法制度が存在している場合や、「性愛」がどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「区別取扱い」をする制度が存在すれば、そのこと自体が違憲となるのであり、そのような制度が存在するとしても許されるかのように論じていること自体が誤りである。
加えて、ここでは「同性愛者と異性愛者の間において」のように「同性愛者」と「異性愛者」の二分論を前提としており、自然人はすべて「同性愛者」か「異性愛者」かのどちらかに分類できることを前提としているようであるが、「性愛」に着目した分類方法では、他にも「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」「無性愛者」などが議論されているのであり、このような二分論で論じることができるかのように考えていることも誤りということができる。
原告らは、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。しかし、本件諸規定の下では男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができ、同性とは婚姻することができないのであって、男性か女性のどちらか一方につき性別を理由に区別取扱いをするものではない。よって、原告らの上記主張は採用することができない。
【筆者】
この段落では、「性別に基づく区別取扱い」が論点となっている。
「性別に基づく区別取扱い」とは、「男性」と「女性」の性別がある中で、「男性であること」あるいは「女性であること」を理由として、もう一方の性別の者との間で法的な取り扱いに差異を設けた場合に問われるものである。
そして、その「性別」に基づく「区別取扱い」に合理的な理由がない場合には、憲法14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「性別」に基づく「区別取扱い」の有無とは、下記のようなものである。
◇ 男性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
◇ 女性:婚姻している場合に、別の人と重ねて婚姻することはできない
ここに男女の「性別」による「区別」は存在しない。
◇ 男性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
◇ 女性:「異性」と婚姻することができるが、「同性」と婚姻することができない
ここに男女の「性別」による区別取扱いは存在しない。
これについて、国(行政府)の主張も参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF
◇ 男性:「再婚禁止期間」は存在しない
◇ 女性:「再婚禁止期間」が存在する場合がある
ここに男女の「性別」による「区別」が存在する。この場合、その区別の「合理的な理由」の存否を審査することになる。
しかし、今回の事例では、この判決が示している通り、「性別に基づく区別取扱い」が存在する事例ではない。
国(行政府)の下記の主張も参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被告第2準備書面第5の2(2)エ(ア)(34及び35ページ)における主張は、男性と女性の間の差別を念頭に置いたものである。上記主張における「性別」は、原告らが「生物学的な特徴をもとに割り当てられることとされている」性別として主張する性別(法律上の性別)(訴状15ページ)上の男性と女性の区別を主張するものであり、男性間又は女性間の区別は憲法14条1項の「性別」による「差別」には当たらない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
被告は、本件諸規定の下では、同性愛者も異性と婚姻することができるのだから区別取扱いは生じていない、本件諸規定は、性的指向について中立的な規定であり、その結果同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても事実上の結果ないし間接的結果に過ぎないから区別取扱いとはいえない旨主張する。しかし、前記のとおり、婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので前記精神的及び肉体的結合の対象を定めるものであるから、同性愛者が異性と婚姻することができるとしても、そのような婚姻は、婚姻の本質を有さないものであり、同性愛者は異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない以上、婚姻制度を利用することができないことになる。よって、同性同士の婚姻を認めない本件諸規定は、同性愛者が婚姻制度を利用できないという区別取扱いがあり、性的指向が婚姻の本質と結びついている以上、その結果は決して事実上ないし間接的なものということはできないから、被告の上記主張はいずれも採用することができない。
【筆者】
被告(国)の主張として、「本件諸規定の下では、同性愛者も異性と婚姻することができるのだから区別取扱いは生じていない、」を取り上げている。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)を適法に利用する意思があるのであれば、どのような思想、信条、信仰、感情を有する者であるとしても、婚姻制度を利用することが可能である。
当然、ここでいう「同性愛者」を称する者についても、婚姻制度(男女二人一組)を利用することができ、「同性愛者」であることを理由として「区別取扱い」が行われているという事実はない。
これについては、「同性愛者」を称する者だけでなく、「異性愛者」、「両性愛者」、「全性愛者」、「近親性愛者」、「多性愛者」、「小児性愛者」、「老人性愛者」、「死体性愛者」、「動物性愛者」、「対物性愛者」、「対二次元性愛者」、「無性愛者」などを称する者であるとしても同様であり、それらを称する者であることを理由として「区別取扱い」をしているという事実はない。
また、「キリスト教徒」、「イスラム教徒」、「ユダヤ教徒」、「ゾロアスター教徒」、「仏教徒」、「神道を信じる者」、「武士道を重んじる者」、「軍事オタク」、「鉄道オタク」、「アニメオタク」、「アイドルオタク」、「ADHD」、「アスペルガー」、「自閉症」、「サイコパス」、「統合失調症」を称する者であっても同様であり、それらを称する者であることを理由として「区別取扱い」をしているという事実はない。
婚姻制度は特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の内心を審査して区別取扱いをする制度ではなく、特定の思想、信条、信仰、感情に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないからである。
よって、被告(国)の主張は妥当であるということができる。
被告(国)の主張として、「本件諸規定は、性的指向について中立的な規定であり、その結果同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても事実上の結果ないし間接的結果に過ぎないから区別取扱いとはいえない」を取り上げている。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものではない。
そのため、被告(国)の主張として「性的指向について中立的な規定であり、」と述べている部分は、その通りということができる。
「同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても」との部分であるが、「性愛」の思想、信条、信仰、感情については、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであるから、このような個々人の内心の一側面のみを切り取って、その者を「同性愛者」や「異性愛者」などと明確に区別することができるという性質のものではない。
そのため、個々人の内心に基づいて「同性愛者」や「異性愛者」などと分類し、その分類に基づく形で人を区別して考えることができることを前提としていること自体が、法律論を論じるものとして誤っている。
また、「性的指向による差異が生じているとしても」の部分についても、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことから、法律論としては「性的指向」には感知しておらず、それによる法的な「差異」というものは存在しない。
もし何らか法的な「差異」があるとすれば、それは法律が特定の「性愛」を取り上げて制度化し、その他の「性愛」や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情との間で区別取扱いをする制度ということになる。
これは、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、特定の「性愛」を有することを求めたり、前提とした制度とすることは、憲法19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」にも抵触して違憲となる。
さらに、特定の「性愛」を抱く者を優遇し、その他の「性愛」や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で個々人の内心に基づいて区別取扱いをする制度であることになるから、憲法14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
そのため、法的な意味で「性的指向による差異が生じている」ことになれば、その制度自体が特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を優遇したり、その特定の「性愛」を抱く者だけを優遇することを目的とした制度となることから、そのこと自体で違憲となる。
文の最後で、被告(国)が法的な意味において「区別取扱いとはいえない」としていることは妥当であるということができる。
「前記のとおり、婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので前記精神的及び肉体的結合の対象を定めるものであるから、同性愛者が異性と婚姻することができるとしても、そのような婚姻は、婚姻の本質を有さないものであり、同性愛者は異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない以上、婚姻制度を利用することができないことになる。」との記載があるが、誤った認識となっている。
まず、「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」の部分から検討する。
これは、最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明していることを引用しているつもりのようである。
しかし、最高裁判決の文面では、明確に「両性」と書かれている。
この「両性」の文言を「両当事者」の文言に変えていることは、最高裁判決では「男女」であることが前提となっているにもかかわらず、その「男女」の要素を意図的に無視し、「二人一組」の意味に変更することで、この福岡地裁判決が特定の結論を導き出そうとする恣意的な判断があると考えられる。
このような特定の結論を導き出すことを前提として、勝手に文言を変更して用いることは規範の意味を曖昧化させたり、流動化させることとなり、法的安定性を損なわせることとなるため不適切である。
このような手続きを経た上で何らかの結論を導き出そうとしても、その結論は正当化することはできない。
司法判断は、裁判官個人の恣意的な思いを述べる場ではないことを常々心得る必要がある。
次に、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。
◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
そのため、具体的な法制度が存在しないにもかかわらず、直ちに「婚姻」という概念そのものから「婚姻の本質」と称する説明が根拠もなく導き出されるという性質のものではない。
そして、婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いを行う制度ではないことから、婚姻制度の要件を満たした上で、婚姻意思をもって適法に制度を利用しているのであれば、利用者がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているとしても、「婚姻の本質」と称している法律関係を形成することが可能である。
これについて、この判決は「同性愛者が異性と婚姻することができるとしても、そのような婚姻は、婚姻の本質を有さないものであり、」と述べており、「同性愛者」を称する者が婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たし、婚姻意思を有して適法に制度を要しているとしても、「婚姻の本質」を有することにはならないなどと、法律関係を形成することができない者であるかのように扱うものとなっており、不当な説明となっている。
「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の要件に従って、婚姻意思を有して適法に制度を利用しているのであれば、その法的な地位は完全なものであり、それを否定されるいわれはないのである。
実際、「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用している事実は認められる。
「同性愛者は異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない以上、婚姻制度を利用することができないことになる。」との部分であるが、誤りである。
そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「恋愛・性愛」の有無や「恋愛・性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「恋愛・性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度(男女二人一組)の要件を満たし、婚姻意思をもって適法に制度を利用するのであれば、「同性愛者」を称する者であるとしても、「婚姻制度を利用すること」にまったく支障はないのであり、「婚姻制度を利用することができない」との認識は誤りである。
「同性愛者」を称する者にだけ、婚姻制度(男女二人一組)を利用する場合に「異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない以上、婚姻制度を利用することができない」などと、制限を加えることは憲法14条の「平等原則」における「法適用の平等」に違反する判断に他ならない。
このような判断は、「同性愛者」を称する者の法的な地位を不当に貶めるものであり、違法である。
法制度は個々人の内心に対して中立的でなければならず、個々人の「恋愛・性愛」の対象を審査して区別取扱いをするようなことがあってはならないのである。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能である。
上記とは別の視点で、この判決が「婚姻の本質」と称する説明を法学的な意味で理解するのではなく、文学的な意味で理解していると見られる記述があることから、その誤った考え方に合わせる形で、この文面が言いたいであろうことを汲み取って検討する。
この判決がこの一文で言いたいものは、下記のようにまとめることができると考えられる。
「性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもの」
↓ ↓
「性的指向は」「精神的及び肉体的結合の対象を定めるものである」
↓ ↓
「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」
↓ ↓
「同性愛者は異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない」
↓ ↓
「同性愛者が異性と婚姻することができるとしても、そのような婚姻は、婚姻の本質を有さない」
↓ ↓
「同性愛者は」「婚姻制度を利用することができない」
このように、この判決は婚姻制度に対して「恋愛・性愛」という個々人の内心による価値観を持ち込み、それに従う形で婚姻制度を利用しなければならない、するべきものである、することが正当である、と考えた上で、その価値観に従う場合に「婚姻制度を利用することができない」場合があることを論じるものとなっている。
しかし、そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「恋愛・性愛」の有無や、「恋愛・性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「恋愛・性愛」に基づく形で制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「婚姻の本質」と称する説明の「精神的及び肉体的結合」の部分は、この判決が言うような「恋愛・性愛」という人の内心による価値観を示すものではない。
法律上の婚姻制度は「婚姻意思」の存否が問われるが、「恋愛・性愛」の感情を抱くことを求められているわけではないからである。
婚姻制度を利用する場合には、「相互の協力」や「貞操義務」を負うことにはなるが、個人の思想、信条、信仰、感情には関知していないのであり、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を抱くことを求められているわけではないのである。
このような説明は、「社員を大切にしない者は社長になってはならない」などの特定の価値観や格言に過ぎないものを、法制度として後押ししている状態と何ら変わらないのであり、法律論から逸脱するものである。
法制度に対して個人の価値観や人生觀を重ね合わせて論じるべきではない。
また、もし法制度が「恋愛・性愛」というような特定の価値観を保護することを目的とした制度となっていた場合には、憲法20条1後段、3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも法制度を利用する者の「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かを審査することがあれば、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
また、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有するか否かや、「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うような制度を立法した場合には、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
さらに、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護する法制度を立法した場合には、その「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する者を優遇し、その他の思想、信条、信仰、感情を有する者を優遇しないことになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、法制度が「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度として存在していても許されると考えている点で誤りである。
また、その中でも特定の「恋愛・性愛」の思想、信条、信仰、感情を優遇する制度となっているとしても、それも許されるかのように考えている点でも誤りである。
よって、「婚姻の本質」と称する説明の意味を読み違えているし、「同性愛者」は「婚姻制度を利用することができないことになる。」との結論を導き出すまでの判断の過程や、その結論も誤っていることになる。
ここでは最高裁判決の示した「婚姻の本質」と称する説明の中で使われている「両性」の文言を「両当事者」に変えている。
ここで「両当事者」に変えてもよいと考えている認識の背景には、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」があると考えられる。
【参考】私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
「同性同士の婚姻を認めない本件諸規定は、同性愛者が婚姻制度を利用できないという区別取扱いがあり、性的指向が婚姻の本質と結びついている以上、その結果は決して事実上ないし間接的なものということはできない」との記載がある。
「同性同士の婚姻を認めない本件諸規定は、同性愛者が婚姻制度を利用できないという区別取扱いがあり、」との部分について検討する。
このような認識を抱いている背景には、婚姻制度が「男女二人一組」となっていることは、「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としており、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であり、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものであるという前提認識があると考えられる。
そして、「性愛」がどのような対象に向かうかには優劣がないことから、「異性愛」だけでなく「同性愛」も同様に保護するべきであり、「異性愛者」だけでなく「同性愛者」を対象とした制度を設けるべきであり、「同性愛」に基づいて制度を利用することを求めても許されるとの認識が導かれていると考えられる。
しかし、婚姻制度は「性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかについて一切関知していないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
また、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在した場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に基づいて制度を利用することを求める場合には、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を抱く者との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、婚姻制度と個々人の内心に関わる「性愛」という思想、信条、信仰、感情を結び付けるものとなっている場合には、そのこと自体が憲法違反となる。
そのことから、「同性同士の婚姻を認めない本件諸規定は、同性愛者が婚姻制度を利用できない」のように、個人の内心の思想、信条、信仰、感情と、法制度を結び付けて考えている部分が誤りである。
そのため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度は利用することができるし、「同性愛者」を称する者を「区別取扱い」をしているという事実はない。
「性的指向が婚姻の本質と結びついている以上、その結果は決して事実上ないし間接的なものということはできない」との記載がある。
しかし、先ほども述べたように、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことから、「性的指向」とは結び付いていない。
また、「婚姻の本質」と称している説明も、これは婚姻制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係を簡潔に示したものであることから、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを示すものではないことから、「性的指向」とは結び付くものではない。
よって、「性的指向が婚姻の本質と結びついている以上、」との認識は誤りである。
「その結果は決して事実上ないし間接的なものということはできない」との部分についても、もともと「区別取扱い」は存在しないし、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度というわけでもないため、論じる必要のないものである。
以上のとおり、本件諸規定は性的指向に基づく区別取扱いをするものであるところ、前記第2の1(1)及び前記1(1)のとおり、ほとんどの場合性的指向は人生の初期か出生前に本人の意思とは関わりなく定まっており、性的指向を自己の意思や精神医学的療法で変えることは困難であることは、医学的に明らかになっており、このような本人にとって自ら選択ないし修正の余地のない事柄をもって婚姻の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要である。
【筆者】
「本件諸規定は性的指向に基づく区別取扱いをするものであるところ、」との記載がある。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しない。
よって、「性的指向に基づく区別取扱いをするものである」との認識は誤りである。
また、もし「性的指向」と称するものに基づいて「区別取扱い」を行っていることになれば、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって人を区別し、その区別に従う形で婚姻制度の利用の可否を決めていることになるが、そもそも個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査することそのものが19条の「思想良心の自由」や20条1項後段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
また、個々人の内心に基づいて人を区別して婚姻制度の利用の可否を決めることになることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
さらに、婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていることになるから、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
よって、「性的指向に基づく区別取扱いをする」ような法制度が存在している場合には、そのこと自体が違憲となる。
この部分では「本件諸規定は性的指向に基づく区別取扱いをするものであるところ、」のように「性的指向に基づく区別取扱いをする」ような制度であることを前提として、その区別のに「合理的な理由」があるか否かを論じていくのであるが、そもそも「性的指向に基づく区別取扱いをする」ような制度が存在するとしても許されるかのように考えている部分が誤りである。
「ほとんどの場合性的指向は人生の初期か出生前に本人の意思とは関わりなく定まっており、性的指向を自己の意思や精神医学的療法で変えることは困難であることは、医学的に明らかになっており、このような本人にとって自ら選択ないし修正の余地のない事柄をもって婚姻の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要である。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、「性的指向」と称するものによって「区別」している事実がないため、「区別を生じさせることに合理的な理由があるか否か」のように、「区別」が存在した場合においてのみ可能な「区別」に「合理的な理由があるか無いか」という審査を行う前提を欠いている。
よって、「合理的な理由があるか否か」を「検討」しようとしていること自体が誤りとなる。
また、婚姻制度の内容が「男女二人一組」となっているとしても、その制度を利用する者がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているのかなど、一切関知していないのであり、当然、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについても同様に関知していないことを押さえる必要がある。
もし婚姻制度が「性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情という個人の内面にのみ存在する精神的なものを保護することを目的として制度を立法している場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、制度を利用する際に「性愛」を有することを求めたり、その中でも特定の「性愛」を有することを求めたり、勧めるようなことになれば、19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
さらに、「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して個々人を「区別」するような制度が存在するのであれば、個々人の内心に基づいて「区別」するものであるから、その時点で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、ここでは「区別」が存在することを前提に、そこに「合理的な理由があるか否か」を検討するものとなっているが、そもそも個々人の内心に基づいて「区別」して法制度の適用の可否を決めるような制度が存在するのであれば、そのこと自体で違憲となり、その制度を無効としなければならないのであって、「合理的な理由」があれば個々人を内心に基づいて「区別」してもよいかのような考え方をしていること自体が誤りである。
この段落は一つの文であるが、非常に読み取りにくいので、下記のように整理する。
「本人にとって自ら選択ないし修正の余地のない事柄をもって婚姻の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要である。」
↓ ↓
「本件諸規定は性的指向に基づく区別取扱いをするものである」
↓ ↓
「医学的に」「ほとんどの場合性的指向は人生の初期か出生前に本人の意思とは関わりなく定まっており、」「自己の意思や精神医学的療法で変えることは困難であることは、」「明らかになっており、」
↓ ↓
『慎重に検討することが必要である。』(二回目)
しかし、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「性愛」に関知していないのであり、それがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものについても同様に関知していない。
よって、「性的指向に基づく区別取扱い」というものが、そもそも存在しない。
そして、「区別取扱い」が存在しないことから、「区別取扱い」が存在することを前提とした「合理的な理由」の存否についても審査することはできないのであり、法的な審査を行うための前提を欠くものである。
そのことから、「性的指向」と称するものが「本人の意思」、「自己の意思」で変えることができるか否かにかかわらず、「区別取扱い」は存在しないし、法的に審査することはできない。
よって、結論として「慎重に検討することが必要である。」と、法的な検討をしようとしている部分も誤りとなる。
ウ 本件諸規定による区別取扱いの合理性の有無について
(ア) 本件諸規定の下では原告らは婚姻をすることができない結果、相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務を発生させることができず(上記②、④)、私的な関係でも公証の利益を得られないものであるところ(上記③)、このような効果は婚姻によってしか発生させることができず、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、原告らは婚姻制度を利用できずこれらを享受する機会を得られないことで重大な不利益を被っているといえる。
【筆者】
タイトルの「ウ 本件諸規定による区別取扱いの合理性の有無について」の部分から検討する。
ここで「区別取扱い」としているものは、この判決が「2(4)イ」のところで「本件諸規定は、同性愛者と異性愛者の間において性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。」と説明している部分を指している。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによって「区別取扱い」をしているという事実はなく、「区別取扱い」があることを前提として、「合理性の有無」を審査しようとしている部分が誤りである。
「本件諸規定の下では原告らは婚姻をすることができない結果、」との記載がある。
まず、「原告ら」の部分であるが、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の基に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「原告ら」を法的な主体としての視点で見れば、一人一人として扱うことが必要となる。
また、民法上の法主体には「自然人」と「法人」があり、自然人の場合は出生によって「権利能力」を取得し、死亡することによって「権利能力」が消滅する。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自然人 Wikipedia
法人 Wikipedia
人の始期 Wikipedia
権利能力 Wikipedia
「原告ら」は自然人であるから、「個人」として「権利能力」の主体となる。
よって、法律論上では、「原告ら」のようにまとめて一つの単位として扱うことができるわけではなく、その者たちが「二人一組」の人的結合関係を形成しているとしても、それは個人と個人が人的結合関係を形成しているという状態として扱う必要がある。
そのため、法的な主体としての地位を認識する場合には、すべて「個人」として扱われることとなる。
そして、その「原告ら」としている中の個々人について「婚姻をすること」ができるか否かであるが、婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能である。
よって、「婚姻をすること」はできることになるから、「本件諸規定の下では原告らは婚姻をすることができない結果、」との評価は誤りとなる。
これとは別に、「同性間の人的結合関係」で「婚姻」することができるか否かを考える。
これについては、婚姻制度は「男女二人一組」となっていることから、これを満たさない以上は「婚姻」することはできない。
注意したいのは、これは「男女二人一組」という条件を満たしていないことが原因となって「婚姻」することができないのであり、決して「同性愛者」を称する者であるとか、個々人の内心が原因となって「婚姻」することができない状態となっているわけではない。
よって、あたかも「同性愛者」を称する者であることを理由として婚姻制度を利用することができないかのように理解することは誤りである。
このことは、たとえこの判決がいう「異性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」という条件を満たしていないのであれば、「婚姻」することはできないことを考えればより明らかである。
「相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務を発生させることができず(上記②、④)、私的な関係でも公証の利益を得られないものであるところ(上記③)、」との記載がある。
まず、「相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務を発生させることができず」の部分であるが、「原告ら」の個々人については、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従うのであれば、婚姻することができるため、婚姻の「相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務を発生させること」はできることになる。
よって、「相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務を発生させることができず」との認識は誤りである。
次に、婚姻制度の要件に従わない形で婚姻制度を利用できるかについては、もちろんできないということができる。
これは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、一定の枠組みを設けることによって、その目的を達成することを目指す仕組みとなっているからである。
その婚姻制度の対象となる場合と、対象とならない場合とがあることは、制度が政策的なものである以上当然のことであるし、そのことは、「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。
次に、「私的な関係でも公証の利益を得られない」との部分であるが、これは、婚姻制度そのものの法的効果を述べるものではないし、「私的な関係」について法律を立法する作用や、法律を執行する作用によって解決することのできる問題ではない。
よって、「私的な関係」を取り上げていること自体が不適切である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
ここでは「私的な関係でも公証の利益を得られないものであるところ(上記③)」と記載されているが、③のところには「③戸籍制度による家族関係の公的認証(戸籍法6条)が与えられるとともに、」と記載されており、「私的な関係」におけるこの判決が「公証の利益」と称しているものについては直接指し示すものではない。
そのため、指し示そうとしている対象が妥当でない。
「このような効果は婚姻によってしか発生させることができず、」との記載がある。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対して、法的効果や一定の優遇措置を与え、その目的の実現を目指すものである。
婚姻制度が法的効果や一定の優遇措置を設けていることは、その目的の実現に資することが理由である。
また、婚姻制度の法的効果や優遇措置を、婚姻制度の対象でない者に対して与えるようなことをすれば、婚姻制度の政策目的の実現を阻害することに繋がり、婚姻制度そのものが成り立たなくなる。
そのことから、それらの法的効果や一定の優遇措置について、ここで「婚姻によってしか発生させることができず、」のように、婚姻制度が一元的に集約する形で定めていることは当然のことである。
「国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、」との記載がある。
「(前記1(4)エ)」の項目に記されているのは、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「男女二人一組」の枠組みを定めている場合において生じている「国民の意識」である。
この「国民の意識」が「婚姻」を「重要」と考えているとしても、それは「男女二人一組」の婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として妥当な内容となっていることが広く支持されていることに由来するものである。
このような枠組みであることから、「国民の意識」が「婚姻」を「重要」と考えているにもかかわらず、この「国民の意識」が「重要」と考えていることを根拠として「男女二人一組」の枠組みを変更した場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという機能を十分に果たさなくなり、「国民の意識」は「婚姻」を「重要」とは思わなくなることが考えられる。
よって、婚姻制度の枠組みそのものを考えるときには、「国民の意識」というような現在の枠組みに依存して成り立っている事情を勘案することは不適切である。
そのため、「併せ鑑みれば、」のように、これを鑑みようとすることは、適切ではない。
「原告らは婚姻制度を利用できずこれらを享受する機会を得られないことで重大な不利益を被っているといえる。」との記載がある。
しかし、「原告ら」としている個人については、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従う形でなお婚姻したいと望むのであれば、婚姻することは可能である。
そのため、「婚姻制度を利用できずこれらを享受する機会を得られない」との認識は誤っている。
「同性間の人的結合関係」が「婚姻」として認められていないことについては、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを対象とする制度であることによるものである。
法制度は政策目的を達成するための手段として定められるものである以上は、制度の対象となる場合とならない場合があることは当然予定されていることである。
また、婚姻制度の対象とならない場合であるとしても、単に優遇措置がないという状態にとどまり、国家から個人に対して具体的な侵害行為が存在するわけではないため、「重大な不利益」と称される状態にあるわけではない。
そのため、これについて「重大な不利益を被っているといえる。」と述べている点も誤りとなる。
憲法は「個人の尊厳」を定めており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、その「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)というべきものである。
その「婚姻していない者(独身者)」の状態で「不利益」がないにもかかわらず、何らかの人的結合関係を形成した段階で「不利益」と称される状態が生じることなどないのである。
よって、裁判所は、その主張を取り上げる際には、現在の婚姻制度の枠組みを超えた新たな制度の創設を国家に対して求めるものに他ならないと認定することが妥当であり、それを「不利益」であるかのように認定することは誤りである。
これは、国(行政府)が下記のように述べている部分に対応するものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
裁判所は、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに何らの「不利益」とされるものはなく、そのままの状態で自信をもってよいことを述べるべきものである。
それにもかかわらず、あたかも「婚姻していない者(独身者)」の状態が「不利益」を受けた存在であるかのような認識を次々に認定し、その主張にお墨付きを与えるようなことをすることは不適切である。
このような認識をもって論じていること自体が、その者が「不利益」を受けた劣位にある存在であるかのようなレッテルを貼り続けることに繋がり、一種の差別を引き起こす原因となるものである。
自身が「不利益」を受けていると訴える者に、安易に賛意を示して「不利益」を受けた存在であるかのように追認することは、本人に対して「不利益」を受けた存在であるとレッテルを貼り続けることに繋がることに気付くべきである。
それを国家権力の行使として行うことは、どれほどに強力なレッテルを貼ることになるかを心得る必要がある。
「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であるにもかかわらず、あたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)であるかのように基準点を移し替えた上で自身の被害を訴える者の論じ方に安易に乗ることは適切であるとはいえない。
正しくは、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であり、その状態は何らの「不利益」と称される状態にはないが、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、その過大な優遇措置に関する規定が14条の「平等原則」に違反することになって失効し、その格差が是正されると論じることが適切である。
よって、この判決が「婚姻している者(既婚者)」を基準(スタンダード)であるかのような前提の下に「重大な不利益を被っているといえる。」などと「不利益」があるかのように認定している部分は、基準点を見誤ったものであり、論じ方として誤っている。
この一文が非常に読み取りづらい理由は、下記のようにまとめることができる。
◇ 「原告らは婚姻をすることができない結果」と「原告らは婚姻制度を利用できず」の部分で、同じことが二回繰り返されている。
◇ 「原告らは婚姻をすることができない結果」、「権利義務を発生させることができず、」「公証の利益を得られない」の部分で一旦話が完結しているにもかかわらず、そこに「権利義務」と「公証の利益」の部分だけを拾って、「このような効果は婚姻によってしか発生させることができず、」のように別の話を付け加えていること。
◇ 「国民の意識における婚姻の重要性(…)も併せ鑑みれば、」の部分は、後の「重大な不利益を被っているといえる。」と関係するが、その前の「原告らは婚姻をすることができない結果」、「権利義務を発生させることができず、」「公証の利益を得られない」の部分や「このような効果は婚姻によってしか発生させることができず、」の部分とは関係しておらず、不自然な配置であること。
◇ 「これらを享受する機会」の「これら」の指すものは「権利義務」と「公証の利益」であるが、その「権利義務」と「公証の利益」の部分は、「権利義務を発生させることができず」や「公証の利益を得られない」のように、まったく別の文脈の中で使われている文言であり、にわかには「これら」の指すものを特定することが難しいこと。
これらの問題を解消してまとめ直すと、下記のようになる。
「国民の意識における婚姻の重要性(…)も併せ鑑みれば、」「本件諸規定の下では」「原告らは婚姻制度を利用できず」、「婚姻によってしか発生させることができ」ない「相手方又は行政機関等との間で、生涯有効となる種々の権利義務」や「私的な関係」での「公証の利益」「を享受する機会を得られないことで重大な不利益を被っているといえる。」
これでも長いので、さらに短く整理することにする。
この文は、この判決が「②③④」の番号で示しているものを繰り返しているだけの部分があるから、それも省略すると、下記のようにまとめることができる。
「原告らは婚姻制度を利用できず」「重大な不利益を被っているといえる。」
しかし、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす形で枠組みを定め、その枠組みを利用する者に対して法的効果や一定の優遇措置を与えることによって、目的の実現を目指すものである。
そのため、婚姻制度を設けている時点で、婚姻制度の対象となる場合には法的効果や一定の優遇措置を与え、その対象とならない場合には法的効果や一定の優遇措置を与えないという差異が生じることは初めから予定されていることである。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」のもとに「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができ、そこには何らの「不利益」も存在しない。
実際に、「婚姻していない者(独身者)」は存在しており、その状態に何らの「不利益」と称されるものはないのである。
その「婚姻していない者(独身者)」が集まって人的結合関係を形成したとしても、その個々人は「婚姻していない者(独身者)」であることに違いはないのであるから、そこに「不利益」と称されるものはそもそも存在していない。
「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」がないにもかかわらず、人的結合関係を形成したことによって初めて生じる「不利益」というものは、あるはずがないのである。
その他、婚姻制度は「婚姻している者(既婚者)」に対して一定の優遇措置を行うものであるが、この優遇措置の内容が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に照らして不必要に過大な内容となっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において14条の「平等原則」に抵触することとなり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効して格差が是正されることになる。
このように、比較の際の基準(スタンダード)となるのは「婚姻していない者(独身者)」であり、その「婚姻していない者(独身者)」が「不利益」を受けているとはいえないにもかかわらず、その状態に対して「重大な不利益を被っているといえる。」と述べていることは誤りとなる。
被告は、上記不利益は緩和ないし免除可能であると主張する。確かに、上記②について、相互の権利義務の定め、離婚の際の財産分与や相続に関する当事者による契約等により一定の緩和が可能となるが、各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等はなお残存する。また、前記1(4)アのとおり、今日多くの地方自治体がパートナーシップ制度を導入しているものの、これは諸外国の登録パートナーシップ制度と異なり、法的効果を発生させるものではなく、婚姻における上記②、④の機能を代替するものではない。パートナーシップ制度は、自治体による公証として上記③の役割を期待され得るものの、現在のところ、具体的な活用例は少なく、その効果も自治体や場面によって様々と認められる(甲A202、原告ら本人)ことからすれば、上記③の機能を代替するものとまではいい難い。更に、同性愛者らは婚姻ができなくとも、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことは妨げられない(上記①)ものの、権利義務の発生(上記②、④)や当該共同生活が国により公証される公証の利益(上記③)が、その者の社会生活において重要であることは前記のとおりであり、これは婚姻によらない共同生活では解消されないから、上記不利益は緩和ないし免除されているとはいえない(なお、異性間の事実婚の場合は、当事者が自らの意思により婚姻による公証の利益等を放棄しているから、同性カップルが婚姻できない不利益を事実婚の場合と同様に理解することはできない。)。被告の上記主張は採用することができない。
【筆者】
「被告は、上記不利益は緩和ないし免除可能であると主張する。」との記載がある。
しかし、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しており、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態である。
そのため、その既に完全な状態である「婚姻していない者(独身者)」の状態に何らの「不利益」と称されるものは存在していないのであり、それを「緩和ないし免除」しなければならないことなどもともと存在していない。
もし「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的からは導かれないような不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との関係において14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が、個別に失効して格差が是正されるだけである。
これは、常に「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となるのであって、その状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」などないのであり、その「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」があるかのような前提で論じている部分が誤りである。
この判決の「婚姻している者(既婚者)」を基準(スタンダード)として考え、「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」があるかのような説明を行うことは、「婚姻していない者(独身者)」の立場を「成年者」と「未成年者」との関係における「未成年者」(制限行為能力者)の方であるかのように扱うものであり、「婚姻していない者(独身者)」の立場を不当に格下げする意味をもたせるものである。
人生において「婚姻」することこそが正しい価値観であり、「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるべき状態であり、「婚姻していない者(独身者)」は「不利益」を受けた存在であるかのような説明を行うことは、「婚姻していない者(独身者)」を見下す態度に他ならず、不適切である。
「上記②について、相互の権利義務の定め、離婚の際の財産分与や相続に関する当事者による契約等により一定の緩和が可能となるが、各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等はなお残存する。」との記載がある。
しかし、先ほども述べたように、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、「契約等」を行いながら生活している状態が基準(スタンダード)である。
よって、その「婚姻していない者(独身者)」として「契約等」を行いながら生活している状態が基準(スタンダード)であり、そこに「緩和」しなければならないという不利益は存在しない。
そのような中、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で、法制度のパッケージとして設けられたものである。
これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として法的効果を設定し、一定の優遇措置を行うものとなっている。
そのため、もし「婚姻制度を利用している者(既婚者)」に対して、その目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行うものとなっていた場合には、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との関係で14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な優遇措置を行う規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
よって、ここでいう「各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等はなお残存する。」と述べている部分について、その内容が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置となっている場合には、その「各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等」に関する規定が個別に失効することになって、「婚姻していない者(独身者)」との間の格差が是正されることになるのであり、「婚姻していない者(独身者)」に対してそれらの「各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等」を与えなければならないということにはならない。
この点、基準(スタンダード)の採り方を誤って論じるものとなっている。
「今日多くの地方自治体がパートナーシップ制度を導入しているものの、これは諸外国の登録パートナーシップ制度と異なり、法的効果を発生させるものではなく、婚姻における上記②、④の機能を代替するものではない。」との記載がある。
まず、「今日多くの地方自治体がパートナーシップ制度を導入しているものの、」との部分であるが、地方自治体の「パートナーシップ制度」は、法律上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、違法となる。
これについて、当サイト「パートナーシップ制度」で詳しく解説している。
「婚姻における上記②、④の機能を代替するものではない。」との部分であるが、そもそも婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その目的を達成するための手段として法的効果を設定し、一定の優遇措置を行うものである。
そのため、ここでいう「②、④の機能」としているものについても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を実現するために設けられているものであることから、その目的に沿わない人的結合関係に対して「②、④の機能」としているものを与えることはできない。
なぜならば、目的を達成するための手段として整合的でない者に対しても同様の法的効果や優遇措置を与えた場合には、そもそも法制度が目的を達成するための手段として機能しなくなり、制度そのものが無意味なものとなってしまうからである。
よって、婚姻制度が有している「②、④の機能」と称しているものを、別の制度によって「代替」しなければならないことはないし、むしろ「代替」しようとした場合には、婚姻制度の果たしている機能を損なわせ、立法目的の実現を阻害することとなり、婚姻制度そのものが破壊されることに繋がる。
そのため、婚姻制度が存在する中において、婚姻制度についての「②、④の機能」としているものを「代替」するような制度を別に創設することが可能であるかのような前提で論じている部分が誤りである。
「パートナーシップ制度は、自治体による公証として上記③の役割を期待され得るものの、現在のところ、具体的な活用例は少なく、その効果も自治体や場面によって様々と認められる(…)ことからすれば、上記③の機能を代替するものとまではいい難い。」(カッコ内省略)との記載がある。
「自治体」の「パートナーシップ制度」について、「その効果も自治体や場面によって様々と認められる」としているが、「自治体」の「パートナーシップ制度」については、ほとんどの場合、法的な効力は存在しないとしており、「その効果」の部分が法的な効果があるかのように論じているのであれば、妥当でない。
また、「自治体」の「パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、その制度はそもそも違法となる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「同性愛者らは婚姻ができなくとも、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことは妨げられない(上記①)ものの、権利義務の発生(上記②、④)や当該共同生活が国により公証される公証の利益(上記③)が、その者の社会生活において重要であることは前記のとおりであり、これは婚姻によらない共同生活では解消されないから、上記不利益は緩和ないし免除されているとはいえない」との記載がある。
まず、「同性愛者らは婚姻ができなくとも、」との部分について検討する。
婚姻制度は「同性愛者」であることを理由として利用を認めないことはないため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の要件に従う形で制度を利用する意思があるのであれば、婚姻することは可能である。
よって、「同性愛者らは婚姻ができなくとも、」のように、「婚姻ができな」いかのように論じている部分が誤りである。
次に、「同性愛者らは婚姻ができなくとも、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことは妨げられない(上記①)ものの、」の部分について検討する。
この「(上記①)」にあたる「2(1)」に記されていることは、下記の通りである。
第一段落:「①両当事者が上記意思を持って共同生活を開始することを、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)、」
第二段落:「現行法上、婚姻とは、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを市町村長に届け出(上記①)」
よって、ここでいう「婚姻ができな」い場合については、この判決が「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」と称している何らかの状態にあるとしても、「届け出ること」や「市町村長に届け出」ることをしていないのであるから、「(上記①)」には該当しない。
そのため、ここで「(上記①)」と示していることは誤りである。
また、最高裁判決(昭和62年9月2日)の示した「婚姻の本質」と称する説明は、「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」というものであるが、これは具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、それを利用する者の法律関係の状態について述べているものである。
そのため、「婚姻ができな」いのであれば、この法律関係を形成することはできない。
そのことから、その法律関係を形成することができるという前提で「妨げられない」という文面のように見える点は、妥当なものではない。
「権利義務の発生(上記②、④)や当該共同生活が国により公証される公証の利益(上記③)が、その者の社会生活において重要であることは前記のとおりであり、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度についての「権利義務」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられているものである。
そのため、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象とし、それを満たさない人的結合関係は対象とならないという差異が生じることは、もともと予定されている。
そのことから、婚姻制度の対象とならない場合については、「権利義務」の適用がないことは当然のことである。
また、もし婚姻制度の立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係に対して婚姻制度の「権利義務」を適用した場合には、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害し、婚姻制度そのものが成り立たなくなる。
よって、婚姻制度の枠組みに当てはまらない者に対して「権利義務」の適用の余地があるかのような前提で、「その者の社会生活において重要である」と論じていることは妥当でない。
「共同生活が国により公証される」であるが、そもそも婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対して法的効果を設定しているものであり、単に「共同生活」をしているというだけで「公証」を与えようとする制度というものではない。
よって、婚姻制度が枠組みを定めて法的効果を設定しているとしても、その婚姻制度を利用する形での「共同生活」やその法的効果の一部分を切り出して、それを与えることが婚姻制度の立法目的となっているかのような前提で、「共同生活」をしていれば婚姻制度の法的効果を適用する余地があるかのように論じていることは妥当でない。
「これは婚姻によらない共同生活では解消されないから、上記不利益は緩和ないし免除されているとはいえない」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、それが基準(スタンダード)となるべき状態であるから、そこに「不利益」とされるものはない。
よって、何か「緩和ないし免除」しなければならないとする「不利益」などないし、「解消」しなければならないとする「不利益」も存在しない。
よって、「婚姻していない者(独身者)」の「共同生活」に「不利益」があるかのような前提で論じている部分が誤りである。
また、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ法的効果を設定しているものであり、単に「共同生活」をしているというだけで、その法的効果を与えなければならないということにはならないのであり、「共同生活」をしていることを理由として婚姻制度の法的効果を与えられることを期待している論じ方も誤りである。
「(なお、異性間の事実婚の場合は、当事者が自らの意思により婚姻による公証の利益等を放棄しているから、同性カップルが婚姻できない不利益を事実婚の場合と同様に理解することはできない。)」との記載がある。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、「婚姻していない者(独身者)」こそが基準(スタンダード)となるべきものである。
よって、「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」など一切生じていない。
そして、ここでいう「同性カップル」の個々人は「婚姻していない者(独身者)」であるから、その個々人について「不利益」は生じていない。
「不利益」の生じていない「婚姻していない者(独身者)」が何らかの人的結合関係を形成したとしても、そこに「不利益」が生じるということもない。
よって、「同性カップルが婚姻できない不利益」などと、「婚姻していない者(独身者)」が「不利益」を受けているかのように論じている部分は誤りである。
これについては、ここでいう「異性間の事実婚」についても同様で、その個々人は「婚姻していない者(独身者)」であり、「不利益」など存在しないのである。
次に、「異性間の事実婚」と「同性カップル」を比較しようとしている部分について検討する。
法律論上で比較対象とすることができる者は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士の間だけである。
ここでいう「異性間の事実婚」と「同性カップル」は、「法人」としての「権利能力」を取得していないため、法的に比較して論じることはできない。
よって、この文は「カップル間不平等論」の誤りとなっている。
何かを比較するとしても、「権利能力」を有する個々の自然人が婚姻制度を利用できるか否かという視点で考えることが必要である。
三つ目に「婚姻による公証の利益等」であるが、私的な関係における何らかの利益と称するものは別として、婚姻制度の法的効果や一定の優遇措置については、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、その目的の達成に沿わない場合には、もともと法的効果や優遇措置が与えられないことは当然に予定されている。
このことから、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度の対象となっていない場合であるから、もともと法的効果や一定の優遇措置が与えられるという前提にはない。
それにもかかわらず、婚姻制度の法的効果や一定の優遇措置が得られることを前提として、それを得られていないことを「不利益」と論じていることは誤りである。
(イ) しかしながら、前記のとおり、憲法24条1項にいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、異性間の婚姻の自由は尊重されるべきものと解され、同条2項においては、異性間の婚姻についての立法を要請しているものと解することができる。そして、前記1(2)のとおり、本件諸規定を含む現行の婚姻制度は、明治民法で初めて定められた婚姻制度を基礎として、これに憲法24条の要請を受けて、戸主制度等を廃止する等の修正を経たものであるが、旧民法から現行民法制定当時までの学説の理解(前記1(2)イ)や現行民法の嫡出推定、親子関係に係る規律の存在からすれば、当時の婚姻制度の目的は、婚姻の法的効果や戸籍制度との関係上、その要件を明確にする必要があるところ、その範囲を生物学的に生殖可能な組合せに限定することで、国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護することにあったと認められる。このような、生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものであるし、婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできないのは前記のとおりである。そうすると、憲法24条2項の異性婚の立法の要請に従って定められた本件諸規定は憲法のこうした要請に基づくものということができるから、本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。
【筆者】
「憲法24条1項にいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、異性間の婚姻の自由は尊重されるべきものと解され、同条2項においては、異性間の婚姻についての立法を要請しているものと解することができる。」との記載がある。
ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で枠組みを形成する際に、「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それを一定の形式で法的に結び付ける概念を「婚姻」と呼んでいる。
24条1項の「両性」や「夫婦」の文言についても、この意味に対応するものとして用いられている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、「異性間の婚姻を指し、」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念と、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。
よって、「異性間の婚姻」という言葉を使うことは適切ではない。
「本件諸規定を含む現行の婚姻制度は、明治民法で初めて定められた婚姻制度を基礎として、これに憲法24条の要請を受けて、戸主制度等を廃止する等の修正を経たものであるが、旧民法から現行民法制定当時までの学説の理解(…)や現行民法の嫡出推定、親子関係に係る規律の存在からすれば、当時の婚姻制度の目的は、婚姻の法的効果や戸籍制度との関係上、その要件を明確にする必要があるところ、その範囲を生物学的に生殖可能な組合せに限定することで、国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護することにあったと認められる。」(カッコ内を省略しているところがある)との記載がある。
「明治民法で初めて定められた婚姻制度」や「当時の婚姻制度」との部分であるが、ここでいう「婚姻」とは、そもそも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消を解消することを目的として設けられた枠組みのことを指している。
そして、これは一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを「貞操義務」などの一定の形式で結び付け、産まれてきた子供の父親を特定することができる関係として形成されている。
「現行民法の嫡出推定、親子関係に係る規律の存在」は、この仕組みに基づいて定められたものである。
ここでいう「その範囲を生物学的に生殖可能な組合せに限定することで、国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護することにあった」という部分も、この仕組みに基づくものということができる。
「生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものであるし、婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできない」との記載がある。
まず、「生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものである」との部分を検討する。
これは、なぜ一定の関係の「生殖とその子の養育」を「保護」することが「重要」なのかについて、十分に説明できているとはいえない。そのため、これについて検討する。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
そのため、これらを解決するために、下記の目的を達成するための枠組みが必要となる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成するためには、これらの目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を、他の様々な人的結合関係とは区別する形で枠づけることが必要となる。
その要素となるものは、下記の内容である。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
(・一定の年齢に達していること)
これらの要素を満たす人的結合関係に対して「貞操義務」などを設けた上で一定の優遇措置を与えることにより、立法目的の実現を目指す仕組みとする必要がある。
このような「目的」に従って、「その目的を達成するための手段」となる枠組みを定めることが、「婚姻」という概念が生じる経緯である。
そのため、上記のような「目的」と「その目的を達成するための手段」として整合的な要素を満たす枠組みを明らかにしないままに、「国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護すること」や「生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものである」と述べたとしても、その「男女二人一組」の関係の「生殖とその子の養育」を「保護」することにどのような意図が含まれているのかを十分に説明しているとはいえない。
また、「生殖とその子の養育の保護という目的」のいう「目的」とは、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味であり、婚姻制度の枠組みが導き出される際の「① 国の立法目的」の意味ではないことに注意が必要である。
次に、「婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできない」との部分について検討する。
「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを選び出し、一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている。
そのため、その「婚姻は男女によるものである」とされる「社会通念」は、「婚姻」という枠組みが「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成された概念であることが理由である。
よって、「婚姻」という言葉が使われている時点で、それは「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されている概念を指していることになるのであり、その言葉の「社会通念」を問うたところで、「男女のもの」という答えが出ることは当然である。
◇ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消する目的
↓
◇ 「男性」と「女性」の組み合わせ
↓
◇ 「婚姻」という枠組みを形成
↓
◇ 「婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念」
これは、「婚姻は男女によるものである」ことは、「社会通念」が「男女によるもの」であることが理由なのではなく、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成された概念が「婚姻」であることが理由である。
「社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできない」との部分についても、その「社会通念」と述べているもの背景には「婚姻」という概念が有している「目的」と「その目的を達成するための手段」の関係が存在するのであり、その「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みを検討せずに、「社会通念」が「変遷」しているとか、していないか述べたところで、何らかの結論が得られるわけではない。
この判決では他の部分でも見られるが、「婚姻」という概念が形成される際の「目的」と「その目的を達成するための手段」となる枠組みの関係を切り離して、「婚姻」の意味そのものを単なる「音の響き」に過ぎないものにまで解体した上で、その空箱となった「音の響き」に過ぎないものに対してどのような人的結合関係でも詰め込むことができるかのような前提で論じている部分があり、妥当でない。
そのような論じ方は、条文に記された文言の意味を解体して無意味なものとし、法律上の規範としての意味を失わせるものとなるから、法解釈として不適切である。
「婚姻」の定義や意味そのものを変えようとする試みについて、「説得定義」の議論も参考になる。
【動画】【ハイライト】憲法を変えるな!~安保法制違憲訴訟の勝利を目指して ―講演:石川健治 東京大学教授 2022.1.27
「憲法24条2項の異性婚の立法の要請に従って定められた本件諸規定は憲法のこうした要請に基づくものということができるから、本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」との記載がある。
まず、ここで「異性婚」という文言があるが、この段落の第一文では「異性間の婚姻」と述べており、文言が統一されていないことは不適切である。
また、「異性婚」は法律用語ではないし、この段落の初めの部分で解説したように「異性間の婚姻」についても同義反復となるため適切な表現ではない。
次に、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査しして区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻するこを求めるものでも勧めるものでもない。
そして、「憲法24条2項の異性婚」としているものについても、「本件諸規定」についても、「性愛」とは関わりがないことから、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しない。
よって、「本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」と述べている部分についても、そもそも婚姻制度は個々人の「性愛」に関知しておらず、「性的指向」と称するものによって「区別取扱い」をしていないのであるから、「区別取扱い」が存在することを前提としてその「合理的な根拠」が「存する」か否かを論じようとしている点で誤りである。
ここで「本件諸規定」が婚姻制度を「男女二人一組」(ここでいう『異性婚』)としていることについて、「合理的な根拠が存するものと認められる。」としている。
そうであれば、法律上の立法政策として「男女二人一組」に限定していることに「合理的な根拠が存するものと認められる。」ということであるから、当然、憲法上の立法政策として憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて「男女二人一組」に限定しているとしても、そのこと自体には「合理的な根拠が存するものと認められる。」と述べていることになる。
すると、法律上の「婚姻」と憲法上の「婚姻」が同一の立法目的によるものであるにもかかわらず、この判決の「2(2)ア」のところで憲法24条1項について「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と断定していることは、24条1項の規定が憲法上の立法政策として「男女二人一組」に限定する意味で立法裁量の限界を画しているという解釈を退けるだけの説得的な根拠となるものを何ら示すものではなく、一貫性を欠くものとなっている。
このような一貫性を欠く説明を行いながら、その説明を裏付ける根拠を十分に示さないようでは、解釈の客観性が保たれているとはいえず、正しい解釈をめぐって紛争を招き、法的安定性を損なうことになる。
説得的な根拠が示されていないのであれば、裁判官個人が特定の結論を導きたいがために行った恣意的な断定を行っているだけとなるため、裁判官個人による人治主義に陥り、法の中に規範を見出す法治主義を逸脱することになってしまう。
これでは、裁判所の役割を果たしているとはいえない。
そのため、この判決が24条1項について「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べて、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるかのように論じている部分については、法の論理に基づくものとはなっておらず、その判断も正当化することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
この段落は話が前後して非常に読み取りづらいものとなっているため、下記に整理する。
「婚姻の法的効果や戸籍制度との関係上、その要件を明確にする必要がある」
↓ ↓
「当時の婚姻制度の目的」
「その範囲を生物学的に生殖可能な組合せに限定することで、国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護すること」
↓ ↓
「明治民法で初めて定められた婚姻制度」(旧民法)
↓ ↓ (旧民法から現行民法制定当時までの学説の理解)
「憲法24条1項にいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」
「同条2項においては、異性間の婚姻についての立法を要請している」
↓ ↓ (憲法24条2項の異性婚の立法の要請)
↓ ↓ (憲法のこうした要請)
↓ ↓ (憲法24条の要請を受けて、戸主制度等を廃止する等の修正)
「本件諸規定を含む現行の婚姻制度」(現行民法)
「現行民法の嫡出推定、親子関係に係る規律の存在」
↓ ↓
「生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものである」
↓ ↓
「婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできない」
↓ ↓
「本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存する」
したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが性的指向による区別取扱いに当たりその合理性には慎重な判断を要するとしても、立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。
【筆者】
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが性的指向による区別取扱いに当たりその合理性には慎重な判断を要するとしても、」との部分について検討する。
ここには「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが性的指向による区別取扱いに当たり」とあるが、誤りである。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、たとえ婚姻制度が「異性間」を対象としているとしても、それは「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを意味しないし、「異性愛者」を称する者を対象とした制度であることも意味しない。
よって、婚姻制度は個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについては一切関知しておらず、「性的指向による区別取扱い」を行っているという事実はない。
そのことから、「性的指向による区別取扱いに当たり」と述べている部分は誤りである。
また、もし「性的指向による区別取扱い」を行う制度が存在する場合には、それは「性愛」いう特定の思想、信条、信仰、感情を保護することになるから、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情に対して制度を設け、その他の「性愛」の思想、信条、信仰、感情や、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情との間で区別することになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となるし、制度を利用する者が特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を有することを求めるものとなるから、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となる。
よって、「性的指向による区別取扱い」をする制度は、その存在自体が憲法に違反することになるのであり、そのような「区別取扱い」をするような制度が存在していても、許されることを前提として論じていることも誤りとなる。
別の事例で、婚姻制度が「婚姻適齢に満たない者」との間で婚姻することを認めていないとしても、これは「小児性愛者」を称する者であることを理由として「区別取扱い」をしていることを意味しない。
婚姻制度が「近親者」との間で婚姻することを認めていないとしても、これは「近親性愛者」を称する者であることを理由として「区別取扱い」をしていることを意味しない。
婚姻制度が「三人以上の人的結合関係」で婚姻することを認めていないとしても、これは同時に複数名に対して「性愛」を抱く者であることを理由として「区別取扱い」をしていることを意味しない。
同様に、婚姻制度が「同性」との間で婚姻することを認めていないとしても、それは「同性愛者」を称する者であることを理由として「区別取扱い」をしていることを意味しない。
そのため、制度の内容がある組み合わせに限定しているとしても、そのことと「性愛」などの内心の問題とは関係がないのであり、これを関係づけて考えようとしている点で誤っている。
次に、「その合理性には慎重な判断を要するとしても、」の部分についても、そもそも「性的指向による区別取扱い」は存在していないことから、「区別取扱い」が存在することを前提とした「合理性」の審査を行う余地はないのであり、これを判断しようとしている点で誤りとなる。
三つ目に、「性的指向」とは関係なく、「婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと」について、「区別取扱い」と考えることができるかを検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理を定めており、「個人主義」の下に自然人はすべて「個人」として取り扱われることになる。
そのため、権利・義務を関係づけることができる法主体としての地位は、「個人」に属する。
よって、憲法上で何らかの比較を行う際には、「個人」が主体となり、別の「個人」との間で比較することになる。
また、憲法14条の「平等原則」についても、その性質は「個人権」であり、「個人と個人の間の平等」をいう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
【札幌・第7回】被告第4準備書面 令和2年10月21日 PDF (P4)
そのため、法制度を利用できるか否かについて、「個人」と「個人」の間に差異がある場合に、「区別取扱い」として認識し、その間を比較することは可能である。
例として、下記のような比較を挙げることができる。
◇ 個人と個人の間の比較
・年収
婚姻制度は、個々人の年収を審査しておらず、「年収の多い者」と「年収の少ない者」とを区別して取扱っているという事実はない。
「年収の多い者」の婚姻している割合が多いとしても、「年収の少ない者」も婚姻することは可能である。
「年収の少ない者」であっても、実際に婚姻している者はいる。
そのため、「年収の少ない者」であることを理由として「区別取扱い」をしているという事実はない。
・年齢
婚姻制度は、個々人の年齢を審査して、「婚姻適齢を満たす者」と「婚姻適齢を満たさない者」とを区別して、「婚姻適齢を満たす者」のみに婚姻制度の利用を認めている。
これは、「年齢」による「区別取扱い」ということができるから、14条の「平等原則」によってその合理性を審査することができる。
このような事柄については、14条の「平等原則」によって、「区別取扱い」の有無や、「区別取扱い」が存在した場合における合理性を審査することができる。
しかし、法制度の内容がどのような組み合わせを対象としているかについては、これとは別の視点である。
◇ 相手との関係性
× 近親者との人的結合関係
× 三人以上の人的結合関係
× 三人一組の人的結合関係
× 四人一組の人的結合関係
× 五人一組の人的結合関係
× 六人一組の人的結合関係
× __人一組の人的結合関係
× 婚姻適齢に満たない者との人的結合関係
× 同性同士の人的結合関係
憲法14条の「平等原則」は「個人権」であり、個人と個人を比較する際には「区別取扱い」と表現することが適切であるということができる。
しかし、婚姻制度がどのような組み合わせを対象としているかについて、同じように「区別取扱い」と表現することが適切といえるかは検討の余地がある。
制度の内容が「目的」を達成するための「手段」として合理性を有した妥当な内容であるか否かについて検討すること自体は考えられるが、これを14条の「平等原則」の審査の中に取り込むことによって解決を図ることが妥当であるかは、一般的な14条の「平等原則」の審査とは視点が異なるように思われる。
ただ、そもそも憲法24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言によって一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、今回の事例の「同性間の人的結合関係」については、これを満たさないことから、憲法14条によって審査する必要のある場面ではなく、これを「区別取扱い」と考えるべきかどうかの論点に関わらないままに結論が導き出される問題であるといえる。
「立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、婚姻制度が「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものによって区別取扱いをしているという事実はないため、「憲法14条1項」の「平等原則」によって審査することができるとする前提を欠いている。
その意味で、ここでいう「憲法14条1項に違反するとはいえない。」と同じ結論に至るのであるが、この判決は「憲法14条1項」で審査することができる対象であることを前提とした上で、その審査の結果として「憲法14条1項に違反するとはいえない。」という結論が導き出されているかのように論じるものとなっており、判断の過程が誤っている。
次に、「性的指向」とは関係なく、「婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと」について、「憲法14条1項に違反するとはいえない。」と判断している場合を検討する。
この判決は、その「憲法14条1項に違反するとはいえない。」という結論に至るまでの判断として、「憲法24条2項の異性婚の立法の要請に従って定められた本件諸規定は憲法のこうした要請に基づくものということができるから、本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」のように述べており、24条が「異性間の人的結合関係」を要請していることを根拠とするものとなっている。
これは、14条の「平等原則」の審査において、そこで問われている事柄についての合理性を、憲法上の別の規定によって裏付けようとするものということである。
しかし、そもそも憲法上に別の規定があるのであれば、14条の「平等原則」の適用そのものがなされないのであって、14条の「平等原則」の審査に持ち込むこと自体が適切であるとはいえない。
それにもかかわらず、それを14条の「平等原則」の審査を行う形で、「憲法14条1項に違反するとはいえない。」という結論を出すことは、憲法上の規定を整合的に読み解くものとなっておらず、適当でない。
この一文は、読み取りづらいものとなっている。
その理由は、この14条の「平等原則」の審査を行う項目において、判断の「前提」→判断の「過程」→判断の「結論」のように順を追って説明しているにもかかわらず、その順番に沿わない文面を入れているからである。
◇ 判断の「前提」
↓
◇ 判断の「過程」
↓
◇ 判断の「結論」
この段落の最後の部分で「立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」と述べている部分は、判断の「結論」にあたるものである。
この前の段落で「本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」と述べている部分までが判断の「過程」の部分であることを見れば、「過程」→「結論」の順に構成されていることを見ることができる。
しかし、この段落の前半部分には、「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが性的指向による区別取扱いに当たりその合理性には慎重な判断を要するとしても、」と述べており、判断の「前提」となる文を繰り返すものとなっているのである。
これは、以前の段落で既に述べていることであり、ここで改めて繰り返す必要のないものである。
このため、読者は「前提」→「過程」→「(前提)→結論」のように、不必要に「前提」が繰り返されていることによる混乱が生じ、文面を難解に感じてしまうことになるのである。
◇ 判断の「前提」
↓
◇ 判断の「過程」
↓
◇ 判断の「(前提)→結論」
よって、この段落を改善するためには、前の段落の最後の部分で「本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。」と述べていることにそのまま応じる形で、「したがって、」「立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」と述べて済ませればよかったということである。
(ウ) 原告らは、本件諸規定による別異の取扱いは憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)に基づくものであり、上記区別取扱いに合理的根拠が認められるか否かの審査は厳格に行われるべきであり、同性愛者の不利益は甚大であることや、婚姻制度の目的が共同生活の保護にあることなどからすれば、上記区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張する。
【筆者】
「本件諸規定による別異の取扱いは憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)に基づくものであり、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して取扱いを変えるものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は個々人の「性愛」に関知しておらず、干渉するものでもないことから、「性的指向」と称するものによる「別異の取扱い」は存在しない。
よって、「別異の取扱い」が存在しないものについては、「憲法14条1項」の「平等原則」によって審査する前提を欠いており、「憲法14条1項」で審査できることを前提に論じ始めている部分が誤りである。
次に、「憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)に基づくものであり、」との部分で、「性別」について言及しているが、「性愛」(『性的指向』と称しているものも同様)については、個々人の内心にのみ存在する精神的なものであり、これは身体を基準とした「性別」とは異なるものである。
よって、「性的指向」が「性別」に含まれるかのように論じようとしている点が誤りである。
ただ、そもそも「性的指向」による「別異の取扱い」は存在しないのであり、「別異の取扱い」が存在することを前提として「憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)」との関係を考えようとする前提を欠いている。
「上記区別取扱いに合理的根拠が認められるか否かの審査は厳格に行われるべきであり、」との部分について検討する。
先ほども述べたように、「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しないのであり、「区別取扱い」が存在することを前提としてその「合理的根拠」の有無を問うための前提を欠いている。
よって、「合理的根拠が認められるか否かの審査は厳格に行われるべき」との部分については、そもそも「区別取扱い」は存在しないという点で妥当でないことになる。
先ほど「別異の取扱い」と表現していたにもかかわらず、ここで「区別取扱い」別の文言を用いていることは疑問である。同じことを指しているのであれば、読み手を混乱させないために、統一することが望ましいということができる。
「同性愛者の不利益は甚大であることや、」との部分について検討する。
婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いを行うものではないため、「同性愛者」を称する者であっても、婚姻制度の要件に従って制度を利用したいと望むのであれば「婚姻」することは可能である。
そのため、「同性愛者」と称する者であることを理由として法的な「不利益」が存在するということにはならない。
よって、「同性愛者の不利益」のように、「同性愛者」が「不利益」を受けているかのような論じ方は誤りとなる。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができ、「婚姻していない者(独身者)」の状態について「不利益」があるかのような論じ方をしていることも誤りである。
「婚姻制度の目的が共同生活の保護にあることなどからすれば、」との部分について検討する。
まず、「婚姻制度」の目的は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することにある。
そして、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対して一定の優遇措置を行うことによって、その目的を達成することを目指す仕組みとなっている。
そのため、「共同生活の保護」という側面があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた「保護」であるから、その目的との整合性を満たす人的結合関係のみを対象とするものであることが前提となっている。
そのことから、立法目的を達成するための手段となる枠組みの対象外となっている人的結合関係の「共同生活」が「保護」されないことは当然のことである。
よって、「婚姻制度の目的」の理解を誤っているし、婚姻制度の内容について「共同生活の保護」という側面があるとしても、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みに当てはまる者を対象とするものであり、そこに当てはまらない者について「保護」が受けられることを期待することも誤りである。
「上記区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らかである」との部分について検討する。
この段落の始めの部分で解説したように、「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しない。
そのため、「区別取扱い」が存在することを前提とした「合理的理由」の存否の判断を行う前提を欠いている。
よって、「合理的理由が存在しない」と評価している部分についても、それ以前に「区別取扱い」が存在しないという点によって排斥される主張であり、誤りとなる。
しかしながら、前記のとおり、憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されないことからすれば、同性愛者の不利益の程度や婚姻制度の目的の一つが共同生活の保護にあると考えられることを考慮しても、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法14条1項に違反するとはいい難い。
【筆者】
この段落は、前の段落の「原告ら」の主張に対して応答するものとなっているが、話が噛み合っていないように思われる。
前の段落の論点は下記のようになる。
① 本件諸規定による別異の取扱い
② 憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)に基づくもの
③ 区別取扱いに合理的根拠が認められるか否かの審査は厳格に行われるべき
④ 同性愛者の不利益は甚大であること
⑤ 婚姻制度の目的が共同生活の保護にあること
⑥ 区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らか
この論点に答えると、下記のようになる。
① そもそも「性的指向」と称するものによる「別異の取扱い」は存在しない。
② ・「性的指向」は個々人の内心にのみ存在するものであり、身体を基準とする「性別」とはいえない。
・「性的指向」は個々人の内心にのみ存在するものであり、身分関係を形成するものではなく「社会的身分」とはいえない。
・そもそも「性的指向」と称するものによる「別異の取扱い」が存在しないことについて、14条の「平等原則」によって審査することはできない。
・14条の「性別」についても、この判決の上記「(4)イ」で「男性か女性のどちらか一方につき性別を理由に区別取扱いをするものではない。」として否定されている。
③ 「区別取扱い」が存在しないものに対して、「区別取扱い」があることを前提とする「合理的根拠」の有無の「審査」を行うことはできない。
④ ・婚姻制度は「性愛」を審査して「区別取扱い」を行っている事実はない。
・「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」とされるものはない。
⑤ ここで「婚姻制度の目的が共同生活の保護にある」という場合の「目的」の意味は、「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味として使われているものであり、婚姻制度の枠組みを定める際の「国の立法目的」の意味で使われているものではない。
そのため、この「目的」の意味によって、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
よって、この「婚姻制度の目的が共同生活の保護にある」という文を見て、それを理由として婚姻制度の枠組みの変更を求めることができることにはならない。
⑥ そもそも「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しないため、「区別取扱い」があることを前提とした「合理的理由」の存否を述べていること自体が妥当でない。
このように答えることが妥当である。
しかし、この段落は、このような形で一つ一つ答えるのではなく、「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されないこと」を理由として「憲法14条1項に違反するとはいい難い。」と結論付けるものとなっている。
憲法上の規定である24条で定められていることについては、14条に違反することはないという意味では妥当であるとしても、問題提起と答えが噛み合っていないことは疑問である。
「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されないことからすれば、」との部分について、詳しく検討する。
ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。
まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で枠組みを形成する際に、「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それを一定の形式で法的に結び付ける概念を「婚姻」と呼んでいる。
24条1項の「両性」や「夫婦」の文言についても、この意味に対応するものとして用いられている。
そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、「異性間の婚姻を指し、」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。
このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念と、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。
よって、「異性間の婚姻」という言葉を使うことは適切ではない。
ここでは「同性間の婚姻」との文言もある。
しかし、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みであり、この目的を離れて「婚姻」を観念することはできないことから、「婚姻」であることそれ自体によって、「婚姻」の中に含めることのできる人的結合関係には内在的な限界がある。
「同性間の人的結合関係」については、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提の下に、「同性間の婚姻」という文言を用いていることも誤りとなる。
次に、「同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されない」との文面について検討する。
まず、24条は「婚姻」について定めており、これは「婚姻」を24条によって統制することを求めるものであるから、法律上で定められる「婚姻」はすべて24条の「婚姻」と同一のものということになる。
そのため、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「婚姻」と称する制度が存在することはできない。
このことから、ここではあたかも「同性間の婚姻」と称する制度が24条の「婚姻」とは別に存在していて、それに対して「憲法24条1項による保護」が及ぶか否かを検討するような文面となっているが、そもそも24条の「婚姻」を離れて「婚姻」と称する制度を立法することはできないという点で誤りとなる。
もう一つ、「憲法24条1項による保護」としている部分について、「保護」の意味を検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、憲法上の権利の主体となる者は「個人」である。
そのため、「憲法24条1項による保護」が及ぶか否かを論じる際には、常に個々人を主体として考える必要があり、「憲法24条1項による保護」の意味についても、個々人が「憲法24条1項」の定める婚姻制度を利用することができるか否かについて「保護」があるか否かを論じるものということになる。
しかし、この部分の文面では「同性間の婚姻」という何らかの制度か、あるいは「同性間の人的結合関係」に対して「憲法24条1項による保護」が及ぶか否かを論じるものとなっており、適切ではない。
憲法上の権利を及ぼす対象となるものは「個人」であり、このような何らかの制度や人的結合関係に対して「保護」をするというものではない。
よって、これらの何らかの制度や人的結合関係に対して「憲法24条1項」を適用するか否かを論じている部分は、妥当な説明とはいえない。
これに対して、この段落の始めの部分の「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している」の部分については、制度について「要請」をしているか否かを論じるものであり、「保護」しているか否かを問うものではないため、適切であるということができる。
このように、憲法上の権利が適用される主体となるものが「個人」であり「保護」が及ぶか否かについても「個人」を主体として考える必要があることと、憲法上で制度を構築することが「要請」されているか否かの問題は切り分けて論じる必要がある。
「同性愛者の不利益の程度や」との部分について検討する。
まず、「同性愛者」の部分であるが、法律論上は個々人の思想、信条、信仰、感情に基づいて人を区別して取扱ってはならないのであり、「同性愛者」などという形で、個々人の内心における精神的なものに着目して人を分類して区別することを前提とする形で論じていること自体が不適切である。
次に、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができる。
その「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、そこに「不利益」と称されるものは存在しない。
よって、たとえ「同性愛者」と称する者が「婚姻していない者(独身者)」の状態にあるとしても、その状態は既に完全な状態であり、「不利益」と称されるような状態にあるわけではない。
三つ目に、その「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、そこに「不利益」と称されるものはないことが前提である中で、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられている。
その内容は「子の福祉」「近親交配の回避」「生殖機会の公平」「母体の保護」という立法目的を達成するために、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、その間に「貞操義務」などを設けて一定の形式で法的に結び付けることによって、その立法目的の実現を目指すものとなっている。
これは「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度を利用するための要件を満たし、婚姻制度を利用する意思があれば、誰でも婚姻制度を利用することができる。
これはたとえ「同性愛者」を称する者であるとしても同様であり、このような目的を達成するための手段として設けられた制度を利用する意思を有するのであれば、当然に婚姻制度(男女二人一組)を利用することは可能である。
よって、「同性愛者」を称する者が、「同性愛者」を理由として制度の利用が妨げられているという事実は存在しておらず、「同性愛者」を称する者であることを理由として「不利益」を受けているということにはならない。
このことから、この部分で「同性愛者の不利益」のように、「同性愛者」を称する者が「不利益」を受けているかのような前提で論じている部分は誤りとなる。
「婚姻制度の目的の一つが共同生活の保護にあると考えられることを考慮しても、」との部分について検討する。
まず、「目的」の多義性に注意が必要である。
「目的」の意味は、「① 国の立法目的」、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」、「③ 個々人の利用目的」に分けることができる。
そして、この「婚姻制度の目的の一つが共同生活の保護にある」と述べている部分の「目的」とは、婚姻制度が機能した場合に「共同生活」が「保護」されるという結果を示すものであるから、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味にあたるものである。
これが「① 国の立法目的」の意味ではないかを検討するとしても、そもそも婚姻制度はどのような人的結合関係でも「共同生活」をしていれば「保護」されるということを前提としていないことから、制度の枠組みを導き出す際の立法目的ということはできない。
そのため、ここで使われている「目的」の意味を、「① 国の立法目的」を示したものと考えることはできない。
よって、このような「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味の「目的」を理由として、婚姻制度の枠組みを変更するための理由とすることはできないのであり、これを「考慮しても、」のように「考慮」しようとしていること自体が妥当でない。
「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法14条1項に違反するとはいい難い。」との部分について検討する。
これは、既にこの判決のいう「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」の話ではなくなっているようにも見える。
審査しようとしている内容について、論理の一貫性が保たれているのか疑わしい部分がある。
原告らの上記主張は採用することができない。
【筆者】
この「(4) 本件諸規定は憲法14条1項に反するか」の項目は、話が前後したり、無用に繰り返されたりするため、読み取ることが難しくなっている。
これをまとめると、要するにこの項目が言いたいことは、下記のようになる。
=======================================
【本件諸規定は憲法14条1項に反するか】
「憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、」「合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものである」
<本件諸規定による区別取扱いの有無について>
「同性間の婚姻は認められておらず、その結果、同性愛者は婚姻制度を利用することができない」
↓ ↓
「原告らは、」
「憲法14条1項後段列挙事由(「性別」又は「社会的身分」)に基づく」「性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。」
「同性愛者の不利益は甚大であることや、婚姻制度の目的が共同生活の保護にあることなどからすれば、」
「上記区別取扱いに合理的根拠が認められるか否かの審査は厳格に行われるべきであり、」「区別取扱いに合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張する。」
↓ ↓
「しかし、」
「男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができ、同性とは婚姻することができない」
「男性か女性のどちらか一方につき性別を理由に区別取扱いをするものではない。」
↓ ↓
「被告は、」
「同性愛者も異性と婚姻することができるのだから区別取扱いは生じていない」
「性的指向について中立的な規定であり、」「同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても事実上の結果ないし間接的結果に過ぎないから区別取扱いとはいえない旨主張する。」
↓ ↓
「しかし、」
「性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので」「精神的及び肉体的結合の対象を定めるものである」
「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」
「性的指向が婚姻の本質と結びついている」
「同性愛者は異性に対して恋愛・性愛の対象が向かない以上、」「同性愛者が異性と婚姻することができるとしても、そのような婚姻は、婚姻の本質を有さない」
「婚姻制度を利用することができない」
「同性同士の婚姻を認めない本件諸規定は、同性愛者が婚姻制度を利用できないという区別取扱いがあり、」「決して事実上ないし間接的なものということはできない」
↓ ↓
「婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが性的指向による区別取扱いに当たり」
「本件諸規定は性的指向に基づく区別取扱いをするものである」
「同性愛者と異性愛者の間において性的指向に基づく区別取扱いをするものと解される。」
↓ ↓
「医学的に」「ほとんどの場合性的指向は人生の初期か出生前に本人の意思とは関わりなく定まっており、性的指向を自己の意思や精神医学的療法で変えることは困難である」
「本人にとって自ら選択ないし修正の余地のない事柄をもって婚姻の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要である。」
「その合理性には慎重な判断を要する」
<本件諸規定による区別取扱いの合理性の有無について>
「原告らは婚姻をすることができない結果、」
「婚姻制度を利用できず」
↓ ↓
「生涯有効となる種々の権利義務を発生させることができず」
「私的な関係でも公証の利益を得られない」
「このような効果は婚姻によってしか発生させることができず、」
↓ ↓
「国民の意識における婚姻の重要性」
「これらを享受する機会を得られないことで重大な不利益を被っているといえる。」
「被告は、上記不利益は緩和ないし免除可能であると主張する。」
↓ ↓
「確かに、」
「相互の権利義務の定め、離婚の際の財産分与や相続に関する当事者による契約等により一定の緩和が可能となる」
「同性愛者らは婚姻ができなくとも、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことは妨げられない」
↓ ↓
「各手続を行う経済的負担や相続の際の遺留分侵害請求等はなお残存する。」
「権利義務の発生(…)や当該共同生活が国により公証される公証の利益(…)が、その者の社会生活において重要である」
「これは婚姻によらない共同生活では解消されない」
↓ ↓
「今日多くの地方自治体がパートナーシップ制度を導入しているものの、これは諸外国の登録パートナーシップ制度と異なり、法的効果を発生させるものではなく、」「現在のところ、具体的な活用例は少なく、その効果も自治体や場面によって様々と認められる」
「婚姻における」「機能を代替するものではない。」
「パートナーシップ制度は、自治体による公証として」「期待され得るものの、」「機能を代替するものとまではいい難い。」
↓ ↓
「不利益は緩和ないし免除されているとはいえない」
「婚姻の法的効果や戸籍制度との関係上、その要件を明確にする必要がある」
↓ ↓
「当時の婚姻制度の目的」
「その範囲を生物学的に生殖可能な組合せに限定することで、国が一対の男女(夫婦)の間の生殖とその子の養育を保護すること」
↓ ↓
「明治民法で初めて定められた婚姻制度」(旧民法)
↓ ↓ (旧民法から現行民法制定当時までの学説の理解)
「憲法24条1項にいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」
「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」
↓ ↓
「同性間の婚姻については、」「憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されない」
↓ ↓
「同条2項においては、異性間の婚姻についての立法を要請している」
「同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している」
↓ ↓ (憲法24条2項の異性婚の立法の要請)
↓ ↓ (憲法のこうした要請)
↓ ↓ (憲法24条の要請を受けて、戸主制度等を廃止する等の修正)
「本件諸規定を含む現行の婚姻制度」(現行民法)
「現行民法の嫡出推定、親子関係に係る規律の存在」
↓ ↓
「生殖とその子の養育の保護という目的は現在においても重要なものである」
↓ ↓
「婚姻は男女によるものであるという当時の社会通念もまた、変遷しつつあるものの、現在においてもなお失われているということはできない」
↓ ↓
「本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存する」
↓ ↓
「婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法14条1項に違反するとはいい難い。」
「立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。」
=======================================
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護するものではないし、「性的指向」と称するものによる「区別取扱い」は存在しないし、「婚姻の本質」と称する説明も誤った理解をするものとなっている。
もし「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、制度を利用する者に「性愛・恋愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を求めることは19条の「思想良心の自由」、20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、特定の「恋愛・性愛」を対象として制度を設け、それ以外の「恋愛・性愛」や、「恋愛・性愛」以外の思想、信条、信仰、感情との間でその内心に基づいて区別取扱いをするものとなるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
また、「性的指向」と称するものによって区別するような制度が存在するのであれば、そのこと自体で違憲となるのであり、そのような制度が存在していても許されるかのように述べていることも誤りである。
その他、「不利益」があると述べている部分についても、そもそも「同性愛者」であることを理由として区別取扱いを行っている事実はないし、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」といわれるようなものはない。
よって、この項目の内容は結論に至るまでの判断の過程が適切ではない。
(5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか
ア 前記のとおり、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものである。そうすると、本件諸規定が憲法24条2項にも適合するものとして是認されるか否かは、当該規定の趣旨や同規定に係る制度を採用することによる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量を超えるものと見ざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
【筆者】
最高裁判決との対応関係を確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決 (PDF) (再婚禁止期間大法廷判決)
最高裁判決では「このような観点から,」との文言があるが、この判決では抜けている。
この判決の「……である。そうすると、……」の部分以降は、この判決の独自の説明である。
前記2(1)のとおり、同性カップルの人的結合に関する事項は、憲法24条1項に基づく婚姻の自由は認められないものの、同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題であるから、同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。そして、前記1(2)の起草過程のとおり憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものであるから、同性カップルに関する事項についても、国会の立法裁量が与えられると同時に、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである。
【筆者】
「同性カップルの人的結合に関する事項は、憲法24条1項に基づく婚姻の自由は認められないものの、」との記載がある。
ここでは「同性カップルの人的結合」について、24条1項の「婚姻をするについての自由」(ここでいう『婚姻の自由』にあたるもの)が適用されるか否かを検討するものとなっている。
しかし、24条1項の「婚姻をするについての自由」は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている個々の自然人を対象とするものであり、人的結合関係を対象とするものではない。
そのため、ここでいう「同性カップルの人的結合」のような何らかの人的結合関係を形成している状態の全体に対して、そこに24条1項が適用されるか否かを検討することは、法律論として誤った検討である。
この文は「憲法24条1項に基づく婚姻の自由は認められない」という結論においては妥当であるが、その判断の過程には法律論として誤った認識が存在することに注意が必要がある。
「同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題であるから、同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。」との記載がある。
まず、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を」の部分を検討する。
これは最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明したことを引用する形で論じることを試みるものと考えられる。
しかし、この最高裁判決の「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。
その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。
◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。
◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。
(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)
◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が「相互の協力」を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。
(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)
◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。
このように、「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について示されているものである。
よって、具体的な婚姻制度の枠組みに当てはまる者が、適法に婚姻制度を利用した場合に初めて「婚姻の本質」と称する法律関係の状態を形成することが可能となるのであり、そもそも婚姻制度を利用していない者や、婚姻制度の対象となっていない者については、この「婚姻の本質」と称する法律関係の状態に入ることはできない。
次に、上記を前提として、この判決は「同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題であるから、」と述べている部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度を利用するための条件を満たしていないため、婚姻制度を利用している者には該当しない。
そのため、婚姻制度を利用した場合に生じる「婚姻の本質」と称する法律関係の状態にはない。
よって、「同性間の人的結合関係」については、この判決が引用しようとしている「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」という法律関係の状態にはないのであり、これがあることを前提として説明を試みていることは誤りである。
この判決は「婚姻」が「恋愛・性愛」を保護するための制度であることを前提として、ここでいう「精神的及び肉体的結合」の文言を「恋愛・性愛」を指すものと考え、「同性間」の「恋愛・性愛」を「婚姻及び家族」に含めることができると考えているようである。
しかし、法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容でなければならないのであり、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として立法することは許されない。
よって、「婚姻」が「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度であると考えている部分が誤りである。
これにより、「同性間」の「恋愛・性愛」を「婚姻及び家族」と結び付けて考えることができることを前提にして、「同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題である」のように、「同性間」の「恋愛・性愛」を「婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題である」と判断していることも誤りとなる。
法制度である「婚姻及び家族」の枠組みに、「恋愛・性愛」という特定の価値観を混じり込ませている点で、制度に色を付けようとするものであり、不適切である。
三つ目に、「婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきか」との部分について検討する。
24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けられた制度である。
そのため、その「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として枠組みを定め、その立法目的を達成することを目指すものとなっている。
具体的には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として一般的・抽象的に自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに「貞操義務」を設けることによって、その下に子供が産まれた場合に遺伝上の父親を特定できる関係となることを中心として定められ、「生殖」によって子が生じるという因果関係によって形成される血縁関係を明確にする機能によって、立法目的を達成することを目指すものである。
そのため、この目的を達成するための手段として整合的でない人的結合関係については、もともと「婚姻及び家族」の制度の対象にはならない。
これは、「婚姻及び家族」の枠組みが定められた時から、当然に予定されていることである。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「男性」と「女性」による組み合わせではないことから「婚姻」ではないし、それが「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」に含まれないのであれば、24条2項の「家族」の中にも含まれない。
よって、「婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきか」のように、「婚姻及び家族」の枠組みに含まれることを前提に論じている部分が誤りである。
「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない人的結合関係については、通常通り、21条1項の「結社の自由」によって保障されるものとして扱われることになる。
四つ目に、「同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。」との部分について検討する。
先ほども述べたように、「同性間の人的結合関係」については「婚姻」の中に含めることはできないし、それが「親子」や「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」の中に含まれないのであれば「家族」の中にも含まれない。
そのため、そこに含まれない関係については、24条2項の「婚姻及び家族」の中に含まれることを前提に論じることはできない。
よって、「同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。」と述べていることは誤りとなる。
最後に、「真摯な意思をもって」との部分には、既に「意思」があるにもかかわらず、その後に「営む意思を」と重ねて「意思」を持ち出すことは不自然である。
この「真摯な意思をもって」という文が含まれる「婚姻の本質」と称する説明を示している最高裁判決の内容は、婚姻制度の法的効果を及ぼすべきかどうかが論点となっている事案であり、その中で婚姻制度を利用する「意思」が既に問われている事例である。
そこで問われていた「真摯な意思」を抜き出して、その「真摯な意思」を持つ「意思」があるかをここで更に問うことは、不自然な説明である。
これは、この福岡地裁判決が最高裁の示した「婚姻の本質」と称している説明の意味を正しく理解できていないことの表れであると見ることができる。
「起草過程のとおり憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものであるから、同性カップルに関する事項についても、国会の立法裁量が与えられると同時に、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである。」との記載がある。
「起草過程のとおり憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、」との部分であるが、「憲法24条」に限らず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいている。
ただ、「憲法24条」2項は「婚姻及び家族」の制度について「個人の尊厳」を満たすように求める規定であり、その「婚姻及び家族」の中に当てはまらない場合には「憲法24条」2項の「個人の尊厳」は適用されない。
よって、「個人の尊厳」を理由として、どのような人的結合関係でも「婚姻及び家族」の中に含めることができるということにはならない。
そのようなことをすれば、「婚姻及び家族」の枠組みそのものが機能しなくなり、「婚姻及び家族」の枠組みが有する立法目的を達成することができなくなることに繋がる。
また、「婚姻及び家族」という枠組みを他の様々な人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻及び家族」の枠組みそのものが雲散霧消してしまうからである。
そのような状態となることを「婚姻及び家族」の枠組みが許しているはずはないのであり、もしそのようなことをすれば、24条1項の「婚姻」や2項の「婚姻及び家族」の文言に抵触して違憲となる。
次に、「これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものであるから、」との部分について検討する。
憲法は法制度であり、個々人の思想、信条、信仰、感情に対して中立的な内容であり、憲法19条で「思想良心の自由」、20条1項前段で「信教の自由」を定めており、「内心の自由」を保障している。
よって、憲法の原理としての「個人の尊厳」は、どのような思想、信条、信仰、感情を有している者であるとしても、当然に保障される。
(もう一つ、『個人の尊厳』の原理によって、個々人に対して法主体としての地位が与えられ、その者に対して、『内心の自由』が保障されるという視点で見ると、順序が逆になる。)
よって、「異性愛者」を称する者も、「同性愛者」を称する者も、当然「個人の尊厳」は保障されている。
ここでは「異性愛者」と「同性愛者」の二分論しか考えていないようであるが、「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」「無性愛者」などを称する者であるとしても同じである。
「異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものであるから、同性カップルに関する事項についても、」との部分について検討する。
まず、「婚姻及び家族」の制度は、「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、「婚姻及び家族」の制度を用いる者はすべて「異性愛者」を称する者であるとする前提そのものが誤っている。
そのため、それに対する形で「同性愛者」を称する者について取り上げていることも誤りである。
また、「婚姻及び家族」の制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないことから、「性愛」に基づいて人的結合関係を形成していることを前提とする制度ではない。
よって、ここで「同性愛」と「同性カップル」を結び付ける形で論じ初め、それを「婚姻及び家族」の制度に照らし合わせて考えることができるかのように述べていることも妥当でない。
ただ、「婚姻及び家族」の制度は、個々人の内心に対して中立的な内容であることから、「異性愛者であっても同性愛者であっても」その他の「性愛」を有すると称する者であっても、「性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を持つと称する者であっても、制度の要件に従う形であれば、適法に利用することができる。
「同性カップルに関する事項についても、国会の立法裁量が与えられると同時に、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである。」との部分について検討する。
まず、「憲法24条2項の裁量の限界にも画される」ことになるのは、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合だけである。
ここでいう「同性カップルに関する事項」である「同性間の人的結合関係」についは、「婚姻」ではないし、「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などとに含まれないのであれば、「家族」にも含まれない。
よって、この「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない場合については、「憲法24条2項の裁量の限界にも画される」とする対象とはなっていない。
そのことから、24条2項の「個人の尊厳」の文言も適用されないのであり、これが適用されるかのように論じている部分が誤りである。
もう一つ、ここでは「同性カップルに関する事項」のように、「二人一組」であることを前提とするものとなっている。
ここで「二人一組」を比較対象として取り上げていることは、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」であることを前提として、その「男女」の部分を切り取って、「二人一組」の部分だけを取り上げて比較対象とすることができるのではないかとの発想によるものと思われる。
しかし、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであり、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、「男性」と「女性」の間では自然生殖を想定することができ、その者の間に「貞操義務」を設けることによって、子供が産まれた場合に、その子供の遺伝的な父親を特定することができるという仕組みに理由がある。
そのため、婚姻制度の枠組みが「男女二人一組」となっていることは、その間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせであることが重要な要素となっているものであり、これを切り取って、「二人一組」の部分だけを前提として比較対象とすることができるという性質のものではない。
そのことから、婚姻制度の枠組みを超える人的結合関係との間で比較をする場合には、「二人一組」に限らず、「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の組み合わせ」などを網羅的に論じなければならないものである。
それにもかかわらず、「同性カップル」という言葉を用い、「二人一組」の人的結合関係のみを比較対象として取り上げれば済むかのような説明となっていることは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているものである。
これに対し、被告は、憲法24条2項も同条1項と同じく「両性」との文言が存すること等から、婚姻が異性間の人的結合を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請している規定と理解すべきである旨主張する。しかし、同性カップルも異性カップルと変わらない人的結合関係にあるということができるし、前記のとおり「婚姻」を異性婚に限ると理解するとしても、婚姻と並んで「家族に関するその他の事項」が対象となっていること、「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解されるものの、他方で前記のとおり婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においてはこれに限定される必要はなく、同性カップルを「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然であるし、上記憲法24条2項の裁量の限界を画するものとして「両性の本質的平等」と併せて「個人の尊厳」が挙げられているところ、個人の尊厳については同性愛者も異性愛者と変わらず尊重されるべきことは前記のとおりである。被告の上記主張は採用することができない。
【筆者】
第一文について検討する。
「これに対し、被告は、」との記載があるが、ここでいう「これ」にあたる一つ前の段落の記述は、この判決が初めて示したものであり、この判決の内容に対して後ほど「被告」が反論を行うことは考えられるとしても、この判決の内部でその反論がすでに行われているかのように取り上げることは時系列的に無理である。
よって、この判決は「被告」(国〔行政府〕)の主張の取り上げ方を誤っているということができる。
これとは別に、その後続くこの「被告」の主張に対する裁判所の考えについても、「被告」が主張する内容に応答するものとはいえず、話が噛み合っていない。
そのため、この段落の最後で「被告の上記主張は採用することができない。」と述べるのであるが、「被告」の主張を「採用」しないとする理由にはならない。
ストローマン Wikipedia
第二文について検討する。
この第二文であるが、「。」で区切るべきところを区切っておらず、一文が長すぎる。
様々な情報を一度に考えようとしている点で、この判決の文を書いた裁判官も論理的な過程を十分に整理して理解することができていないと思われる。
このような悪文となることを防ぐためには、一つ一つ内容を分解して、順を追って丁寧に検討することが必要である。
「同性カップルも異性カップルと変わらない人的結合関係にあるということができるし、」との部分を検討する。
まず、「同性カップルも異性カップルと変わらない人的結合関係」であるが、どのような基準によって「変わらない」と評価しているのか、ここでは明らかにされていない。
恐らくこの判決の論じ方から見れば、「性愛」という価値観に基づく「人的結合関係」として「変わらない」と論じているものと思われるが、そうであれば「近親者との人的結合関係」でも、「三人以上の人的結合関係」でも、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」でも「変わらない」と評価することができる。
また、ここでは「カップル」という「二人一組」を取り上げて比較するものとなっているが、人的結合関係の中には「トリオ」という「三人一組」もあるし、「四人一組」や、それ以上の人的結合関係もあるのであり、「二人一組」のみを取り上げればそれで済むかのように考えている点で妥当ではない。
これは、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っているということができる。
「「婚姻」を異性婚に限ると理解するとしても、婚姻と並んで「家族に関するその他の事項」が対象となっていること、「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解されるものの、他方で前記のとおり婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においてはこれに限定される必要はなく、同性カップルを「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然であるし、」との記載がある。
「異性婚」との文言がある。
しかし、これは法律用語ではないし、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「組合婚」「会社婚」などと「~~婚」と書けばどのような関係でも「婚姻」とすることができるというものでもないため、法律論として厳密に論じる際には「~~婚」という表現を用いることは適切とは言い難い。
また、ここで「異性婚」という表現を用いたとしても、常に「婚」の部分である「婚姻」そのものがどのような枠組みであるかが問われるのであって、この「婚姻」の内在的な限界を超えるものについては、法的に「婚姻」とすることはできないことが前提である。
よって、ここで「異性婚」という言葉を用いて、「異性間の人的結合関係」が「婚姻」となっていることを示したとしても、その言葉に対する形で「異性があれば同性もあるのではないか」との発想に基づいて「同性婚」という言葉を作ったとしても、そもそも「同性間の人的結合関係」を法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かの論点を回避することはできない。
そのため、「異性婚」という言葉が「異性間の人的結合関係」が「婚姻」として扱われている事実に基づくとしても、その文言は、それに対する形として示している「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする理由となるものではない。
このことから、この「異性婚」の言葉の響きに合わせる形で「同性婚」という言葉を用いたとしても、その「同性婚」という言葉は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする理由を示していることにはならない。
よって、「異性婚」という言葉に対する形で「同性婚」という言葉を用い、あたかも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのような前提に立って論じようとすることは誤りとなる。
法律論を論じる際には、このような言葉のトリックに惑わされることがないように注意する必要がある。
24条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」の文言について、ここでは「家族に関するその他の事項」の形で抜き出している。この点について意味を整理する。
まず、「家族」とは、「夫婦」と「親子」の関係によって形成されるものをいう。
これは、この一文の中でも「「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解される」と示している通りである。
そして、ここでいう「夫婦」とは、適法に「婚姻」した一組の男女を指す言葉であるから、「家族に関するその他の事項」の形で抜き出した場合においても、その「家族」の中には「婚姻」の意味が含まれている。
つまり、「家族に関するその他の事項」と表現した場合には、その中に「婚姻」「に関するその他の事項」の意味も同時に含まれていることになる。
当サイトでも「家族に関するその他の事項」の形で一つのまとまりのように表記している場合があるが、その意味で用いている。
この判決でも「家族に関するその他の事項」の形で抜き出しているのであるが、その意味を変更しようとするものとなっている。
具体的には、「婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においては」「夫婦及びその子の総体を中心とする概念」「に限定される必要はな」いとして、「夫婦」ではなく、「親子」にも、「親子」の関係を基本とする「兄弟」「姉妹」などに含まれない「同性カップル」と称する「同性間の人的結合関係」を「家族に関するその他の事項」の「家族」の文言の中に含めることができると述べるものとなっている。
そして、その「同性カップル」と称する「同性間の人的結合関係」を「「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然である」と結論付けようとしている。
しかし、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みは、24条1項の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて示しているように「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として一夫一婦制(男女二人一組)を定めている「婚姻」を前提として、その「婚姻」と結び付く形で形成される「家族」の枠組みを定めているものである。
これらは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという同一の目的を共有し、「生殖」によって子供が産まれるという因果関係を基にして血縁関係を明確にするという機能によって立法目的の達成を目指すものである。
そのため、一般的・抽象的にその間で生殖を想定することができる「夫婦」と、血縁関係を明確にするという機能を基にした「親子」の関係によるものしか「婚姻及び家族」の枠組みに含めることはできない。
よって、そこに含まれない「同性間の人的結合関係」を「家族」の文言に含めることができることを前提に、「「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然である」と述べていることは、誤りとなる。
「「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解される」との部分について検討する。
ここでは、「家族」の概念について、「夫婦及びその子の総体」としており、「夫婦」とその下に産まれた「嫡出子」を想定するもののようである。
これは国(行政府)の述べる「夫婦の配偶関係」と「親子・兄弟などの血縁関係」の意味とは異なると思われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ)しかし、現行民法典には「家族」という言葉は存在せず、少なくとも民法の観点からは「家族」を厳密に定義することは困難であるが(大村敦志「家族法(第3版)」23ページ・乙第35号証)、一般的な用語としての「家族」は、「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」を意味するものとされている(新村出編「広辞苑(第7版)」560ページ)。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
【参考】家族関係の基本知識 2022.12.19
【参考】血族について学ぼう!範囲や親族・姻族との違いを詳しく解説 2021.8.9
「家族」が「夫婦」と「親子」の関係を骨格としていることは確かであるが、それは「夫婦」とその「夫婦」の下にある「子」との関係までを指すのか、それに限らず「夫婦」と「親子」によって形成される「血縁関係者」まで含むと考えるのかは詳しく検討する必要がありそうである。
「婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においてはこれに限定される必要はなく、」との部分について検討する。
「婚姻、家族の形態が多様化し、」の部分であるが、法律論上、「婚姻、家族の形態」は24条1項の「婚姻」や2項の「婚姻及び家族」、民法上の「婚姻」や「家族」の制度で定められている事柄であり、これが「多様化」しているという事実はない。
よって、「婚姻、家族の形態が多様化し、」のように、「婚姻、家族の形態」が「多様化」していると述べていることは、事実に基づかない主張であり、誤りである。
恐らく、ここで言いたいものは「婚姻、家族」の形態ではなく、「共同生活者」や「世帯」の形態であると思われる。
しかし、「共同生活者」や「世帯」の形が変わったからと言って、法制度としての「婚姻」や「家族」の制度が影響を受けることはないのであり、これらを混同している点で妥当な説明ではない。
「これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においては」の部分についても、「国民の意識が多様化している」ものは、「共同生活者」や「世帯」の在り方であり、「婚姻、家族」の在り方ではない。
「共同生活者」や「世帯」の在り方についての「国民の意識」が変化したとしても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「婚姻及び家族」の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
よって、「現在においてはこれに限定される必要はなく、」の部分については、法学的な意味の「婚姻」や「家族」の意味を「共同生活者」や「世帯」などにあたる意味と取り違えて判断したものとなっており、「これに限定される必要はなく、」のように、「夫婦及びその子の総体」によるものに限定されないかのように述べている部分は誤りとなる。
「同性カップルを「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然であるし、」との部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」と「家族」の文言に内在する限界によって、「婚姻」とすることはできないし、「親子」や、「親子」を基本として形成される「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば「家族」とすることもできない。
よって、この判決は「文言上自然」と述べている部分についても、「文言上」において「自然」とはいえない。
そのため、「文言上自然」と述べていることは、この判決を書いた裁判官の独自の価値観として「自然」か「不自然」かを断定しようとするものであり、法解釈として妥当な内容ではない。
「憲法24条2項の裁量の限界を画するものとして「両性の本質的平等」と併せて「個人の尊厳」が挙げられているところ、個人の尊厳については同性愛者も異性愛者と変わらず尊重されるべきことは前記のとおりである。」との記載がある。
この文そのものの意味としてはその通りである。
法制度は個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものではないことから、「同性愛者」を称する者も、「異性愛者」を称する者も、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の枠組みに従って制度を利用するのであれば、「個人の尊厳」の文言が適用されることになる。
しかし、この部分の前のところからの文脈として、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、それが「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」に含まれないのであれば、「憲法24条2項」の「婚姻及び家族」の中には含まれず、「憲法24条2項」の「個人の尊厳」が適用されるものではない。
もう一つ、「同性愛者も異性愛者と変わらず」との記載があることから、婚姻制度があたかも「異性愛者」を称する者を対象とした制度であるかのような前提を有しているように見受けられる。
しかし、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
よって、婚姻制度が「異性愛者」を対象とした制度であることを前提としていることが誤りであるし、それに対する形で別の「性愛」を抱くものとして「同性愛者」を取り上げていることも誤りとなる。
この「ア」の項目の第二段落と第三段落は非常に読み取りづらいものとなっている。
そのため、この第二段落と第三段落を整理してまとめ直すと下記のようになる。
=======================================
「被告は、憲法24条2項も同条1項と同じく「両性」との文言が存すること等から、婚姻が異性間の人的結合を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請している規定と理解すべきである旨主張する。」
↓ ↓
「同性カップルの人的結合に関する事項は、憲法24条1項に基づく婚姻の自由は認められない」
「「婚姻」を異性婚に限ると理解する」
↓ ↓
「婚姻と並んで「家族に関するその他の事項」が対象となっている」
「「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解される」
↓ ↓
「他方で」「婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においてはこれに限定される必要はなく、」
↓ ↓
「同性カップルも異性カップルと変わらない人的結合関係にあるということができる」
「同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題である」
↓ ↓
「同性カップルを「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然である」
「同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。」
↓ ↓
「起草過程のとおり憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、」
「憲法24条2項の裁量の限界を画するものとして「両性の本質的平等」と併せて「個人の尊厳」が挙げられている」
↓ ↓
「個人の尊厳については同性愛者も異性愛者と変わらず尊重されるべき」
「これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものである」
↓ ↓
「同性カップルに関する事項についても、国会の立法裁量が与えられると同時に、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである。」
=======================================
しかし、この論理展開は誤っている。
24条2項の「婚姻及び家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられている枠組みであり、その目的の達成に沿わない人的結合関係についてはもともと対象としていない。
「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」には含まれないし、それが「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」に含まれないのであれば、「家族」にも含まれない。
「共同生活者」の在り方が多様化しても、「婚姻及び家族」の枠組みが変わることはない。
婚姻制度は「恋愛・性愛」を保護することを目的としていないため、「恋愛・性愛」の価値観を有しているか否かを「婚姻及び家族」の制度と結び付けて論じることも妥当でない。
24条2項の「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合に適用されるが、そこに当てはまらない場合には適用されない。
法制度は個々人の内心に関知していないため、そもそも「異性愛者」や「同性愛者」などと、その内心に基づいて分類を行っている事実はなく、これを区別していることを前提として論じていること自体が妥当でない。
このように、複数ヵ所の誤りが同時に展開されており、その主張の全体についても誤りとなる。
イ そこで検討するに、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきである。特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである(最高裁判所平成26年 第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁参照)。
【筆者】
最高裁判決の文面との対応関係は下記のようになる。
(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(PDF) (夫婦別姓訴訟)
一文目について、最高裁判決では「定められるべきものである。」となっているが、この判決では「定められるべきである。」となっており、「もの」が抜けている。
しかし、二文目について、最高裁判決でもこの判決でも「決められるべきものである。」のように、「もの」は抜けていない。
これを見ると、引用する際に統一的な形で規則性を持って文言を変えているわけではなく、その時々の気分で変えているだけであるように思われる。
本件諸規定の下では、原告らは婚姻制度を利用できずこれによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っており、このような不利益は個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過することができないものである。すなわち、婚姻は家族の単位の1つであり、前記のとおり、永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみであるところ、同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しないことを意味するものである。そして、前記のとおり、婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められるところ、原告らが婚姻制度を利用できない不利益は前記のとおり憲法13条に反するとまでは言えないものの、上記人格的利益を侵害されている事態に至っているといえる。
【筆者】
「本件諸規定の下では、原告らは婚姻制度を利用できずこれによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っており、このような不利益は個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過することができないものである。」との記載がある。
まず、「原告らは婚姻制度を利用できず」との部分について検討する。
ここでいう「原告ら」は「婚姻していない者(独身者)」であり、その個々人については婚姻制度(男女二人一組)の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、なお婚姻制度を利用することを希望したのであれば、婚姻制度を利用することが可能である。
よって、これらの「婚姻していない者(独身者)」である個々人について、「婚姻制度を利用できず」との認識は妥当でない。
次に、「これによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、」の部分を検討する。
先ほども述べたが、個々人については婚姻制度の要件に従う形で制度を利用する意思があるのであれば、婚姻制度を利用することは可能である。
そのため、「権利利益を享受する機会を得られ」ないかのように説明していることは妥当でない。
三つ目に、「法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っており、このような不利益は」との部分について検討する。
日本国憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々の「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、この「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、この状態について「不利益」が存在するわけではない。
よって、ここでは「婚姻制度を利用できずこれによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っており、このような不利益は」と述べているのであるが、そもそも法律論上は「婚姻していない者(独身者)」として既に完全な状態であり、それが何かと比べて劣っているなどということはない。
よって、その「婚姻していない者(独身者)」については、何らの「不利益」とされるような状態にあるわけではない。
実際に、日本国内では「婚姻していない者(独身者)」として生活している者がいるのであって、その者たちに「不利益」と称されるものが観念できない以上、その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成したところで、「不利益」と称される状態に変わるということにはならないからである。
よって、「婚姻していない者(独身者)」である個々人について、「重大な不利益を被っており、」や「このような不利益は」のように「不利益」があるかのような判断をしていることは誤りとなる。
これとは別に、「同性間の人的結合関係」が「婚姻」となっていないことについて、「重大な不利益」と論じていることが考えられる。
しかし、「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付けるものとして形成されている。
よって、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができない「同性間の人的結合関係」については、「生殖と子の養育」の趣旨に沿わないことから、「婚姻」とすることはできない。
「同性間の人的結合関係」が「婚姻」ではないとしても、そもそも「婚姻」という概念そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である以上は、「婚姻」の中に含まれる人的結合関係と含まれない人的結合関係が存在することはもともと予定されていることである。
もし「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」と比べて、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻している者(既婚者)」の得ている過大な優遇措置に関する規定が14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、格差が是正されることになる。
よって、「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」の間に婚姻制度の目的を達成するための手段として合理的な理由を説明することができない差異が生じている場合には、婚姻制度の内容となっている優遇措置が減少する方向で差異が是正されることになる。
そのため、何らかの差異があることを理由として、婚姻制度の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係までをも、「婚姻」という概念の中に含めなければならないということにはならない。
もしこのような形で婚姻制度の枠組みの中に、婚姻制度の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係を含めようとした場合には、婚姻制度そのものが「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための制度として機能しなくなる。
すると、「婚姻」という枠組みそのものが破壊されることになるし、他の様々な人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが雲散霧消してしまうことになる。
よって、「重大な不利益」として「到底看過することができない」と論じていることについて、これが「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間に何らかの差異が生じていることを認識し、その結果として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めなければならないという結論を導き出そうと試みるものであったとしても、その主張の内容は妥当なものではない。
また、「法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っており、」との部分についても、そもそも法学的な意味の「家族」とは、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みを指しており、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されている「婚姻」と同一の目的を共有する形で規律される枠組みであるから、この中に含まれる人的結合関係の範囲には、内在的な限界がある。
そのため、「家族」の概念に含まれる人的結合関係の範囲は予め定められており、この枠組みに当てはまらない場合については、「家族」として扱われないことも当然に予定されていることである。
よって、「家族」の中に含まれない人的結合関係があるとしても、それを「家族」の中に含めなければならないことにはならない。
また、「家族」の制度の対象とならない場合においても、単に優遇措置がないというだけであり、国家から個人に対して何らかの行為を制限したり、制裁を課すようなことはなく、個々人の有する「国家からの自由」という「自由権」を侵害する性質のものではない。
よって、「家族」の中に含まれないものがあるとしても、そこに「重大な不利益」が生じるというものではない。
四つ目に、「このような不利益は個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過することができないものである。」との部分について検討する。
ここでいう「個人の尊厳」は、「同性間の人的結合関係」が24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまることを前提として、その24条2項の「個人の尊厳」を適用することができるという考えの下に論じているものと考えられる。
しかし、24条2項の「個人の尊厳」を適用することができる対象は、24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合だけであり、ここに当てはまらない場合については、「個人の尊厳」を用いて「人格的利益」の侵害の可否を論じることはできない。
そこで、24条2項の「婚姻及び家族」の範囲について検討する。
24条2項の「婚姻及び家族」は、24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることを前提として、その「婚姻」と結び付く形で定められているものである。
よって、24条2項の「家族」についても、その直前に書かれている「婚姻」と同様に、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという同一の立法目的を共有し、その目的を達成するための手段として設けられた枠組みである。
そのため、この目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす関係に対してのみ法的効果や一定の優遇措置を与えるものであることを前提としており、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たさない人的結合関係については、法的効果や優遇措置を与えないとするものである。
このような差異が生じることは、「婚姻及び家族」の枠組みが設けられている時点から当然に予定されていることである。
そして、24条2項は「婚姻及び家族」の対象となっている場合については「個人の尊厳」の文言が適用されることになるが、「婚姻及び家族」の対象となっていない場合については「個人の尊厳」の文言は適用されない。
そして、ここでいう「同性間の人的結合関係」についても、「婚姻及び家族」の枠組みの「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「婚姻及び家族」の枠組みには含まれないため、24条2項の「個人の尊厳」が適用される対象ではない。
よって、そのような「同性間の人的結合関係」について、24条2項の「個人の尊厳」の文言が適用されることを前提として、その「人格的利益」の侵害の有無を論じようとしている点で誤っていることになる。
「婚姻は家族の単位の1つであり、前記のとおり、永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみであるところ、同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しないことを意味するものである。」との記載がある。
「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみであるところ、」との部分について検討する。
まず、この判決は最高裁判決の示した「婚姻の本質」と称する説明を法学的な意味で「婚姻制度を利用している者」の形成する法律関係の意味ではなく、文学的な語感に基づいて、「精神的及び肉体的結合」の部分を「恋愛・性愛」に対応するものである考えているようである。
そのため、ここでは「婚姻制度」は、「永続的な」「恋愛・性愛」の「相手を選び、公証する制度」と考えていることになる。
しかし、そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「恋愛・性愛」の有無や「恋愛・性愛」を有した場合にそれがどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「恋愛・性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、婚姻制度は「恋愛・性愛」の「相手を選び、公証する制度」ではない。
ここでは「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみであるところ、」と述べているが、そもそも婚姻制度は「恋愛・性愛」(ここでいう『精神的及び肉体的結合』)の「相手を選び、公証する制度」ではないという点で誤っている。
また、「恋愛・性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度は20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、制度を利用する者に「恋愛・性愛」という特定の価値観を抱くことを求めることは19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、「恋愛・性愛」以外の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で内心に基づいて区別取扱いをするものとなることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「恋愛・性愛」を保護することを目的とした制度が存在していても許されるかのような前提で論じている部分も誤りである。
「同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しないことを意味するものである。」との部分について検討する。
「婚姻及び家族」の枠組みは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係を対象とする制度であり、その対象とならない人的結合関係が存在することは当然予定されていることである。
「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまる場合は「法的に家族」となるが、当てはまらない場合は、「法的に家族」とならないということは、制度が政策目的を達成するための手段として定められている枠組みである以上は当然のことである。
「法的に家族として承認しないことを意味するものである。」の理由として、「公証の利益も得られないことは、」を挙げている点は、因果関係を認めることができないため妥当でない。
ここでは、「カップル」のように「二人一組」のみを取り上げるのであるが、人的結合関係の中には「三人一組」の「トリオ」や、それ以上の人的結合関係も存在するのであり、「カップル」という「二人一組」の単位だけを取り上げて論じていることは、「カップル信仰論」となっている。
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められるところ、原告らが婚姻制度を利用できない不利益は前記のとおり憲法13条に反するとまでは言えないものの、上記人格的利益を侵害されている事態に至っているといえる。」との記載がある。
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性(前記1(4)エ)も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められるところ、」との部分について検討する。
この「(前記1(4)エ)」で示している「国民の意識」は、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けた制度となっていることを示すものである。
その「国民の意識」が「婚姻」を「重要」と考えているのであれば、それは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として妥当な内容となっていることが知られていることによるものである。
これは、現在の婚姻制度が「男女二人一組」の制度となっていることによって形成されている「国民の意識」であり、その枠を変えてしまった場合には、「国民の意識」が「婚姻」を「重要」であるとは考えなくなることも起こり得る。
そのため、このような現在の婚姻制度の枠組みによって形成されている「国民の意識」を根拠として、その制度の枠組みを変更しようとすることは、制度の枠組みを変更するための理由にはならないことに注意が必要である。
「婚姻制度を利用できるか否かは」の部分であるが、婚姻制度は要件に従う形で、誰もが利用することが可能であり、たとえ「同性愛者」を称する者であるとしても「婚姻制度を利用できる」ということができる。
そのため、「婚姻制度を利用できるか否かは」を論じていることは誤りである。
ここで問われているのは、どのような人的結合関係が「婚姻」の中に含まれるか、婚姻制度の対象となっているかであり、「婚姻制度を利用できるか否か」ではないのである。
この点で、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には、その目的との関係で内在的な限界が存在するにもかかわらず、その限界を取り払うことを求める意味で、「婚姻制度を利用できるか否か」に論点をすり替えるものとなっている点で、妥当な主張ではない。
「婚姻制度を利用できるか否か」を問う場合であっても、そこでいう「婚姻」とは何かが問題となるのであり、その対象とならない場合についても、「婚姻制度を利用できるか否か」の論点によって論じることができるかのように主張することは適切ではない。
「婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められるところ、」との部分であるが、この文そのものの意味についてはその通りである。
婚姻制度は個々人の「性愛」を審査して区別取扱いをするものではないため、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度の要件に従う形で婚姻する意思があるのであれば、適法に婚姻制度を利用することが可能である。
しかし、先ほども述べたことと同様に、「婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するか」の文面の、ここでいう「婚姻」とは何かが問われるのであり、その「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的の関係で、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲には内在的な限界がある。
この「婚姻」の枠を超える形の人的結合関係を「婚姻」として扱うことを求めることができることにはならないし、そのような主張を「人格的利益」によって裏付けることもできない。
「原告らが婚姻制度を利用できない不利益は前記のとおり憲法13条に反するとまでは言えないものの、上記人格的利益を侵害されている事態に至っているといえる。」との部分について検討する。
「原告らが婚姻制度を利用できない」の部分について、個々人は婚姻制度(男女二人一組)の要件に従う形でなお婚姻制度を利用することを望むのであれば、婚姻制度を利用することができるため、「婚姻制度を利用できない」との認識は妥当でない。
「不利益」の部分についても、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、何らの人的結合関係も形成しておらず、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、「不利益」とされるものは存在しない。
よって、「婚姻制度を利用できない不利益」のように、「婚姻していない者(独身者)」の状態に「不利益」があるかのように考えている点は誤りである。
また、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その対象となる場合とならない場合があることは、制度が政策的なものである以上は当然のことである。
そして、婚姻制度の対象でないとしても、それは優遇措置が得られないというだけであり、国家から個人に対して具体的な侵害行為が生じているわけではない。
そのため、婚姻制度の対象でないとしても、そこに「不利益」と言われるものはない。
これとは別に、もし「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で合理的な理由のない差異を生じさせていることとなり、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
この場合、その不必要に過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
「憲法13条に反するとまでは言えないものの、」との部分について、そもそも「不利益」が存在しないし、国家から個人に対して具体的な侵害行為が行われているわけでもないため、「憲法13条」の審査を行う前提にはない。
「人格的利益を侵害されている事態に至っているといえる。」との部分を検討する。
ここでいう「人格的利益」は、憲法24条2項の「個人の尊厳」の文言から導き出しているようであるが、そもそも24条2項の「個人の尊厳」の文言は、「婚姻及び家族」の枠組みの対象となっている場合において適用されるものであり、「婚姻及び家族」の枠組みの対象とはなっていない場合には、適用されない。
そして、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」には含まれないし、「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」に含まれないのであれば、「家族」にも含まれない。
よって、これに含まれない人的結合関係を形成する者に対しては、24条2項の「個人の尊厳」が適用される対象ではなく、「人格的利益」が実現されているか否かを検討する前提を欠いている。
そのため、24条2項の「個人の尊厳」の文言が適用されることを前提として「人格的利益を侵害されている事態に至っているといえる。」と述べている部分についても、その前提を誤っており、妥当でない。
この段落は非常に読み取りづらい内容となっている。そのため、前後関係を整理して、下記でまとめ直す。
「婚姻は家族の単位の1つ」
↓ ↓
「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみである」
↓ ↓
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項」
「国民の意識における婚姻の重要性」
↓ ↓
「婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められる」
↓ ↓
「同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しないことを意味する」
↓ ↓
「原告らは婚姻制度を利用できずこれによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、法的に家族として承認されない」
↓ ↓
「重大な不利益を被っており、このような不利益は個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過することができない」
「人格的利益を侵害されている事態に至っている」
↓ ↓
「原告らが婚姻制度を利用できない不利益は」「憲法13条に反するとまでは言えない」
これでも長いため、更にまとめ直すと、要するに下記の通りである。
「婚姻して家族を形成する」ことは「尊重されるべき人格的利益である」。
「婚姻制度を利用できず」に「法的に家族として承認されない」ことは「人格的利益を侵害されている事態に至っている」である。
結局、この段落では、これだけのことを述べているに過ぎない。
しかし、このように述べたところで、その「婚姻」や「家族」の枠組みそのものが、立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係のみを対象とするものであることから、この「婚姻」や「家族」の概念に含まれる内在的な限界を超える人的結合関係を「婚姻」や「家族」の中に含めて考えることができることにはならない。
そのため、「婚姻」や「家族」に含まれない人的結合関係について、24条2項の「個人の尊厳」が適用されることはないのであり、この「個人の尊厳」が適用されることを前提して、「人格的利益」が侵害されているか否かを論じることもその前提を欠くものであり、誤りとなる。
また、本件諸規定の基となった旧民法や明治民法制定時における学説にも、婚姻について必ずしも子を得ることを目的としないとの理解が存在し、明治民法の起草過程における議論の結果、生殖能力を有しないことを婚姻障害事由等にしていないこと(前記1(2)イ)からすれば、本件諸規定を含む婚姻制度の目的には婚姻相手との共同生活の保護にもあったものと認められる。また、前記1(4)エのとおり、平成26年段階の結婚を希望する未婚の者に対する意識調査において、国民の婚姻制度を用いる理由は、子を持つことと同様又はそれ以上の比率で、婚姻相手と一緒にいること、家族となることにあると認められることから婚姻制度の目的において、婚姻相手との共同生活の保護という側面が強くなってきていると認められる。加えて、今日、婚姻件数、婚姻率、合計特殊出生率及び子のいる世帯の割合は本件諸規定の立法時に比べて大きく低下しており(前記1(4)オ)、婚姻は全ての者が行うものではなく、各人が、生涯を共に過ごす者を選び、公認された家族を作るという人生における自己決定の尊重と保護という側面が強くなってきているといえ、婚姻及び家族の実態やその在り方に対する国民の意識が変遷しているということができる。
【筆者】
この段落の第一文と第二文について、三回登場する「目的」の文言を中心に合わせて検討する。
「目的」の文言を下記のように、A、B、Cに分けて考える。
A 「本件諸規定の基となった旧民法や明治民法制定時における学説にも、婚姻について必ずしも子を得ることを目的としないとの理解が存在し、明治民法の起草過程における議論の結果、生殖能力を有しないことを婚姻障害事由等にしていないこと(前記1(2)イ)からすれば、」
B 「本件諸規定を含む婚姻制度の目的には婚姻相手との共同生活の保護にもあった」
C 「結婚を希望する未婚の者に対する意識調査において、国民の婚姻制度を用いる理由は、子を持つことと同様又はそれ以上の比率で、婚姻相手と一緒にいること、家族となることにあると認められることから婚姻制度の目的において、婚姻相手との共同生活の保護という側面が強くなってきている」
ここで使われている「目的」の文言がどのような意味で用いられているかを正しく読み解くために、下記で「目的」の意味の多義性について検討する。
① 「国の立法目的」の意味
概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。
例
・「会社法」の立法目的
・「宗教法人法」の立法目的
・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること
② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味
ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。
制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)
例
・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。
→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。
・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。
→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。
・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。
→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。
この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。
これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。
そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。
③ 「個々人の利用目的」の意味
個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。
例
・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。
・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。
・私は子供をつくることを目的として婚姻する。
このように、同じ「目的」の文言が使われている場合でも、その「目的」の意味は異なる意味で使われている場合がある。
そこで、この段落のA、B、Cの文中で用いられている「目的」の意味についても、いずれの意味であるかを丁寧に読み解く必要がある。
<A>の「本件諸規定の基となった旧民法や明治民法制定時における学説にも、婚姻について必ずしも子を得ることを目的としないとの理解が存在し、明治民法の起草過程における議論の結果、生殖能力を有しないことを婚姻障害事由等にしていないこと(前記1(2)イ)からすれば、」との文脈における「目的」の意味から検討する。
「婚姻について必ずしも子を得ることを目的としないとの理解が存在し、」と述べている部分は、下記の部分に対応するものとなっている。
「1(2)イ(イ)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当時の学説においても、婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、必ずしも子を得ることを目的としないという考えがあった(乙4)。また、律令制度以来の離婚法では「無子」が棄妻の一事由とされていたが、明治民法においては、生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった(甲A209、210、553)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記の「1(2)イ(イ)」や<A>の文には、「婚姻」や「夫婦」の文言がある。
この「婚姻」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを立法目的(①の『国の立法目的』の意味)として、「生殖と子の養育」の観点から、その間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で法的に結び付けるものとして設けられた枠組みである。
そして、「夫婦」とは、婚姻制度を利用している「男女」のことである。
これを前提に考えると、まず、「1(2)イ(イ)」の「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもの」という文は、「婚姻」や「夫婦」との文言から、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的(①の「国の立法目的」の意味)とした具体的な制度の枠組みが存在することを前提としており、その制度の枠組みが機能すると「同居義務」などによって「共同生活」という結果が生じることについて述べるものとなっている。
よって、この「1(2)イ(イ)」の「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもの」との文脈で使われている「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」を意味している。
また、この「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の部分に着目した説明であることは、この文の内容は「サークル」「部活」「組合」「会社」「宗教団体」「政党」などの他の様々な人的結合関係の枠組みとの間で区別するために、その機能を明らかにするための文脈となっていることになる。
次に、「1(2)イ(イ)」や<A>の「必ずしも子を得ることを目的としない」という部分で使われている「目的」の意味は、これが「学説」について説明するものとなっていることや、「1(2)イ(イ)」の所で「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、」の文に続く形で説明されていることから、上記と同様に「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味のであると考えることが妥当である。
また、この「必ずしも子を得ることを目的としない」の文は、「1(2)イ(イ)」の「生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった」や、<A>の「生殖能力を有しないことを婚姻障害事由等にしていない」との文と結び付く形で説明するものとなっている。
そのため、婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用することを望む者が、婚姻障害に該当するか否か、つまり、法律関係を有効に形成することができるか否かについて述べる文脈で使われていることになる。
そして、 婚姻制度の機能の面から「婚姻」を有効とすることができることを述べているものであるから、この「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味である考えることが妥当である。
よって、上記のように<A>のいう「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味であると考えることが妥当である。
<B>の「本件諸規定を含む婚姻制度の目的には婚姻相手との共同生活の保護にもあった」との文脈における「目的」の意味を検討する。
ここに「婚姻相手」とあるように、「婚姻」という「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的(①の「国の立法目的」の意味)とした枠組みが存在することを前提として、その制度を利用する場合に、その「相手」となる者との間の「共同生活」に対して「保護」を行うことについて、「目的」と述べているものである。
これは、婚姻制度が機能した場合にどのような「保護」(効果)が生じるかに着目した説明となっている。
よって、<B>のいう「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味であると考えることが妥当である。
<C>の「結婚を希望する未婚の者に対する意識調査において、国民の婚姻制度を用いる理由は、子を持つことと同様又はそれ以上の比率で、婚姻相手と一緒にいること、家族となることにあると認められることから婚姻制度の目的において、婚姻相手との共同生活の保護という側面が強くなってきている」との文脈における「目的」の意味の検討する。
ここでは「結婚を希望する未婚の者に対する意識調査」における「国民の婚姻制度を用いる理由」について述べるものとなっている。
そして、その理由は、「子を持つこと」、「婚姻相手と一緒にいること」、「家族となること」が挙げられており、個々人が婚姻制度を利用する場合の目的(制度の活用方法)について触れていることを確認することができる。
ここで「婚姻相手と一緒にいること」と述べられている部分について、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な制度が存在することを前提として、その制度を利用する場合に、その制度の枠の相手方となる者と「一緒にいること」を意味するのであり、婚姻制度の要件を満たさない者については、そもそも「婚姻相手」に含まれないから、「婚姻相手と一緒にいること」という意味の中に含まれていないことに注意が必要である。
また、「家族となること」の部分についても、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な制度が存在することを前提として、その制度を利用する場合に、その制度の枠に当てはまる者との関係を指すことから、「家族」の制度の対象外の関係については、「家族となること」という意味の中に含まれないことに注意が必要である。
よって、「婚姻相手と一緒にいること」や「家族となること」の意味を理由として、そもそも「婚姻」や「家族」の枠組みに含まれない人的結合関係を「婚姻」や「家族」の中に含めるべきであるとの主張を正当化することができる理由にはならないことを押さえる必要がある。
これに続く形で、「婚姻制度の目的」が述べられていることから、ここで使われている「目的」の意味は、「③ 個々人の利用目的」の意味ということができる。
ただ、「婚姻制度の目的」の文言の後の部分との関係に視点を移すと、「婚姻制度の目的において、婚姻相手との共同生活の保護という側面が強くなってきている」と述べるものとなっている。
これは、<B>のところで説明した「婚姻相手との共同生活の保護」を「目的」としているものであることから、<B>のところと同じように「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味で用いられていることになる。
しかし、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」について増減があるとしても、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」が変化することはなく、そこには因果関係を認めることができない。
よって、この文が婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」の変化することによって、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」が変化するかのような説明をしていることは誤りである。
上記のとおり、<C>のいう「目的」の意味は、「③ 個々人の利用目的」の意味と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味を混乱したまま用いていることになる。
<A><B><C>をまとめると、この段落の第一文、第二文で用いられている「目的」の文言は、②の「制度が機能することによって生じる結果(目的)」か、③「個々人の利用目的」を意味している。
そのため、①の「国の立法目的」を示すものは存在しないことになる。
また、ここで使われている「目的」という文言だけを見て、その文脈の中で使われている「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」や「③ 個々人の利用目的」の意味から刈り取って、あたかも「目的」の文言が①の「国の立法目的」を意味しているかのようにのように意味を置き換えようとすることは、不正な手続きであり、誤りであることに注意が必要である。
この判決では、②の「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味で使われている「目的」の部分を見て、それを①の「国の立法目的」であるかのように「目的」の意味を混同して論じており、結論を導き出すまでの判断の過程が誤っている。
「今日、婚姻件数、婚姻率、合計特殊出生率及び子のいる世帯の割合は本件諸規定の立法時に比べて大きく低下しており(前記1(4)オ)、婚姻は全ての者が行うものではなく、各人が、生涯を共に過ごす者を選び、公認された家族を作るという人生における自己決定の尊重と保護という側面が強くなってきている」との記載がある。
まず、「今日、婚姻件数、婚姻率、合計特殊出生率及び子のいる世帯の割合は本件諸規定の立法時に比べて大きく低下しており」との部分について、下記の記事が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、民法が制定された当初から子を産まない夫婦が一定数いたことを考えるなら、そうした夫婦の数が増えたというだけでは本質的な反論にはならないからである。
そもそも結婚したカップルが結果的に子を産むかどうかは結婚したときには分からないため、法律としては結果的に子を産もうが産まなかろうがそうした可能性のある関係に法的保護をあたえると規定するしかない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
このように、婚姻制度を立法したときから子のいない夫婦がいることはもともと予定されていたことである。
そのため、個々人が婚姻制度を利用する場合の利用方法に変化があったとしても、それをもって婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みが変わるということを理由づけることにはならない。
次に、「婚姻は全ての者が行うものではなく、各人が、生涯を共に過ごす者を選び、公認された家族を作るという人生における自己決定の尊重と保護という側面が強くなってきている」との部分について検討する。
これは具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、個々人がどのような価値観に従って利用するかという「③ 個々人の利用目的」の変化を述べるものであり、これをもって婚姻制度についての「① 国の立法目的」や「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」が変化することにはならない。
「婚姻及び家族の実態やその在り方に対する国民の意識が変遷しているということができる。」との記載がある。
ここでいう「婚姻及び家族の実態やその在り方」とは、「③ 個々人の利用目的」について述べている部分に対応するものであり、その「国民の意識」とは、まさに国民が婚姻制度を利用するか否かや、利用する場合における「個々人の利用目的」についての「変遷」を述べるものである。
しかし、これは「婚姻及び家族」という枠組みそのものを変更することができるとする理由になるものではない。
前記のとおり、婚姻は男女によるものという社会通念は現在においてもなお失われていないものの、今日変わりつつある。すなわち、前記1(1)~(3)のとおり、本件諸規定の立法過程に影響を与えた諸外国の状況が変化してきている。欧米ではキリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていたが、家族の在り方及び前記知見の変化によりこれを国家的に認める動きが生じ、平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。また、前記1(1)のとおり、我が国にも影響を与えた同性愛者を精神病として病理化する知見は、今日では誤りであったことが明白となっている。国際連合は、平成23年、国連人権規約として1966年に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約を根拠に、今日、性的指向に基づく差別は禁止されていることを決議し(前記1(3)ウ)、我が国に対しても前記1(4)カのとおり、平成20年以降、自由権規約委員会、社会権規約委員会から、同性カップルの権利についての懸念と勧告が度々表明されている。これらは、同性カップルにも異性カップルと同様の婚姻の意思(上記①)を有することができ、同等の権利を与えるべきという動きが世界の潮流となっているものと評価することができる。
【筆者】
「婚姻は男女によるものという社会通念は現在においてもなお失われていないものの、今日変わりつつある。」との記載がある。
「婚姻は男女によるもの」であることについて、ここでは「社会通念」に理由があると考えているようである。
しかし、「婚姻は男女によるものという社会通念」が存在することは、「婚姻」という概念そのものが、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを一定の形式で結び付けるものであることが理由である。
そのため、「婚姻」についての「社会通念」を問うた場合には、当然「男女によるもの」という答えが出てくることになる。
これが「現在においてもなお失われていない」や「今日変わりつつある」と述べて、変化するものであるかのように述べているが、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係の範囲は、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」と「その目的を達成するための手段」として整合的な要素を満たすか否かによって導かれているものであり、「社会通念」があるとかないとか述べたところで変化するものではないし、何らかの結論を導き出すことができるというものではない。
「本件諸規定の立法過程に影響を与えた諸外国の状況が変化してきている。」との記載がある。
まず、外国の法制度は、その国の社会事情の中で発生している不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として設けられているものである。
そのため、その外国の法制度と日本国の法制度の間で何らかの類似点を見出すことができる場合があるとしても、それはそれぞれの国の社会事情の中で形成された別個の制度であり、同一の制度を指していることにはならない。
また、外国の法制度について、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という言葉をあてて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならない。
それぞれの国の社会事情の中で生じている問題を解消することを目的として制度が設けられているだけであり、その立法目的や、その立法目的を達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
よって、「諸外国の状況が変化してきている。」としても、日本国の法制度における「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるとする根拠となるわけではない。
もし翻訳者が「婚姻」という言葉を使って翻訳している外国の法制度が変化したことによって、日本国の「婚姻」の立法目的や、その立法目的を達成するための手段となる枠組みが変動したり、変更することが可能となるようなことがあれば、外国の法制度において「近親者との人的結合関係」や「三人以上の複数名」、「婚姻適齢に満たない者」との間で何らかの制度が存在した場合に、日本国の「婚姻」においてもそれを認めなければならないことになるのであり、妥当ではない。
「欧米ではキリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていたが、家族の在り方及び前記知見の変化によりこれを国家的に認める動きが生じ、平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」との記載がある。
まず、「欧米ではキリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていた」の部分であるが、日本国においては、憲法19条で「思想良心の自由」が定められていることから、個々人の内心そのものが否定されることはないのであり、「同性愛自体」についても否定されているという事実はない。
「平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」との部分であるが、イスラム教の普及する地域では、古くから「一夫多妻制」を採用している事実がある。
そのため、単に「同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」ことをもって、日本国の婚姻制度を変更しなければならないとする理由になるわけではないし、日本国の婚姻制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段となる枠組みが変わることにはならない。
「我が国にも影響を与えた同性愛者を精神病として病理化する知見は、今日では誤りであったことが明白となっている。」との記載がある。
婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
そのため、そもそも日本国憲法の下では憲法19条で「思想良心の自由」が定められており、その内心そのものが否定されるようなことはないことが前提であるが、「同性愛者を精神病として病理化する知見」が誤りであることが明白となったと誰かが宣言したとしても、そのことと婚姻制度との間には何らの因果関係も認められない。
また、婚姻制度の内容が「男女二人一組」の内容であるとしても、そのことは「異性愛者」を称する者を対象とする制度であることを意味しない。
もし「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情に着目して法制度を立法しているのであれば、そのこと自体で20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「異性愛」という思想、信条、信仰、感情を有する者に対して制度を設け、その他の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で異なる取扱いをすることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
同様に、「同性愛」に着目して法制度を立法した場合においても、そのこと自体で憲法に違反することになるのであり、「同性愛者を精神病として病理化する知見は、今日では誤りであったことが明白となっている。」などということを理由として、「同性愛」に着目した法制度を立法したのであれば、その制度は憲法に違反することになる。
よって、このような事柄を根拠として婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。
「国際連合は、平成23年、国連人権規約として1966年に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約を根拠に、今日、性的指向に基づく差別は禁止されていることを決議し(…)、我が国に対しても前記1(4)カのとおり、平成20年以降、自由権規約委員会、社会権規約委員会から、同性カップルの権利についての懸念と勧告が度々表明されている。」(カッコ内省略)との記載がある。
まず、日本国憲法では19条で「思想良心の自由」が定めらていることから、個々人の内心は内心に留まる限りは絶対的なものとして保障されている。
よって、ここでいう「国際連合」が「性的指向に基づく差別は禁止されていることを決議し」としているが、そもそも日本国憲法制定当初からこのような内心に基づく法的な差別取扱いは禁じられているのであり、その議決が日本国の法制度に何らかの影響を与えるとする理由にはならない。
次に、「同性カップルの権利についての懸念と勧告が度々表明されている。」との部分であるが、「同性カップルの権利」との表現が妥当でない。
法的には「権利能力」を認められている個々の自然人について「権利」を認めることはできるが、「同性カップル」という何らかの人的結合関係については、「法人格」を取得して「法人」としての「権利能力」を認められていないのであれば、「権利」の主体として認められない。
よって、「同性カップルの権利」と表現している点について、人的結合関係に「権利能力」があるかのような論じ方をしている点で適切な表現ではない。
ただ、個々人が何らかの人的結合関係を形成することについては、21条1項「結社の自由」で保障されることになる。
もう一つ、ここでは一つの文として「性的指向」と「同性カップル」を結び付けて論じるものとなっているが、法制度は個々人の内心には中立的な内容でなければならないことから、個々人の内心に着目して法制度を立法している場合には、そのこと自体が憲法違反の原因となるのであり、それが許されるかのような前提で論じていることも適切ではない。
「同性カップルにも異性カップルと同様の婚姻の意思(上記①)を有することができ、同等の権利を与えるべきという動きが世界の潮流となっているものと評価することができる。」との記載がある。
「婚姻の意思」とあるが、ここでいう「婚姻」とは何かが問われることになる。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
これは、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせの間に「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、その立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため「婚姻」とすることはできない。
よって、「同性間の人的結合関係」については、婚姻制度の対象とはなっていないため、その間で婚姻制度を利用する意思を形成することはできない。
「(上記①)」の部分については、そもそも最高裁判決の「婚姻の本質」と称する説明を法的な意味で読み解くものではなく、文学的な語感に基づいて理解することを試みるものとなっており、法律論から逸脱するものであるため妥当でない。
「同等の権利を与えるべきという動きが世界の潮流となっているものと評価することができる。」との部分であるが、そもそもここでは「カップル」という「二人一組」を前提として、それを単位であるかのように考えて「同等」と論じている点で妥当でない。
法律論上は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている「自然人」の間、あるいは「法人」の間でしか比較を行うことはできない。
ここでいう「カップル」と称する「二人一組」については、「法人」としての法人格を取得しているものではないことから、個々の「自然人」が人的結合関係を形成しているだけである。
そして、個々の「自然人」は婚姻制度の要件に従う形で「同等」に制度を利用することができるのであり、既に「同等の権利」を有しており、それが与えられていないことを前提として「同等の権利を与えるべき」との主張をすることは、前提となっている事柄を見誤ったものであり、妥当でない。
ここでは、「カップル」という「二人一組」を取り上げて論じているが、なぜ「二人一組」だけを取り上げているのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている。
我が国においても、政府は、平成22年以降、性的指向に基づく差別を禁止する措置を様々な分野で宣言し、地方自治体は、平成27年以降、人権保障、多様性の尊重及び安心して暮らせる社会づくりの目的でパートナーシップ制度を導入し始め、令和4年11月時点の導入自治体の人口カバー率は62.1%であるし、国会でも平成27年以降、同性婚の可否に関する質疑が度々行われている(前記1(4)ア)。国民の意識においても、平成27年段階で、同性婚に賛成する者の数は50%前後で、反対派をわずかに上回っていたが、賛成派の割合は年々増加し、平成30年の時点で60%を超えるようになり、その後も増加を続けている(前記1(4)イ)。同性婚の実現への支持を表明する企業団体、弁護士会は増加し続けている(前記1(4)カ)。これらのことから、我が国でも婚姻は異性のものという社会通念に疑義が示され、同性婚に対する国民の理解も相当程度浸透されているものと認められる。
【筆者】
「我が国においても、政府は、平成22年以降、性的指向に基づく差別を禁止する措置を様々な分野で宣言し、」との記載がある。
法的な「差別」を禁止する場合、その審査の方法には「法適用の平等」と「法内容の平等」の違いがある。
◇ 「法適用の平等」と「法内容の平等」の違い
14条の「平等原則」における審査では、「法適用の平等」と「法内容の平等」を分けて考える必要がある。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The
Burning Issues vol.27】 2022/09/25
◇ 「法内容の平等」の審査
「法内容の平等」については、➀「区別(差別)」の存否と、②「区別(差別)」が存在した場合における「合理的な理由」の存否が問われることになる。
そして、②の「合理的な理由」の内容については、「立法目的」とその「達成手段」が問われることになる。
「法適用の平等」については「絶対的平等」であり、個々人の「性的指向」を審査して特定の「性的指向」を有する者とそうでない者を区別し、法制度の適用をしないなどの措置を行った場合には、「法適用の平等」に違反するものとして14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「法内容の平等」については、個々人の「性的指向」を審査して特定の「性的指向」を有する者とそうでない者を区別する法制度を立法した場合について考えられる。ただ、「性的指向」と称している者は、個々人の内心にのみ存在するものであり、外部から客観的に識別することができるものではない。そのため、これを審査して区別取扱いをする場合には、14条の「平等原則」だけでなく、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」にも関わるものである。
もう一つ、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをしている事実はないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。そのため、婚姻制度において「性的指向」と称するものによる区別取扱い(差別)は存在しないことを押さえる必要がある。
「地方自治体は、平成27年以降、人権保障、多様性の尊重及び安心して暮らせる社会づくりの目的でパートナーシップ制度を導入し始め、令和4年11月時点の導入自治体の人口カバー率は62.1%であるし、」との記載がある。
しかし、「地方公共団体」の「パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度に抵触する場合には違法となる。
婚姻制度の立法目的と、その立法目的を達成するための手段は、下記のように整理することができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「地方自治体」の「パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
また、憲法は14条で「平等原則」、19条で「思想良心の自由」、20条1項・3項、89条で「政教分離原則」を定めており、特定の思想や信条に着目して法制度を整備し、何らかの優遇措置を与えることは違憲となる。
「地方自治体」の「パートナーシップ制度」の内容が、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として定められたものとなっている場合には、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「同性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護し、その他の思想、信条、信仰、感情を保護しないことになることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
他にも、「同性愛」の思想、信条、信仰、感情を有する「同性愛者」を称する者を対象とした制度となっていることについても、個々人の内心に基づいて区別取扱いを行い、その他の思想、信条、信仰、感情を有する者との間で、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
さらに、婚姻制度が「生殖と子の養育」の観点から一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男女二人一組」を対象としていることに対して、「パートナーシップ制度」はそのような観点を含まない「二人一組」のみを制度として一定の優遇措置を設けるものとなっている。
このような措置は、「三人一組」や「四人一組」などその他の人的結合関係を形成する者との間や、何らの人的結合関係も形成していない者との間で正当化することのできない差異を生じさせるものであることから、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、民法上の婚姻制度や憲法上の規定との整合性を検討をしないままに、「地方公共団体」の「パートナーシップ制度」が適法な制度であることを前提として論じていることは、妥当でない。
詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「国会でも平成27年以降、同性婚の可否に関する質疑が度々行われている」との記載がある。
しかし、「国会」で「質疑」が行われていることを理由として、憲法上の規範の意味が変わることはないのであって、それによって法解釈の結論が変わることもない。
そのため、これを裁判所が判決文における法解釈を導く際の根拠として取り上げていること自体が不適切ということができる。
「国民の意識においても、平成27年段階で、同性婚に賛成する者の数は50%前後で、反対派をわずかに上回っていたが、賛成派の割合は年々増加し、平成30年の時点で60%を超えるようになり、その後も増加を続けている」との記載がある。
まず、そもそも「同性間の人的結合関係」については、それが「親子」や「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに含まれないのであれば、「家族」の中に含まれないのであり、24条2項の「家族」が適用される対象ではない。
よって、これを「家族」の中に含まれることを前提として、論じようとしていること自体が誤りとなる。
これとは別に、このような「国民意識」と称する調査を根拠として持ち出しているということは、「同性婚に賛成する者の数」が多いか少ないかによって、憲法24条2項に違反するか否かが変わることを前提として論じていることになる。
しかし、24条2項に違反するか否かは法解釈の問題であるから、「賛成派」や「反対派」の数というその時々の調査によって結論が変わるような資料を根拠として規範の意味を論じることも不適切である。
「同性婚の実現への支持を表明する企業団体、弁護士会は増加し続けている」との記載がある。
企業や団体、弁護士会などは、様々な意見を表明する自由があり、実際に様々な意見を表明しながら活動を行っている。
ここで取り上げようとしてるものも、その自由の中で表明された一つの意見に過ぎない。
また、企業や団体、弁護士会などが賛否を表明したからと言って、それによって裁判所が法解釈を行う際に合憲・違憲の判断が変わることはない。
もしそれによって結論が変わるようなことがあれば、法の支配、立憲主義、法治主義を逸脱することになるのであり、このような事柄を結論を導き出すまでの解釈の過程として用いていること自体が不適切である。
裁判所は賛成・反対の数によって結論が変わるような判断を担う機関ではない。
裁判所に期待されている役割は、世論の集約ではなく、法の解釈であること十分に認識する必要がある。
「我が国でも婚姻は異性のものという社会通念に疑義が示され、同性婚に対する国民の理解も相当程度浸透されているものと認められる。」との記載がある。
「婚姻は異性のものという社会通念」の部分について、そもそも「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から「男性」と「女性」の組み合わせを選び出し、一定の枠組みによって結び付けるものとして形成されているものであり、その「婚姻」が「異性のもの」とされる「社会通念」は、「婚姻」という枠組みが「男性」と「女性」の組み合わせを一定の枠組みによって結び付けるものとして形成された概念であることが理由である。
この「婚姻」という概念そのものが有する目的と、その目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす枠組みによって「婚姻」という概念に含めることができる範囲には内在的な限界があり、それは「社会通念」があるかないかを述べるだけで変わるというものではない。
「同性婚に対する国民の理解も相当程度浸透されているものと認められる。」との部分についても、法解釈はその時々の国民の賛成意見が多いか、反対意見が多いかによって変わるものではない。
裁判所は国民の意見の集約を行うための機関ではなく、このような事柄によって結論が変わるかのような前提で論じていることが不適切である。
以上のとおり、本件諸規定の下で原告ら同性カップルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っていること、婚姻制度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつあること、婚姻に対する社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていないとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されていることに照らすと、本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。
【筆者】
この文章は一文であるが、読み取りにくいものとなっている。それは、下記が原因である。
・「本件諸規定」が三回出てくること
・「同性カップル」が二回出てくること
・似たような文が繰り返されていること
事例 1
「婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず」
「婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず」
事例 2
「法的に家族と承認されない」
「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」
・文を区切るべきところで区切っていないこと
・論理的に意味が通じておらず、法的な判断の過程を誤っていること
「本件諸規定の下で原告ら同性カップルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っていること、」との部分について検討する。
まず、「原告ら」 の個々人は婚姻制度(男女二人一組)の要件に従う形で婚姻する意思を有しているのであれば適法に婚姻することが可能である。
そのため、「婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず」と述べるのであるが、「婚姻制度を利用することによって得られる利益」のすべてを「享受」することが可能である。
よって、「法的に家族と承認されない」との理解は妥当でないし、「重大な不利益を被っている」と評価しようとしてることも妥当でない。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づき、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しており、「婚姻していない者(独身者)」で既に完全な状態である。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」の状態でなんら「不利益」といわれるようなものはないのであり、その状態を「重大な不利益」と論じていることは誤りである。
これとは別に、婚姻制度が「男女二人一組」の形となっており、「同性間の人的結合関係」が対象となっていないことについて述べているものと考えて検討する。
婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのため、婚姻制度の対象となる場合とならない場合があることは、制度が設けられた時点から当然に予定されている。
また、制度の対象とならないとしても、単に優遇措置がないというだけであり、国家から個人に対して具体的な侵害行為が行われているわけではない。
そのため、それに対して「重大な不利益を被っている」と評価していることも誤りである。
もし「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」のとの間に何らかの差異があり、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、その過大な優遇措置に関する規定が14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その過大な優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
そのため、何らかの差異があることを「重大な不利益」と評価しようとしているのであれば、「婚姻している者(既婚者)」の得ている優遇措置に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。
それにもかかわらず、あたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるかのような前提の下に、「婚姻している者(既婚者)」が得ている利益をその制度の対象とならない場合にも得られるはずであると考えて「重大な不利益」と認定しようとしている部分が誤りである。
「婚姻制度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつあること、婚姻に対する社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていないとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されていること」との部分について検討する。
これ以前の段落の内容を確認しても、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」に変化があることや、「共同生活者」や「世帯」にあたるものが変わったことを述べているだけである。
そのため、これらの事情を示したところで「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとする理由にはならない。
「本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。」との記載がある。
「本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、」との部分について、その理由として示されているものは、これに以前の部分で「不利益」、「③ 個々人の利用目的」の変化、「共同生活者」や「世帯」にあたるものの変化を述べているだけである。
しかし、そもそも「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり「不利益」といわれるようなものは存在しない。
「③ 個々人の利用目的」が変化しても、「① 国の立法目的」が変化することはない。
「共同生活者」に変化があるとしても、そもそも「婚姻及び家族」の枠組みはそれら様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であるから、それによって「① 国の立法目的」が変わるということにはならない。
よって、これらはどれも「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられている「婚姻及び家族」の制度についての「① 国の立法目的」が変わるとする理由にはならない。
その他、「婚姻及び家族」の枠組みについて国会で法律を改正するときに、「婚姻適齢」が多少変わるとか、「法定相続分」が多少変わるとかいうことは考えられる。
その場合に、それら個別の規定について、国会でここでいう「立法事実」にあたるものが変わったかどうかが検討されることは考えられる。
しかし、「婚姻及び家族」の枠組みそのものについては、「婚姻」や「家族」の概念であることそのものによる内在的な限界が存在するため、その限界を超えるものを「婚姻」や「家族」の枠組みに含めることができることにはならない。
そのため、「婚姻及び家族」の枠組みそのものについては、「立法事実」の「変遷」を述べることによって、その概念そのものの意味を変えることが解釈として可能となるわけではないことに注意が必要である。
まとめると、「婚姻及び家族」の枠組みについての「① 国の立法目的」が変わらないし、その概念に含まれる内在的な限界も存在することから、「本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、」との認識は妥当でない。
「婚姻制度の利用によって得られる利益」というのは、これは婚姻制度ではなく、法的効果や優遇措置の一部をいうものである。
よって、このような内容については、24条2項の「婚姻及び家族」の文言によって要請されているものではない。
そのため、ここで述べているものの実質は、現行の「婚姻及び家族」の枠組みを超えて、新たな制度の創設を国家に対して求めるものに他ならないということができる。
国(行政府)の主張では、下記に対応するものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
しかし、これは24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらないものであるから、24条2項が要請するものではないし、24条2項を適用することはできず、24条2項の「個人の尊厳」を満たすか否かについても検討することができるものではない。
よって、その後、これを理由として「個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。」と述べていることは誤りである。
これについて、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(オ)さらに、被控訴人原審第3準備書面第3の2(3)(15ないし17ページ)で述べたとおり、憲法24条が婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とするものとして明文で定め、婚姻に係る法制度の構築を法律に委ねているものの、それ以外の法制度の構築を明文で定めていないことからすると、憲法は、法律(本件諸規定)により異性間の人的結合関係のみを対象とする婚姻を制度化することを予定しているとはいえるものの、同性間の人的結合関係を対象とする婚姻制度を構築することを想定していないことはもとより、パートナーと家族になるための法制度を含め、同性間の人的結合関係を対象とする新たな婚姻に準じる法制度を構築することを具体的に想定しておらず、同制度の構築を立法府に要請しているものでもないから、同制度の不存在が憲法24条2項に違反する状態となることもないと解される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF
「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定は」の部分について検討する。
24条2項の「婚姻及び家族」の枠組みの「家族」とは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた「婚姻」と同一の目的を共有する形で、その目的を達成するための手段として「婚姻」と結び付くものとして定められている枠組みである。
そのため、ここで「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段」と述べているが、そもそもそこでいう「家族」の枠組みは予め定められており、その中に含まれる場合と含まれない場合があることは当然に予定されている。
「自らの選んだ相手」についても、その「家族」の枠組みの中で存在する選択肢の中で「自らの選んだ相手」との間で「法的に家族になる」ことが可能となるだけである。
「婚姻及び家族」の枠組みは、立法目的とその立法目的を達成するための手段として定められているものであり、その枠組みに当てはまらない場合にまで「自らの選んだ相手」であることを理由として「婚姻及び家族」の枠組みに当てはめて考えなければならないということにはならない。
そのようなことをすれば、「婚姻及び家族」の枠組みが果たしている機能が阻害され、「婚姻及び家族」の枠組みそのものが成り立たなくなるからである。
そのため、「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」ことを述べたとしても、常にそこでいう「家族」の意味が問われるのであって、それを超える関係を「家族」として扱わなければならないということにはならない。
そして、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば「家族」にも含まれない。
よって、これらの関係に対して24条2項は適用されないのであり、その後、「個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。」と述べていることについても誤りとなる。
この「(5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか」の項目の「ア」と「イ」の内容は非常に読み取りづらいものとなっている。
そこで、下記のように整理する。
=======================================
「同性カップルの人的結合に関する事項は、憲法24条1項に基づく婚姻の自由は認められない」
「「婚姻」を異性婚に限ると理解する」
↓ ↓
「婚姻と並んで「家族に関するその他の事項」が対象となっている」
「「家族」の概念については憲法24条の制定過程からすれば夫婦及びその子の総体を中心とする概念であると理解される」
↓ ↓
「他方で」「婚姻、家族の形態が多様化し、これに伴い婚姻、家族の在り方に対する国民の意識が多様化している現在においてはこれに限定される必要はなく、」
↓ ↓
「同性カップルも異性カップルと変わらない人的結合関係にあるということができる」
「同性間の永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む意思を婚姻及び家族に関する諸規定に照らしてどのように扱うべきかという問題である」
↓ ↓
「同性カップルを「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含めることは文言上自然である」
「同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に該当するものということができる。」
↓ ↓
「起草過程のとおり憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、」
「憲法24条2項の裁量の限界を画するものとして「両性の本質的平等」と併せて「個人の尊厳」が挙げられている」
↓ ↓
「個人の尊厳については同性愛者も異性愛者と変わらず尊重されるべき」
「これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものである」
↓ ↓
「同性カップルに関する事項についても、国会の立法裁量が与えられると同時に、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである。」
「欧米ではキリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていた」
↓ ↓
「我が国にも影響を与えた同性愛者を精神病として病理化する知見は、今日では誤りであったことが明白となっている。」
「国際連合は、平成23年、国連人権規約として1966年に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約を根拠に、今日、性的指向に基づく差別は禁止されていることを決議」
↓ ↓
「家族の在り方及び前記知見の変化によりこれを国家的に認める動きが生じ、平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」
(国際連合は、)「我が国に対しても」「平成20年以降、自由権規約委員会、社会権規約委員会から、同性カップルの権利についての懸念と勧告が度々表明されている。」
↓ ↓
「本件諸規定の立法過程に影響を与えた諸外国の状況が変化してきている。」
「同性カップルにも異性カップルと同様の婚姻の意思(上記①)を有することができ、同等の権利を与えるべきという動きが世界の潮流となっている」
↓ ↓
「婚姻は男女によるものという社会通念は現在においてもなお失われていないものの、今日変わりつつある。」
「我が国においても、」
「政府は、平成22年以降、性的指向に基づく差別を禁止する措置を様々な分野で宣言」
「国会でも平成27年以降、同性婚の可否に関する質疑が度々行われている」
↓ ↓
「国民の意識においても、」
「平成27年段階で、同性婚に賛成する者の数は50%前後で、反対派をわずかに上回っていたが、賛成派の割合は年々増加」
「平成30年の時点で60%を超えるようになり、その後も増加を続けている」
「同性婚の実現への支持を表明する企業団体、弁護士会は増加し続けている」
↓ ↓
「地方自治体は、平成27年以降、人権保障、多様性の尊重及び安心して暮らせる社会づくりの目的でパートナーシップ制度を導入し始め、令和4年11月時点の導入自治体の人口カバー率は62.1%である」
↓ ↓
「我が国でも婚姻は異性のものという社会通念に疑義が示され、同性婚に対する国民の理解も相当程度浸透されているものと認められる。」
「婚姻に対する社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていないとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されている」
「旧民法や明治民法制定時における学説にも、婚姻について必ずしも子を得ることを目的としないとの理解が存在」
「明治民法の起草過程における議論の結果、生殖能力を有しないことを婚姻障害事由等にしていない」
↓ ↓
「婚姻制度の目的には婚姻相手との共同生活の保護にもあった」
↓ ↓
「今日、婚姻件数、婚姻率、合計特殊出生率及び子のいる世帯の割合は本件諸規定の立法時に比べて大きく低下」
「婚姻は全ての者が行うものではなく、」
「平成26年段階の結婚を希望する未婚の者に対する意識調査において、国民の婚姻制度を用いる理由は、」
「子を持つこと」
「婚姻相手と一緒にいること」
「家族となること」
↓ ↓
「婚姻制度の目的において、婚姻相手との共同生活の保護という側面が強くなってきている」
「各人が、生涯を共に過ごす者を選び、公認された家族を作るという人生における自己決定の尊重と保護という側面が強くなってきている」
↓ ↓
「婚姻及び家族の実態やその在り方に対する国民の意識が変遷している」
「婚姻制度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつある」
「婚姻は家族の単位の1つ」
↓ ↓
「永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみである」
↓ ↓
「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわたって影響を及ぼす事項」
「国民の意識における婚姻の重要性」
↓ ↓
「婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であると認められる」
↓ ↓
「同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しないことを意味する」
↓ ↓
「原告らは婚姻制度を利用できずこれによりもたらされる権利利益を享受する機会を得られず、法的に家族として承認されない」
↓ ↓
「重大な不利益を被っており、このような不利益は個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過することができない」
「原告らが婚姻制度を利用できない不利益は」「人格的利益を侵害されている事態に至っている」
「本件諸規定の下で原告ら同性カップルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」
「本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、」
↓ ↓
「本件諸規定は」「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」
↓ ↓
「もはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。」
=======================================
しかし、この説明は誤っている。
まず、「同性間の人的結合関係」は、それが「親子」や、「親子」の関係を基本とした「兄弟」「姉妹」などではないのであれば、24條2項の「婚姻及び家族」の枠組みには含まれない。
次に、国民の賛成意見が多いか、反対意見が多いかによって、法解釈の結論が左右されることはない。
三つ目に、婚姻制度についての「③ 個々人の利用目的」が変わったとしても、「① 国の立法目的」が変わることにはならない。
四つ目に、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全であり、その状態に「不利益」は存在しない。
「婚姻制度の利用によって得られる利益」については、「婚姻及び家族」の制度ではないことから、現行の「婚姻及び家族」の枠組みを超えて、新たな制度の創設を国家に対して求めるものに他ならないということができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
しかし、これは「婚姻及び家族」の枠組みではないことから、24条2項の要請する「婚姻及び家族」の制度ではなく、24条2項を適用することはできず、24条2項の「個人の尊厳」について検討する前提を欠いている。
また、「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段」についても、そもそもそこでいう「家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「婚姻」と同一の目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係の範囲に限られている。
そのため、「家族」の制度に従って存在する選択肢の中で「自らの選んだ相手」と「家族」になることは可能であるとしても、「自らの選んだ相手」であることを理由として「家族」の制度の枠組みに当てはまらない場合についてまで、「家族」としなければならないということにはならない。
よって、ここでは、「個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。」のように、24条2項を適用することができることを前提に、24条2項の「個人の尊厳」に照らして違憲状態を述べているが、そもそも24条2項を適用することができる事例ではないため、「憲法24条2項に違反する状態にある」とする結論も誤りである。
ウ しかしながら、前記のとおり婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益ではあるものの、憲法上直接保障された権利とまではいえず、その実現の在り方はその時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決せられるものである。そして、憲法24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について立法府の合理的裁量を認めているところ、上述の同性愛者らの重大な不利益を解消し、自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。上記①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度としては、婚姻制度を適用する以外にも、前記1(3)アのとおり、諸外国で制度化されてきた同性間の人的結合に関する制度が複数あり、婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与える登録パートナーシップ制度は、同性間の人的結合に法的権利義務や公証の利益を与えるものとして、その内容次第では婚姻制度の代替となり得るものであり、同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否かについても立法府における議論に委ねることが相当である。また、同性間の人的結合においては、生物学上の親子と戸籍上の親子が一致せず、これを前提にした規定が必要となること等から、嫡出推定の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療の可否については、現行の婚姻制度と異なるものとする余地があり、このような制度設計や枠組みの在り方については、我が国の伝統や国民感情を含めた社会的状況における種々の要因を踏まえつつ、さらに、子の福祉等にも配慮するといった様々な検討・調整が避けられず、立法府における検討や対応に委ねざるを得ない。
【筆者】
「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益ではあるものの、憲法上直接保障された権利とまではいえず、その実現の在り方はその時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決せられるものである。」との記載がある。
ここには「同性愛者にとっても」のように、「同性愛者」を称する者について取り上げ、その者の「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定すること」が「尊重されるべき人格的利益」であるか否か、また、「憲法上直接保障された権利」であるかを述べるものとなっている。
しかし、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従っているのであれば、その者がどのような思想、信条、信仰、感情を有しているとしても利用することが可能である。
そのため、婚姻制度の枠組みに従う形で存在する選択肢の中で、「婚姻」することを望むのであれば、たとえ「同性愛者」を称する者であるとしても、等しく制度の利用は認められている。
よって、婚姻制度(男女二人一組)の要件に従っているのであれば、「同性愛者」を称する者であるとしても、「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定すること」は認められているし、これは憲法24条1項の「婚姻をするについての自由」としても裏付けられており、憲法上で保障されているということができる。
そのため、ここで「同性愛者」を称する者について、「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定すること」が「憲法上直接保障された権利とまではいえず、」のように、憲法上で保障されていないかのように述べていることは誤りである。
これにより、その後の「その実現の在り方はその時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決せられるものである。」と述べている部分についても、そもそも「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用することができるという点で検討する前提を欠いているものである。
「憲法24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について立法府の合理的裁量を認めているところ、上述の同性愛者らの重大な不利益を解消し、自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。」との記載がある。
まず、「同性愛者らの重大な不利益を解消し、」の部分であるが、婚姻制度は個々人の内心を審査して区別取扱いを行うものではないため、婚姻制度の要件に従う形で婚姻制度を利用することを望むのであれば、それがたとえ「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度を利用することは可能である。
よって、「同性愛者」を称する者であっても婚姻制度を利用することは可能であるため、「同性愛者」であることを理由とする「重大な不利益」とされるものは存在しない。
また、そもそも、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいて「個人主義」を定めていることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態として取り扱われることとなっており、その「婚姻していない者(独身者)」の状態で「重大な不利益」とされるものは存在しない。
よって、「同性愛者らの重大な不利益を解消し、」のように、「重大な不利益」があることを前提として、それを「解消」をしなければならないと論じていることは、誤りとなる。
これとは別に、「婚姻している者(既婚者)」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得るものとなっている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で合理的な理由のない差異を生じさせるものとして、14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その過大な優遇措置を定めている規定が個別に失効して格差が是正されることになる。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)となり、「婚姻している者(既婚者)」の優遇措置に関する規定が減らされる方向で格差が是正されることになる。
それにもかかわらず、あたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)であるかのような前提の下に、「婚姻していない者(独身者)」に対して優遇措置を与えなければならないという論じ方をしていることは誤りである。
他にも、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的から導かれない人的結合関係に対して優遇措置を行うことは、何らの人的結合関係も形成していない者との間でも合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「婚姻していない者(独身者)」に対して、新たな制度を設けなければならないかのように論じていることも、妥当でない。
次に、「自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。」との部分について検討する。
「自己決定」については、「国家からの自由」という「自由権」に属する13条の「幸福追求権」や21条1項の「結社の自由」によって、各々自由に人的結合関係を形成すればよいのであり、国家が制度を設ける必要はない。
また、先ほども述べたように、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、その目的を達成するための手段として合理的な範囲内で、「婚姻している者(既婚者)」は、「婚姻していない者(独身者)」との間で優遇措置を与えられることが正当化されるが、このような目的を有しない制度については、何らの制度も利用してない者との間で得られる利益の内容に合理的な理由を説明することができない差異を生じさせることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、何らかの制度を立法することを前提として、その「様々な考慮」を論じているものとなっているが、そもそもそのような制度を立法することは憲法に違反することが考えられることを考慮していない点で、妥当でない。
「憲法24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について立法府の合理的裁量を認めているところ、……(略)……自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。」との記載がある。
しかし、24条2項は「婚姻及び家族」についての制度を要請するものではあるが、それ以外の制度を要請するものではない。
そして、「婚姻及び家族」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという同一の目的を共有する形で統一的な制度として定められ、「夫婦」と、「親子」の関係を基本とした「血縁関係者」を対象とするものとなっている。
この関係を超える人的結合関係についての制度として「自己決定を尊重する制度」と称するものについては、立法することは要請されていない。
そのため、これは結局、「婚姻及び家族」の枠を超えた新たな制度の創設を国家に対して求めるものに他ならないということができる。
国(行政府)の主張では、下記の部分である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
しかし、このような制度を創設することは、もともと24条2項では要請されていないことから、24条2項に基づいてこれを立法することが要請されているかのような前提で論じている部分が誤りである。
「上記①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度としては、婚姻制度を適用する以外にも、前記1(3)アのとおり、諸外国で制度化されてきた同性間の人的結合に関する制度が複数あり、婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与える登録パートナーシップ制度は、同性間の人的結合に法的権利義務や公証の利益を与えるものとして、その内容次第では婚姻制度の代替となり得るものであり、同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否かについても立法府における議論に委ねることが相当である。」との記載がある。
まず、「上記①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度としては、」との部分であるが、婚姻制度が「①~④」のような法的効果や一定の優遇措置を設けている理由から検討する必要がある。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、その目的を達成するための手段として、法的効果や一定の優遇措置を定め、制度を利用する者を増やすことによって、その目的を達成することを目指すものとなっている。
もし、婚姻制度以外の制度でそれらの法的効果や優遇措置を得られる場合には、人々は次第に婚姻制度を利用しなくなっていくことが考えられ、婚姻制度の立法目的の達成を困難とすることに繋がる。
そのため、婚姻制度以外の制度によって、それらの法的効果や優遇措置を与えることは、婚姻制度の立法目的の実現を阻害することになるから、「①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度」を別に立法することはできない。
そのようなことをした場合には、婚姻制度そのものが破壊されてしまうことになるからである。
よって、「①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度」というものを、婚姻制度の他に立法することができるかのような前提で論じている部分が誤りである。
また、24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、この24条の規定を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
よって、「①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度」というものは、「生殖と子の養育」に関わる制度や、影響を与える制度となることが考えられ、そのような制度を設けることは24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
次に、「婚姻制度を適用する以外にも、」との部分であるが、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付ける枠組みをいうから、「同性間の人的結合関係」はここに含めることはできないため、ここでいう「婚姻制度を適用する」ことはできない。
よって、「婚姻制度を適用する」ことができるかのような前提で論じている部分が誤りとなる。
「諸外国で制度化されてきた同性間の人的結合に関する制度が複数あり、婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与える登録パートナーシップ制度は、同性間の人的結合に法的権利義務や公証の利益を与えるものとして、その内容次第では婚姻制度の代替となり得るものであり、」との部分について検討する。
24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律していることから、24条を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を設けた場合には、24条に抵触して違憲となる。
よって、ここでいう「婚姻とほとんど同じ法的効果」を持つ制度など、「生殖と子の養育」に関わる制度や、影響を与える制度を設けた場合には、24条に抵触して違憲となる。
ここでは「同性カップル」のように「二人一組」の人的結合関係に対して何らかの制度を設けることを述べているが、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に従って「男性」と「女性」の組み合わせに「貞操義務」を設けることで生まれてきた子供の父親を特定することができるという仕組みであることを理由に、「婚姻していない者(独身者)」との間で差異を設けることが正当化されることに対して、そのような仕組みを有していない「同性間の人的結合関係」について法的効果や優遇措置を与えることは、制度を利用していない者との間で合理的な理由のない差異を生じさせることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
また、「生殖」に関わらないのであれば、その関係を「二人一組」とする合理的な理由も説明することはできず、その関係だけを法的効果や優遇措置の対象とすることを正当化することはできない。
これについて、「同性カップル」のように「二人一組」の人的結合関係だけを取り上げていることも、なぜ「二人一組」なのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」になっており、妥当でない。
「その内容次第では婚姻制度の代替となり得るものであり、」の部分についても、そもそも婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律しており、「婚姻制度の代替」となるような制度を別に立法することはできない。
そのため、「婚姻制度の代替」となるような制度を立法することができることを前提として論じている部分が誤りである。
その他、当サイト「パートナーシップ制度」でも解説している。
「同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否かについても立法府における議論に委ねることが相当である。」との部分について検討する。
「婚姻制度と異なる制度を設けるか否か」とあるが、「同性間の人的結合関係」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできない。
また、「婚姻制度と異なる制度」についても、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しているため、24条を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を立法することはできないのであり、そのような制度を立法した場合には、24条に抵触して違憲となる。
よって、「婚姻制度と異なる制度」のようなものを「立法府」が立法することができることを前提として、「立法府における議論に委ねることが相当である。」と述べていることは、判断として誤りとなる。
「同性間の人的結合においては、生物学上の親子と戸籍上の親子が一致せず、これを前提にした規定が必要となること等から、嫡出推定の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療の可否については、現行の婚姻制度と異なるものとする余地があり、このような制度設計や枠組みの在り方については、我が国の伝統や国民感情を含めた社会的状況における種々の要因を踏まえつつ、さらに、子の福祉等にも配慮するといった様々な検討・調整が避けられず、立法府における検討や対応に委ねざるを得ない。」との記載がある。
「同性間の人的結合においては、生物学上の親子と戸籍上の親子が一致せず、これを前提にした規定が必要となること等から、嫡出推定の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療の可否については、現行の婚姻制度と異なるものとする余地があり、」との部分について検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
その内容は、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることによって、子供が生まれた場合に父親を特定することができることを中心として枠組みを定め、目的の達成を目指すものとなっている。
そして、憲法24条ではその「婚姻」について、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
ここでいう「同性間の人的結合」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
また、「同性間の人的結合」について「婚姻制度と異なるもの」を立法することができるか否かであるが、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を別に立法することはできないため、その内容が「生殖と子の養育」に関わる場合や、影響を与える場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。
他にも、婚姻制度が「男女二人一組」の形としていることは、「男性」と「女性」の間に「貞操義務」を設けることで産まれてきた子供の父親を特定することができるという仕組みが立法目的を達成するための手段として合理的であることから、法的効果や一定の優遇措置を与えることが正当化されるが、そのような関係を有しない「同性間の人的結合」に対して制度を設けることは、制度を利用しない者との間で合理的な理由のない差異を生じさせることとなるから14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「同性間の人的結合」に対して「婚姻制度」を設けることや、「婚姻制度と異なるもの」の制度を設けることが可能であるかのような前提で論じている部分が妥当でない。
ここでいう「同性間の人的結合」は「二人一組」を前提としているが、「人的結合」には「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の組み合わせ」など、様々であるにもかかわらず、「二人一組」だけを取り上げるものとなっている。
これは、なぜ「二人一組」なのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」となっていることに注意する必要がある。
「このような制度設計や枠組みの在り方については、我が国の伝統や国民感情を含めた社会的状況における種々の要因を踏まえつつ、さらに、子の福祉等にも配慮するといった様々な検討・調整が避けられず、立法府における検討や対応に委ねざるを得ない。」との部分について検討する。
「子の福祉等にも配慮する」との部分であるが、そもそも婚姻制度は「子の福祉」を中心的な課題として、その「子」が生じるという結果をもたらす「生殖」の仕組みに着目し、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
よって、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせに対して「貞操義務」を設けるなど一定の形式で法的に結び付け、子供が産まれた場合にその父親を特定することができる仕組みとなる状態を推進し、立法目的の達成を目指すものとなっている。
そのため、「子の福祉」を検討した結果が、「男女二人一組」の婚姻制度を設けて法的効果や一定の優遇措置を行うという形に行き着いているわけである。
ここでいう「子の福祉」とは、子供が産まれた場合に、何らの制度も設けずに放置するような社会よりも、子供が産まれた場合にその原因となった者にその子供の養育について責任を担わせる社会を選択するという意味や、子の遺伝上の父親を特定することができる関係とすること、遺伝上の父親を特定できることによって近親者を把握して「近親交配」に至ることを防ぐ仕組みを持つ制度であること、生活する上で次世代の者が子を持ちたいとの望んだ場合に「子を持つ機会」を公平に得られる社会となっていること、低年齢での妊娠・出産のリスクを減らせる社会となっていることなども含まれている。
これは、単に子の養育者を増やせばよいという意味ではなく、社会的な制度が「生殖」という人間の世代を渡る生命活動の連鎖を適切にサポートし、安定的で持続可能な形にとどまるような仕組みとすることが必要ということである。
よって、この「男女二人一組」を超える人的結合関係に対して何らかの制度を設けることを前提として、その後に「子の福祉」を考えるというのは、そもそも婚姻制度が「男女二人一組」の形に対して法的効果や一定の優遇措置を与えることによって「子の福祉」の充実を目指していることと矛盾する主張となっており、妥当でない。
また、24条2項の下では「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の中に一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
よって、「立法府における検討や対応」などと、そのような制度を「立法府」が立法することができるかのような前提で論じている部分が誤りである。
この段落の文面は、非常に読み取りづらいものとなっている。
整理してまとめると、下記のようになる。
「憲法24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について立法府の合理的裁量を認めている」
↓ ↓
「同性愛者にとっても」
「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは」「尊重されるべき人格的利益ではある」
(憲法上直接保障された権利とまではいえず、)
↓ ↓
「同性愛者らの重大な不利益を解消し、自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。」
↓ ↓
「同性間の人的結合においては、生物学上の親子と戸籍上の親子が一致せず、これを前提にした規定が必要となること等から、嫡出推定の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療の可否については、現行の婚姻制度と異なるものとする余地があり、」
「同性婚について」「婚姻制度と異なる制度を設けるか否かについても立法府における議論に委ねることが相当である。」
↓ ↓
「上記①~④の婚姻の特徴を満たす法的制度としては、」
・「婚姻制度を適用する」
・「諸外国で制度化されてきた同性間の人的結合に関する制度」
・「婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与える登録パートナーシップ制度」
⇒「同性間の人的結合に法的権利義務や公証の利益を与えるものとして、その内容次第では婚姻制度の代替となり得る」
↓ ↓
「このような制度設計や枠組みの在り方については、我が国の伝統や国民感情を含めた社会的状況における種々の要因を踏まえつつ、さらに、子の福祉等にも配慮するといった様々な検討・調整が避けられず、」
「その実現の在り方はその時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決せられるものである。」
↓ ↓
「立法府における検討や対応に委ねざるを得ない。」
しかし、この内容は間違っている。
まず、婚姻制度は個々人の内心に中立的な内容であり、「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度(男女二人一組)を利用することができる。
また、婚姻制度の要件に従う形で「婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定すること」は可能であり、憲法24条1項によっても保障されている。
そのため、「同性愛者」を称する者に法的な区別取扱いは存在せず、「不利益」といわれるものはない。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることから、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であり、そこに「不利益」といわれるものも存在しない。
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
「同性間の人的結合」は「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
そのため、「立法府」がそのような制度を立法することができることを前提として論じていることは誤りである。
また、前記のとおり、我が国において、国会で同性婚に関する質疑が行われ、地方自治体によるパートナーシップ制度が初めて導入され、同性婚に関する各種意識調査が開始されたのはいずれも平成27年以降であり、この頃に初めて同性婚に関する問題が我が国で本格的に議論され始めたものと認められる。近時の調査によっても、20代や30代など若年層においては、同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多数を占めるものの、前記のとおり60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と否定的な意見が拮抗しており、国民意識として同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは、比較的近時のことであると認められる。そうすると、立法府による今後の検討や対応に委ねることが必ずしも不合理であるとまでは言えない。
【筆者】
「我が国において、国会で同性婚に関する質疑が行われ、地方自治体によるパートナーシップ制度が初めて導入され、同性婚に関する各種意識調査が開始されたのはいずれも平成27年以降であり、この頃に初めて同性婚に関する問題が我が国で本格的に議論され始めたものと認められる。」との記載がある。
これについて、「地方公共団体」の「パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触している場合には、その制度は違法となる。
詳しくは、当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。
「近時の調査によっても、20代や30代など若年層においては、同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多数を占めるものの、前記のとおり60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と否定的な意見が拮抗しており、国民意識として同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは、比較的近時のことであると認められる。」との記載がある。
ここでは「肯定的な意見」と「否定的な意見」を取り上げているが、それ以前に法的に可能かどうかの論点がある。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から、他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
そのため、「同性間の人的結合関係」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさず、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の意味にも当てはまらないことから、「婚姻」とすることはできない。
また、24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、24条の「婚姻」を離れて別の制度として「生殖と子の養育」に関わる制度を設けることはできない。
ここでは「同性婚又は同性愛者のカップル」としているが、人的結合関係の中には「三人一組」や「四人一組」、「それ以上の人的結合関係」など様々であるにもかかわらず、「二人一組」のみを取り上げるものとなっている。
これは、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」となっており、妥当でない。
「立法府による今後の検討や対応に委ねることが必ずしも不合理であるとまでは言えない。」との記載がある。
先ほども述べたように、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」とすることはできないし、24条の「婚姻」を離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。
また、「生殖と子の養育」の趣旨を満たす人的結合関係に対して一定の優遇措置を設けることは、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に資することから正当化することができるが、その趣旨を満たさない人的結合関係に対して優遇措置を設けることは、制度を利用していない者との間で合理的な理由のない差異を生じさせることになるから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、「立法府」でそのような制度を立法することができるかのような前提で論じている部分が妥当でない。
以上によれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が立法府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとして憲法24条2項に反するとまでは認めることができない。
【筆者】
「同性間の婚姻」との文言があるが、「同性間の人的結合関係」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、そもそも「立法府たる国会」には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについての「裁量権」が存在しない。
そのことから、ここでは「立法府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとして憲法24条2項に反するとまでは認めることができない。」と述べて、「裁量権」の存在を前提として、その「逸脱」があるかないかを論じるものとなっているが、そもそも「立法府たる国会」に「裁量権」は存在しないため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」としていなくとも、「憲法24条2項」に違反しないと判断することが適切である。
3 争点(2)(本件諸規定を改廃しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。)について
(1) 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、それゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに同項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利・利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。(最高裁判所昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁、同裁判所平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁、同裁判所令和2年(行ツ)第255号、同年(行ヒ)第290号、第291号、第292号同4年5月25日大法廷判決民集76巻4号711頁参照)
(2) そこで、本件諸規定を改廃しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるかについて検討すると、前記2のとおり、本件諸規定は憲法13条、14条1項及び24条に反するものではなく、原告らの主張は前提を欠くものである。
前記のとおり、同性カップルに婚姻制度によって得られる利益を一切認めていない本件諸規定は、憲法24条2項に反する状態にあり、立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべきとはいえるものの、前記のとおり、この方法は多種多様な選択肢があり、上記の状態にあることから原告らが主張する同性間の婚姻を可能とする立法措置を講ずべき義務が直ちに生ずるものとは認められない。
【筆者】
「同性カップルに婚姻制度によって得られる利益を一切認めていない本件諸規定は、憲法24条2項に反する状態にあり、立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべきとはいえるものの、」との部分について検討する。
ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、それが「親子」や、「親子」の関係によって形成される「兄弟」「姉妹」などの「血縁関係者」に含まれないのであれば、「家族」とも言えない。
そして、「婚姻及び家族」の枠組みに含まれないものについては、24条2項が制度の創設を要請していないため、それを対象とした制度が存在しないとしても、24条2項に違反することはない。
よって、「憲法24条2項に反する状態」であるとの判断は誤っている。
また、「立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべきとはいえるものの、」の部分についても、そもそも「この状態」にあたる「憲法24条2項に反する状態」との判断が誤っているため、「解消」する必要のある問題は生じていない。
よって、「この状態を解消する措置に着手すべきとはいえる」との判断も誤っている。
この文を「立法者」に対して何らかの制度を立法するように促そうとするものとして読み解いた場合には、これは結局、現行の「婚姻及び家族」の枠組みを超えて、新たな制度の創設を国家に対して求めるものということができる。
これは、国が下記のように述べているものに対応する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうすると,原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は,「両性」の本質的平等に立脚すべきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて,同性間の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって,国家からの自由を本質とするものではないから,このような自由が憲法13条の幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控訴人らが本件規定により侵害されていると主張する権利又は利益の本質は、結局のところ、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならず、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は人格的生存に不可欠の利益として憲法で保障されているものではないから、このような内実のものが憲法13条の規定する幸福追求権の一内容を構成すると解することはできない。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面 令和5年6月8日 PDF
しかし、そもそもここでいう「同性間の人的結合関係」については「婚姻及び家族」の枠組みに含まれていないのであり、24条2項を適用することができるものではない。
そのため、24条2項が要請していない制度について、裁判所が「立法者」に対して創設することを要求するものとなることから、権限外の行為であり、越権行為となる。
よって、「立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべきとはいえる」のように、「立法者」に対して何らかの制度を立法することを促している部分についても、司法権の行使として正当化することのできるものではなく、不適切である。
「この方法は多種多様な選択肢があり、上記の状態にあることから原告らが主張する同性間の婚姻を可能とする立法措置を講ずべき義務が直ちに生ずるものとは認められない。」との部分について検討する。
「同性間の人的結合関係」については、そもそも「婚姻」とすることはできないことから、「立法措置を講ずべき義務」は生じない。
ここでは「直ちに」のように、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるとの前提であるが、その点の判断の過程が妥当なものではない。
「方法は多種多様な選択肢」についても、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、「生殖と子の養育」に関わる制度や影響を与える制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
また、「生殖と子の養育」の趣旨を有しない人的結合関係に対して優遇措置を行うことについても、制度を利用しない者との間で正当化することのできない差異を生じさせることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、何らかの制度を立法することを促すような部分についても、判断の根拠を欠くものであり、適切ではない。
したがって、本件諸規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
第4 結論
以上のとおりであって、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの請求にはいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第6民事部
裁判長裁判官 上田洋幸
裁判官 橋口佳典
裁判官 馬渡万紀子
<理解の補強>
私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023.06.27
(私たちは「重婚」を認められるか…?「同性婚」問題の先に浮かび上がる「多様性をめぐる根本的な難点」 2023/6/27)
判決の誤りを継承する解説
下記に挙げたこの福岡地裁判決の記事や解説について、当サイトをお読みの方ならば、どの部分が妥当でないかを見抜くことができるはずである。
「違憲と言い切ってほしかったが“前進”」同性婚“違憲状態”判決にみる裁判所の価値観 2023/06/08
結婚の平等・九州訴訟は「国会、早よせんね!」判決。「違憲」とした福岡地裁はどんなメッセージを発したのか 2023年06月08日
曇天の違憲判決。もう一歩踏み込んでほしかった。「結婚の自由」福岡地裁判決を傍聴 2023/6/9
(社説)同性婚判決 「違憲」の是正を急げ 2023年6月9日
<社説>同性婚訴訟判決 政治の怠慢への警告だ 2023年6月9日
同性婚巡る司法判断 法制化議論は不可避だ 2023/06/09
同性婚巡る司法判断 法制化議論 早期に着手せよ 2023年6月10日
【社説】「同性婚」5判決 大きな流れを立法措置へ 2023/6/10
同性婚訴訟 国は法整備へ議論始めよ 2023年06月11日
社説:同性婚訴訟 判決踏まえ法整備急げ 2023年6月14日
社説(6月19日)同性婚訴訟 法制化議論 本格化急げ 2023.6.19
憲法カフェ ぷち㉘ 同性婚を認める法制度を 2023年7月4日
第299号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟福岡地裁判決 名古屋市立大学大学院 小林直三 2023年10月16日
【動画】少数者の人権を守るための裁判所~受講生・受験生の皆さんへ第184弾 2023年6月9日
今回もお読みいただきありがとうございました。