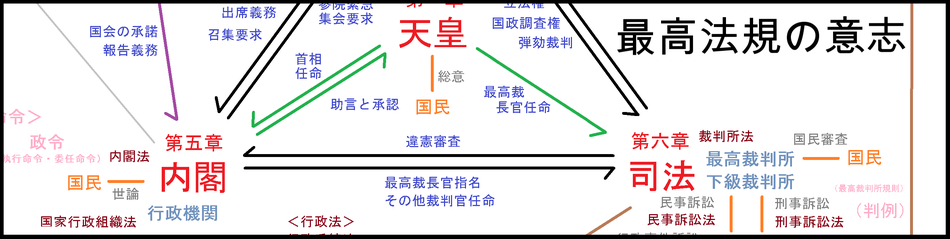同性婚訴訟 大阪地裁判決の分析
【このページの目次】
はじめに
ポイント
〇 「平等」の審査方法
〇 比較する対象の誤り
〇 内心による区別取扱いの違憲性
〇 個人と婚姻の関係
〇 婚姻制度の立法目的と大阪地裁判決の理解
大阪地裁判決の内容
判決の誤りを継承する解説
はじめに
「同性婚訴訟 大阪地裁判決」の内容を分析する。
判決
損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和4年6月20日 (PDF)
【大阪】判決全文 PDF
判決要旨
【大阪】判決要旨 PDF
【判決要旨全文】「結婚平等が認められないのは合憲」大阪地裁が判断 2022/6/20
【判決要旨全文】「結婚平等が認められないのは合憲」大阪地裁が判断 2022年06月20日
この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。
ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。
ポイント
判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。
「平等」の審査方法
14条における「平等」を論じる際には、何と何を比較しているのかを明確にする必要がある。これが曖昧になると、区別の有無や、区別の合理性を適切に審査することができなくなる。
下図で、比較の対象となるパターンを(A)~(G)に分類した。
◆ 法の下の平等( A )
14条の「法の下の平等」は、「権利能力」(法人格)を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人を対象として審査するものである。この(A)のパターンは、最も典型的な事例である。
この点について、国(行政府)の主張でも触れられている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)
個々人の間での区別が存在し、その区別に合理性が認められないのであれば、14条の「平等権」に抵触して違憲となる。
◆ 法の下の平等( B )
同種の「法人」と「法人」の間で区別取扱いがある場合には、その合理性が審査されることになる。
区別に合理性がない場合には、14条の「平等権」に抵触して違憲となる。
◆ 法の下の平等( C )
「婚姻している者(既婚者)」に対して比較対象となるのは、常に「婚姻していない者(独身者)」である。
「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との比較においてその合理性が審査されることになる。
優遇措置の内容が合理性を有しない場合は、その優遇措置に関する規定が14条の「平等権」に抵触して違憲・無効となる。
この点について、国(行政府)は下記のように述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被控訴人としても、本件規定における特定の法的効果(優遇)の内容が婚姻制度の目的との関連で合理性を欠くものであれば、当該効果に係る規定が憲法14条1項に違反すると評価され得る場合があることを否定するものではない。…(略)…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 法の下の平等( D )
この( D )の事例は、基本的には先ほど挙げた( C )の事例と同様である。
ただ、( D )の事例は( C )の事例に比べて「生殖」に関する問題で「婚姻している者(既婚者)」との立ち位置が近いことを意識して、あえて( C )と( D )に分けた。
◆ 法の下の平等( E )
この事例は、下記の判例がある。
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日
◆ 法の下の平等( F )と( G )
「婚姻及び家族に関する法制度」の内部の問題については、14条の「法の下の平等」だけでなく、24条の「両性の本質的平等」による審査がなされることになる。
この事例は、下記の判例がある。
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (再婚禁止期間違憲訴訟)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (夫婦別姓訴訟)
国(行政府)は下記のように理解している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ) この点,再婚禁止期間違憲判決においても,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法適合性の判断に当たっては,憲法14条1項適合性判断の枠組みにおける検討がされているとともに,その検討に当たり併せて憲法24条の趣旨及び意義が考慮されており,同条2項にいう「両性の本質的平等」違反の有無に関する立法府の立法裁量の範囲を逸脱していないかの審査も同時に行われている(加本・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕685ページ)。
また,憲法14条1項適合性と憲法24条2項適合性との関係について,「憲法24条2項にいう『両性の本質的平等』については,同項により立法に当たっての要請,指針が示されていることから,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法14条1項の形式的平等を害していない場合であっても,実質的平等の観点から憲法24条2項に違反するとの判断はあり得ると解されるが,同規定が憲法14条1項に違反する場合には,同時に憲法24条2項にも違反するとの結論が導かれることとなるであろう」(加本・前掲解説民事編平成27年度〔下〕684及び685ページ)と説明されているとおり,憲法14条1項適合性については,憲法24条2 項の解釈と整合的に判断する必要があることが明らかにされている。
さらに,平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決については,「憲法14条1項の『平等』が,少なくとも裁判規範としては基本的に形式的な平等をいうものであることを示し」ており,「実質的平等の観点は,憲法14条1項適合性の判断において直ちに裁判規範とはなるものではないものの,(中略)憲法24条に関連し,(中略)考慮すべき事項のーつとしたものであ」る(畑・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕746及び747ページ)との理解がされている。
(ウ)以上のとおり,婚姻及び家族に関する事項の立法行為又は立法不作為の憲法14条1項適合性については,憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要があるというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年8月24日 PDF (P9)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……再婚禁止期間違憲判決では、民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法適合性の判断に当たって、憲法14条1項適合性の判断の枠組みにおける検討に当たり憲法24条の趣旨及び意義が考慮されている。この点は、平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決に関し、「このような憲法24条の解釈からすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた規定が憲法13条や14条1項に違反する場合には、同時に憲法24条にも違反することになるが(中略)憲法13条や14条1項に違反しない場合であっても、上記の観点からさらに憲法24条にも適合するものかについて検討することになろう」と指摘されているところである(畑佳秀・最高裁判所判例解説民事編平成27年度〔下〕754ページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF (P15)
(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)
◆ 札幌地裁判決と大阪地裁判決の「カップル間不平等論」の誤り
札幌地裁判決やこの大阪地裁判決では「カップル」と称する単位を取り上げて、その「カップル」と「カップル」の間を比較し、差別取扱いがあるか否かを検討しようとしている部分がある。
しかし、そのように「カップル」と「カップル」の間で比較しようとするのであれば、先に「カップル」という単位が「法人」としての「権利能力」(法人格)を有していることを立証することが求められる。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうでなければ、「法の下の平等(B)」のパターンに当てはまらず、14条の「平等権」を審査する場合の比較対象として取り扱うことはできないからである。
「権利能力」(法人格)を有しないのであれば、法主体としての地位を認められていないのであるから、法律論上で比較対象として取り上げることはできないのである。
この点で、札幌地裁判決もこの大阪地裁判決も、「カップル」と称する単位が「権利能力」(法人格)を有しているかどうかについて何らの立証もしないままに比較対象として取り上げている部分があり、論じ方として誤っている。
また、たとえ法人として「権利能力」を取得しているとしても、法人の「権利能力」の性質は自然人に適用されるものとは性質が異なる場合があるため注意が必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人の権利能力
法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。
性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
権利能力 Wikipedia (下線は筆者)
札幌地裁判決やこの大阪地裁判決が「カップル」と称しているものは、単なる「婚姻していない者(独身者)」の形成している人的結合関係であり、その個々人は「婚姻していない者(独身者)」である。
そのため、「婚姻している者(既婚者)」との間で比較対象として取り上げることができるのは、常に「婚姻していない者(独身者)」としての立場である。
これは、「法の下の平等(C)」のパターンの比較である。
そのため、「カップル」と称する「権利能力」(法人格)を有していない単位を比較対象として持ち出すことはできないのであり、論じ方を誤っている。
比較する対象の誤り
この大阪地裁判決が比較する対象を誤っていることを考えるため、下図で三つの視点を上げる。
◆ カップル間不平等論
この大阪地裁判決は、14条の「平等権」を論じる際に、「カップル」と「カップル」の間の不平等の存否を検討しようとしている部分がある。
しかし、これは「カップル信仰論」に陥っており、比較対象の選択を誤っている。
まず、「カップル」という「二人一組」の単位が、「権利能力」を有する法主体としての地位を有していることを示さなければ、この間の不平等を比較することはできない。
民法上の法主体は「自然人」と「法人」に分かれる。「カップル」という「二人一組」については、「自然人」ではない。また、「法人」であるというのであれば、法人の設立手続きや登記の存在を証明しなければならない。
それにもかかわらず、「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を有していない「カップル」を単位として、比較対象として取り上げていること自体が法解釈として適切ではない。
◆ 異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論
これについては、下記の国(行政府)の主張が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF
(これは大阪地裁ではなく、東京地裁二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被告第2準備書面第5の2(2)エ(ア)(34及び35ページ)における主張は、男性と女性の間の差別を念頭に置いたものである。上記主張における「性別」は、原告らが「生物学的な特徴をもとに割り当てられることとされている」性別として主張する性別(法律上の性別)(訴状15ページ)上の男性と女性の区別を主張するものであり、男性間又は女性間の区別は憲法14条1項の「性別」による「差別」には当たらない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
(これは大阪地裁ではなく、東京地裁二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)
◆ 性愛に基づく不平等論
これについては、下記の国(行政府)の主張が参考になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら,法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かについては,結果(実態)として生じている,又は生じ得る差異から判断するのは相当でなく,当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断するのが相当である。この点,夫婦同氏制を定める民法750条の規定の憲法14条1項適合性が争われた平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決も,民法750条の規定が「その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定(引用者注:民法750条)の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。」,「夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。」と判示し,上記の考え方に沿う判断を示している。また,国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。)3条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367ページ,民法(平成25年法律第94号による改正前のもの。)900条4号ただし書前段の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成7年7月5日大法廷判決・民集49巻7号1789ページ及び最高裁平成25年9月4日大法廷判決・民集67巻6号1320ページ,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた再婚禁止期間違憲判決等も,上記の考え方を当然の前提としているものと解される。
このような観点から本件諸規定をみると,本件諸規定は,その文言上,婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり,当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく,その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから,性的指向について中立的な規定であるということができる。そうであるとすると,本件諸規定は,区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当でない。本件諸規定から,結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻することができないという事態が生じ,同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても,それは,性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF (P12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ) 本件規定は、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものではないこと(前記②の主張に対する反論)
被告第4準備書面第3の2(2)エ(25ないし27ページ)において述べたとおり、法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かは、当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断すぺきであって、結果(実態)として生じている、又は生じ得る差異から判断するのは相当でない。
このような観点から本件規定をみると、本件規定は、一人の男性とー人の女性との問の婚姻を定めるものであり、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく、その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから、性的指向について中立的な規定であるということができる。さらに、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第4準備害面第3の2(3)ウ(7)(37及び38ページ)において述べたとおり、我が国において、ー人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性的指向に着目して法的な差別的取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性的指向について中立的なものであることは明らかである。そうであるとすると、本件規定が区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当ではない。多種多様な人的結合関係のうち、本件規定が一人の男性と一人の女性の人的結合関係について婚姻を認める結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができないという事態が生じ、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは、性的指向につき中立的な本件規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきであり、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものと評価することは相当ではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF (P16)
(これは大阪地裁ではなく、福岡地裁における国〔行政府〕の主張である。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性自認や性的指向に着目して法的な差別取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性自認や性的指向について中立的なものであることは明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)
内心による区別取扱いの違憲性
特定の思想・信条を優遇することは、違憲になる。
また、人の内心に着目して区別取扱いを行う制度を立法することも、違憲になる。
上図に示したように、特定の思想・信条・感情のみを保護するために制度を構築すると、違憲になる。
そのため、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想・信条・感情を保護することを目的とする場合には、違憲になる。
この大阪地裁判決は、婚姻制度が特定の「性愛(性的指向)」(特に異性愛)を保護することが立法目的であるかのような前提で論じている部分があるが、そのような立法目的に基づいて制度を構築することは違憲となる。
また、婚姻類似の制度を立法する際にも「性愛(性的指向)」によって区別することが可能であるかのように論じている部分があるが、「性愛(性的指向)」という人の内心に着目し、区別することを可能とする制度は、それ自体で違憲である。
法制度は思想や感情に対して中立性を保たなければならない。
個人と婚姻の関係
憲法は「個人の尊厳」を中核的な原理としている。
このため、憲法は「個人主義」を採用しており、「自律的な個人」として生存していくことを基準(スタンダード)としている。
そして、それら個々人が集い、人的結合関係を形成することや、「共同生活」を送ることは可能である。これは、憲法21条の「結社の自由」によって保障される。
ただ、国民が「生殖」することによって社会的な不都合が発生することを抑制するために、国家の政策的な要請として「生殖と子の養育」の観点から一定の人的結合関係を選び出し、その枠組みを「婚姻」として扱うことを制度化している。
これが、「結社の自由」で保障される他の人的結合関係から区別する意味で「婚姻」という枠組みを設けている理由である。
これについて、国(行政府)は下記のように理解している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると,本件諸規定に基づく婚姻は,人が社会生活を送る中で生成され得る種々の,かつ多様な人的結合関係のうち,一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し,夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め,種々の権利を付与するとともに,これに応じた義務も負担させることによって,夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち,本件諸規定の目的は,一人の男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(ア)婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった。したがって,同性の性的結合関係や共同生活関係は婚姻たりえないとされてきた」ところ,「国ないし社会が婚姻に法的介入をするのは,婚姻が社会の次世代の構成員を生産し,育成する制度として社会的に重要なものであったからである」(乙第1号証)などと指摘されている。このように,伝統的に,婚姻は,生殖と密接に結び付いて理解されてきており,それが異性間のものであることが前提とされてきた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
もし「婚姻」という制度を立法する目的から「生殖と子の養育」の趣旨が失われた場合には、その時点で他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが消失することになる。
婚姻制度の立法目的と大阪地裁判決の理解
下図で、「婚姻」の形成過程と大阪地裁判決の理解を取り上げる。
大阪地裁判決では、婚姻の趣旨について述べられている。
しかし、それ以前の婚姻の立法政策上の目的について十分に説明できているとはいえない。
大阪地裁判決の内容
具体的に、判決の誤りを確認する。
〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大している部分がある。
〇 法律論として重要でない部分や訴訟手続き上の話などは「灰色」で潰した。
〇 「個人の尊厳」に色付けしている。
〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「異性愛者」「同性愛者」に色付けしている。(これは法律用語ではない)
〇 「異性間のカップル」「異性カップル」「同性間のカップル」「同性カップル」「LGBTカップル」「カップル」を太字にした。(これは法律用語ではない)
〇 「同性間の婚姻」に関わる部分に色付けしている。
〇 「公認に係る利益」と称するものに色付けしている。
〇 主要な文に色付けているところがある。
〇 リンクを加えた。
【論点番号】
下記の15の論点を押さえれば、この判決の誤りが明確になる。
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
③ 「婚姻している者(既婚者)」との比較対象は「婚姻していない者(独身者)」であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑦ 「異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論」になっていること
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること
【筆者】
インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告らに対し、各100万円及びこれに対する平成31年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、同性の者との婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条、13条、14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨を主張して、被告に対し、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年3月4日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実
当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠(なお、証拠について枝番号を省略したものは枝番号を全て含む趣旨である。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は、次のとおりである。
(1) 性的指向
性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に対して向くことが同性愛である(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。これに対し、性自認とは、自分の性をどのように認識しているかであるところ、性自認の性(心の性)が生物学上の性と一致する場合もあれば、一致しない場合もあり、性自認と生物学上の性が一致しない者をトランスジェンダーという。女性の同性愛者(レズピアン)、男性の同性愛者(ゲイ)、同性愛と異性愛の双方の性的指向を有する者(バイセクシャル)及びトランスジェンダーの性的少数者を総称してLGBTという。
【筆者】
「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」との記載がある。
ここに示されているように、「性的指向」と称するものの内容は「情緒的、感情的」なもので「魅力を感じること」であるというのであるから、これは精神的なものであり、「内心の自由」の範囲のものである。
憲法上の具体的な条文においては、19条の「思想良心の自由」や14条の「信条」によって捉えられるべきものである。
法律論としては、このような思想や感情を基にして自然人を分類することはできないし、このような人の内心を基準として異なる取扱いをすることは、19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「性自認とは、自分の性をどのように認識しているかであるところ、性自認の性(心の性)が生物学上の性と一致する場合もあれば、一致しない場合もあり、性自認と生物学上の性が一致しない者をトランスジェンダーという。」との記載がある。
しかし、「トランスジェンダー」とは「ジェンダー」と述べている通り、生物学的な「性別」とは異なる概念であり、精神的なものである。
このような精神的なものを科学的な裏付けもなしに何の疑問も抱くことなく受け入れて判決の文面で定義として用いることは妥当でない。
「なんか最近一周回ってよく分からなくなってきたんだけど、トランスの人たちは何をトランスしたいの?」 Twitter
「セックスがスペクトラムならトランスは何から何にトランスするんでしょうね」 Twitter
また、「トランスジェンダー」と称しているものと、「性同一性障害」は異なる概念であるとする考え方もあり、科学的に確定的な定義とはいえない。
埼玉県議会の LGBTへの理解増進を図る条例 成立の報を受けて 2022年7月8日
「GIDの権利と女性の安全を守る会」設立しました 2022年9月12日
トランス問題をどのように考えるべきか ――最初の一歩―― 2022年11月28日
このような精神的なもので、客観性を有しないものについては、科学とはいえないのであり、「『のんびりおっとりしたイメージ』であれば、『パンダ系女子』である」というような性格診断と区別することができないものである。
「草食系・肉食系」という分類もある。
我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが、LGBTに該当する人については、平成27年4月当時において全国の20歳~59歳の約7万人を対象とした調査で7.6%、平成28年5月当時において上記年代の約10万人を対象とした調査で約5.9%、同年6月当時において全国の20歳~59歳の有職の男女の約1000人を対象とした調査で8%とする調査結果等がある(甲A567)。
【筆者】
「我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが」との記載がある。
しかし、この「性的指向」と呼んでいるものは、精神的なものであり、持続的で明確な確信を有している者から、曖昧な認識の者まで様々である。
もともと精神的なものであるから、生物学的な性別のように明確に割り切ることができる性質のものではない。
これは「内心の自由」に属するものであり、「思想良心の自由(憲法19条)」、「信教の自由(憲法20条1項)」によって保障される性質のものである。
精神的なもの、心理的なものを基準とした人口調査であるが、「自分は幸運であると感じている者」、「自分は才能がないと感じる者」、「前世を信じる者」などの人口調査と変わらないものである。
このような調査には明確な定義や客観性ある境界線となるものは存在しないのであり、これを基準として法律論を組み立てることはできない。
「LGBTは自己申告なので第三者からの否定は難しい」 Twitter
【動画】#13 佐波優子の保守から見えるLGBTの風景 2021/12/10
アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日
ここでは、前の段落と合わせて「(1) 性的指向」という項目を立てている。
しかし、この項目の中では「性自認」について解説を始め、その後「LGBT」の話に移り変わり、最後には「我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではない」と述べた後に「LGBTに該当する人」の割合の調査を述べて締めくくっている。
結局、「性的指向」について述べているのは、最初の一文だけである。
また、この調査結果を見ても、「異性愛以外の性的指向を持つ者の人口」は分からないままである。
さらに、そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」という思想や感情を保護することを目的とする制度ではないのであるから、このような調査を取り上げたところで、法律論上の論点に何らの影響も与えないのであり、このような内容を判決文として取り上げる必要そのものがないものである。
婚姻制度の立法目的は「性愛(性的指向)」という思想や感情を保護することにあるわけではないのであるから、判決の内容として婚姻制度の枠組みが定めている対象者の範囲について論じる際に、「性愛(性的指向)」という内心の問題に関連付けて論じようとしている点で誤っている。
他にも、「性愛(性的指向)」という特定の思想や感情を保護することを目的として法律を立法することは、「政教分離(20条1項・3項、89条)」に違反して違憲となる可能性がある。
また、「婚姻制度を利用する者(既婚者)」のすべてが「性愛」を満たすことを目的として「婚姻」しているわけでもない。
「性愛」を満たすことを目的とする「婚姻」こそが正しい価値観であるかのような論じ方をすることも誤りとなる。
法律論としては、婚姻制度そのものと、「内心の自由」に属する個々人の価値観とを区別して考える必要がある。
(2) 原告らの関係等
ア 原告1及び原告2は、いずれも男性であり、同性愛者である。
原告1及び原告2は、平成31年2月、居住地において婚姻届を提出したが両者が同陛であることを理由に不受理とされた。
イ 原告3及び原告4は、いずれも女性であり、同性愛者である。
原告4は、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の国籍を有しており、原告3及び原告4は、平成27年8 月、米国オレゴン州において婚姻し(甲C3)、平成31年1月、日本の居住地においても婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた。
ウ 原告5及び原告6は、いずれも男性であり、同性愛者である。
原告5及び原告6は、平成31年2月、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた。
【筆者】
通常、ここには職業が記載されるのであるが、「同性愛者である。」と記載されている。ここでいう「同性愛者」は職業ではないと思われるため、単に自己の思想、信条、信仰を告白するものということになる。
3 民法及び戸籍法の関連規定
(1) 民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるとし、戸籍法74条1号は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定する(以下、民法の規定については、昭和22年法律第222号による改正後の民法の家族法部分の規定を総称して「現行民法」、同改正前の民法の家族法部分の規定を総称して「明治民法」、同改正のことを「昭和22年民法改正」という。また、原告らが主張する、同性間の婚姻を認めていない民法第四編第二章及び戸籍法の諸規定を「本件諸規定」という。)。
(2) 戸籍法では、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製し(同法16条1項本文)、当該戸籍には、戸籍内の各人について、夫又は妻である旨が記載され(同法13条6号)、子が出生した場合にはこれを届け出なければならず(同法49条1項)、子は親の戸籍に入ることとされてお(同法18条)、戸籍の正本は市役所等に備え置くこととされて公証されている(同法8条2項)。
また、民法には「婚姻」の章が設けられ(同法731条以下)、婚姻の成立要件等の規定や、婚姻の効果として、氏の統一(同法750条)、夫婦相互の同居、協力及び扶助の義務(同法752条)が、夫婦の財産に関しては、婚姻費用の分担(同法760条)や夫婦の財産の帰属(同法762条)が、離婚に関しては、財産分与(同法768条)等が規定され、他の章にも、夫婦の子についての嫡出の推定(同法772条1項)、親権に関する規定(同法818条以下)、配偶者の相続権(同法890条)等婚姻の重要な法律上の効果に関する規定が置かれている。
【筆者】
これは、戸籍法と民法上の「婚姻」の内容について具体的に示されたものである。
これに関連して、この判決が「婚姻の本質」と述べている部分について検討する。
この判決の中では、下記のように「婚姻の本質」と称するものが説明されている。
◇ 2(2)(ウ)
「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」
◇ 3(2)ア
「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、」
この判決では、突然に何の根拠もないままにこの「婚姻の本質」と称するものを説明(定義)して、その「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かという視点から、婚姻制度の対象者の範囲が適切であるか否かを論じようとしている部分がある。
しかし、このような「婚姻の本質」と称するものを示すことができる場合があるとしても、それはここに挙げられているような具体的な制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の枠組みを読み解いた場合に、それを利用する者の通常想定される利用者像を簡単な言葉で示したものに過ぎない。
つまり、「婚姻の本質」と称しているものは、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の通常想定される利用メカニズムについて、簡潔な言葉に集約した場合の説明として述べられているだけのものである。
そのため、具体的な婚姻制度の枠組みが存在しない中では、そもそも婚姻制度を利用する者についての通常想定される利用者像も分からないのであるから、「婚姻の本質」と称する説明もすることができないことになるのである。
このことから、具体的な婚姻制度の枠組みが存在しない中で、突然「婚姻の本質」と称する観念が根拠もなく登場するわけではないのであり、その「婚姻の本質」と称する説明だけを絶対的な根拠となるものであるかのような認識の下に、その説明の中に当てはまるか否かのみを論じるだけで、婚姻制度の対象者の範囲の当否を論じようとすることはできない。
この点を押さえる必要がある。
4 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨
本件の争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙2のとおりである。
(1) 本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか。
(2) 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。
(3) 原告らの損害、損害額
(4) 原告4につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見
ア 性的指向及び同性愛に関する現在の知見
性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遺伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている。しかし、精神衛生(メンタルヘルス)に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学における主たる見解も、性的指向は、意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。精神医学においても、同性愛者の中には性行動を変える者がいるものの、それは性的指向を変化させたわけではなく行動を変えたにすぎず、自己の意思や精神医学的な療法によっても性的指向が変わることはないとされている。(甲A2、7、322、324)
イ 欧米諸国における同性愛に関する知見の変遷
(ア) 中世~19世紀末頃における知見
欧州や米国では、中世においては、キリスト教の影響により、同性愛を否定する考え方が確立されていたが、 9世紀末頃から、自らを同性愛者と考える者の存在が表面化するようになると、ドイツ、米国、英国では、同性間の性行為が刑法上の犯罪として取り締まられるようになった。また、この頃から、同性愛は精神的病理として医療の対象としても扱われるようになっていった。(甲A24、163)
(イ) 20世紀初頭~1973年(昭和48年)頃までの知見
米国精神医学会が、1952年(昭和27年)に刊行した「精神障害のための診断と統計の手引き第1版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders〔DSM-Ⅰ〕)」及び1968年(昭和43年)に刊行した同第2 版〔DSM-Ⅱ〕においては、同性愛は、病理的セクシュアリティーを伴う精神病質人格又は人格障害とされていた(甲A48 、161)。
また、世界保健機関が公表した疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 〔ICD〕。以下「国際疾病分類」という。)においても、1992年(平成4年)に改訂第10版(lCD-10)が公表されるまでの改訂第9版(ICD-9)以前においては、同性愛は性的偏倚と性的障害の項目に位置付けられていた(甲A29、30)。
(ウ) 1973年(昭和48年)頃以降における知見の変化
米国精神医学会は、1973年(昭和48年)、同学会の精神障害の分類から同性愛を除外する決議を行い、 1975年(昭和50年)には、米国心理学会も、上記米国精神医学会の決議を支持し、同性愛それ自体では、判断力、安定性、信頼性、一般的な社会的能力ないし職業遂行における障害を意味しないとの決議を採択した(甲A1)。
米国精神医学会は、1980年(昭和55年)に刊行した「精神障害のための診断と統計の手引き第3版(DSM-Ⅲ)」において、同性愛は、自我異和的同性愛、すなわち同性愛者である患者自身が、同性に性的興奮を感じる状態を望まず、その状態が苦痛で、変わりたい旨を訴える場合にのみ精神疾患に当たるものと改訂したが、これも1987年(昭和62年)に刊行された第3版の改訂版(DSM-Ⅲ)においては削除され、同性愛は精神疾患とはみなされなくなった(甲A27、28、48、161、164)。
世界保健機関は、1992年(平成4年)、同性愛を疾病分類から削除した国際疾病分類改訂第10版(lCD-10)を発表した。世界保健機関は、併せて、同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない旨宣明した。(甲A30、48、161、164)
ウ 我が国における同性愛に関する知見の変遷
(ア) 近代以前
我が国でも、近代以前から、同性間の親密な関係は存在していたが、キリスト教の影響をほとんど受けていなかった我が国では、このような関係が特段否定されたり禁止されたりする状況にはなく、特に男性間の関係については、男色、衆道などと呼ばれて種々の文学作品の題材になるなどしていた(甲A163、365)。
(イ) 明治期における知見(19世紀末頃以降)
明治20年代になり、西欧文明の導入や近代化が進む中、我が国においても、同性愛は健康者と精神病者との中間にある変質狂のーつである色情感覚異常又は先天性の疾病であるという知見が紹介されるようになった。色情感覚異常の著明な症状は、色情倒錯又は同性的色情であり、男子が年少の男子に対して色情を持ち、「鶏姦」(男性間の性的行為)をすることや、女子が女子を愛することなどは変質徴候の第1とされていた。このような色情感覚異常者に対する治療法として、催眠術を施すほか、臭素剤を投与する、身体的労働をさせる、冷水浴をさせる、境遇を変化させることなどが行われていた。(乙25、26)
また、青年期における同性愛は、愛情に対する欲求が極めて強いために起こることであり、ある程度を越えなければ心配する必要はないが、同性の者同士が愛情を深め、不純な同性愛に向くこともあり、このような場合には注意すべきことであって、絶対に禁止すべきものとされていた(乙27)。
なお、明治5年に制定された条例により男性間の性行為が犯罪とされ、その翌年には、刑法266条に鶏姦罪が新たに規定されたが、明治15年には旧刑法(明治13年太政官布告第36号)の施行に伴い廃止された(甲A24、366)。
(ウ) 戦後初期(昭和20年頃)から昭和50年頃までの間における知見
戦後初期においても、鶏姦と女子相姦は、変態性欲のーつとされ、陰部暴露症などと並んで精神異常者や色欲倒錯者に多くみられるものとされた。
心理学の分野においても、同性愛は、民族や階級等にかかわらず存在する、性欲の質的異常とされていた。同性愛は、異性愛への心理的成熟以前に、精神的又は肉体的な同性愛を経験し、それが定着した場合に生ずることがあるとされ、その後、異性愛者となり、健康な結婚生活を営むことができるようになる場合がー般的ではあるものの、外的要因によって同性愛が病的に定着してしまうことがあり、それは一般の健康な親愛とは違って、性的不適応の一種であるとされた。そのように病的に同性愛が定着してしまった場合の心理療法として、自己観察や異性愛が抑圧されている原因の探求などを行うものとされ、異性愛に対する障害を取り去ることが根本的対策であるともされていた。(以上につき、甲A147~151)
(エ) 昭和50年頃以降における知見の変化
a 昭和56年頃になると、前記イ(ウ)の欧米諸国の状況を受け、我が国においても、精神医学の分野で、同性愛は、当事者が普通に社会生活を送っている限り精神医学的に問題にすべきものではなく、当事者が精神的苦痛を訴えるときにだけ治療の対象とすれば足りるとの知見が紹介され、平成7年には、日本精神神経学会は、市民団体からの求めに応じて、「ICD-10に準拠し、同性への性的指向それ自体を精神障害とみなさない」との見解を示し、その後、同性愛は精神疾患とはみなされなくなった(甲A48、162、164)。
b 教育領域においては、昭和54年1月に当時の文部省が発行した中学校、高等学校の生徒指導のための資料である「生徒の問題行動に関する基礎資料」に、性非行の中の倒錯型性非行として同性愛が示されており、正常な異性愛が何らかの原因によって異性への嫌悪感となり得ること、年齢が長ずるに従い正常な異性愛に戻る場合が多いが成人後まで続くこともあること、一般的に健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり、また社会的にも健全な社会道徳に反し、性の秩序を乱す行為となり得るもので、現代社会にあっても是認されるものではないことなどが示されていた(甲A26)。
しかし、昭和61年に当時の文部省が発行した「生徒指導における性に関する指導」では、同性愛に関する記載が見られなくなった(甲A163、弁論の全趣旨)。
(2) 婚姻制度について
ア 欧米諸国における婚姻制度
人類は、歴史的に、男女が性的結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、このような男女の結合関係を、国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。中世の欧米では、主に教会からの統制による宗教婚が行われていたが、次第に、国家が法律(民法)によって成立要件を定めて婚姻当事者に一定の権利義務等を発生させる法律婚制度が台頭するようになり、18世紀になると、欧米の多くの国で、男女から成る当事者の意思の合致に基づく婚姻に一定の要件の下で国家等が承認を与える近代的婚姻制度が採用され、確立されていった。なお、当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていたが、後記(3)のとおり、2000年(平成12年)以降は、オランダを始めとして同性間の婚姻を認める国が現れるようになっている。(甲A174、乙2)
【筆者】
「人類は、歴史的に、男女が性的結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、このような男女の結合関係を、国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。」
ここで「男女が性的結合関係」や「種の保存」、「男女の結合関係」を基準にして「婚姻制度が生まれた。」と考えているのであるから、この段階で既に「婚姻」という制度の中には、子供の遺伝的な父親を特定しようとすることや、その特定された父親にも子供に対する責任を担わせること、父母と子の関係を確定し、「子の養育」を予定するものであることが明確になっている。
また、「国家や宗教等の規範によって統制する」ことの背景には、「近親交配」により遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ぐこと、未婚の男女の数の不均衡によって「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれることを抑制すること、母体を保護すること、などの目的(政策)も含まれていると考えられる。
これが、「国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。」ことの歴史的な経緯であり、「男女の結合関係」(男女が性的結合関係)としている理由である。
この大阪地裁判決は、後ほど別の個所で婚姻制度の立法目的が「性愛」を保護することにあるかのような前提で論じようとしているところがあるが、もともと「婚姻」という制度そのものは「性愛」を保護することを目的とする制度ではないため、そのような前提の下に論じることは誤っている。
「当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていた」との記載がある。
ここでいう「当時」とは「18世紀」のことであり、場所は「欧米」である。
それら「欧米」の国の中では「同性愛が否定されていた」という事実があるとしても、世界のすべての地域で「同性愛が否定されていた」わけではない。
また、世界中の大半の地域では古くから「婚姻」にあたる枠組みを有しているのであり、「性愛」という思想や感情に基づいて制度を設けている地域もあるのかもしれないが、そのような「性愛」というような思想や感情とは関係なく、あるいは意図的に区別して婚姻制度を設けている地域も存在する。
そのため、「当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていた」という部分が、あたかも婚姻制度が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という特定の思想や感情を保護することを目的として立法された制度であるかのような理解をしているのであれば、世界中の制度に共通するというような普遍的なものということはできない。
また、日本の地域や現在の日本国の法令の下に置いても、婚姻制度は「性愛」(その中でも特に『異性愛』)を保護するために立法された制度ではないから、そのような理解が通用するわけではない。
このような論じ方をしたいのであれば、日本国における婚姻制度の立法過程で、婚姻制度が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的として立法されていることを裏付ける根拠や資料を示す必要がある。
それを示さないままに、日本国の婚姻制度が立法される過程で、「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的としているかのように論じることは、日本国の婚姻制度とは異なる目的によって形成された「欧米」の制度について、単に外国語を翻訳する際に「婚姻」という同一の言葉が充てられていることを根拠として、異なる制度であるにもかかわらず外国法を基準として自国の法制度に同一の立法目的が存在するかのように考えようとする論理に依拠する主張となるのであり、日本国の婚姻制度の立法目的を適切に捉えているとはいえないことになる。
また、日本国憲法の下では「性愛」という特定の思想や信条を保護することを目的として制度を立法することはできないことも理解する必要がある。
イ 我が国における婚姻制度
(ア) 明治民法(明治31年7月16日施行)における婚姻制度
a 起草段階
明治民法が制定される以前から、我が国においても、ー男一女が儀式等をして夫婦として共同生活を送る慣習としての婚姻は存在し、人生における重要な出来事とされていたが、明治維新後、このような慣習による婚姻を近代的な法律婚制度として確立するため、民法の家族法部分の起草作業が行われた。起草に当たっては、フランス民法、イタリア民法など8か国の外国法が参照されたが、従来の我が国における慣習を直ちに改めるのではなく、慣習を踏襲しつつも、慣習をそのまま認めれば弊害となる事項や慣習からは明らかでない事項について法により規律するものとして制定されることとなった。(乙3)
【筆者】
「人生における重要な出来事とされていた」との記載がある。
ただ、日本国憲法には「個人の尊厳」が定められており、自然人である一人一人は「自律的な個人」として既に尊重されている。
そのため、「婚姻しなければ一人前にはなれない」というような価値観は存在しない。
日本国憲法の下では「婚姻」は利用したい人が利用すればよいというだけの制度であり、 一定の年齢に達した時点で「成人」として扱われる(成人式をする者もいる。)というような、すべての人に共通する出来事というわけではない。
ここで「婚姻」について「人生における重要な出来事」という位置づけで理解していることは、「婚姻」をあたかも「すべての人が通るべき道」であるかのような特定の価値観が含まれてしまうため、日本国憲法の下においては適切ではないことに注意が必要である。
法律論としては「婚姻」しない生き方も同様に尊重されるべきものであり、「婚姻していない者(独身者)」があたかも「人生における重要な出来事」を歩むことができていない者であるかのような否定的な評価に繋がるような言葉遣いを用いるべきではない。
むしろ、日本国憲法の下では、「個人の尊厳」の観点から、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態として扱われているのであり、「婚姻していない者(独身者)」こそが基準(スタンダード)となるべきものである。
「人生における重要な出来事」のように、「婚姻している者(既婚者)」こそが正しい生き方であるかのような「婚姻している者(既婚者)」を基軸として理解するような説明を行うことは、特定のグループを持ち上げるものであり、法律論としては偏った説明となる。
法解釈においては制度を無色化できる言葉遣いを用いなければならない。
同性間の婚姻に関しては、当時の外国法には同性間の婚姻を明示的に禁止するものもみられたが、明治民法においては、婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった(甲A206、214、乙11)。
【筆者】
「婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった」との記載がある。
ここでいう「禁止する旨の規定」の意味は、「~~してはならない」のような義務文・否定文による「禁止」を定める規定をいうものである。
しかし、婚姻制度は法制度であることから、法律上の要件として男女であることが求められているのであれば、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」としては成立しないのであり、結論として「禁止」していることと同じ状態ということができる。
そのため、「~~してはならない」というような義務文・否定文による「禁止する旨の規定」が存在しなくとも、そもそも「婚姻」として成立しないという意味ではそのこと自体で「禁止する旨の規定」ともいうことができるのである。
このような厳密な理解を前提とせずに、「特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった」と述べたとしても、このことによって「義務文・否定文による『禁止する旨の規定』が置かれていないのであるから、同性間の人的結合関係を『婚姻』とすることも許容されるはずである」とする主張の根拠にはならないことに注意が必要である。
「婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は様々な人的結合関係の中から、「生殖」に関わる問題について発生し得る社会的な不都合を解決するための手段として、「生殖と子の養育」の観点から、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そのことから、「婚姻」という制度の中には、常に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれているのであり、この趣旨に当てはまらない人的結合関係を「婚姻」として扱わないことについては「言ハスシテ明カ」等とされているものと考えられる。
この「婚姻」という意味を引き継ぐ形で憲法24条の「婚姻」が定められているのであるから、憲法24条の「婚姻」にもこの「同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等」との趣旨が含まれていることになる。
そのため、同性間の人的結合関係については、憲法24条の「婚姻」に含まれないのであり、24条の下で「婚姻」として扱うことはできないことになる。
また、生殖能力を持たない男女の婚姻の可否についても起草段階から議論されたが、婚姻の性質について、男女が種族を永続させるとともに、人生の苦難を共有して共同生活を送ることにあると解し、生殖能力を持たない男女は、婚姻の目的を達し得ないから、婚姻の条件を欠き婚姻し得ないとの見解と、男女が種族を永続させることを婚姻の性質に含めることは、老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できない、婚姻の本質は両者の和合にあり、生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの見解がある中、最終的には、婚姻とは男女が夫婦の共同生活を送ることであり、必ずしも子を得ることを目的とせず、又は子を残すことのみが目的ではないとされて、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立することとされた(甲A213、218、219、乙4)。
【筆者】
「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否についても起草段階から議論されたが、」との記載がある。
まず、婚姻制度の立法目的として、下記を挙げることができる。
・ 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・ 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・ 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・ 母体を保護すること
婚姻制度はこれらの立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているものである。
そのため、これらの立法目的を達成することを阻害する人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできない。
逆に、これらの立法目的を達成することを阻害しない範囲であれば、「婚姻」として扱うことも可能と考えられる。
その意味で、「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否」については、「生殖能力」がないためその間で子供が産まれないのであり、「『子の福祉』が実現される社会基盤を構築すること」や「遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること」、「母体を保護すること」には影響を与えない。「男女二人一組」の形であれば、その社会の中で未婚の男女の数の不均衡が発生することもないため、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすという目的の達成も阻害することがない。
よって、「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否」については、可能とすることもできると考えられる。
国(行政府)は下記のように説明している。
「現行民法が子を作る能力や意思の有無でその法的地位を区別していないことと,現行民法が抽象的・定型的に子を産み育てることを目的とする男女の共同生活に対して法的保護を与えることをその目的としていることは,何ら矛盾するものではない。」
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかしながら、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ウ)(44ないし45ページ)で述べたとおり、パッケージとして構築される婚姻及び家族に関する制度においては、婚姻を要することができるか否かの基準が明確である必要がある。
また、現行民法が子を作る能力や意思の有無でその法的地位を区別していないことと、現行民法が抽象的・定型的に子を産み育てることを目的とする男女の共同生活に対して法的保護を与えることをその目的としていることとは、何ら矛盾するものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF
(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)
「子供のない夫婦は「制度」の遊び。」 Twitter
「それは制度の「遊び」の部分として許容されている。」 Twitter
「子供のいない夫婦もあるってか。子供を作ろうとしてもできない時もある。制度の円滑な運用のため、多少の遊びは見る必要はある。」 Twitter
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現行の憲法および民法は、生殖可能性のある男女のカップルを類型的に取り出し、それに法的保護を与えている。不妊、高齢等の理由で実際には生殖能力のない男女のカップルでも現行法が婚姻可能としているのは、生殖能力の有無を国家が調べて「婚姻」を許可する制度が個人の尊厳(憲法24条2項)を著しく害するからにすぎない。それゆえに男女のカップルであれば一律に生殖能力があるものとみなしているのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18
「婚姻の性質について、男女が種族を永続させるとともに、人生の苦難を共有して共同生活を送ることにあると解し、生殖能力を持たない男女は、婚姻の目的を達し得ないから、婚姻の条件を欠き婚姻し得ないとの見解と、男女が種族を永続させることを婚姻の性質に含めることは、老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できない、婚姻の本質は両者の和合にあり、生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの見解がある中、最終的には、婚姻とは男女が夫婦の共同生活を送ることであり、必ずしも子を得ることを目的とせず、又は子を残すことのみが目的ではないとされて、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立することとされた」との部分について検討する。
まず、この文の最後の部分に「婚姻も有効に成立することとされた」と記載されていることから、ここで論点になっているものは、「婚姻」が「有効に成立する」か否かの問題である。
これは、具体的な法制度が存在していることを前提とし、その制度が定める要件に当てはまる者の間で「婚姻」が「有効に成立する」場合と、「有効に成立」せず、無効な場合を区別しようとする論点ということである。
この時に、「生殖能力を持たない男女」は「婚姻の条件を欠き婚姻し得ない」とする見解と、「生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではない」とする見解があり、最終的に「生殖不能な者の婚姻も有効に成立する」としているものである。
ここで重要となっているものは、具体的な法制度として婚姻制度が存在することを前提とし、「生殖能力を持たない男女」の「婚姻」が「有効に成立する」かどうか、つまり、その制度の適用を受ける地位があるかないかである。
よって、ここで述べられている「婚姻の性質」の説明は、具体的な婚姻制度が存在することを前提とし、その法制度を利用する者の利用者像として述べられているものであり、婚姻制度そのものが立法される際の「国の立法目的」とは異なるものである。
そのため、ここで「生殖能力を持たない男女」の「婚姻」が「有効に成立する」ことを根拠として、婚姻制度を整備している「国の立法目的」の中から「生殖と子の養育」の趣旨が失われるというわけではない。
この点、婚姻制度についての「国の立法目的」と、「婚姻」が有効に成立するための条件と、「個々人の利用目的」などを混同しないように注意する必要がある。
「目的」の意味の多義性について、当サイト「同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析」で詳しく解説している。
b 明治民法における婚姻制度
明治民法においては、婚姻は、特定の儀式を不要とし、国家に対する届出によって成立する法律婚として整備された。しかし、そこでは、従来の家を中心とする家族主義の観念を踏襲し、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ、当事者間の合意のみによってはできないものとされた上、夫の妻に対する優位が認められていた。なお、このような明治民法における婚姻は、終生の共同生活を目的とする、男女の、道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であり、又は、異性間の結合によって定まった男女間の生存結合を法律によって公認したものであると考えられており、婚姻が男女間におけるものであることは当然のこととされていた。したがって、同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていないものの、同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。なお、立法当時において、立法担当者らの間で同性愛が精神障害に当たることが特に議論されたことはうかがわれない。 (甲A19、206、207、541、542、乙3~5)
【筆者】
「同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていないものの、同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との記載がある。
しかし、「明治民法」における「婚姻は、特定の儀式を不要とし、国家に対する届出によって成立する法律婚」として定められているのであり、「同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていない」としても、法律上の要件を満たさないのであれば、「法律婚」(宗教上の婚姻とは違うという意味)が成立しないのであり、成立しないものに対して「禁じる規定」が存在しないことを殊更に取り上げることに意味があるとは思えない。
ここでいう「禁じる規定」の意味は、「~~してはならない。」というような義務文・否定文による「禁じる規定」のことを指していると思われるが、「法律婚」として成立しないということは、「法律婚」をすることができないのであり、結果として「禁じる規定」と読み解いたとしても同じことである。
例えば、基本的に弁護士資格を取得するためには司法試験で合格しなければならないが、司法試験で合格していない者を弁護士とすることを「禁じる規定」が存在しないとしても、基本的には司法試験で合格しない限りは弁護士とはなれないのであるから、司法試験で合格していない者が弁護士となることについて禁じられていると考えても同じことである。
その意味では、現在の制度について、基本的に司法試験に合格していない者が弁護士となることを「禁じる規定」である考えても、結論は同じである。
そのことから、恐らくここで「禁じる規定」という言葉を使っている背景にある理解としては、「~~してはならない。」という義務文・否定文が存在するか否かという観点によって論じようとするものと考えられるが、法律上の要件を満たさないのであれば、「法律婚」としては成立しないのであるから、義務文・否定文による「禁じる規定」が置かれていないことを取り上げること自体が不自然であり、法律論として不要である。
「同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との部分であるが、「同性間」については法律上の要件を満たさないため「法律婚」として成立しないのであるから、「同性間の婚姻」という概念自体が存在しないはずである。
「同性間で婚姻をすることについては、」のように、できるだけ詳細に描き出さなければ、語感が独り歩きし、論理的な過程を思い描きにくくなり、書き手と読み手の間で認識にズレが生じやすくなるため注意が必要である。
「婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との部分について検討する。
そもそも法律上の要件を満たさないのであれば、「婚姻」として成立しないのであるから、「婚姻意思」の存否というような、「婚姻」が成立することを前提として「婚姻意思」の存否が問題となる事例に当てはめて考えている点で妥当でないように思われる。
「婚姻意思」が問われる場合とは、書面の上では法律上の要件を満たしていたが、本人たちの間に「婚姻意思」がないために、法的効果を及ぼすことが適当でない事例についての問題である。
「同性間」については、そもそも書面の上でも法律上の要件を満たしていないのであるから、法的効果が発生しない原因を「婚姻意思」の存否に結び付くかのように考えている点で不当であるように思われる。
「立法当時において、立法担当者らの間で同性愛が精神障害に当たることが特に議論されたことはうかがわれない。」との記載がある。
しかし、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的とする制度ではないから、そもそも「異性愛」が正しい「性愛」であるかどうかという議論もなされていないはずであり、当然、それに対する形で「同性愛」が「精神障害」に当たるか否かに関することも、議論されていないはずである。
この大阪地裁判決の文脈では、あたかも婚姻制度が「性愛」(その中でもとりわけ『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的として立法された制度であるかのような論じ方をしているが、婚姻制度が「性愛」を保護することを立法目的としていることを証明するような資料が提示されているとはいえない。
また、「異性愛」や「同性愛」、「その他の性愛」など、特定の思想や感情を保護するために法律を立法することは、「思想良心の自由(憲法19条)」、「政教分離原則(憲法20条1項・3項、89条)」、「平等原則(14条)」に抵触して違憲となると考えられる。
さらに、婚姻制度を利用する者の中には、制度の活用方法として様々な利用目的を有する者が想定されるのであり、利用者の有する様々な利用目的を差し置いて、「異性愛」という思想や感情に基づいて「婚姻」に至ることこそが正しい価値観であるかのような前提で論じている点で、制度に対して特定の価値観を反映しようとする者の主張となっており、妥当でない。
「異性愛」という思想や感情に基づいて「婚姻」することこそが正しい価値観であるとする裁判官個人の思想を露顕するものに過ぎず、法律論として正当化することはできない。
(イ) 憲法(日本国憲法)の制定(昭和22年5月3日施行)
第二次世界大戦後の昭和22年、我が国では、大日本帝国憲法(明治23年施行)を改正する形で、現行の憲法(日本国憲法)が制定された。大日本帝国憲法は、家族に関する規定を置かず、家族制度の設計を法律に委ねていたのに対し、新たに制定される憲法では、13条及び14条において、全て国民は個人として尊重され、法の下に平等であって、性別その他により経済的又は社会的関係において差別されないことを明らかにし、24条において、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないこと、及び配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを宣言した。
憲法24条1項の起草過程において、GHQ民生局のベアテ・シロタ・ゴードンの起草に係る草案では、「家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪ンカレ国民ニ浸透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等(英語の原案では「undisputed legal and social equality of both sexes」)ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ・・・」という文言があり、日本側がこれを基に整えた憲法改正草案要綱にも「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」とされていた。
その後、各条項について字句の表現等が検討された結果、表現上の訂正等を経て、大日本帝国憲法改正案22 条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされ、さらに帝国議会での審議を経て現行の憲法24条として制定されることになった。なお、同条の制定に当たっては、帝国議会での審議において、伝統的な家族制度が維持されることになるかは論点となったものの、同性間の婚姻に関して議論された形跡は見当たらない。(以上につき、甲A186、187、188、190、192、228、弁論の全趣旨)
(ウ) 昭和22年民法改正における婚姻制度
a 起草過程
明治民法は、家を中心とする家族主義の観念から、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻も、戸主や親の同意を要件とし、当事者間の合意のみによってすることのできないものとし、夫の妻に対する優位も認めていた(前記(ア)参照)。昭和22年民法改正は、このような明治民法を、憲法の個人主義的家族観に沿うものに改めるべく、家制度を廃止するほか、未成年者以外における父母や、継父母・嫡母の婚姻同意に関する規定を廃止し、戸主の婚姻同意権も廃止して婚姻の自主性を宣言したものである。
このように、昭和22年民法改正は、明治民法のうち憲法の基本原則(前記(イ)参照)に抵触する規定を中心に行われ、憲法に抵触しない規定については明治民法の規定を踏襲したものであり、この際に同性間の婚姻について議論された形跡はない。(以上につき、甲A19、143、182、183、185、186、192、乙6、7、13、17、弁論の全趣旨)
b 昭和22年民法改正当時における婚姻制度
昭和22年民法改正当時、夫婦関係とは、永続的な男女の精神的、肉体的結合であるとされ、婚姻意思とは、当事者に社会の習俗によって定まる夫婦たる身分を与え、将来当事者間に生まれた子に社会の慣習によって定める子たる身分を取得させようとする意思、又は、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成する意思であるなどと解されていた。
このように、昭和22年民法改正によっても、婚姻は男女間におけるものであることが当然のことで、同性間の婚姻は、上記のような夫婦関係には当てはまらず、その意味で婚姻ではないとされ、明治民法下と同様に婚姻意思を欠き、無効な婚姻であると解されていた。(以上につき、甲A152、153、乙8~10)
(3) 諸外国及び地域における同性間の婚姻制度等に関する状況
ア 諸外国及び地域における法制度等の状況
(ア) 欧米でも、中世においては、前記のとおりキリスト教の影響等から同性愛自体が否定されていたため、同性間の婚姻も考えられていなかった。しかし、同性愛に対する知見が変化する中で、1989年(平成元年)、デンマークにおいて、婚姻とは異なるものの、同性の二者間の関係を公証し、又は一定の地位を付与する登録制度(導入した主体によって制度の内容は異なるが、以下、総称して「登録パートナーシップ制度」という。)が導入され、2001年(平成13年)にはドイツ及びフィンランド、2004年(平成16年)にはルクセンブルク、2009年(平成21年)にはオーストリア、2010年(平成22年)にはアイルランドにおいて登録パートナーシップ制度が導入された。(甲A181)
(イ) また、次の各国においては、次に掲げる年に同性間の婚姻制度が導入された(特に断りのない限り法律の制定年又は裁判所がこれを容認する判断をした年)。これらの国の中には、既に登録パートナーシップ制度が存在していた国も相当数含まれているが、同性間の婚姻制度の導入とともに、これらの制度が廃止された国もあれば、併存する国もある。
(甲A181、355、564)
2000年(平成12年) オランダ
2003年(平成15年) ベルギー
2005年(平成17年) スペイン及びカナダ
2006年(平成18年) 南アフリカ
2008年(平成20年) ノルウェー
2009年(平成21年) スウェーデン
2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド及びアルゼンチン
2012年(平成24年) デンマーク
2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル及び英国(イングランド及びウェールズ)
2014年(平成26年) ルクセンブルク
2015年(平成27年) アイルランド及びフィンランド
2017年(平成29年) マルタ、 ドイツ、オーストリア及びオーストラリア
2019年(平成31年、令和元年) エクアドル(ただし、施行年)
2020年(令和2年) 英国(北アイルランド)及びコスタリカ(ただし、施行年)
(ウ) 上記の国に加え、米国においては既に36の州やワンントン・コロンビア特別区及びグアムで同性間の婚姻が認められていたが、これを認めていない州もあったところ、そのような州法の規定の合憲性が争われた事件(いわゆるObergefell
事件)において、米国連邦最高裁判所は、2015年(平成27年)6月26日、婚姻の要件を異性間のカップル(以下「異性カップル」という。)に限り、同性間のカップル(以下「同性カップル」という。)の婚姻を認めない州法の規定は、デュー・プロセス及び平等保護を規定する合衆国憲法修正第14条に違反する旨の判決を言い渡した(甲A181、195)。
【筆者】
米国における「婚姻」は、日本国における婚姻制度とは性質が異なっている。
ただ、米国のObergefell判決を、日本国の法制度に照らし合わせて考えると、下記の論点で誤っていると考えられる。
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
さらに、台湾においては、2017年(平成29年)、憲法裁判所に当たる司法院が、同性間の婚姻を認めない民法の規定は違憲である旨の解釈を示し、2019年(令和元年)、これに基づき同性間の婚姻を認める民法の改正が行われた(甲A101、139)。
(エ) 他方、イタリアにおいては、憲法裁判所が、2010年(平成22年)に婚姻は異性間の結合を指す旨判断し、2014年(平成26年)にも同様の判断をしたが、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国の法制度上存在しないため、この点が同国憲法の規定に違反する旨の判断をし、その結果、2016
年(平成28年)に婚姻とは別の婚姻類似の制度である「民事的結合」と呼ばれる制度を認める法律が成立した(甲A181)。
(オ) また、ロシアにおいては、1993年(平成5年)の刑法典改正により同性愛行為が処罰対象から外されたが、2013年(平成25年)、同性愛を宣伝する活動を禁止する法律が成立し、2014年(平成26年)、憲法裁判所は、同性愛の宣伝行為の禁止は同国憲法の規定に違反しない旨の判断をした。
ベトナムにおいては、2014年(平成26年)、それまで禁止の対象となっていた同性との間で結婚式をすることを禁止事項から除く法改正を行ったが、同時に、婚姻は男性と女性との間のものと明記し、法律は同性間の婚姻に対する法的承認や保護を提供しないとされた。
韓国においては、2016年(平成28年)、地方裁判所に相当する地方法院において、同性間の婚姻を認めるか否かは立法的判断によって解決されるべきであり司法により解決できる問題ではないとの判断をした。同国での2013年(平成25年)の調査においては、同性間の婚姻を法的に認めるべきとする者が25%だったのに対し、認めるべきではないとする者が67%に上っていた。(以上につき、甲A181)
【筆者】
外国の法制度が必ずしも進んでいるとは言えない事例として、「安楽死」の合法化問題がある。
安楽死や自殺幇助が合法化された国々で起こっていること 2012.10.01
オランダ、ベルギー、米国、カナダ、オーストリア、英国、スイスなどの国も制度を有しているようであるが、必ずしも適切な政策であるとは言えないように思われる。
外国の事例を並べたとしても、それが適切であるかどうかは別の問題であることに注意が必要である。
イ 日本に所在する外国団体の動向
在日米国商工会議所は、平成30年9月、日本を除くG7参加国においては同性間の婚姻又は登録パートナーンップ制度が認められているにもかかわらず、日本においてはこれらが認められていないことを指摘し、外国で婚姻した同性カップルが我が国においては配偶者ビザを得られないなど同性愛者の外国人材の活動が制約されているなどとして、婚姻の自由をLGBTカップルにも認めることを求める意見書を公表した。また、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商業会議所、在日カナダ商工会議所及び在日アイルランド商工会議所も、同月、上記意見書に対する支持を表明し、その後、在日デンマーク商工会議所も支持を表明した。(甲A112、130、131)。
(4) 我が国におけるLGBTをめぐる状況
ア 平成14年3月、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律7条に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「人権教育・啓発に関する基本計画」が閣議決定され、平成22年12
月に第3次男女共同参画基本計画、平成27年12月に第4次男女共同参画基本計画、令和2年12月に第5次男女共同参画基本計画がそれぞれ閣議決定され、いずれにおいても、性的指向を理由とする差別や偏見の解消を目指して、啓発活動や相談、調査救済活動に取り組むことなどが明記された(甲A57、356~358)。
イ 性同ー性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が、平成15年7月16日に成立し、平成16年7月16日に施行された。同法3条1項2号では、家庭裁判所が、性同一性障害者からの請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる場合の要件として、「現に婚姻をしていないこと」を定めている。この規定について、最高裁判所において、「現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえない」として、憲法13条、14条1項、24条に違反するものとはいえない旨の判断がされている(最高裁令和元年(ク)第791号同2年3月11日第二小法廷決定)。
【筆者】
この段落であるが、この訴訟で論点となっているものは、婚姻制度の対象となっていない同性間の人的結合関係についての問題であり、「性同一性障害」の話は直接的な関係がない。
関係のない話を取り上げて、あたかも関係性があるかのように論じようとしている点で、論題から逸れており適切ではない。
ウ 平成27年10月に東京都渋谷区が、同年11月に東京都世田谷区が登録パートナーシップ制度を導入したのを始めとして、登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加し、現在では導入した地方公共団体数が130を超えた(甲A75~91、98、553)。
【筆者】
「登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体」であるが、その「登録パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度に抵触する場合には違法となる。
婚姻制度は下記の立法目的に応じて、それを達成するための手段として枠組みが定められていると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「登録パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
また、憲法は14条で「平等原則」、19条で「思想良心の自由」、20条1項・3項、89条で「政教分離原則」を定めており、特定の思想や信条に着目して法制度を整備し、何らかの優遇措置を与えることや、特定の思想や信条を有する者を選び出して区別し、何らかの優遇措置を与えることは、これらの規定に抵触して違憲となる。
この論点について、詳しくは「2(3)イ(ウ)」の第二段落の解説部分や、当サイト「パートナーシップ制度」のページで解説している。
エ 我が国における、権利の尊重や差別の禁止などLGBTに対する基本方針を策定している企業数は、平成28年の調査では173社であったが、令和元年の調査では364社であった(甲A391、392)。
(5) 婚姻、結婚に関する統計
ア 婚姻に対する意識調査の結果
(ア) 内閣府による平成17年版国民生活白書によれば、独身の時に子供ができたら結婚した方がよいかとの質問に対し、15~49歳のいずれの年齢層においても、そう思うとの回答が4~6割であり、そう思わないとの回答はおおむね1割に満たないものであった。また、いずれ結婚するつもりであると回答した男女は、昭和57年から平成14年までの各年の調査を通じてそれぞれ9割を超えていた。(甲A332)
(イ) 厚生労働省による平成25年版厚生労働白書によれば、平成21年の調査では、「結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい」という考え方に賛成又はどちらかといえば賛成する者は70%であったが、平成22年に20~49歳を対象として行った調査では、「結婚は必ずするべきだ」又は「結婚はしたほうがよい」との意見を持つ者は合計で64.5%に上り、米国(53.4%)、フランス(33.6%)、スウェーデン(37.2%)を上回った(甲A333)。
(ウ) 国立社会保障・人口問題研究所が平成27年に行った調査の結果は、次のとおりであった(甲A239の52)。
a 結婚することに利点があると思う未婚の者は、男性で64.3%%、女性で77.8%であり、その理由として回答が多かったもの(二つまで選択可の選択肢式による調査)は、次のとおりである。
「精神的安らぎの場が得られる」(男性31.1%、女性28.1%)
「親や周囲の期待に応えられる」(男性15.9%、女性21.9%)
「愛情を感じている人と暮らせる」(男性13.3%、女性14%)
「社会的信用や対等な関係が得られる」(男性12.2%、女性7%)
b 未婚者に対する「生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない」との質間には、男性の64.7
%、女性の58.2%が賛成し、「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」との質問には、男性の74.8%、女性の70.5%が賛成と回答をした。
イ 婚姻に関する統計
(ア) 厚生労働省が行った平成30年の我が国の人口動態に関する調査の結果は、次のとおりであった(甲A330)。
a 平成28年の婚姻件数は、最も多かった昭和47年の約110万組と比較すると約半分となって減少傾向ではあるものの、62万0531組であった。
b 我が国の婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は、昭和47年以降、増減がありつつも減少傾向にあり、平成28年には5%となったが、イタリア(3.2%)、ドイツ(4.9%)、フランス(3.6%)、オランダ(3.8%)等のヨーロッパ諸国を上回っている。
出生に占める嫡出でない子の出生割合は、日本は2.3%であり、米国(40.3%)、フランス(59.1%)、ドイツ(35%)、イタリア(30%)、英国(47.9%)等よりも低い割合である。
【筆者】
日本国の「嫡出でない子の出生割合」は他国とは大きく異なっており、婚姻制度の内容や機能が他国とは異なることは明らかである。
【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05
【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年
外国の法制度と比較する際には、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という同一の言葉を充てて説明しているからといって、それぞれの国の間でまったく同一の制度を指していることにはならないことに注意する必要がある。
(イ) 厚生労働省が昭和61年から平成30年までに行った調査によれば、昭和61年以降、児童のいる世帯が全世帯に占める割合は年々減少し、昭和61年には46.2%であったものが、平成30年には22.1%まで減少した(甲A331)。
(6) 同性間の婚姻の賛否等に関する意識調査の統計
ア 毎日新聞社が平成27年に行った世論調査では、「同性同士の結婚」に賛成する者が44%、反対する者が39 %で、賛成が反対を上回ったが、無回答も17%あった(甲A105)。
イ 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが全国47都道府県の20歳~79歳の男女2600人を対象に行った、性的マイノリティについての意識に関する平成27年の全国調査によれば、1259人の回答者中、男性の44.8%、女性の56.7%が「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、男性の50%、女性の33.8%は反対又はやや反対と回答し、男性の5.3%、女性の9.5%は無回答であった。この調査においては、20~30代の72.3%、40~50代の55.1%は「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代の賛成又はやや賛成の回答は32.3%にとどまり、同年代の56.2%は反対又はやや反対と回答した。(甲A104)
上記研究代表者による令和元年の全国調査によれば、回答者約2600人のうち、男性の59.3%、女性の69.6%が「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、男性の37%、女性の23.9%はこれに反対又はやや反対と回答した。この調査においては、20~30代の81%、40~50代の74%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代の賛成又はやや賛成の回答は47.2%であり、同年代の43.4%は反対又はやや反対と回答し、約10%が無回答であった。(甲A512)
ウ NHKが平成29年に行った世論調査では、「同性同士の結婚を認めるべきか」という質間に対し、「そう思う」が約51%、「そうは思わない」が約41%、「わからない」が約8%となった。また、朝日新聞が同年に行った調査では、「同性婚」を法律で認めるべきだとの回答が約49%、認めるべきではないという回答が約39%、その他や無回答が合計約12%であった。(甲A106、109)
エ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った全国家庭動向調査によれば、同性カップルにも何らかの法的保障が認められるべきだとの調査項目に対し、全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は75.1
%であった。また、「同性同士の結婚」を法律で認めるべきだとの調査項目については、全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は69.5%であった。(甲A298)
オ 他方、NHKが平成27年にLGBTを含む性的マイノリティ当事者約2600人を対象に行ったウェブ調査の結果によれば、①地方公共団体が登録パートナーシップ制度を導入した場合には結婚相当の証明書を申請したいという者が38.8%、パートナーができたら申請したいという者が43.6%おり、②「同性間の結婚」をどう思うかという質問には、結婚を認める法律を作ってほしいと答えた者が65.4%であった一方、結婚ではなくパートナー関係の登録制度を国が作ってほしいと答えた者が25.3%であった(甲103)。
また、宝塚大学看護学部教授日高庸晴が、令和元年9月~12月に1万人以上の性的少数者を対象としてSNS上でアンケートを実施した結果、対象者全体の約60%が異性間の婚姻と同じ法律婚が同性間にも適用されることを望むと回答し、約16%が公的制度を作る必要はないが社会の理解は浸透してほしいと回答したが、残る24%の者のほとんどは、国レべル又は地方公共団体レベルのパートナーシップを制定してほしいという回答であった(甲A301)。
2 本件諸規定が憲法24条、13条に違反するかについて(争点(1)関係)
(1) 原告らが主張する本件諸規定について
原告らは、婚姻を異性間の婚姻に限定している民法第四編第二章及び戸籍法の規定全てを本件諸規定として、これらが違憲である旨主張するものであるが、少なくとも本件諸規定に含まれると原告らが主張する民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずると定め、これを受けた戸籍法74条は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏等を届出書に記載して、その旨を届け出なければならないと定めているにすぎず、その他の規定をみても同性間の婚姻を禁止する旨定めた明文の規定はなく、民法731条以下の婚姻の実質的要件に係る規定中にも「同性でないこと」を明示する規定はない。しかし、民法等において婚姻の当事者について「夫婦」などの文言が用いられていることに加え、明治民法から現行民法に至るまでにおいても、一貫して、婚姻は男女問によるものであることが当然の前提とされ、同性間については、婚姻の意思を欠くなどと解釈されて、婚姻として取り扱われてこなかったこと(認定事実(2))、実際、原告らは我が国の各地方公共団体において婚姻届を提出したが、いずれも同性であることを理由に不受理とされたこと(前提事実(2))を踏まえると、本件諸規定を含む我が国における婚姻制度は、配偶者が異性であることを当然の前提とするものであり、配偶者が異性であることを婚姻の要件とするものと解釈できる。そこで以下では(後記3、4についても含む。)、本件諸規定が上記のように解釈されることを前提に、本件諸規定が憲法の規定に違反するか否かを検討する。
(2) 本件諸規定が憲法24条1項又は13条に違反するかについて
ア 憲法24条1項に違反するかについて
(ア) 憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しており、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。(最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁)
【筆者】
この最高裁判決の引用は、最高裁判決が「同条1項は,」としている点を「憲法24条1項は、」に変えていること以外は同じである。
ただ、最高裁判決の中では、この24条1項の説明の前に24条2項の説明がなされており、この2項の要請する法律の規定が存在することを前提として、この1項の解釈において上記に挙げられているような「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」との文が出てくるわけである。
この点、この大阪地裁判決では、最高裁判決の文脈から24条1項の解釈部分を切り取って一つの段落にしたわけであるが、このような切り取り方は最高裁判決の全体の文脈の趣旨を正確に受け継ぐことを困難とするため、適切な方法であるとは言い難い。
(イ) 原告らは、婚姻をするについての自由は、憲法24条1項に基づき、異性間のみならず同性間の婚姻についても保障されているから、婚姻制度から同性間の婚姻を排除している本件諸規定が同項に違反する旨主張する。そこで、まず同項にいう「婚姻」に同性間の婚姻が含まれているかを検討する。
憲法24条1項においては、婚姻は「両性の合意」のみに基づいて成立する旨が規定され、婚姻をした当事者については「夫婦」との文言が用いられており、同条2項においても「両性の本質的平等」との文言が用いられている。このような「両性」や「夫婦」の文言は、婚姻が男女から成ることを意味するものと解するのが通常の解釈であって、上記条文中に、これらが同性の概念を含む意味で用いられていることをうかがわせる文言は見当たらない。憲法その他の法令において、上記の文言を、同性を含む意味として用いられている例も見当たらない。
そして、我が国では、明治民法において初めて法律婚としての婚姻が制度化されたが、その起草過程においては、婚姻については基本的に従来の慣習を踏襲することとされ、その意義についても、終生の共同生活を目的とする男女間の生存結合を法律によって公認したものとされていたことからすると、婚姻は異性間でするものであることが当時から当然の前提とされており、同性間で婚姻をすることができないことは、あえて民法に規定を置くまでもないものと考えられていたことが認められる(認定事実(2)イ(ア))。
さらに、昭和22年に憲法が制定され、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した婚姻制度を確立するために憲法24条が定められたが、同条の起草過程で「both sexes」を訳して「男女両性」や「男女」という文言が用いられていたこと等からすると、この時点でも、婚姻は男女間のものであることが当然の前提となっていたと考えられる(認定事実(2)イ(イ))。なお、同条の要請を受けた昭和22年民法改正においても、その起草過程で同性間の婚姻について議論された形跡はない(認定事実(2)イ(ウ))。
上記のような憲法24条の文理や制定経緯等に照らすと、同条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。
そうすると、憲法24条1項が同性間の婚姻について規定していない以上、同条により社会制度として設けることが求められている婚姻は異性間のもののみであるといえ、同項から導かれる婚姻をするについての自由も、異性間についてのみ及ぶものと解される。
以上によれば、本件諸規定が憲法24条1項に違反するということはできないというべきである(なお、原告らは、憲法の趣旨に加え、婚姻や家族の在り方についての近時における社会的な認識、社会状況の変化があることを踏まえると、同項にいう「両性」とは「両当事者」との意味である旨を主張するが、そのような社会的な認識の変化等があるとしても、上記で述べた文理や制定経緯等からすると、それのみで憲法24条1項が同性間の婚姻制度を設けることを要請していると解釈することはできない。)。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
(ウ) もっとも、憲法24条1項が両性の合意のみに基づいて婚姻が成立する旨規定している趣旨は、婚姻の要件として戸主等の同意を求める明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から、婚姻が、当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意のみに委ねられることを明らかにする点にあったものと解される。
【筆者】
(この判決の解説の最後に示した図で解説している。)
そうすると、「両性」という文言がある以上、憲法24条1項が異性間の婚姻を対象にしているということは否定できないとしても、このことをもって直ちに、同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、同性愛と異性愛が単なる性的指向の違いに過ぎないことが医学的にも明らかになっている現在(認定事実(1))、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないということができる。しかも、近年の各種調査結果からは、我が国でも、同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる(認定事実(6))。
【論点番号】
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
【筆者】
「『両性』という文言がある以上、憲法24条1項が異性間の婚姻を対象にしているということは否定できないとしても、このことをもって直ちに、同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との記載がある。
憲法24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分について検討する。
■ 「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできないこと
24条は「婚姻」について、24条の統制の下に置くことを求める規定である。
そのため、「婚姻」という名の付いた制度である以上は24条による統制が及ぶことになるのであり、「婚姻」という名の付いた制度を24条の規定の効力が及ばない形で立法することはできない。
もし24条の「婚姻」を離れて別の制度として「婚姻」を定めようとした場合には、24条に抵触して違憲となる。
このことから、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分の意味が、あたかも「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することができるかのように考えるものであれば、誤りである。
■ いくつかの立場との関係性
24条1項の解釈について、いくつかの立場から検討する。
▼ 義務文・否定文であるかの論点
「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分が、24条1項は「~~してはならない。」のような義務文・否定文による「禁止」の規定ではないという意味の場合を考える。
この文は一段落前で「憲法24条1項が両性の合意のみに基づいて婚姻が成立する旨規定している趣旨は、」と記載されている。
そして、この段落でも「『両性』という文言がある以上、」と記載されている。
この文脈から、24条1項の「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分を意識した上で、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という結論を導き出そうとするものとなっている。
確かに、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分は、「~~してはならない。」というような義務文・否定文で記載されているわけではない。
しかし、24条1項全体で見れば、最後に「されなければならない。」と記載されており、24条1項は義務文・否定文によって「禁止」する意味を有していると読むことが可能である。
また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このことから、24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって「禁止」する意味を有していると考えることが可能である。
そのため、義務文・否定文による「禁止」であるかという論点から見ても、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と断定することはできない。
その他、ここでは24条1項の「両性」の文言のみを見て「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と判断しているようであるが、24条1項には「夫婦」の文言も存在している。
そのため、「夫婦」の文言による制約を検討しないままに、24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と断定してしまうことも、解釈として網羅的な検討を行った上で結論を導き出したものとは言えず、妥当でない。
◇ 「婚姻」の由来説
この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、その目的とそれを達成するための手段と整合的な形で考えるものである。
また、「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮されることになる。
「同性間」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、そもそも「同性同士の組み合わせ」は「生殖と子の養育」の趣旨を含まないため「婚姻」とすることはできないのであり、その「婚姻」とすることができないものに対して「禁止」することはできないという意味で、その通りであるといえる。
これについて、後ほど「24条の『婚姻』が『生殖と子の養育』の趣旨を含むこと」の項目でも解説する。
◇ 存在しない説
この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であり、「同性間」については自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間の婚姻」という概念は存在しないとするものである。
この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、存在しないものを「禁止」することはできないことから、その通りであるといえる。
存在するものを防ぐ意図をもって規定を定めることを「禁止」というのであり、存在しないものは「禁止」することができないからである。
◇ 成立条件説
この立場は、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示しており、「両性」の部分が男性と女性が合意することを必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないとするものである。
この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、もともと成立しないものに対してそれを防ぐことを意図して「禁止」することはできないことから、その通りであるといえる。
◇ 想定していない説
この立場は、24条は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを想定していないとするものである。
上記三説と下記の二説の両方の可能性がある。
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができず、24条は一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできないとするものである。
この立場から見れば、次の二つがある。
① 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分について、24条1項が「~~してはならない」というような義務文・否定文による禁止を示したものではないという意味では、そのように読むことが可能な場合もあり、その通りということもできる。しかし、24条は一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、「同性間」の人的結合関係は「婚姻」とすることはできない。
② 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という解釈は誤っており、24条1項は一夫一婦制(男女二人一組)に限定し、立法裁量の限界を画することによって「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。
◇ 禁止説
この立場は、24条の規定が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることの論点を認知した上でそれを防ぐ意図をもって禁止しているとするものである。
この立場から見れば、次の二つがある。
① 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との解釈は誤りであり、24条1項は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。
② 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という解釈は誤っており、24条1項は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文の規定であり、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。
■ 「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
これは、下記のような経緯によるものである。
その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目し、国家の政策の手段として一般的・抽象的に規格化する形(パッケージ)で設けられるようになった枠組みである。
そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。
そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としており、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
そして、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
そのため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間」の人的結合関係(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとは言えず、「婚姻」の中に含めることはできない。
▼ 24条の「婚姻」による限界
24条に定められたものが「婚姻」である以上は、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された制度を引き継いでいることは明らかである。
そのことから、24条の「婚姻」の文言の中にも、「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
これにより、24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条に抵触して違憲となる。
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないから、24条の「婚姻」の中には含まれない。
そのため、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。
すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。
例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。
これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。
そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。
このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。
すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。
これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。
これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。
このような考えは解釈として妥当でない。
そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。
そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。
そのことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。
よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 「生殖と子の養育」の趣旨の内容
「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を含んだままでも、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるのではないかとの主張が考えられる。
これを検討する。
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するため「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。
そのため、下記の立法目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
このような立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできず、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。
そのため、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、「婚姻」に含まれる「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念が成り立つための境界線を保つことができるからである。
このことから、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。
そして、憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。
24条が「婚姻」を定めている以上は、「婚姻」の立法目的を達成することを損なうことはできないという内在的な限界が含まれている。
また、24条の規定は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が定められており、「一夫一婦制」(男女二人一組)を前提としている。
ここで24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていることや、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言によって「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めていることの理由は、下記の要素を満たすからであると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これにより、これらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。
もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う立法を試みた場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
もし「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条に抵触して違憲となる。
よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないし、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。
そのため、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、同性愛と異性愛が単なる性的指向の違いに過ぎないことが医学的にも明らかになっている現在(認定事実(1))、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないということができる。」との記載がある。
「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」との部分について検討する。
この「婚姻の本質」と称する説明は何を根拠として導かれたものであるのかを検討する必要がある。
なぜならば、もし何らの根拠もなく、この判決を書いた裁判官が独断で決めているとすれば、別の裁判官が判決を下す時に「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、妥当でないからである。
・ 「永続的な」との部分は、現在の婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれたものと考えられる。
・ 「精神的及び肉体的結合」との部分は、現在の婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることことから導かれたものと考えられる。
・ 「公的承認を得て」の部分であるが、戸籍上は婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱われ、婚姻制度を利用しない者は「婚姻していない者(独身者)」として扱われているだけであるから、「婚姻している者(既婚者)」だけに特別に与えられるような「公的承認」というものがあるのか疑問である。
これについて、詳しく検討する。
まず、日本国憲法の下では「結社の自由(21条1項)」が定められているため、個々人が人的結合関係を形成することは「公共の福祉(憲法12条、13条)」や「公序良俗(民法90条)」、個別の法律に違反しない限りは自由である。そのため、人的結合関係を形成することはそれらに反しない限りは何らの制限を受けていないのであり、人的結合関係を形成することが「公的承認」を得ていないかのような理解は誤りである。
次に、この「公的承認」というものが戸籍法と関係するものと考えているのかもしれないが、戸籍上は、婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱われ、婚姻制度を利用していない者は「婚姻していない者(独身者)」として扱われているだけであるから、そこに法律論上の優劣はない。そのため、「婚姻していない者(独身者)」についても、戸籍上では「公的承認」を得ているということもできるのであり、「婚姻している者(既婚者)」だけが「公的承認」を得ているかのような理解を有しているのであれば誤りである。
三つ目に、婚姻制度の中に「公的承認」を与えるという具体的な規定が存在するのか疑問である。「公的承認」を与える旨の具体的な規定が存在するのであれば、それを示す必要がある。また、もし具体的な規定が存在するとしても、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段としてどのような法的効果を設定するかを検討した結果として定められているものであるから、その制度の利用者に対して与えられるものであり、その制度を利用していない者には与えられないという差異が生じることは制度が政策的なものである以上は当然のことである。そのため、その制度の立法目的とそれを達成するための手段の当否を検討することなく、その制度の対象者となっていない人に対して「公的承認」と称する利益を与えなければならないということにはならない。
四つ目に、あたかも「婚姻」していることが素晴らしいものであると考える価値観を有している者が社会の中に一定数存在しており、その者たちから称えられるというような意味で「公的承認」と論じているのかもしれないが、それは法律論上の利益ではない。これは、「婚姻」していることに優越した価値があると考えている宗教団体があるとして、その団体の信者に称えられている状態に過ぎないのであり、法制度とは何らの関係もないことである。
よって、「公的承認を得て」という部分については、この判決独自の解釈と思われるが、妥当でないと考えられる。
・ 「共同生活を営むこと」の部分は、現在の婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれているものと考えられる。
このように、この「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の通常想定される利用方法(利用者像)について示されているものである。
このため、具体的な婚姻制度の枠組みの方が上位法であり、その婚姻制度の枠組みから導かれる解釈(下位法)として「婚姻の本質」と称する説明が出てきているのである。
目的:国の立法目的
↓
手段:婚姻制度の枠組み
↓
利用:「婚姻の本質」と称する説明
この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して導かれたものであるから、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を説明したものとは異なる。
よって、この下位法にあたる「婚姻の本質」と称する説明を根拠として、上位法にあたる具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできない。
この点に注意が必要である。
「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」の文であるが、これは、下記の最高裁判決を参考にしているように思われる。
しかし、最高裁判決をそのまま抜き出したものではないことに注意が必要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判決においては、「両性」と書かれているが、この大阪地裁判決では抜けている。また、最高裁判決には「真摯な意思をもつて」の文言があるが、大阪地裁判決では「公的承認を得て」に変わっている。
このように、「婚姻の本質」の理解が、裁判所ごとに違うことになれば、一体何が「婚姻の本質」なのかについて統一的理解を不能にしてしまう。
「婚姻の本質」が根拠なく持ち出されて、あたかも絶対的な定義であるかのような前提で論じるような独自の説が飛び交うことにならないように注意が必要である。
この大阪地裁判決が上記の最高裁判決を参考にしているのであれば、そこには明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものである。
「婚姻の本質」の論点については、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。
「近年の各種調査結果からは、我が国でも、同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる」との記載がある。
「同性愛」という思想や信条、感情に対する理解が進んだとしても、そのことと「同性カップル」と称する同性間の人的結合関係に対して制度を創設することができるかという問題の間には直接的な関係性がない。
また、「同性愛」という思想や信条を保護することを目的として法制度を創設することは、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、他の思想や信条との間で憲法14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
そのため、「同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解」との部分について、「同性愛」という思想や信条を保護することを目的として法制度を構築することができるかのような前提で論じているのであれば、誤りとなる。
ただ、憲法19条では「思想良心の自由」が定められており、「同性愛」やここでいう「同性カップル」にあたる者たちの内心の自由については、保障されており、その意味で「法的保護」が存在するということができる。
これについては、現在でも既に「法的保護」がなされているということである。
この文の前後を確認すると、この段落の第一文で憲法24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と示しており、次の段落で「以上によれば、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解するべきではない。」と示していることからすれば、この文は、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないことの根拠として取り上げようとしているものと考えられる。
しかし、このように「近年の各種調査結果」によって「同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる」ことが24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないとする根拠になるのであれば、その後の「各種調査結果」において「同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで」「減少」していることがうかがわれることになった場合には、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していることになることを意味することになり、その時々の国民の意識によって憲法上の規定に抵触するか否かが変わることを前提としていることになる。
裁判所がこのような理解に基づいて法令の意味を確定しようとしていることは、「法の支配」、「法治主義」とはいえない状態であり、国民のその時々の意識という「空気」による支配をするものとなっている。
そのため、このような「近年の各種調査結果」を基にして、24条1項の規範の意味を確定しようとする論じ方は、法解釈として誤っている。
よって、この文は、「しかも、」という言葉を繋いで、24条1項の解釈の根拠を示そうとするのであるが、この文の内容によって24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないと結論付けるだけの説得的な根拠を示したことにはならない。
むしろ、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないと結論付けるための説得的な根拠を示すことができないことから、国民の意識が支持しているかのような「各種調査結果」を盾にして取り繕うとしているのではないかとさえ感じさせるものがある。
以上によれば、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解するべきではない。そこで、本件諸規定については、憲法24条1項に違反しないとしても、同項の上記解釈を前提として、同条2項適合性を検討することが相当である(後記(3))。
【論点番号】
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
【筆者】
━━24条1項の論点━━
(上記で既に解説済み)
24条1項の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるか否かについては、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。
イ 憲法13条に違反するかについて
原告らは、同性間の婚姻をするについての自由が憲法24条1項で規定されていないとしても、このような自由は自己決定権の重要な一内容として、憲法上の権利としても保障されるべきものであるとして、本件諸規定は憲法13条に違反する旨主張する。
しかし、婚姻及び家族に関する事項は、憲法24条2項に基づき法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律に基づく制度によって初めて個人に与えられるか、又はそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益であるということはできない。
したがって、憲法24条が異性間の婚姻のみを定めており、これを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。また、包括的な人権規定である同条によって、同性間の婚姻制度を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。
【筆者】
「同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。」との記載があるが、誤解しやすいため注意が必要である。
「婚姻をするについての自由」とは、憲法24条2項が要請する具体的な法律によって定められた婚姻制度について、憲法24条1項の解釈として「婚姻をするについての自由」が導き出されているものである。(再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決(平成27年12月16日))
この判決の「2(2)ア(ア)」の部分でも、「上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。」と述べており、憲法24条1項に対応するものとして扱っている。
ここで「婚姻をするについての自由」という文言を使うのであれば、それは憲法24条1項に対応するものとして論じられるべきものであって、憲法24条1項を離れて、憲法13条の議論でも「婚姻をするについての自由」という同一の文言を使うことは、混乱しやすくなる。
たとえ「憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。」のように、憲法13条の規定が適用されないという結論に至るとしても、憲法24条1項について示された「婚姻をするについての自由」とは異なる側面からの検討であることを明らかにすることが望ましいように思われる。
なぜならば、この論旨を反対に読み解くと、「同性間」については13条で保障されないとしても、あたかも 「異性間」については「婚姻をするについての自由」が13条の人格権として保障されるかのような誤解を引き起こすからである。
「婚姻をするについての自由」は、24条1項によって導き出されているものである。
よって、本件諸規定が憲法13条に反するとはいえない。
ウ 憲法24条2項において考慮すべき権利利益について
以上のように、同性間で婚姻をするについての自由が憲法24条1項や憲法13条から導かれるとはいえず、本件諸規定がこれらに違反するということはできない。
しかし、そもそも婚姻とは、二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度であるところ、婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。特に、公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。そうすると、同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。このような人格的利益は、後記(3)のとおり、本件諸規定が憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると解される。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「そもそも婚姻とは、二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度である」との記載がある。
この説明は、最後に「制度である」としている通り、具体的な婚姻制度の枠組みが存在し、その制度の枠組みを解釈した結果として、このように理解することができることを述べているものである。
そのため、ここで示された「婚姻とは、」の内容が、具体的な法律上の制度よりも上位の概念として位置付けられているわけではない。
「二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、」の部分について検討する。
「二当事者」の部分であるが、これは現在の婚姻制度が「男女二人一組」の形であることの、「二人一組」の部分を抜き出して「二当事者」と表現しているものである。これは婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みが「男女二人一組」であることから「二当事者」と表現されているだけであり、この婚姻制度の枠組みを離れて、単に「二当事者」が優遇されるべきであるという性質のものではない。「二当事者」であることが根拠もなく取り上げられることになれば、「カップル信仰論」に陥るため注意が必要である。
次に、「永続的」の部分であるが、婚姻制度には有効期限がなく、制度の利用者が死亡するまで利用することができることを意味するものである。もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この「永続的」との説明も根拠を失ってなくなることになる。
「真摯な精神的・肉体的結合関係」との部分は、民法上の「同居義務」や「貞操義務」から導かれるものと考えられる。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのため、「貞操義務」のある制度を読み解くことによって「真摯な……(略)……肉体的結合関係」と表現しているのであり、もし「貞操義務」がなければ「真摯な……(略)……肉体的結合関係」という表現は導かれないことになる。
「法的承認が与えられるとともに、」の部分であるが、民法や戸籍法は、婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱い、婚姻制度を利用しない者については「婚姻していない者(独身者)」として扱っているだけであるから、ここに優劣はない。そのため、婚姻制度を利用することによって初めて「法的承認」という何かが与えられるかのように考えているのであれば、民法や戸籍法の解釈を誤っている可能性がある。
このように、具体的な制度の枠組みが存在することを前提とし、その制度の枠組みを解釈することによってこのような説明が示されているというものである。
このような説明が、具体的な制度の上位概念として存在するわけではないことに注意が必要である。
「その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度である」との部分については、婚姻制度の立法目的を達成するためにどのような優遇措置を講ずるかが検討されて生まれたものである。そのため、「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、その優遇措置に関する規定が、「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において14条の「平等原則」に抵触して違憲となる場合は考えられる。
この「二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、」の文は、下記の最高裁判決を参考にしているように思われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、最高裁判決が「両性」と「男女二人一組」を前提としているのに対し、この判決は「二当事者」となっており、「男女」の要素が抜けている。
また、「真摯な」の位置が異なっており、掛かる言葉が違うため、意味も異なっている。
その後の部分も文言が違うことから、この文はこの大阪地裁判決の独自の理解として示しているものと思われる。
「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。」との記載がある。
「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、」との部分について検討する。
まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されている。
そのような中で、「契約」や「遺言」などによって、自然人の間で「経済的利益等」を取り交わすことが可能である。
このような「婚姻していない者(独身者)」の活動を基準(スタンダード)と考える必要がある。
その中で、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から婚姻制度が法制度のパッケージとして構築され、その中に「相続や財産分与等の経済的利益等」などの仕組みが設けられたものである。
このことから、婚姻制度の立法目的を達成するための手段となる枠組みに沿わない関係については、もともと制度の対象ではないのであるから、法制度のパッケージとして構築されている「相続や財産分与等の経済的利益等」を利用することができないことは当然のことである。
婚姻制度は、このような「相続や財産分与等の経済的利益等」を含めて、婚姻制度のパッケージとして構築されているのであり、このような内容の制度を利用したいと希望する者が一定数現れるようにインセンティブを与え、婚姻制度を利用する者が増えることによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを予定しているのである。
これが国家政策として設けられている婚姻制度の意義であり、その枠組みや内容の利益等は、これら「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして役立つものとなるように設計されているものである。
そのことから、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられている「相続や財産分与等の経済的利益等」の仕組みであるにもかかわらず、それを単なる「経済的利益等」と考えて、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として対象者となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えなければならないということにはならない。
むしろ、婚姻制度の対象となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えることは、国民が婚姻制度を利用しようとするインセンティブを損なうことになり、婚姻制度を利用する者が減ることにより、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しなくなり、立法目的を達成することを阻害することに繋がる。
そのため、婚姻制度の対象となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えてはならないという場合もある。
「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、……(略)……当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。」との部分について検討する。
まず、日本国民であれば皆「戸籍法」の戸籍を有しているのであり、大抵の場合は親子の関係などが定められている。よって、戸籍に記載があるのであれば、それだけで既に「公的承認を受け、公証され」ているのであり、この意味での「公認に係る利益」は既に有していることになる。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されているのであり、人的結合関係を有していない状態のままで、既に完全な状態として取り扱われている。
その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成して「共同生活を営むこと」も自由である。これは、「結社の自由(21条1項)」によって保障されている。
そのため、何らかの人的結合関係を形成しなければ「公に認知され」ないとか、人的結合関係が保障されないというものではない。
憲法の「個人の尊厳」の原理は「個人主義」によって「自律的な個人」として生存している状態のままで、既に「公に認知され」るように求めるものであり、そのような生活をする者が「公に認知され」ていないだとか、「共同生活を営むこと」が制限されるというものではないのである。
そのような前提の中、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、国家の政策として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する形で設けられたものである。
これは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが定められているものであり、この枠組みに当てはまる場合には制度を利用することができ、これに当てはまらない場合には制度を利用できないというだけである。
そして、婚姻制度を利用する者については、単に「婚姻制度を利用する者」として社会の中で認知されているだけである。
これを「公認に係る利益」と呼ぶかは別としても、何らかの法制度を利用する者は「制度を利用する者」として認識され、利用しない者は「制度を利用しない者」として認識されているだけである。
法制度である以上は、対象者と、対象外の者が生まれることは当然のことであり、対象外の者に対して、制度の利用者の得る利益と同様の利益を与えなければならないということにはならない。
その制度による利益を得たいのであれば、制度の要件に従って制度を利用すればよいのである。
この点を押さえる必要がある。
ここでは、「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益」と表現されている。
しかし、「カップル」という「二人一組」であることを根拠もなく持ち出しているが、この「カップル」という単位を殊更に強調して論じることは、「カップル信仰論」に陥るため注意が必要である。
婚姻制度が「二人一組」という枠組みを定めていることは、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として枠組みが定められていることによるものであり、その立法目的とその達成手段の当否の問題を離れて、「二人一組」の人的結合関係(ここでいう『カップル』)であることを取り上げても意味がないのである。
このような形で「カップル」を強調する論じ方は、次第になぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥ることになり、後に出てくる「カップル間不平等論」の誤りに通じることになる。
「公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。」との記載がある。
「公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みとして定められているものであり、この制度の対象者となる者が制度を利用した場合には制度による利益を得ることができ、制度を利用しない者や制度の対象とならない者は制度による利益を得られないというのは当然のことである。
この婚姻制度の立法目的の中に「公認に係る利益」と称するものを与えようとする意図があるのか不明であるが、「婚姻制度を利用する者」は制度利用者として社会的に認知されているだけであり、それが「将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がる」かどうかは、その制度に対する個々人の主観によるものか、その制度に対する社会の受け止め方によるものであり、法律上の利益とはいえない。
また、ここでは「婚姻した当事者」について、あたかも「将来にわたり安心して安定した共同生活を営むこと」が保障されるかのような論じ方をしているが、法律論として見れば単に「婚姻している者(既婚者)」として認知されているだけのことである。
反対に、「婚姻していない者(独身者)」についても、「婚姻」していないことこそが「将来にわたり安心して安定した」「生活を営むこと」に繋がると考える者もいるのであり、それは個々人の価値観の問題である。「婚姻していない者(独身者)」についても、「婚姻していない者(独身者)」として社会的に認知されているわけであり、その地位を不当に低く見られるいわれはない。
「公認に係る利益は、……(略)……自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。」との部分について検討する。
「人格的利益」は、具体的な法制度のパッケージとして構築されている婚姻制度を利用するか否かの自由に関わる場合は考えられる。
つまり、婚姻制度の要件を満たす場合には、その者は婚姻制度を利用するかしないかを選択することが「人格的利益」として保障されることは考えられる。(『人格的利益』としては保障されず、『人格的自律・自己決定権』かもしれない。)
しかし、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みを超えて、その制度の対象とならない関係に対して、婚姻制度から得られる利益を同様に与えなければならないということにはならない。
この点を押さえておく必要がある。
また、ここでは「婚姻している者(既婚者)」は「自己肯定感や幸福感の源泉」を得ているかのように述べるものなっているが、「婚姻していない者(独身者)」も「婚姻していない者(独身者)」として「自己肯定感や幸福感の源泉」を得ているのであり、このような個々人の主観や価値観に属する感覚の問題について、「婚姻している者(既婚者)」をやたらに持ち上げるような言い方をするべきではない。
法律論としては、婚姻があたかも素晴らしいものであるかのような論じる「婚姻信仰論」に陥らないように注意する必要がある。
「我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、」との部分について検討する。
この「我が国において法律婚を尊重する意識が浸透している」という意味は、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として定められた枠組みが合理的であり、社会的な不都合を解消するための制度として役立っていることの妥当性が尊重されていることをいうものである。
そのため、もし婚姻制度の内容を変更することにより、立法目的を達成することが困難となるような制度に変わってしまった場合や、他の制度を創設することによって婚姻制度の政策効果が損なわれてしまった場合には、そもそも婚姻制度を「尊重する意識」が国民の間で広がらなくなることも考えられる。
このように、どのような内容の婚姻制度であっても、「婚姻」と称すれば国民は必ず「法律婚を尊重する意識」を持つというわけではないことから、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題を論じずに、これを越えて、婚姻制度の対象外の者に対してこの判決のいう「公認に係る利益」にあたるものを与えなければならないということにはならないことを押さえる必要がある。
「このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。」との記載がある。
この判決のいう「人格的利益の有する価値」が存在するかは別として、法制度を利用することができるか否かについて、個々人の内心に基づいて区別取扱いをしてはならないという意味では、その通りである。
「異性愛者」を称するものであっても、「同性愛者」を称する者であっても、「両性愛者」を称する者であっても、「多性愛者」を称する者であっても、「無性愛者」を称する者であっても、そのような分類を用いない者であっても、「キリスト教徒」を称する者であっても、「イスラム教徒」を称する者であっても、「仏教徒」を称する者であっても、「神道を信じる者」を称する者であっても、「武士道を重んじる者」を称する者であっても、どのような内心を有する者であっても、「異なるものではない。」ということができる。
憲法には19条で「思想良心の自由」、20条1項で「信教の自由」が定められており、個人の「内心の自由」が保障されている。また、法制度においても個人の内心に属する事柄を取り上げて、区別取扱いを行ってはならないのであり、もし個々人の内心によって区別取扱いをするようなことがあれば、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、合理的な理由のない区別取扱いにあたるから14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
そのため、この「異なるものではない。」という部分については、個々人の内心に基づいて区別取扱いをしてはならないという意味では、その通りである。
しかし、この判決文では、そもそも自然人を「異性愛」や「同性愛」という思想や感情に基づいて「異性愛者」と「同性愛者」という風に勝手に分類して論じようとしている点で妥当でない。
性別は「男性」と「女性」に限られるが、「性愛(性的指向)」は「内心の自由」に属する精神的なものであるから、「異性愛者」と「同性愛者」に二分できるわけではないし、「性愛(性的指向)」とその他の思想や感情、信条との間で明確に区別できるという性質のものでもない。
そのため、「異性愛者」と「同性愛者」の二分論を持ち出して論じようとしていることも、そもそも事柄の性質を捉え間違っている。
また、婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的としているわけではないのであるから、「異性愛」の思想や感情を抱く「異性愛者」を対象として制度が設けられているわけでもない。
婚姻制度はもともと自然人を「異性愛者」と「同性愛者」に区別して対象者を選び出す目的をもって創設されているわけではなく、区別取扱いをしていないのである。
もし「異性愛」の思想や感情を抱く「異性愛者」を保護することを目的として制度を定めた場合には、個人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
また、特定の思想や信条を保護するための法律を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
このことは、たとえ「同性愛」の思想や感情を抱く「同性愛者」を保護することを目的とした制度を定めるとしても同様であり、それらの規定に抵触して違憲となることは変わらない。
「同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。」との記載がある。
しかし、ここでいう「公認に係る利益」とは、三つ前の文で「婚姻をした当事者が享受し得る利益」とされているのであるから、「婚姻」していない者については享受し得ないことが前提となっている。
そのため、「同性間」の「当該人的結合関係」については「婚姻」していないのであるから、もともと「公認に係る利益」と称するものを得ることはできない。
このことから、「同性間」の「当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。」と述べている部分は、「婚姻」していない者であるにもかかわらず、その者に対して「婚姻をした当事者が享受し得る利益」について尊重されるべきものと述べていることになり、論理的に意味が通じていない。
これは、「同性間」の「人的結合関係」だけでなく、「三人以上の人的結合関係」についても同様である。
婚姻制度を利用していない者やその人的結合関係は、婚姻制度から得られる「利益」は有していないのであり、これを有することを前提として「尊重されるべきもの」と述べることは、誤っている。
「このような人格的利益は、後記(3)のとおり、本件諸規定が憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると解される。」との記載がある。
婚姻制度を利用する者については、「人格的利益」に関わる問題が生じたときに「憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討」が行われることは考えられる。
しかし、婚姻制度を利用していない者は、そもそも婚姻制度を利用していないのであるから、婚姻制度を利用することによって生じる「人格的利益」を主張する余地はない。
これは、24条2項の解釈を検討するに当たって考慮するべきことである。
一文前の「同性間」の「人的結合関係」については、婚姻していないのであるから、「婚姻をした当事者が享受し得る利益」としている「公認に係る利益」と称するものはもともと得ることはできないし、婚姻制度を利用する者についての「人格的利益」ももともと得ていないのであるから、「憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を審査することができる対象ではない。
これを押さえて24条2項の解釈を考える必要がある。
(3) 本件諸規定が憲法24条2項に違反するかについて
ア 憲法24条は、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は、関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから、当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ、憲法24条2項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。
そして、憲法24条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。そうすると、憲法24条の要請、指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集第69巻8号2586頁参照)
【筆者】
この「夫婦別姓訴訟」の判例の引用であるが、所々、省略している部分があり、正確に引用しているものではない。
また、省略している部分についても「(略)」などの文言を用いて読み手に分かるように記載しているわけではない。
このような引用の仕方をすると、次第に本来の判決の趣旨から乖離し、文言だけが独り歩きし、もともとの意味が改竄されてしまう場合がある。
そのため、裁判官が特定の結論に導こうとするために恣意的な操作を行っていないか注意して読み解く必要がある。
下記で、この大阪地裁判決が省略している部分を確認する。
(この夫婦別姓訴訟の判決文から、この同性婚訴訟の大阪地裁判決に示された文と同一の部分は灰色で潰した。黒字で残っている部分が、この大阪地裁判決が省略している部分である。
(この夫婦別姓訴訟の判決文の『(2) そうすると,』の部分は、大阪地裁判決では改行が無くなっている。この点も異なる。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。
婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。
そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。
3(1) 他方で,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められるべきものである。
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PDF (夫婦別姓訴訟・上記のリンクのPDF版)
イ 以上の観点から、本件諸規定の憲法24条2項適合性について、本件諸規定により異性間の婚姻のみを対象とする現行の婚姻制度の趣旨及び影響を踏まえて検討する。
(ア) そもそも、人類には、古来から、男女が共同で生活を営み、自然生殖により子が生まれることにより子孫を残し、次世代へと承継してきた実態が歴史的・伝統的に存在していたところ、近代社会において、このような一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に生まれた未成熟子から構成される家族が、社会を構成する自然かつ基礎的な集団単位として認識されるとともに、その家族の中心的存在である男女の人的結合関係が特に婚姻関係として社会的に承認され保護されるようになったものである(認定事実(2)ア)。
【筆者】
「古来から、男女が共同で生活を営み、自然生殖により子が生まれることにより子孫を残し、次世代へと承継してきた実態が歴史的・伝統的に存在していた」との記載がある。
これは男女の自然生殖によって子供が産まれるという因果関係を示すものである。
「近代社会において、このような一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に生まれた未成熟子から構成される家族が、社会を構成する自然かつ基礎的な集団単位として認識される」との記載がある。
これは、「一人の男性一人の女性」の間に「人的結合関係」があり、「その間に生まれた未成熟子」を想定していることから、遺伝的な父親を特定することができる人的結合関係を重視していることを読み取ることができる。
「その家族の中心的存在である男女の人的結合関係が特に婚姻関係として社会的に承認され保護されるようになった」との記載がある。
この「婚姻関係」が「社会的に承認」されるようになった背景には、下記の理由があると考えられる。
・一人の男性と一人の女性との人的結合関係は遺伝的な父親を特定することができること
・特定された遺伝的な父親に対して子に対する養育の責任を担わせることができること
・遺伝的な父親を特定することで近親者を把握することができ「近親交配」に至ることを防ぐことができること
・一人の男性と一人の女性の組み合わせを単位とすれば「子を持ちたい」と希望する男女の数の均衡を崩さずに「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を抑制することができること
・一定の年齢に達することを求めることで低年齢での妊娠と出産を抑制することができ母体を保護できること
・「子の養育」や「子の福祉」の実現に支障がないこと
このように、「婚姻関係」が「社会的に承認」されている原因は、立法目的とそれを達成するための手段が、社会的に発生し得る不都合を解消することのできる枠組みとして妥当性が高いことによるものである。
そのため、どのような人的結合関係でも「婚姻」と呼ぶだけで「社会的に承認」されるという性質のものではない。
「社会的に承認」を得られる制度となるかどうかは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題ということである。
もし現在の婚姻制度の枠組みを変更した場合には、立法目的とそれを達成するための手段としての妥当性が損なわれ、今まで「社会的に承認」されていた事実が覆され、婚姻制度そのものが「社会的に承認」されなくなることもあり得るのである。
「婚姻関係」が「社会的に承認」されている事実があるとしても、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題を離れて「社会的に承認」されることについて論じることはできないことに注意が必要である。
このことから、婚姻制度の立法目的を達成するための手段としての枠組みの対象とはならない人的結合関係については、立法目的を達成するための手段として妥当でないのであるから、その人的結合関係が「社会的に承認」されるように配慮しなければならないということにはならないし、「保護」する必要もない。
「社会的に承認」されるかどうかや「保護される」かどうかを論じる際には、これを押さえる必要がある。
我が国においても、明治以前から男女が共同体を築き家族を形成してきた関係が存在し、その関係が慣習上も結婚ないし婚姻として社会で認められていたところ、明治民法における法制度の近代化に伴い、上記のような慣習が法律婚として制度化された。このように、明治民法では、婚姻は男女間のものであったのであり、現行民法においても、憲法の要請する個人の尊厳の観点から必要な改正はされたものの、婚姻が男女間のものであることについては特に議論されることなく承継され、現在の婚姻制度が整えられた(認定事実(2)イ)。
【筆者】
この判決では、婚姻制度があたかも「性愛(性的指向)」を保護することを目的とする制度であるかのような前提で論じている部分があるが、上に述べられているような立法経緯においても、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することが目的であるとか、「婚姻」する目的は「性愛(性的指向)」を満たすことであるとか、そのような議論もなされていないはずである。
それにもかかわらず、そのような前提を持ち出して論じている点で、この判決の内容は法律論から逸脱している部分がある。
こうして成立した現在の婚姻制度は、民法において、婚姻当事者である夫婦の権利義務について定める規定だけでなく、嫡出推定制度等親子関係を定める規定(同法772条以下)や親権に関する規定(同法818条以下)等、婚姻した夫婦とその間の子について特に定めた規定があり、戸籍法では、夫婦の婚姻の届出(同法74条)のほか、子の出生時の届出(同法49条1項)や、子の親の戸籍への入籍(同法18条)などについての規定もある。
【筆者】
この判決では「婚姻の本質」と称するものが出てくるが、それはここに挙げられたような具体的な規定を解釈することによって導かれる説明である。
そのため、このような具体的な制度の枠組みを離れて、「『婚姻の本質』はこういうものだ」という根拠なき信念や信仰心に基づいて、婚姻制度の枠組み変更の当否を論じることはできない。
そのような論じ方をすることは、制度の「本質」と称する定義や説明を根拠なく取り上げ、それを絶対的な基準であるかのように考えて制度の枠組み変更の当否を論じようとする「本質信仰論」に陥ることになるため注意が必要である。
そうすると、本件諸規定が異性間の婚姻のみを対象としているのは、婚姻を、単なる婚姻した二当事者の関係としてではなく、男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、このような男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるものと考えられる(認定事実(2)イ、弁論の全趣旨)。このような婚姻の趣旨は、我が国において、歴史的、伝統的に社会に定着し、社会的承認を得ているということができる。
【論点番号】
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
「本件諸規定が異性間の婚姻のみを対象としているのは、婚姻を、単なる婚姻した二当事者の関係としてではなく、男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、」との記載がある。
この文は、「婚姻」の内容が「男女二人一組」であることを示している。
この「婚姻」について「男女二人一組」の枠組みとしていることの背景には、一つ上の段落に示された民法上や戸籍法の条文から「生殖と子の養育」の観点が含まれていることは当然、それだけでなく、民法が「重婚(民法732条)」や「近親婚(民法734条)」を認めていないこと、「婚姻適齢(民法731条)」が設けられていることも挙げることができる。
これら民法上の「婚姻」の規定からは、婚姻制度の立法目的として下記の要素があることを裏付けることができる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するための手段として「婚姻」は「男女二人一組」を枠組みとしていると考えられる。
「男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるものと考えられる」との記載がある。
「社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ」との部分であるが、これは主に戸籍法に「婚姻している者(既婚者)」として記載されることをいうものと思われる。
ただ、「婚姻している者(既婚者)」は「婚姻している者(既婚者)」として記され、「婚姻していない者(独身者)」は「婚姻していない者(独身者)」として記載されているだけであり、その両者に法律論上の優劣は存在しない。
そのため、そのような「識別、公示の機能」は「婚姻している者(既婚者)」だけが得られるという性質のものではなく、「婚姻していない者(独身者)」は「婚姻していない者(独身者)」として「識別、公示」されていることになる。
「法的保護を与えようとする趣旨」との部分であるが、婚姻制度の立法目的に従って、それを達成するための手段として枠組みが定められ、その制度の利用者はその制度の利用者としての地位によって法的に何らかの保護が与えられる場合があるとしても、それは立法目的を達成するための手段として設けられている「法的保護」である。
そのため、婚姻制度の立法目的を達成することに沿わない関係に対して「法的保護」を与えなければならないということにはならないことに注意する必要がある。
ただ、「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として、不必要に過大な優遇措置や「法的保護」を与えるようなものとなっているのであれば、その過大な優遇措置や「法的保護」について、「婚姻していない者(独身者)」との比較において合理性を有しない区別となり、14条の「平等原則」に抵触して違憲となることは考えられる。
この場合は、その過大な優遇措置や「法的保護」についての規定が個別に失効することになるのであり、婚姻制度の対象ではない者や「婚姻していない者(独身者)」に対して、同様の優遇措置や「法的保護」を与えなければならないということになるわけではない。
この点も押さえておく必要がある。
「このような婚姻の趣旨は、我が国において、歴史的、伝統的に社会に定着し、社会的承認を得ているということができる。」との記載がある。
「歴史的、伝統的に社会に定着し、社会的承認を得ている」というのは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の枠組みの妥当性が立法政策として社会的に認められていることをいうものである。
なぜならば、もし婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みが妥当性を有していないのであれば、立法政策として不合理であるということになり、その社会の中ではその制度を利用しようとする者はほとんど現れず、その制度が継続されることはないだろうし、「歴史的、伝統的に社会に定着」することもなく、「社会的承認」も得られていないはずだからである。
このことから、「社会的承認」とは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の枠組みの妥当性の問題ということである。
これを前提とすれば、婚姻制度の内容を変更することになった場合には、立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの妥当性の存否も変わることになるから、当然、立法政策として社会的に認められるかどうかも変わり得るものである。
そのため、婚姻制度を変更することは、今まで得ることのできていた婚姻制度に対する「社会的承認」も得られなくなる場合もあり得るということである。
そのことから、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの合理性や妥当性の問題を越えて、婚姻制度の「公示の機能」や「社会的承認」だけを取り上げて、もともと婚姻制度の枠組みの対象でない者に対しても、同様の「公示の機能」や「社会的承認」を与えなければならないという論理には繋がらないことに注意が必要である。
以上によれば、本件諸規定が異性間の婚姻のみを婚姻として特に保護する制度を構築した趣旨には合理性があるというべきである。
【論点番号】
⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること
【筆者】
この文は、法律上の立法政策として、婚姻制度を「男女二人一組」(一夫一婦制)としていることに「合理性がある」と述べるものである。
このように法律上の婚姻制度が「男女二人一組」としていることに「合理性がある」ということは、当然、その古くからある「男女二人一組」(一夫一婦制)の「婚姻」という制度を引き継ぐ形で定められた憲法24条の「婚姻」についても、憲法上の立法政策として「婚姻」の文言それ自体や、「両性」「夫婦」「相互」の文言を定めることにより、「男女二人一組」の形(一夫一婦制)に限定し、その立法裁量の限界を画しているとしても、同様に婚姻制度の目的(趣旨)との関係で「合理性がある」と論じることが可能であるということになる。
この大阪地裁判決は、法律上の立法政策として「男女二人一組」に限っていることに合理性が認められるのであれば、当然に憲法上の立法政策として「男女二人一組」に限っているとしても合理性が認められると論じることが可能であるにもかかわらず、憲法24条が「同性間の婚姻」(『同性間の人的結合関係』を『婚姻』とすること)を「禁止していない」と断定していることは、解釈論として紛争を招くものとなっており、妥当とはいえない。
憲法上の立法政策として、24条の規定が「男女二人一組」に限定して立法裁量の限界を画しているとする説を排斥するだけの根拠は何ら示されていないのであり、法の論理に基づくものとはいえない。
そのことから、この判決が24条1項について「同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べて、同性間の人的結合関係を「婚姻」とすることが可能であるかのような論じ方をしている部分については、裁判官個人が特定の結論を導きたいがために行った恣意的な断定が含まれている可能性がある。
これに対し、原告らは、婚姻の目的は夫婦の共同生活の法的保護であり、生殖とは関係がなく、子を産み育てる関係を保護するという本件諸規定の趣旨に合理性はない旨主張する。確かに、夫婦が子をもうけるか否かは本来個人の自己決定に委ねられるべき事柄であり、民法においても、子の有無や子をもうける意思の有無等による夫婦の法的地位の区別はされていない(なお、認定事実(2)イ(ア)aのとおり、明治民法の制定経緯における議論においても、婚姻について必ずしも子を残すことのみが目的ではないとされている。)。取り分け、近年は家族の形態や夫婦の在り方が多様化しており、人々の意識においても、婚姻を、子の養育のためではなく個人の自己実現あるいは幸福追求に資するためのものとして位置付けようとする傾向が高まっている。しかし、そのような価値観の変化があるとしても、現在でもなお、男女が安定した関係の下で共同生活をしながらその間に生まれた子を養育することを保護する婚姻の目的の意義は何ら失われているわけではないし、このような目的と、個人の自己実現等の手段としての婚姻とは矛盾するものではなく、互いに両立し得るものである。そうすると、このような趣旨や目的自体が、歴史的、社会的意味を失っているとはいえない。
【筆者】
この段落は、婚姻制度についての「国の立法目的」と「個々人の利用目的」を区別して読み取ることが大切である。
◇「国の立法目的」に当たる部分
・「男女が安定した関係の下で共同生活をしながらその間に生まれた子を養育することを保護する婚姻の目的の意義」
◇「個々人の利用目的」に当たる部分
・「夫婦が子をもうけるか否かは本来個人の自己決定に委ねられるべき事柄」
・「人々の意識においても、婚姻を、子の養育のためではなく個人の自己実現あるいは幸福追求に資するためのものとして位置付けようとする傾向」
・「個人の自己実現等の手段としての婚姻」
そして、これらは「矛盾するものではなく、互いに両立し得るものである。」と述べている。
それはその通りと思われる。
「原告らは、婚姻の目的は夫婦の共同生活の法的保護であり、生殖とは関係がなく、子を産み育てる関係を保護するという本件諸規定の趣旨に合理性はない旨主張する。」との記載がある。
まず、ここで使われている「婚姻」という概念は他の様々な人的結合関係の中から「生殖と子の養育」の観点から区別される意味で設けられた制度であり、「婚姻」を指している時点で、そこには既に「生殖と子の養育」に関わる法制度を指していることは明らかである。
そのため、その婚姻制度を利用する者が「個々人の利用目的」として「生殖とは関係がなく」のように、「生殖」を目的としない形で制度を利用する場合もあるとは思うが、だからといって、婚姻制度を定めている「国の立法目的」の中から「生殖と子の養育」の趣旨が失われるというものではない。
また、ここで使われている「夫婦」についても、これは既に一人の男性と一人の女性が「男女二人一組」の形で枠づけられていることを意味する言葉であり、この意味によって、既に「生殖と子の養育」の観点を含む枠組みを利用する者たちを指していることは明らかである。
その枠組みを利用しない者同士であれば、「デュオ」「コンビ」「ペア」「カップル」「バディ」「ダブルス」「相棒」「トリオ」「仲間」「ソウルメイト」など、別の言葉で何とでも呼べばいいからである。
そのため、「原告らは、婚姻の目的は夫婦の共同生活の法的保護であり、」と述べている時点で、「生殖と子の養育」の趣旨を含む法制度を利用する「男女二人一組」についての「共同生活」を法的に保護することを指していることになるのであり、これら「婚姻」や「夫婦」の文言を用いながら「国の立法目的」に関するものとして「生殖とは関係がなく、」と述べることは論理矛盾となる。
「近年は家族の形態や夫婦の在り方が多様化しており、」との記載がある。
しかし、法律上の「家族」や「夫婦」については、法律の規定に従った範囲のものであるから、「在り方が多様化」しているという事実はない。
ここでいう「家族の形態や夫婦の在り方」というのは、個々人が生活する上で「家族」と考えている何らかの生活共同体の範囲をいうものと考えられるが、それは法律上の「家族」とは異なる。
裁判所は法律論として法律上の「家族」のことを論じなければならないにもかかわらず、法律論ではない個々人が生活する上で「家族」と考えている範囲の話を持ち出しており、整合性がとれていない。
(イ) 他方で、本件諸規定が異性間の婚姻制度のみを規定し、同性間の婚姻を規定していないため、異性愛者は自由に異性と婚姻をすることができるのに対し、同性愛者は望みどおりに同性と婚姻をすることはできないという重大な影響が生じている。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑦ 「異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること
【筆者】
まず、法律上は個々の自然人がどのような思想や信条、感情を有しているのかを審査しておらず、区別取扱いをしている事実はない。
また、この判決は「内心の自由」に属する「異性愛」と「同性愛」という思想や信条、感情の傾向を取り上げて、自然人を「異性愛者」と「同性愛者」に二分して論じようとしているが、そもそもこれらの「性愛(性的指向)」は精神的なものであるから、明確に二分できるという性質のものではないし、「性愛(性的指向)」とその他の思想や信条、感情との間でも、明確に区別できるという性質のものでもない。
よって、この判決が個々の自然人を「異性愛者」と「同性愛者」に区別して論じようとすることそのものが妥当でない。
このような個人の内心に基づいて区別取扱いをすることは、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
次に、婚姻制度の利用について「異性愛者」と「同性愛者」の違いを強調する論旨であるが、そもそも「性愛(性的指向)」に基づいて「婚姻」することに価値があると考えるか否かは個々人の価値観の問題である。
「性愛(性的指向)」を重視する者もいれば、重視しない者もいるのである。
この論旨は、婚姻制度を利用する際には「性愛(性的指向)」に従うべきであるという特定の価値観を前提とした主張となっている。
しかし、法律論としてこのような特定の思想や信条、信仰を保護するべきであるとの主張は、憲法20条1項・3項・89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
例えば、「キリスト教徒」は「男女二人一組」の形で自由に婚姻することができるのに対し、「イスラム教徒」は望み通りに「一夫多妻」として婚姻することができないという重大な影響が生じている、と論じたときに、これは特定の思想や信条に従って婚姻することが正しい価値観であることを前提とする主張となっているのであり、法律論からは逸脱するものとなる。
婚姻制度は特定の思想や信条を保護するために立法されたものではないことから、「キリスト教」も「イスラム教」も関係ないのであり、「キリスト教徒」のために婚姻制度が設けられているかのような前提で論じることは、そもそも不当な主張となる。
現在の婚姻制度の下では、「イスラム教徒」であっても「男女二人一組」の形で婚姻制度を利用することはできるし、「キリスト教徒」であっても「一夫多妻」はできないのである。
特定の思想や信条、感情を抱く者が、自らの信仰心に重ね合わせる形で法制度を見てしまう場合があるが、そもそも法制度をそのような思想や信条によって色付けして見ようとすることそのものが法律論としては不当である。
よって、婚姻制度は自然人が「異性愛」の思想や信条、感情を抱くか、「同性愛」の思想や信条、感情を抱くか、それ以外の思想や信条、感情を抱くかなど、一切関知していないし、立法目的としてもそれらの思想や信条、感情を保護することを目的とはしていないため、「異性愛者」や「同性愛者」などという思想や信条、感情に基づく分類を持ち出して比較しようとすることそのものが妥当でない。
また、「重大な影響が生じている。」と述べているが、このような論旨では、同様に、「イスラム教徒」は望み通りに「一夫多妻」をすることができないという「重大な影響が生じている。」などと説明できてしまうようなものである。
特定の思想や信条、感情を取り上げて、それに従う形の「婚姻」が正しい価値観であることを前提とするような理解に基づいて「影響」の有無を論じるべきではない。
しかし、本件諸規定の下でも、同性愛者が望む同性のパートナーと婚姻類似の結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりする自由が制約されているわけではない。さらに、婚姻によって生ずる法律上の効果についても、例えば、同居、協力及び扶助の義務(民法752条)については契約により同様の効果を生じさせることができ、当事者の一方の死後にその財産を当事者の他方に帰属させることは、契約や遺言(同法964 条)によっても可能であるほか、包括受遺者となった場合は相続人と同一の権利義務を有する(同法990条)ことになるなど、他の民法上の制度等を用いることによって、一定の範囲では同等の効果を受けることが可能である。
【論点番号】
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
【筆者】
この段落は、「婚姻している者(既婚者)」と比べて、「婚姻していない者(独身者)」も「婚姻類似の結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりする自由」が制約されていないことや、「婚姻によって生ずる法律上の効果」も契約等で同様の効果を受けることが可能であると論じている。
しかし、この論じ方は、あたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)となるべきものであるかのような前提が含まれており、適切ではない。
このような「婚姻している者(既婚者)」を基準(スタンダード)と考えるようなバイアスは排除していく必要がある。
下記で詳述する。
まず、自然人は様々な人的結合関係を結びながら生活することが可能である。
「共同生活を営んだりする自由」については、憲法12条、13条で示された「公共の福祉」や、民法90条の「公序良俗」、その他の法律に違反しない限りは自由である。これらの人的結合関係については、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されることになる。
また、それら個々人は他者との間で意思表示が合致することによって「契約」を結ぶことが可能である。
もちろん、契約や遺言によって「同居、協力及び扶助の義務」にあたる効果を生じさせることができるし、「当事者の一方の死後にその財産を当事者の他方に帰属させること」も可能である。
それら個々人が「二人一組」(ここでいう『カップル』にあたるもの)を特別な関係であると考えて生活することもできるし、「三人一組」(トリオ)を特別な関係であると考えて生活することもできるし、「四人一組」こそが特別な関係であると考えて生活することもできる。
その者たちが、「共同生活を営んだりする自由」は、「公共の福祉」や「公序良俗」、個別の法律の規定に違反しないのであれば、自由である。
このような、個々の自然人が個人として共同生活を営んだり、個人として契約や遺言など民法上の制度等を用いることによって何らかの法的効果を受けながら生活している状態が基準(スタンダード)となるべき状態である。
このことは、その者たちが「異性愛者」「同性愛者」「両性愛者」「多性愛者」「全性愛者」「無性愛者」などを称する者であっても、そのような分類を用いない者であっても、「キリスト教徒」「イスラム教徒」「仏教徒」「神道を信じる者」「武士道を重んじる者」を称する者であっても、「無宗教の者」であっても、「軍事オタク」「アニメオタク」「アイドルオタク」であっても、「アスペルガー」「自閉症」「サイコパス」であってもまったく変わるものではない。
法制度は、「内心の自由」に属する問題については関知していないからである。
そのような前提の下で、その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。
例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。
これらの問題を抑制することを目的として、国の立法政策として「生殖と子の養育」の観点から一般的・抽象的に規格化する形で「婚姻」という制度がパッケージ化されて設けられるようになったものである。
つまり、「婚姻」は「結社の自由」によって保障されている他の様々な人的結合関係とは区別する意味で定められた制度である。
これらの前提から、憲法には「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態として取り扱われている。
そのため、法制度においては、「婚姻していない者(独身者)」がすべての基準(スタンダード)となるべき状態である。
これに対して、この判決の論じ方は、「婚姻していない者(独身者)」の位置づけを、あたかも「成年者」と「未成年者」の関係における「未成年者」(制限行為能力者)の方であるかのように扱い、何かが制限されていることを前提としながら、別の制度で補うことによって不利益がある程度緩和できるかのような位置づけをしている部分がある。
これは、「婚姻している者(既婚者)」が基準(スタンダード)であるかのようなバイアスが含まれているのであり、基準(スタンダード)の採り方を誤っている。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、すべての法制度は「個人主義」を基準(スタンダード)として構築されており、自然人は「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであるから、この「婚姻していない者(独身者)」の状態を完全な状態として扱い、それを基準(スタンダード)として法制度を捉える必要がある。
もっとも、このような方法は、そもそも事前に遺言や契約等をしなければその効果を享受することができないものであるし、税法上の優遇措置、在留資格、公営住宅の入居資格等、契約等によっても享受することが困難な法的地位も多く存していることからすると、同性カップルが享受し得る利益が、異性カップルが婚姻により享受し得る法律上の効果に及ばないことは確かである。
【論点番号】
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
「もっとも、このような方法は、そもそも事前に遺言や契約等をしなければその効果を享受することができないものであるし、」との記載がある。
しかし、一つ上の段落で解説したように、そもそも憲法の下では「個人主義」に根差して「自律的な個人」として生存していくことが基準(スタンダード)であり、その中で「遺言や契約等」をしながら生活する状態が通常の状態である。
その中で、国家の政策の手段として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係から区別する形で婚姻制度が定められているだけであり、「婚姻している者(既婚者)」は単に現在ある制度の枠組みに従ってその制度を利用している者に過ぎない。
婚姻制度による法的な利益を得たいのであれば、婚姻制度の枠組みに従って制度を利用すればよいのであり、その制度の内容に従いたくないのであれば、婚姻制度の枠組みの外で「自律的な個人」として「遺言や契約等」を活用しながら通常状態で生活すればよいというだけである。
そのため、この判決では「もっとも、このような方法は、そもそも事前に遺言や契約等をしなければその効果を享受することができないものであるし、」などと、「遺言や契約等」があたかも何か劣った位置付けを有するものであるかのようなバイアスが含まれた表現が見られるが、「遺言や契約等」を利用することこそが、通常状態であり、基準(スタンダード)というべきものである。
この判決のような「婚姻している者(既婚者)」(法制度上の人的結合関係を形成している者)こそが通常状態であるかのようなバイアスの下に論じることは、「婚姻していない者(独身者)」の地位を不当に貶めるものであり、憲法が「個人の尊厳」の原理を定めていることに反し、正当化することはできない。
「税法上の優遇措置、在留資格、公営住宅の入居資格等、契約等によっても享受することが困難な法的地位も多く存していることからすると、」との記載がある。
このような主張に対して、国(行政府)は、民法典における「婚姻」の問題ではなく、具体的な一つ一つの政策の当否の問題であると述べている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)
当サイトもこの訴訟で論点となっている戸籍法や民法上の「婚姻」の問題と、これらの別の法的地位の問題は切り分けて論じるべきであると考える。
なぜならば、現在の制度において政策的に「婚姻している者(既婚者)」に対して「税法上の優遇措置、在留資格、公営住宅の入居資格等」を与えることが妥当であると判断されているだけであり、婚姻制度の枠組みを変更した場合には、それらの内容を「婚姻している者(既婚者)」に対して与えることが政策的に妥当でないと判断され、結果としてそれらの内容が与えられなくなる場合も考えられるからである。
「同性カップルが享受し得る利益が、異性カップルが婚姻により享受し得る法律上の効果に及ばないことは確かである。」との記載がある。
まず、「カップル」という単位を取り上げて、「カップル」と「カップル」の間を比較しようとするものとなっている。
しかし、法律上で比較対象とすることができるものは、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められている者同士の関係だけである。
法律上で「権利」や「義務」を関係づけることができる地位を有するという意味での「権利・義務の帰属主体」には、「自然人」と「法人」がある。
「カップル」については、「自然人」ではないことから、法律論上の比較対象としてり上げたいのであれば、この「カップル」という単位が「法人格」を有していることを証明しなければならない。
そうでなければ、そもそも法律論上の比較対象として取り上げることはできないからである。
また、「カップル」は「二人一組」を意味するものとなっているが、そもそもこの「二人一組」という取り上げ方をする前提には、婚姻制度が様々な人的結合関係の可能性の中から、「『子の福祉』の実現される社会基盤を構築すること」、「『近親交配』によって遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ぐこと」、「男女の数の不均衡によって『子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者』を減らすこと」、「母体を保護すること」などの立法目的を達成するための手段として、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係と区別する意味で「男女二人一組」という枠組みを定めていることに起因するものである。
それらの婚姻制度の枠組みが設定される以前には、人的結合関係が「二人一組」でなければならないとの前提は存在しないのである。
よって、「カップル」という「二人一組」を前提としていること自体が、既に婚姻制度の枠組みが存在することに依存して成り立つ考え方なのであり、この婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として設けられている枠組みの当否の問題を検討しないままに、「カップル」という「二人一組」のみを比較対象として持ち出していること自体が不当である。
「カップル」という「二人一組」を単位としていること自体が、現在の婚姻制度の立法目的を達成するための手段として導き出された「男女二人一組」という枠組みの数字だけを抜き出して論じるものとなっており、妥当でないのである。
現在婚姻制度の対象となっていない人的結合関係の形を考慮に入れるのであれば、「同性カップル」という「同性の二人一組」だけでなく、「三人以上の組み合わせ」、「近親者との組み合わせ」、「婚姻適齢に満たない者との組み合わせ」についても同様に論じる必要がある。
これらを検討をしないままに、「同性カップル」という「同性の二人一組」の人的結合関係の形のみを取り上げることは、網羅的な検討を行っているものとはいえないし、婚姻制度について全体の整合性を保った形で理解することはできない。
「婚姻により享受し得る法律上の効果」の部分に着目するとしても、「婚姻制度を利用している者(既婚者)」との間で比較対象となるものは、常に「婚姻制度を利用していない者(独身者)」である。
「婚姻制度を利用している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を受けている場合などについては、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」との間で、憲法14条の「平等原則」に違反するかどうかが審査されることになる。
これは、この判決が取り上げるような「カップル間不平等論」による比較ではない。
この判決は、恣意的に「二人一組」の形を選択し、「同性カップル」と「異性カップル」という人的結合関係のみを比較対象として取り上げるのであるが、比較の対象を選択する時点で、既に「カップル信仰論」に陥っており、誤っている。
「婚姻により享受し得る法律上の効果」であるが、これは単に婚姻制度の対象者となっている場合には、婚姻制度を利用することによってその「法律上の効果」を得ることができ、婚姻制度の対象者となっていない場合や婚姻制度を利用しない場合には、「法律上の効果」を得られないというだけのことである。
そのため、婚姻制度の対象となっていないか、婚姻制度を利用していない者に対して、「婚姻により享受し得る法律上の効果」を与えなければならないということにはならない。
ここでは「同性カップル」のみを取り上げて比較しようとするのであるが、それは単に婚姻制度を利用していない者の人的結合関係に過ぎないのであり、そのような者は「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても同様である。
これらの者についても、同様にここでいう「法律上の効果」を得ることはできないのである。
婚姻制度を利用する者と、利用しない者との間で「法律上の効果」に差異が生じることは、法制度が政策目的を達成するための手段として設けられた枠組みである以上は当然のことである。
また、このような不利益は個別的な立法や運用の改善等により解消され得るとしても、かかる個別的な立法等によっては、前記(2)ウで述べたような、同性カップルが社会の中で公に認知されて安心して安定した共同生活を営むために必要な人格的利益である公認に係る利益を満たすことはできない。
【論点番号】
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「このような不利益は個別的な立法や運用の改善等により解消され得るとしても、」との記載がある。
しかし、前の二つの段落の解説で述べたように、憲法の「個人の尊厳」の原理の下では、個々人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことが予定されているのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)である。
そのことから、あたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準となるかのような前提で、「婚姻している者(既婚者)」と比べて「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」があるとの論じ方は、比較の際の基準の採り方を誤っている。
そのため、「個別的な立法や運用の改善等により解消され得る」との部分についても、そもそも「婚姻していない者(独身者)」が基準なのであり、「改善等」をする余地はないし、「解消」する必要のある差異が存在するというものではない。
もし、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との比較において、14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その婚姻制度における過大な優遇措置に関する規定が個別に無効となることによって、差異が「解消」されることになる。
それにもかかわらず、「婚姻している者(既婚者)」が基準となるかのように考えて、あたかも「婚姻していない者(独身者)」が「不利益」を得ているかのような前提で論じていることや、「婚姻していない者(独身者)」に関する「個別的な立法や運用」の方を「改善等」をしなければならないという主張は、基準(スタンダード)の採り方を誤っており、憲法の「個人の尊厳」の原理を正解しないものである。
「かかる個別的な立法等によっては、前記(2)ウで述べたような、同性カップルが社会の中で公に認知されて安心して安定した共同生活を営むために必要な人格的利益である公認に係る利益を満たすことはできない。」との記載がある。
まず、「社会の中で公に認知されて安心して安定した共同生活を営む」ことであるが、これは憲法21条1項の「結社の自由」によって保障されている。
如何なる人的結合関係においても、憲法12条、13条の「公共の福祉」や民法90条の「公序良俗」、その他個別の法律に違反しないのであれば「社会の中で公に認知されて安心して安定した共同生活を営む」ことは可能である。
これは憲法で保障されている自由であることから、「社会の中で公に認知されて」いるし、「共同生活を営む」ことが制限されているわけではない。
この自由が不当に制限されている場合には、「社会の中で公に認知されて」いないということになり、憲法21条1項の「結社の自由」に抵触して違憲となるが、そのような自由が制限されているわけではない。
次に、日本国憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に、各々「自律的な個人」として生存していくことを予定している。
そのため、「自律的な個人」として独身のままに生活していくことが基本であり、「婚姻していない者(独身者)」の状態を基準(スタンダード)として考える必要がある。(例えば、選挙権を得るために婚姻しなければならないということはない。また、生活保護を受ける場合についても、婚姻していなければ受給資格を満たさないというものではない。『婚姻していない者(独身者)』が基準〔スタンダード〕である。)
また、「婚姻していない者(独身者)」同士が集まって「共同生活を営む」ことも自由であり、それが普通の状態である。
そのため、憲法の「個人の尊厳」の原理の下では、独身のままに生活することが基本であり、わざわざ「カップル」を称する者に対して、21条の「結社の自由」によって保障される範囲を越えて、何らかの「利益」(ここでいう『結社の自由』とは別の意味での『公認に係る利益』にあたるもの)を付与しなければならないとの前提そのものが成り立たない。
このことは、「カップル」(二人一組)を称する者たちに限らず、「トリオ」(三人一組)を称する者たちであっても、「四人一組」の者たちであっても同じである。
単に「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成しているというだけで、立法目的とそれを達成するための手段として定められている枠組みの当否の問題を越えて、根拠もなくこの判決のいう「公認に係る利益」と称するものを与えなければならないということにはならないのである。
この判決のように論じることができるのであれば、「トリオ」(三人一組)や「四人一組」についても、「公認に係る利益」を「満たすことはできない。」として、ここでいう「公認に係る利益」を同様に与える必要があると論じることもできるのであり、妥当でない。
この判決はこの点でも、「カップル」を持ち出し、なぜ「二人一組」であるのか、その根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている。
(ウ) 以上のとおり、本件諸規定が異性間の婚姻のみを対象としていることについては、その趣旨には合理性があり、その影響も、これにより生ずる同性カップルと異性カップルの間の享受し得る利益の差は契約等により一定の範囲では緩和され得るということはできるものの、公認に係る利益のような個人の尊厳に関わる重要な利益を同性カップルは享受し得ないという問題はなお存在するということができる。
【論点番号】
⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
【筆者】
「本件諸規定が異性間の婚姻のみを対象としていることについては、その趣旨には合理性があり、」との部分について検討する。
この「その趣旨」とは、「2(3)イ(ア)」に記された「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、このような男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨」のことである。
この趣旨に「合理性」があるということは、24条1項の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言が、憲法上の立法政策として法律上の婚姻制度について「男女二人一組」の形に限定するものであるとしても、同様に「合理性」があると説明することが可能である。
この点、法律上の立法政策としての「婚姻」の「趣旨」と、憲法上の立法政策としての「婚姻」の「趣旨」が同一であるにもかかわらず、この判決が24条1項について「同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と断じてしまうことは、婚姻制度が設けられている「趣旨」との関係において他の解釈を退けるだけの説得的な根拠を示していることにはならない。
「裁判官がそう言っているからそうなんだろう」というようなことになれば、人治主義に陥るのであり、法の中に規範を見出す法治主義から逸脱することになる。
「その影響も、これにより生ずる同性カップルと異性カップルの間の享受し得る利益の差は契約等により一定の範囲では緩和され得るということはできるものの、」との部分について検討する。
「同性カップルと異性カップルの間の享受し得る利益の差は」の部分であるが、比較対象として法律上の「権利能力」を有しない「カップル」という単位を持ち出している点で、法律論として正当化することはできない。
法律上で比較対象とすることができる事柄は、「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているものと、同じく「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているものとの間だけである。
なぜならば下記のような事例に対して法的紛争を解決することはできないからである。
◇ 「人間」と「亀」は平等か
⇒ 「亀」に「権利能力」はなく、法主体としての地位を認められていない。
◇ 「天国」と「地獄」は平等か
⇒ 特定のフィールドに「権利能力」はない。
◇ 「ソウルメイトの関係」と他の「ソウルメイトの関係」は平等か
⇒ 単位の設定が法律論に基づくものではなく、法律論としてはこのような単位を用いて審査することはできない。これが人的結合関係を指すのであれば、法人格を取得して「権利能力」を有して法主体としての地位を認められていなければ、その人的結合関係を取り上げて審査することはできない。
◇ 「カップル」と「トリオ」は平等か
⇒ 単位の設定が法律論に基づくものではなく、法律論としてはこのような単位を用いて審査することはできない。これが人的結合関係を指すのであれば、それぞれの人的結合関係が法人格を取得して「権利能力」を有して法主体としての地位を認められなければ、その人的結合関係を取り上げて審査することはできない。
これらと同様に、「同性カップル」や「異性カップル」のように「カップル」という単位を持ち出しても、法律論としては「権利能力」を有して法主体としての地位を認められているもの同士の関係においてしか法的な審査を行うことはできないのであり、「権利能力」を有していない「カップル」という単位を持ち出して比較しようとする試みそのものが誤っている。
もしそのような「カップル」という単位を用いたいのであれば、その「カップル」と称する単位が法人格を取得して「権利能力」を備え、法主体としての地位を認められていることを予め証明する必要がある。
民法には下記のように定められている。
民法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 (略)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、「カップル」とは、婚姻制度が立法目的を達成するための手段としての枠組みとして「男女二人一組」としていることを前提とし、その「二人一組」という部分のみに着目する形で取り上げようとする場合に用いているものと思われる。
しかし、これは「カップル」という「二人一組」を前提としていること自体が、既に婚姻制度によって創設された枠組みを前提とした考え方に基づく主張となっている。
つまり、様々な人的結合関係の可能性の中から婚姻制度の枠組みが「二人一組」の形で作られたことの背景にある立法目的と、それを達成するための手段となる枠組みの当否を論じることなく、「二人一組」であることの根拠を見出すことはできないのである。
「二人一組」という枠組みを取り上げること自体が、既に婚姻制度がどのような立法目的を有しており、その達成手段としてどのような枠組みを定めているかという問題に依存しているものなのであり、この点を考えずに、根拠もなく「二人一組」という枠組みが揺るぎない絶対的なものであるかのように考えて、それを基に「カップル」という単位を持ち出して比較対象として取り上げることは、「カップル信仰論」に陥ることになる。
他国の場合では、一人の男性と四人の女性による「一夫多妻」の「複婚」が許されている場合もあり、そのような国では「カップル」という「二人一組」を前提として考えること自体が成り立たないことは容易に理解することができる。
このような「カップル」という単位を持ち出している背景には、現在ある婚姻制度の枠組みの一側面のみを、その制度が設けられている目的との整合性を勘案しないままに根拠なく切り取り、それが婚姻制度の枠組みが設定される以前から存在する絶対的な単位であるかのような理解に基づいて取り上げようとしているものと考えられる。
しかし、このような、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じるものは、根拠のない前提を絶対的なものであるかのように言い張ろうとするものであるから、「カップル信仰論」に陥っているものということができ、法律論として妥当でない。
「契約等により一定の範囲では緩和され得るということはできるものの、」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下で「自律的な個人」として生存していくことが予定されている。
そのため、何らかの人的結合関係を形成しなければならないという前提は存在しないのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態ということができる。
そのような個々人は人的結合関係を結びながら生活したり、「契約等」を行いながら生活する自由がある。
このような状態が「個人の尊厳」の原理に基づいた基準(スタンダード)である。
その前提の中、国家が政策として婚姻制度を設けていることは、「生殖」に関わる事柄によって社会的な不都合が発生することを抑制するためである。
その婚姻制度の要件に当てはまる人的結合関係については、その制度による優遇措置を与え、それに当てはまらない人的結合関係については、通常通り「結社の自由(21条1項)」の範囲で保障されることになる。
これにより、「生殖」に関わる事柄によって社会的に不都合が発生することを抑制しているのである。
そのことから、婚姻制度が創設される時点で、制度の対象となる場合には制度を利用することができ、制度の対象とならない場合には制度を利用できないという差異が生じることは当然予定されている。
また、そもそも「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であるから、「婚姻していない者(独身者)」が不利益を受けているという事実はない。
もし「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」との間で、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、14の「平等原則」に照らして不合理な差異ということになり、その優遇措置に関する規定が個別に違憲・無効となるだけである。
このような憲法の「個人の尊厳」の原理による基準(スタンダード)の設定に対して、この判決はあたかも「婚姻している者(既婚者)」が基準となるかのような前提によって「婚姻していな者(独身者)」(ここでいう『カップル』の個々人のこと)の「利益」が「一定の範囲では緩和され得る」と述べている。
しかし、このような理解は、「婚姻していない者(独身者)」をあたかも「成年者」と「未成年者」の比較における「未成年者」(制限行為能力者)の方であるかのような扱いをするものであり、「婚姻していない者(独身者)」の地位を不当に貶めるものである。
「婚姻している者(既婚者)」は完全な「利益」を得ている者であり、「婚姻していない者(独身者)」は完全な「利益」を得られていない者であるかのような前提を有していることは、憲法の「個人の尊厳」の原理により「個人主義」の下で各々「自律的な個人」として生存していくことを予定していることに沿うものではない。
このような基準の採り方は、憲法の「個人の尊厳」の原理に反するものである。
「公認に係る利益のような個人の尊厳に関わる重要な利益を同性カップルは享受し得ないという問題はなお存在するということができる。」との部分について検討する。
まず、「個人の尊厳」であるが、これは自然人は「個人主義」の下に、各々が「自律的な個人」として扱われることを意味し、そのような個々人の状態で生存していくことを予定するものである。
そのため、憲法以下の法令においては、何らの人的結合関係も形成していない「個人」を基本として考えることが求められることになる。
ここで「個人の尊厳」を示しているということは、それは何らの人的結合関係も形成していない状態の者を基準(スタンダード)として考えることを前提とするのであるから、その「個人」がここでいう「同性カップル」のような人的結合関係を形成する場合があるとしても、それに対して何らかの「利益」を与えなければならないとする根拠とはならない。
次に、「公認に係る利益」についてであるが、婚姻制度に「公認に係る利益」と称するものを得させようとする立法目的が存在するかは疑問である。
なぜならば、「婚姻している者(既婚者)」は「婚姻している者(既婚者)」として認知され、「婚姻していない者(独身者)」は「婚姻していない者(独身者)」として認知されるというだけであり、そのこと自体に法律論上の優劣はないからである。
この法律論上の優劣のない事柄について、「婚姻している者(既婚者)」にだけ「利益」があると考えることはできないのである。
婚姻制度に「公認に係る利益」と称するものを与えようとする立法目的や、それを与えるような具体的な規定が存在しないのであれば、制度そのものから導かれない何らかの「利益」について、制度の対象外の者に対して与えるべきかどうかを論じようとするものということになり、法律論を逸脱することになる。
また、24条2項の「個人の尊厳」は、24条2項の示す「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用されるものであり、「婚姻及び家族に関するその他の事項」の中に当てはまらないものに対しては適用されない。
「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「婚姻」の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」や「兄弟」、「姉妹」などに含まれないのであれば法律論上の「家族」でもないのであり、24条2項の示す「婚姻及び家族に関するその他の事項」の中に当てはまらない。
よって、この人的結合関係に対しては、24条2項の「個人の尊厳」は適用されないのであり、24条2項の「個人の尊厳」を適用しようとする意味で「個人の尊厳に関わる重要な利益」と論じようとしているのであれば、誤りである。
憲法24条2項の「個人の尊厳」の解釈であるが、国(行政府)の主張で指摘されている部分がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、前記2のとおり、憲法24条2項は、飽くまで婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであることを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、憲法解釈としては、同項の「個人の尊厳」をこのような規定の在り方と切り離して解釈することは相当でなく、本件諸規定は、このような同項の要請に従って制定されたものである。……(略)……
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第12回】被告第6準備書面 令和4年2月21日 PDF (P14)
「同性カップルは享受し得ないという問題はなお存在する」の部分であるが、婚姻制度は立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが定められており、婚姻制度の対象となる者は婚姻制度を利用することによって婚姻制度による「利益」を得ることができ、婚姻制度の対象とならない者や婚姻制度を利用しない者は婚姻制度による「利益」を得ることができないという差異が生じることは、制度が政策的なものである以上は当然のことである。
よって、婚姻制度の対象とはならない「近親者との人的結合関係」、「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」と同様に、婚姻制度による「利益」は得られないのであり、制度の枠組みに当てはまらない以上は当然のことである。
よって、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが合理性を有する限りは、婚姻制度の対象とならない者が婚姻制度による「利益」を得られないとしても、「問題」とはいえない。
そのため、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の当否を論じることもなく、婚姻制度の対象外の者に対して婚姻制度による「利益」を与えていないことについて「問題はなお存在する」などと、「問題」があるかのように論じることは妥当でない。
しかしながら、同性カップルについて公認に係る利益を実現する方法は、現行の婚姻制度の対象に同性カップルを含める方法(前記(2)ア(ウ)のとおり憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。)に限るものではなく、これとは別の新たな婚姻類似の法的承認の制度(これは、「登録パートナーシップ制度」と名付けることもできれば、「同性婚」と名付けることもできるものである。)を創設するなどの方法によっても可能である。そして、現行の婚姻制度を構成している本件諸規定は、単に異性間の婚姻制度を定めたというにすぎないものであるから、同性間について婚姻以外の婚姻類似の公的承認の制度を創設することを何ら妨げるものではない。我が国でも、既に多くの地方公共団体では、同性カップルについて登録パートナーシップ制度と呼ばれる公的承認及び部分的な保護の制度が導入され、多くの同性カップルがこの制度を自分達の公認の方法として希望して利用していることが認められる。これは、法律上の制度ではないものの、国民の間でもーつの社会の制度として認知されてきているということができる。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること
【筆者】
「同性カップルについて公認に係る利益を実現する方法は、現行の婚姻制度の対象に同性カップルを含める方法(前記(2)ア(ウ)のとおり憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。)に限るものではなく、これとは別の新たな婚姻類似の法的承認の制度(これは、「登録パートナーシップ制度」と名付けることもできれば、「同性婚」と名付けることもできるものである。)を創設するなどの方法によっても可能である。」との記載がある。
「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」の部分について検討する。
■ 「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできないこと
24条は「婚姻」について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
そのため、その24条の「婚姻」の規定の効力が及ばない形で、「婚姻」という名の付いた制度を別に立法することはできない。
これは、「婚姻」であればすべて24条による統制が及ぶのであり、「婚姻」であるにもかかわらず24条の統制が及ばないことになれば、憲法と法律の間に矛盾が生じるからである。
もし24条の統制が及ばない形で「婚姻」を立法しようとしても、それは24条に抵触して違憲となる。
このことから、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」の部分について、「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れた形で別の制度として立法することが可能であるかのように考えているのであれば、誤っている。
■ いくつかの立場との関係性
24条1項の解釈について、いくつかの立場から検討する。
▼ 義務文・否定文であるかの論点
「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」の意味について、「~~してはならない。」のような義務文・否定文による「禁止」ではないという意味であれば、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の部分だけを見れば、そのように読める場合もある。
しかし、24条1項全体で見れば、最後に「されなければならない。」と記載されているため「義務文・否定文による禁止」の意味を有していることも考えられる。
また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されているため、「義務文・否定文による禁止」の意味を有している可能性もある。
そのため、その意味では「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」とはいえない。
◇ 「婚姻」の由来説
この立場から見れば、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」の意味については、その通り、24条の規定は「禁止までするもの」として定められた規定ではない。
しかし、そもそも「同性間」では「生殖と子の養育」の趣旨を含まないため「婚姻」とすることはできない。
この立場について、後ほど「24条の『婚姻』が『生殖と子の養育』の趣旨を含むこと」の項目で解説する。
◇ 存在しない説
この立場から見れば、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」の意味については、その通り、24条の規定は「禁止までするもの」として定められた規定ではない。
しかし、そもそも「婚姻」は異性間で成立するものであり、「同性間」において成立することはなく、「同性間の婚姻」という形は存在しない。
◇ 成立条件説
この立場から見れば、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」という意味については、その通り、24条は「禁止までするもの」として定められた規定ではない。
しかし、そもそも24条は「婚姻」の成立条件を示したものであるから、「同性間」おいては「両性の合意のみに基いて成立し、」という成立条件を満たさないため、「婚姻」として成立しないことになる。(「夫婦」の文言も満たさない。)
◇ 想定していない説
上記の三説と下記の二説の両方の可能性がある。
◇ 立法裁量の限界を画するもの
この立場は、次の二つに分けて考えることができる。
➀ 「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」(義務文・否定文による禁止ではない)が、24条の文言を満たさない「同性間」の人的結合関係は「婚姻」とすることはできない。
② 「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」という解釈は誤っており、24条1項は立法裁量の限界を画することによって「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「禁止までするもの」である。
◇ 禁止説
この立場は、次の二つに分けて考えることができる。
➀ 「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」という解釈は誤っており、24条1項は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「禁止までするもの」である。
② 「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」という解釈は誤っており、24条1項は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文の規定であり、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを「禁止までするもの」である。
■ 「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと
▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界
「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度である。
そのため、「婚姻」には、下記の目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
「婚姻」は、これらの目的を達成することを意図して「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で定められた制度である。
そのため、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
また、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。
このことから、「生殖と子の養育」の趣旨を含まない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。
「同性間」の人的結合関係については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
▼ 24条の「婚姻」による限界
24条が「婚姻」を定めている以上は、24条の「婚姻」の文言の中にもこの「生殖と子の養育」の趣旨が引き継がれている。
そのため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」の中に含めることはできない。
「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
よって、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係は「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること
「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。
そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。
これは、「婚姻」という制度を24条の統制に服させ、その制度の内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。
この24条の立法政策を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。
これは、下記が理由である。
仮に、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することができるとした場合を考える。
すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の制約を回避する形で立法することが可能となる。
これは、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら24条が統制できない状態を許すことになる。
こうなると、「生殖と子の福祉」に関わる制度を、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」、「両性の本質的平等」の文言による制約が及ばない形で立法することが可能となる。
例えば、24条のいう「婚姻」とは別の「生殖結社制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。
そして、その「生殖と子の養育」に関わる制度の内容が「両性の合意」以外の条件を設けるものであったり、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しない制度となっていても、もともとそれは24条の「婚姻」とは異なる制度であることから、その内容を是正することができない。
つまり、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。
また、その「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。
そうなると、「婚姻」という制度そのものが有している政策的な効果が阻害され、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を「婚姻」という制度を設けることによって解消しようとする「婚姻」という制度そのものが有している立法目的を達成することができなくなる。
これでは、「婚姻」を24条による統制の下に置くことで、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように要請する憲法上の立法政策の実現も阻害されることになる。
このように解釈することは、24条の規定を設けている趣旨そのものを損なうことになるため、妥当でない。
このような事態に陥ることを防ぐためには、「生殖と子の養育」に関わる制度については、すべて24条の「婚姻」の中に一元的に吸収されるように解釈することが必要となる。
そのため、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」による制約を回避するような形で定めることは許されない。
もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。
このため、24条の「婚姻」の文言には、「生殖と子の養育」に関わる制度をすべて24条の「婚姻」の中に一元的に集約する形で立法しなければならないとの要請が含まれている。
この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、24条の「婚姻」の文言からこれを切り離して考えることはできない。
そのことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。
よって、「同性間」の人的結合関係については、「生殖と子の養育」の趣旨を含まないため、24条の示す「婚姻」として扱うことはできない。
「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係は「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと
仮に、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていない場合を考える。
すると、24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨も有していないことになる。
そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。
こうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、それが24条の「婚姻」とは異なることから、24条による統制が及ばない状態となる。
つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、もともとそれは24条の「婚姻」ではないことから、その制度の内容を是正することができないということである。
これでは、「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖と子の養育」に関わる制度の内容に対して立法裁量の限界を画することで達成しようとした憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。
このような解釈は、24条の規定の存在意義が損なわれるため、法解釈として成り立たない。
そのため、24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」の趣旨に関わる制度を一元的に集約するものとして定められており、24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。
このため、24条の「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。
これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を含まない人的結合関係を24条の「婚姻」の中に含めることはできない。
よって、「同性間」の人的結合関係については、「生殖と子の養育」の趣旨を含まないため、24条の示す「婚姻」として扱うことはできない。
「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係は「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
▽ 「生殖と子の養育」の趣旨の内容
24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を含んだまま、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるのではないかとの主張が考えられる。
これについて検討する。
まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度である。
このような背景から、下記の目的が存在すると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そして、これらの目的を達成することを意図して「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する形で構築された枠組みであるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むということの本質的な意味は、下記の要素を満たすことであると考えられる。
・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること
・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること
・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること
・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること
これによって、先ほど挙げたような「婚姻」の目的を達成することが意図されているのである。
そのことから、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」という概念に含まれた内在的な限界により、「婚姻」とすることができない。
「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。
そして、24条は「婚姻」を定めており、この意味を引き継いでいる。
他にも、24条には「両性」「夫婦」「相互」の文言により、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。
このように一夫一婦制(男女二人一組)を定めている意図は、先ほど挙げた「生殖と子の養育」の趣旨の内容をすべて満たすことが理由と考えられる。
そのため、それらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」の文言や、「両性」「夫婦」「相互」の文言が一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることの意味を満たすものではなく、「婚姻」として扱うことができない。
「同性間の人的結合関係」については、24条の「婚姻」の文言に含まれる「生殖と子の養育」の趣旨を満たさず、「両性」「夫婦」「相互」の文言にも当てはまらないことから、「婚姻」とすることはできない。
よって、「憲法24条1項も同性間の婚姻を禁止までするものではない。」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係は「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。
「現行の婚姻制度を構成している本件諸規定は、単に異性間の婚姻制度を定めたというにすぎないものであるから、同性間について婚姻以外の婚姻類似の公的承認の制度を創設することを何ら妨げるものではない。」との記載がある。
しかし、婚姻制度を設けている以上は、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害するような影響を与えるような制度を別に創設することはできない。
もしそれをした場合には、婚姻制度の立法目的を達成することができなくなり、婚姻制度を設けている意味がなくなるからである。
婚姻制度の立法目的と、その達成手段には下記を挙げることができる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
これらの目的を達成することを阻害する影響を及ぼすような制度を創設すると、婚姻制度の立法目的を達成することを困難とすることに繋がるため、婚姻制度そのものが成り立たなくなる。
そのため、婚姻制度とは別に「婚姻類似の公的承認の制度を創設することを何ら妨げるものではない。」と言い切ることはできない。
「我が国でも、既に多くの地方公共団体では、同性カップルについて登録パートナーシップ制度と呼ばれる公的承認及び部分的な保護の制度が導入され、多くの同性カップルがこの制度を自分達の公認の方法として希望して利用していることが認められる。これは、法律上の制度ではないものの、国民の間でもーつの社会の制度として認知されてきているということができる。」との記載がある。
しかし、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などは、国会の制定する法律に違反してはならないため、民法に定められた婚姻制度に抵触するものとなっている場合には違法となる。
下記で条例制定権の限界に関する判例を読み取る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)
この判例によれば、下記の場合には、「地方公共団体」において「登録パートナーシップ制度と呼ばれる公的承認及び部分的な保護の制度」を導入していることは、違法となる。
◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」
◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合
そこで、民法上の婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると婚姻制度の立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「登録パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その者にも子に対する養育の責任を担わせることによって、「子の福祉」を実現しようとするものとなっていることから、父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、この目的を達成することを阻害することになるから、婚姻制度に抵触して違法となると考えられる。
また、「登録パートナーシップ制度」の内容が「男女二人一組」の形であるとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、結局は制度の内容に従って適法な行動をしていたとしても、子の母親となる者は「登録パートナーシップ制度」を利用する相手方とは異なる他の男性との間で生殖を行っている可能性を排除することができないことから、父親を特定することができなくなるため、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その父親にも子に対する養育の責任を担わせることによって「子の福祉」を実現しようとするものであるから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を与えないことにより、「生殖」によって子供をつくる者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定できる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。しかし、国民が「登録パートナーシップ制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「登録パートナーシップ制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害することになる。よって、婚姻制度とは異なる選択肢として「登録パートナーシップ制度」を設け、婚姻制度と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
(ここで『婚姻制度とは異なる選択肢として』と記載している意味は、『企業間パートナーシップ』『商工業パートナーシップ』『貿易におけるパートナーシップ』など、婚姻とはまったく関わらない制度については、婚姻制度には抵触しないことを意味するものである。単に地方公共団体の政策担当者が『登録パートナーシップ制度』について『婚姻制度とは異なる制度である』と言い張るだけで、その『登録パートナーシップ制度』が民法の婚姻制度に違反しなくなって適法となるわけではなく、その『趣旨、目的、内容及び効果』が実質的に婚姻制度と競合するかどうかを判断することが必要である。)
婚姻制度には、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、それらの者との間で婚姻制度を利用できないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ぐ目的がある。この観点から、「女性同士の組み合わせ」に対して優遇措置を与えることは、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用を持つものとなるから、遺伝的な近親者の範囲を把握することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。そうなれば、婚姻制度が遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。よって、「登録パートナーシップ制度」の内容が、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)に対して婚姻制度と同様の、あるいは類似する優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「登録パートナーシップ制度」においても婚姻制度と同様の、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間の人的結合関係を結んで「登録パートナーシップ制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数の不均衡が生じることにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度に抵触して違法となる。
さらに、「登録パートナーシップ制度」の中には、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的としているものがあり、このような目的をもって制度を立法することは憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、ある特定の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」を制度の対象としていないことは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、そのような区別取扱いは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
よって、このように「登録パートナーシップ制度」が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触するか否かの論点が存在するにもかかわらず、あたかも「登録パートナーシップ制度」が適法な制度であるかのような前提に基づいて「国民の間でもーつの社会の制度として認知されてきているということができる。」などと、正当化できるかのように述べることは妥当でない。
「登録パートナーシップ制度」が法律に違反するか否かそのものが、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の枠組みの当否の問題に直接的に関わっているにもかかわらず、これを論じずに「登録パートナーシップ制度」が適法に成立することができることを前提に話を進めている点で、十分な検討を行っているとはいえない。
このように、個人の尊厳の観点からは同性カップルに対しても公認に係る利益を実現する必要があるといえるものの、その方法には様々な方法が考えられるのであって、そのうちどのような制度が適切であるかについては、現行法上の婚姻制度のみならず、婚姻類似の制度も含め、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた上で民主的過程において決められるべきものである。
【論点番号】
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
「個人の尊厳の観点からは同性カップルに対しても公認に係る利益を実現する必要があるといえるものの、」との部分について検討する。
しかし、憲法の「個人の尊厳」の原理とは、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、何らの人的結合関係を結んでいない者や、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味するものである。
よって、「個人の尊厳の観点から」考えると、何らかの立法目的が存在しないのであれば、もともと何らの制度を設ける必要がないのであり、その具体的な立法目的が存在しないにもかかわらず、何らかの人的結合関係に対して「利益」(ここでいう『公認に係る利益』)を与えなければならないということにはならない。
また、「婚姻していない者(独身者)」については、「婚姻していない者(独身者)」としてその社会の中で認識されているのであり、それだけで既に「公認」されているともいうことができる状態である。
「婚姻していない者(独身者)」であることについて、その地位を低く扱われる謂われはないのである。
他にも、婚姻制度から得られる「利益」については、婚姻制度の立法目的に従って、それを達成するための手段として枠組みを定め、その対象となる者に対して与えられるものであり、その制度の対象とならない者に対しては与えられないということは当然のことである。
そのため、婚姻制度の対象となっていない者(人的結合関係)に対して、婚姻制度から得られる「利益」を与えなければならないことにはならないし、それを与えることは婚姻制度の政策的な効果を弱めることに繋がり、立法目的の達成を阻害することも考えられる。
そのため、裁判所が「公認に係る利益を実現する必要があるといえる」などと、婚姻制度の対象でない者(人的結合関係)に対して「利益」(ここでいう『公認に係る利益』と称するもの)を与えなければならないと論じることは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段との整合性を勘案する立法政策の議論を差し置いて、立法裁量に属する問題(憲法24条の下では同性間の人的結合関係に婚姻や婚姻類似の制度による保護を与えることはできない可能性もある)について口出しをしようとするものであるから、法規範に適合するか否かという合法・違法(合憲・違憲)の問題しか判断することのできない司法権の範囲を越えると考えられる。
裁判所は一切の政治勢力から独立して、法によってのみ判断することができるのであり、立法権の行使としての政策的な議論に関わる問題について、法技術的な論点を解き明かす作業を離れて、どちらか一方の政治的な立場を推進したいという動機があるのであれば、司法権を行使する裁判官の立場を離れて、立法権を行使する政治家の立場に転身するべきである。
さらに、24条2項の「個人の尊厳」については、24条2項に記されているように「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される事柄であり、ここで「同性カップル」と称している同性間の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度によって達成しようとした立法目的との整合性を保つことのできる範囲で規律される法律上の「家族」でもないのであるから、「婚姻及び家族に関するその他の事項」の中に含まれておらず、24条2項の「個人の尊厳」の文言が適用される事例でもない。
これらの理由により、この判決は「個人の尊厳の観点からは同性カップルに対しても公認に係る利益を実現する必要があるといえる」と述べるのであるが、「個人の尊厳」の理解を誤っているし、婚姻制度の対象者が婚姻制度を利用した場合に与えられる「利益」については、婚姻制度の対象でない者や婚姻制度を利用しない者には与えられないことは当然に予定されていることであり、また、それらの者に「利益」を与えることが政策として妥当であるかどうかについても、婚姻制度の立法目的との整合性を検討する中に決められるものであるから、必ずしもその「利益」を与えることが妥当であるとは限らない。
よって、これらの検討が明らかでない中で、また、立法裁量に属する問題について、裁判所が婚姻制度の対象でない人的結合関係に対して「同性カップルに対しても公認に係る利益を実現する必要があるといえる」と述べることは、誤った判断であると考えられる。
また、このような論じ方が可能であるとすれば、「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても、同様に「公認に係る利益を実現する必要があるといえる」ということになるのであり、婚姻制度そのものの枠組みを破壊し、婚姻制度の政策的な効果を阻害する影響を生み出すものとなるのであり、制度を網羅的な観点から整合的に検討するものとはなっていない。
「同性カップル」のみを比較対象として取り上げ、その他の人的結合関係との整合性を検討していないことは、「カップル信仰論」に陥っていることになる。
「婚姻していない者(独身者)」については、「婚姻していない者(独身者)」としてそのまま尊重すればよいのであり、「婚姻していない者(独身者)」の人的結合関係に対して、何らかの利益を与えなければならないとの前提が誤っている。
「その方法には様々な方法が考えられるのであって、そのうちどのような制度が適切であるかについては、現行法上の婚姻制度のみならず、婚姻類似の制度も含め、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた上で民主的過程において決められるべきものである。」との部分について検討する。
「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた」結果として、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「近親者との人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」については、制度によっては何らの「利益」も与えないことが適切であるという判断もあり得るのであり、その判断の過程を通る以前に「同性カップルに対しても公認に係る利益を実現する必要があるといえる」などと結論を先取りしようとすることは、特定の政治的な立場に肩入れするものとなるのであり、裁判所の中立性を損なうものとなっている。
以上の点を総合的に考慮すると、上記のような状況において、同性カップルの公認に係る利益の実現のためにどのような制度が適切であるかの議論も尽くされていない現段階で、直ちに本件諸規定が個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くと認めることはできない。よって、本件諸規定が、立法裁量の範囲を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するということはできない(なお、上記のような国民的議論を経た上で、国会が本件諸規定を改廃し、同性間の婚姻制度を構築するという選択をすることも可能であることはいうまでもないが、このことと、本件諸規定が憲法24条に違反するか否かという憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものである。)。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
【筆者】
「同性カップルの公認に係る利益の実現のためにどのような制度が適切であるかの議論も尽くされていない現段階で、直ちに本件諸規定が個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くと認めることはできない。」との記載がある。
まず、「同性カップルの公認に係る利益の実現のためにどのような制度が適切であるか」の部分を検討する。
ここでいう「公認に係る利益」と称するものであるが、婚姻制度の中に「公認に係る利益」と称する「利益」が存在するのか疑問である。
なぜならば、「婚姻制度を利用する者(既婚者)」は「婚姻している者(既婚者)」として認識され、「婚姻制度を利用していない者(独身者)」は「婚姻していない者(独身者)」として認識されているだけであり、法律論上、また、民法や戸籍法においても、そこに優劣はないからである。
日本国憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下、各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されているのであり、人的結合関係を形成していない状態で既に完全な状態として取り扱われている。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」であっても、そのままの状態で既に「公認」されているということもできるのであり、「婚姻している者(既婚者)」だけが「公認」されているという性質のものではない。
また、もしこの判決のいう「公認に係る利益」と称するものがあるとしても、この判決は「2(1)ウ」の部分で「婚姻をした当事者が享受し得る利益」と述べているのであるから、「婚姻している者(既婚者)」を対象とした「利益」である。
婚姻制度は立法目的が存在し、それを達成するための手段として枠組みが定められ、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置や利益を与えることにより、立法目的を実現しようとするものであるから、「婚姻していない者(独身者)」がこの「利益」を得られないことは、制度の対象でない以上は当然のことである。
ここでいう「同性カップル」についても、それぞれは「婚姻していない者(独身者)」であるから、婚姻制度による「利益」を得ることができないことは当然のことであり、ここでいう「公認に係る利益」と称するものについても、得られないことは制度が政策的なものである以上、当然のことである。
そして、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の当否の問題を越えて、婚姻制度から得られる「利益」を、婚姻制度の対象でない者に対して与えなければならないことにはならないのであるから、「同性カップルの公認に係る利益の実現のためにどのような制度が適切であるか」のように、同性間の人的結合関係に対して「公認に係る利益」と称するものを与えなければならないことを前提として論じていることも、適切ではない。
次に、「直ちに本件諸規定が個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くと認めることはできない。」の部分を検討する。
24条2項の「個人の尊厳」が適用される事柄は、24条2項に記されているように「婚姻及び家族に関するその他の事項」だけである。
そして、ここで「同性カップル」と称している同性間の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」の立法目的を実現することを阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」、「兄弟」、「姉妹」などに当てはまらないのであれば、法律上の「家族」ともいえないのであり、24条2項の「個人の尊厳」を適用することができる事例ではない。
よって、「同性カップル」という同性間の人的結合関係について、24条2項の「個人の尊厳」を適用できる対象ではないことから、「本件諸規定が個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くと認めることはできない。」というように、あたかも24条2項の「個人の尊厳」が適用されることを前提として「合理性」の有無を論じている点は、解釈の過程を誤っている。
三つ目に、「公認に係る利益」の実現のための制度と、「個人の尊厳」について検討する。
学説上、24条2項の「個人の尊厳」は、13条の「個人の尊重」と同様の趣旨であると考えられている。
そして、この判決の「イ 憲法13条に違反するかについて」の部分では、下記のように述べられている。
2(2)イ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
したがって、憲法24条が異性間の婚姻のみを定めており、これを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。また、包括的な人権規定である同条によって、同性間の婚姻制度を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、この判決では13条で「特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。 」と述べている。
しかし、24条の「個人の尊厳」の解釈においては「公認に係る利益」の実現のための制度を求める権利が保障される場合があるかのような前提で「直ちに本件諸規定が個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くと認めることはできない。」と述べ、合理性を欠く場合には「公認に係る利益」の実現のための制度を求めることができるかのように論じている。
この点、13条の「個人の尊重」と24条の「個人の尊厳」の解釈に一貫性がなく、妥当ではない。
「本件諸規定が、立法裁量の範囲を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するということはできない」との記載がある。
しかし、「立法裁量の範囲を逸脱するものとして憲法24条2項に違反する」か否かを審査することができるのは、24条2項に記されている通り「婚姻及び家族に関するその他の事項」だけである。
「婚姻」は、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係から区別されることによって形成された経緯があることから、「生殖と子の養育」の趣旨を含むものであり、いくつかの立法目的を有している。
そしてここでいう「家族」とは、法律上の「家族」のことであり、「婚姻」という制度を構築した立法目的の実現を阻害しない範囲で規律されて枠組みが定められている範囲の者のことである。
ここで「同性カップル」と称している同性間の人的結合関係については、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係から区別される意味で形成された「婚姻」ではないし、それが「親子」「兄弟」「姉妹」などにも当たらないのであれば、法律上の「家族」でもないのであり、24条2項の示す「婚姻及び家族に関するその他の事項」の中には含まれず、憲法24条2項が適用される対象ではない。
よって、そもそもこの事例に対して24条2項は適用されないのであるから、24条2項に適合するか否かを審査することもできないのであり、24条2項の許容している「立法裁量の範囲を逸脱するもの」であるか否かを審査する段階にも至っていない。
そのことから、24条2項が適用される可能性があることを前提として「本件諸規定が、立法裁量の範囲を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するということはできない」と論じることは、前提を誤っている。
㊥ 「なお、上記のような国民的議論を経た上で、国会が本件諸規定を改廃し、同性間の婚姻制度を構築するという選択をすることも可能であることはいうまでもないが、」との記載がある。
━━24条1項の論点━━
(上記で既に解説済み)
24条1項の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるか否かについては、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。
(エ) これに対し、原告らは、本件諸規定は、同性愛者の婚姻の自由を直接制限するものである以上、立法裁量の範囲内ということはあり得ない等と主張する。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
【筆者】
「原告らは、本件諸規定は、同性愛者の婚姻の自由を直接制限するものである以上、立法裁量の範囲内ということはあり得ない等と主張する。」との記載がある。
しかし、そもそも法律は個々人が「同性愛者」であるか否かを審査して区別取扱いをしていないのであるから、「同性愛者」を称する者に対して婚姻制度の利用を制限しているという事実はない。
「同性愛者」を称する者も、婚姻制度を利用すること自体は自由である。
また、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を満たすことを目的として立法された制度ではないし、「性愛(性的指向)」に従って婚姻することを正しい価値観であると定めているわけでもない。
「性愛(性的指向)」に従った結果として「婚姻」に至ることに価値があると考えるか否かは、個々人の思想・信条によるものであり、一つの価値観の在り方ということである。
「立法裁量の範囲内」との部分であるが、憲法24条には「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言があり、これが「男女二人一組」(一夫一婦制)に限定し、立法裁量の限界を画する趣旨である場合には、「男女二人一組」に当てはまらない人的結合関係については「婚姻」とすることはできない。
そうなると、そもそも「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについての「立法裁量」も存在しないという場合もあり得る。
しかし、前記(2)で説示したとおり、同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障された権利とまではいえない以上、同性間の婚姻が認められていないというだけで直ちに本件諸規定が憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。そして、同性カップルの公認に係る利益は人格的利益として尊重されるべきであるものの、このような憲法上の権利とまでいえない婚姻及び家族に関する人格的利益の実現の在り方については、前記のとおり、その時々の社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において判断される必要がある。特に、この問題は婚姻制度全体に関わる国民全体の問題であり、国会での多方面にわたる検討と判断が必要なものである。そうすると、本件諸規定の制定や改廃について立法裁量に委ねられていると解することは、同項の趣旨にも合致するものといえる。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「前記(2)で説示したとおり、同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障された権利とまではいえない以上、同性間の婚姻が認められていないというだけで直ちに本件諸規定が憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。」との記載がある。
まず、憲法24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される規定であり、「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば、法律上の「家族」とも言えないのであり、24条2項は適用されない。
次に、「本件諸規定が憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。」の部分を検討する。
24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚した法律となるように求めており、これらを満たさない場合には「裁量の範囲を逸脱している」ことになるものである。
しかし、「同性間」の人的結合関係については、「婚姻及び家族に関するその他の事項」に当たらないのであるから、そもそも24条2項が適用される事例ではない。
そのため、この文が「憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。」のように、24条2項が適用される事柄について検討される「裁量の範囲を逸脱している」か否かの次元で論じようとしていることは、そもそも24条2項が適用される事例ではないという点で、24条2項の解釈における前提を誤っている。
「同性カップルの公認に係る利益は人格的利益として尊重されるべきであるものの、このような憲法上の権利とまでいえない婚姻及び家族に関する人格的利益の実現の在り方については、前記のとおり、その時々の社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において判断される必要がある。」との記載がある。
まず、「同性カップル」であるが、これは「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成しているというだけであるから、その一人一人について「婚姻していない者(独身者)」として考える必要がある。
この観点から、「婚姻していない者(独身者)」については、「婚姻していない者(独身者)」として社会の中で認識されているのであるから、その状態で既に完全な状態である。
その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成することは自由であり、憲法21条の「結社の自由」によっても保障されている。
そして、この判決は「婚姻制度を利用する者(既婚者)」は「公認に係る利益」や「人格的利益」を得ているというのであるが、「婚姻している者(既婚者)」は社会的に「婚姻している者(既婚者)」として認識され、「婚姻していない者(独身者)」は社会的に「婚姻していない者(独身者)」として認識されているというだけのことであり、その違いに法律論上の「利益」と呼べるだけのものがあるのか疑問である。
また、何らかの法律上の効果による「利益」があるとしても、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段としてどのような法的効果を設定するかの問題であり、その制度の対象者とならない者に対しては、そのような効果が与えられないことは政策的な制度である以上は当然に予定されていることである。
その立法目的とそれを達成するための手段の当否の問題を論じることもなく、婚姻制度によって得られる何らかの「利益」を、制度の対象とならない者の人的結合関係に対しても同様に与えなければならないということにはならない。
よって、ここでは「同性カップルの公認に係る利益は人格的利益として尊重されるべきであるものの、」と述べられているが、同性間の人的結合関係については、婚姻制度の対象ではないのであるから、この人的結合関係に対して婚姻制度から得られる「利益」を「尊重されるべき」ということにはならない。
これは何も「同性間の人的結合関係」に限られるものではなく、「三人以上の組み合わせ」、「近親者との人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても同様である。
婚姻制度の対象とならない者に対して、婚姻制度を利用する者が得ている「利益」を同様に与えなければならないということにはならないのであり、それを得られることを前提として「尊重されるべき」というものでもないのである。
この文は、「同性カップルの公認に係る利益は人格的利益」と考え、それが「憲法上の権利とまでいえない婚姻及び家族に関する人格的利益」である旨を述べている。
しかし、「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」ではない。
また、ここでいう「家族」とは日常用語としての共同生活者を指すものではなく、法律上の「家族」をいうものであるから、婚姻制度の立法目的を実現することを中心として、その目的を達成することを阻害しない範囲で規律されている枠組みによる法律上の「家族」を指すものであり、「同性間」の人的結合関係がこの範囲に当てはまる「親子」や「兄弟」、「姉妹」などの関係に当てはまらないのであれば、それはここでいう「家族」にも当てはまらない。
よって、ここでいう「同性カップル」については、法律論上の「婚姻及び家族」ではないのであり、「同性カップル」と称する人的結合関係が「婚姻及び家族に関する人格的利益」を有する関係の中に含めて考えることができるかのような前提で論じていることは誤りとなる。
「前記のとおり、その時々の社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において判断される必要がある。」との部分は、この判決の下記の部分の「夫婦別姓訴訟」の判断枠組みからの引用と思われる。
2(3)ア
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。……(略)……(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集第69巻8号2586頁参照)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しかし、この判断枠組みは24条2項が「婚姻及び家族に関するその他の事項」と定めていることに従って、その「婚姻及び家族に関する事項」に当てはまる事例の内部の問題について、この判断枠組みを用いて憲法適合性を判断することを論じるものである。
「同性カップル」と称する同性間の人的結合関係については、そもそも「婚姻」はないし、この「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で形成されている法律上の「家族」の範囲にも含まれない事例であり、これを「婚姻及び家族に関する事項」の内部の問題であるかのように考えて、この24条の解釈についての「夫婦別姓訴訟」の判断枠組みを用いて論じることができるものではない。
これについては、何も「同性間の人的結合関係」に限られるものではなく、「三人以上の人的結合関係」についても同じである。「三人以上の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で形成されている法律上の「家族」の範囲にも含まれない事例であるから、これを「婚姻及び家族に関する事項」の内部の問題として、24条の解釈についての「夫婦別姓訴訟」の判断枠組みを用いて論じることはできないのである。
他にも、「同居人」「シェアハウス仲間」「サークル」「組合」「雇用」「会社」「宗教団体」「学校」などの人的結合関係についても、同様に「婚姻及び家族に関する事項」としては扱うことはできない。
この判決のような主張に従えば、これらすべての人的結合関係についても、その人的結合関係を原因とする形で「婚姻及び家族に関する人格的利益」を有するということになってしまい、妥当でないのである。
「特に、この問題は婚姻制度全体に関わる国民全体の問題であり、国会での多方面にわたる検討と判断が必要なものである。」との記載がある。
しかし、先ほども述べたように、「憲法上の権利とまでいえない婚姻及び家族に関する人格的利益の実現の在り方」というものは、憲法24条2項のいう「婚姻及び家族に関するその他の事項」に当てはまるものについて判断されるものであり、これに当てはまらないものについては「憲法上の権利とまでいえない婚姻及び家族に関する人格的利益」を有していないのであるから、その「実現の在り方」を論じることもできない。
よって、「同性間」や「三人以上の人的結合関係」については、そもそも「婚姻」ではないし、「婚姻」の立法目的の実現を中心として、その達成を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」にも含まれない。
ここでは、「この問題は婚姻制度全体に関わる国民全体の問題であり、国会での多方面にわたる検討と判断が必要なものである。」と述べているが、確かにある人的結合関係が、憲法24条2項のいう「婚姻及び家族に関するその他の事項」を制定することによって達成しようとしている立法政策を阻害するような影響を及ぼすものとなっていないかについて、「婚姻制度全体」との整合性の観点から検討していく必要は考えられる。
しかし、この論旨があたかも「同性間」について憲法24条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」の中に含まれるかのような理解を前提として、「婚姻制度全体」との整合性を検討する必要があると述べているものであれば、誤りとなることに注意が必要である。
「本件諸規定の制定や改廃について立法裁量に委ねられていると解することは、同項の趣旨にも合致するものといえる。」との記載がある。
しかし、法律上の婚姻制度の「制定」については、憲法24条が要請しているのであるから、制定しないという「立法裁量」は存在しないのであり、「制定」について「立法裁量に委ねられている」と解することは誤りとなる。
次に、「改廃」の廃止の部分であるが、婚姻制度は憲法24条が要請しているのであるから、廃止する場合には憲法改正が必要であり、これをしないままに廃止することを国会の「立法裁量」と解することは誤りである。
三つ目に、「改廃」の改正の部分であるが、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」「離婚」「個人の尊厳」「両性の本質的平等」の文言によって、「男女二人一組」の形に限定している場合には、「男女二人一組」の枠組みを変更することはできない。そのため、その場合には法律上の婚姻制度を改正するためにはそれ以前に憲法改正が必要なるため、国会の「立法裁量」と解することはできない場合がある。
(オ) また、原告らは、婚姻に準ずる制度の構築を求めているのではなく、原告らが求めるのは本件諸規定が規定する現行の婚姻制度へのアクセスである旨を主張し、別の制度を設けることは、かえって差別を助長すると主張する。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
【筆者】
まず、婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みを設け、これに当てはまる場合には制度を利用することができ、それに当てはまらない場合には制度を利用できないとしているものである。
そのため、婚姻制度の要件に当てはまる者であれば、誰でも婚姻制度を利用することができるし、要件に当てはまらないのであれば、誰もが利用することはできない。
このことは、婚姻制度に限られるものではなく、自動車運転免許などの他の制度においても同様である。
あらゆる制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが設けられており、それに当てはまる形で制度を利用することができ、それに当てはまらない場合には制度を利用できないとするものである。
制度が政策的な目的をもって定められているものである以上、その制度の要件を満たさない者は、制度を利用できないことは当然である。
そして、婚姻制度はもともと「性愛(性的指向)」を保護することを目的として定められた制度ではないし、「性愛(性的指向)」を満たすことを目的とする「婚姻」を勧めるものでもないし、婚姻制度を利用する者がいかなる「性愛(性的指向)」を有しているかを審査することもしていない。
そのため、婚姻適齢等の要件をクリアしているのであれば、個々人は誰でも「現行の婚姻制度へのアクセス」が可能となっており、この点に「差別」は存在しない。
婚姻制度への「アクセス」は、婚姻制度の要件に合致する形で認められているのである。
特定の思想や信条を保護することを目的として法制度を立法することは、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条との間で14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。
そのため、特定の「性愛(性的指向)」を保護することを目的として法制度を立法することはできない。
この部分の論旨は、婚姻制度があたかも「異性愛」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的とした制度であるかのような理解に基づいて、それと比べて「同性愛」という思想や信条も同様の形で保護するべきであるから、「同性愛」という思想や信条について異なる制度とすることは「差別」となると論じるものである。
しかし、そもそも婚姻制度が「異性愛」という特定の思想や信条を保護することを目的とした制度であれば、既に憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条との間で14条の「平等原則」にも抵触して違憲となるのであり、婚姻制度そのものが無効となる。
そのため、「異性愛」という思想や信条を保護することを目的として法制度を立法することができるとの前提に立ち、「同性愛」についても「異性愛」という思想や信条と同様に扱わなければならないとの主張については、そもそもそのような特定の思想や信条を保護することを目的として法制度を立法することはできないという点によって退けられるものである。
このことは、ここでいう「婚姻に準ずる制度」や「別の制度」についても同様である。
しかし、そもそも婚姻をするについての自由は、いつ誰と婚姻をするかを自由に決定することのできる自由であって、婚姻当事者に婚姻制度の内容を自由に定める権利が保障されているものではないのと同様、同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度についても、当事者がその内容を自由に定めることができるものではない。公認に係る利益を実現するために、現行の婚姻制度、婚姻に準ずる婚姻類似の別の制度その他どのような制度が適切であるかは、民主的過程で議論され判断される必要があることは既に述べたとおりである。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
【筆者】
「そもそも婚姻をするについての自由は、いつ誰と婚姻をするかを自由に決定することのできる自由であって、婚姻当事者に婚姻制度の内容を自由に定める権利が保障されているものではないのと同様、同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度についても、当事者がその内容を自由に定めることができるものではない。」との記載がある。
しかし、論理的な筋道がよく分からない。
憲法24条2項の要請に従って定められた法律上の婚姻制度について、憲法24条1項が「婚姻するについての自由」を保障していることは、婚姻制度を利用するか否かに関する自由の保障であって、「婚姻制度の内容を自由に定める権利」を保障しているものではないというのは理解できる。
しかし、これと「同様、」との文言を繋ぐのであるが、何が「同様」なのかよく理解することができない。
同様に考えれば、まず憲法上の要請として「同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度」を創設することが求められているはずであるが、憲法上にそのような規定はない。
この判決では24条2項に定められた「個人の尊厳」の趣旨から「同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度」を導き出そうとしているのかもしれないが、24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」に関して「個人の尊厳」に立脚して制定されなければならないことを求め、立法裁量の限界を画するものであり、「婚姻及び家族に関するその他の事項」に当てはまらないものに対しては適用されない。
「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」ではないし、この「婚姻」という立法政策の達成を阻害することのない形で規律される「家族」の範囲にも含まれていない。
よって、「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」については、24条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含まれておらず、24条2項に示された「個人の尊厳」の文言も適用されない。
そのため、24条2項の「個人の尊厳」から「同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度」を導き出すことはできない。
さらに、「同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度」を利用するについての自由を定める規定も憲法上に存在していない。
そのことにより、「婚姻をするについての自由」が「婚姻制度の内容を自由に定める権利」とは異なることに照らし合わせる形で論じようにも、そもそも憲法上には「同性カップルのために公認に係る利益を実現するための制度」を利用するについての自由を定める規定は存在しないため、「その内容を自由に定めることができるものではない。」という論じ方と同様には説明できないのである。
もう一つ、一段落前の文では、婚姻制度と別の制度を立法することの是非について主張されているものであるが、ここでは婚姻制度と別の制度を立法することについては既に「是」となっていることを前提として、その「内容を自由に定める」ことができるかどうかという問題に答えようとするものとなっている。
これは、一つ前の段落の文を「問」と考えると、「問」と「答え」が噛み合っていないのである。
そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛(性的指向)」を満たすための「婚姻」を勧めるものでもない。
また、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条を保護するために制度を立法することは、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条との間で憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのことから、婚姻制度や「婚姻に準ずる制度」(別の制度)についても、特定の思想や信条に着目して立法することはできないという前提があるのだが、ここの部分で「問」と「答え」が噛み合わない議論をしていることも疑問である。
「公認に係る利益を実現するために、現行の婚姻制度、婚姻に準ずる婚姻類似の別の制度その他どのような制度が適切であるかは、民主的過程で議論され判断される必要があることは既に述べたとおりである。」との記載がある。
しかし、そもそも憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、単体の個人の状態で既に完全な状態として取り扱われている。
そのことから、「婚姻していない者(独身者)」という状態のままで既に「公認」されているともいうことができる。
この完全な状態の「個人」は、既にそのままで公認されているともいうことができることから、日本国憲法の下で「個人」が公認されていないかのような前提に基づいて、人的結合関係を形成した者に対して新たにここでいう「公認に係る利益」にあたる別の「利益」を与えなければならないということにはならない。
また、一文前の文には「同性カップルのために」との記載もあるが、それは完全な状態である「個人」と「個人」が人的結合関係を結んでいるというだけである。
これは、「個人」が集まることにより、「同性トリオ」「同性四人組」「男女トリオ」「男女四人組」「三人以上の組み合わせ」などの人的結合関係を結んでいる場合も同様である。
何らかの立法目的とそれを達成するための手段の当否の問題を越えて、単なる個々人が集まって形成された人的結合関係に対して「利益」(ここでいう『公認に係る利益』にあたるもの)を与えなければならないということにはならないのである。
他にも、「同性カップル」という「同性間」の「二人一組」の人的結合関係だけを取り上げて「公認に係る利益」と称するものを与えるべきかを論じ、それ以外の人的結合関係に対して「公認に係る利益」と称するものを与えるべきかを論じていないことについては、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている点で妥当でない。
そのため、ここでは「公認に係る利益を実現するために、現行の婚姻制度、婚姻に準ずる婚姻類似の別の制度その他どのような制度が適切であるかは、」と述べるのであるが、そもそも婚姻制度によって得られる利益は婚姻制度の立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、この立法目的とそれを達成するための手段としての枠組みの当否の問題を越えて、婚姻制度の対象にならない者に対して婚姻制度により得られる「利益」を与えなければならないことにはならないのであり、ここでいう「公認に係る利益」と称するものが存在するとしても、婚姻制度の対象とならない者に対してそれを与えなければならないことはならない。
よって、立法目的とその達成するための手段の当否の問題との整合性を示すことなく、「公認に係る利益」を与えなければならないことを前提として「どのような制度が適切であるか」を論じるべきであるという方向性を示すことについても、妥当でない。
婚姻制度の立法目的を達成するためには、婚姻制度の対象外の者に対して積極的な「利益」を与えないことこそが、婚姻制度の立法目的を達成することに資するという結論が導き出されることもあり得るのである。
かえって、現行の婚姻制度には、嫡出推定の規定等、その重要部分において、夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定もあり、これらの規定の存在は婚姻制度全体と密接不可分に結びついているとも考えられることからすると、本件諸規定を違憲無効とすることにより、現行の婚姻制度を現状の法制度のままの形で同性カップルに開放することが相当であるとは直ちにはいい難い。現在、「同性同士の結婚」ないし「同性婚」に賛成であるとの国民の意見が比較的多数となっている旨の調査結果が様々な統計から出されているが(認定事実(6))、これらの調査において、必ずしも「同性同士の結婚」や「同性婚」の意味内容が一義的に定義されていたとはいえない以上、賛成意見の中には、現行法上の「婚姻」制度と、婚姻類似の新たな制度とが厳密に区別されずに回答されたものが含まれている可能性も否定できない。また、同性愛者やLGBTを対象としたアンケートによっても、法的保護の在り方については様々な意見があることが認められる(認定事実(6)) 。さらに、同性カップルの法的承認や保護の制度があるとされる諸外国や地域においても、その保護の方法は、同性間の婚姻制度を採用する国等もあれば、登録パートナーシップ制度等を採る国、これらを併用する国等様々であって、その採用までの経緯も必ずしも一律ではない(認定事実(3))。
【論点番号】
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
【筆者】
「現行の婚姻制度には、嫡出推定の規定等、その重要部分において、夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定もあり、これらの規定の存在は婚姻制度全体と密接不可分に結びついているとも考えられることからすると、本件諸規定を違憲無効とすることにより、現行の婚姻制度を現状の法制度のままの形で同性カップルに開放することが相当であるとは直ちにはいい難い。」との記載がある。
「現行の婚姻制度には、嫡出推定の規定等、その重要部分において、夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定もあり、これらの規定の存在は婚姻制度全体と密接不可分に結びついているとも考えられる」との理解はその通りである。
また、婚姻制度の中には「重婚(民法732条)」や「近親婚(民法734条)」を認めていない規定や、「婚姻適齢(民法731条)」の規定があるなどからすれば、下記の要素を立法目的としていると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」として認めることや優遇措置を与えてインセンティブを与えることは、これらの目的を達成することを困難とするため、妥当でないのである。
また、「婚姻」という制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、国家政策として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する形で、これらの目的を達成するための手段として形成されているものであるから、あらゆる人的結合関係を「婚姻」の中に含めることができるという性質のものではなく、「婚姻」であることそれ自体で、「婚姻」の中に入れることのできる人的結合関係と「婚姻」の中に入れることのできない人的結合関係とがあり、内在的な限界がもともと備わっていることも考えられる。
そして、憲法24条が「婚姻」を定めていることからすれば、憲法24条の文言の中にもその「婚姻」に内在する限界が含まれていることも考えられ、これによれば、ここでいう「同性カップル」という同性間の人的結合関係については、「婚姻」として扱うことはできないという場合も考えらる。
この判決では「現行の婚姻制度を現状の法制度のままの形で同性カップルに開放すること」が可能な場合があることを前提として論じているが、そもそも「婚姻」という制度そのものの意味や、それを引き継ぐ憲法24条の「婚姻」という文言それ自体において、また、憲法24条の「両性」「夫婦」の文言によって、同性間の人的結合関係については、「婚姻」とすることができない可能性もあることを押さえる必要がある。
これは、他の人的結合関係とは区別する形で設けられている「婚姻」という概念を成り立たせる境界線となる一線を損なった場合には、「婚姻」という概念そのものが成り立たなくなるのであり、「婚姻」という枠組みそのものを他の人的結合関係との間で区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが雲散霧消してしまうからである。
「違憲無効とすることにより、」との部分であるが、「2(3)イ(エ)」の部分で、既に「前記(2)で説示したとおり、同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障された権利とまではいえない以上、同性間の婚姻が認められていないというだけで直ちに本件諸規定が憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。」と結論が出ているのであるから、本件諸規定は「違憲無効」ではないのであり、なぜ「違憲無効」ではないものに対してさらに「違憲無効とすることにより、」という検討を行っているのか意味が分からない。
「違憲無効」ではないとの結論が出ている事柄に対して、現在の法制度の枠組みが変更された場合の影響を検討しようとしているということは、これは法規範に適合するか否かを審査するものではなく、政策的に相当か否かについて論じるものということができる。
そうなると、それは立法府や行政府の政治部門に委ねるべき問題であり、司法府の裁判所において論じる必要のある対象ではない。
また、そもそも24条2項の「個人の尊厳」は、24条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対してのみ適用される条文であり、この「個人の尊厳」の文言を適用することによって「違憲無効」となる場合を考えようとしても、前提として同性間の人的結合関係が「婚姻及び家族に関するその他の事項」に当てはまっていることが必要である。
しかし、同性間の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」や「兄弟」、「姉妹」などの中に含まれないのであれば、法律上の「家族」ともいえない。
そのため、ここでいう同性間の人的結合関係については、24条2項の「個人の尊厳」の文言は適用されない事例であり、これが適用される余地があるかのような前提によって「違憲無効とすることにより、」と論じることは、解釈の過程を誤っている。
さらに、この文の論じ方は、「違憲無効」として「現行の婚姻制度を現状の法制度のままの形で同性カップルに開放」した場合に「夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定」との間で問題を生じるから、「違憲無効」とはならないとの論じ方となっている。
しかし、婚姻制度には立法目的が存在しており、その目的を達成するための手段として枠組みが定められているものであるから、現在定められている枠組みが妥当であるか否かについては、立法目的に合理性があるか、また、その目的を達成するための手段としての枠組みに合理性があるかという観点から判断する必要がある。
つまり、本来は「夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定」が達成しようとしている目的を特定し、その目的の達成を阻害する関係に対して優遇措置を行うことはできないことから、「違憲無効」とはならないと論じる必要があるのである。
しかし、「夫婦が自然生殖可能であることを前提に作られた規定もあ」ることから、「現行の婚姻制度を現状の法制度のままの形で同性カップルに開放することが相当であるとは直ちにはいい難い。」というだけでは、婚姻制度の枠組みがどのような目的を達成するために形成されているのか十分に説明しているとはいえない。
「同性カップルに開放することが」との部分であるが、人的結合関係の中には「三人一組」の「トリオ」もいるし、「四人一組」の者もいるのであり、「同性カップル」というように、「カップル」という「二人一組」のみに「開放する」か否かだけを論じようとしている点で、「カップル信仰論」に陥っている。
「また、同性愛者やLGBTを対象としたアンケートによっても、法的保護の在り方については様々な意見があることが認められる」との記載があるが、前提認識に問題がある。
まず、法律論としては、国民を個々人の思想や信条に着目して区別取扱いをしてはならない。そのため、「同性愛者」や「LGBT」という思想や信条を抱く者を区別取り扱いをするような制度を立法してはならないのであり、現在の制度が「同性愛者」や「LGBT」という思想や信条を抱く者を区別していることを前提としたり、また、区別取扱いがされているという理解を正当化できることを前提として論じてはならない。
また、婚姻制度は「異性愛」という特定の思想や信条に着目して「法的保護」を行うことを目的とした制度ではない。
そのような形で特定の思想や信条に対して「法的保護」を行うことを目的とする法制度を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
他にも、特定の思想や信条に対して「法的保護」を行うことを目的とする法制度を立法することは、他の思想や信条との間で14条の「平等原則」に反して違憲となる。
よって、この判決が個々人の内心に着目して「同性愛者」や「LGBT」という思想や信条を抱く者を区別取扱いをしても良いと考えていることが誤りであるし、特定の思想や信条を保護することを目的とする法制度を定めても良いと考えていることも誤りである。
「同性カップルの法的承認や保護の制度があるとされる諸外国や地域においても、その保護の方法は、同性間の婚姻制度を採用する国等もあれば、登録パートナーシップ制度等を採る国、これらを併用する国等様々であって、その採用までの経緯も必ずしも一律ではない」との記載がある。
まず、「諸外国や地域」と日本国との間では社会事情が異なることから、そこで課題となる問題も異なっており、それらの課題を解決することを意図して法制度を構築する際の立法目的も異なっている。
そのため、外国の法制度と日本国の法制度を比較する際には、外国語を翻訳する際に、翻訳者がある制度に対して「婚姻」という言葉を当てて説明しているからといって、日本国の法制度における「婚姻」と同一のものを指していることにはならないことに注意が必要である。
それぞれ「諸外国や地域」の社会事情の中で課題となる問題を解決することを意図してそれらの法制度が構築されているだけであり、その立法目的やそれを達成するための手段・方法には様々な違いがあるからである。
ここでは「同性カップル」のように「カップル」という「二人一組」のみを取り上げているが、国によっては「男性一人と女性四人までの人的結合関係」(一夫多妻)を制度としている場合もある。
「権利能力」を有する個々の自然人をどのように法的に結び付けるかという論点において、あたかも「カップル」という「二人一組」であることが絶対的な前提であるかのように考える「カップル信仰論」に陥らないように注意する必要がある。
加えて、別の制度を創設したからといって、原告らの主張するような同性愛者への差別が助長されるとは必ずしもいえない。実際、我が国においても近年地方公共団体の登録パートナーシップ制度が増加しているが、原告らの主張によっても、これらの制度によって同性カップルに対する差別や偏見は解消されつつあるというのである。差別や偏見の真の意味での解消は、むしろ民主的過程における自由な議論を経た上で制度が構築されることによって実現されるものと考えられる。
【論点番号】
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「別の制度を創設したからといって、原告らの主張するような同性愛者への差別が助長されるとは必ずしもいえない。」との記載がある。
まず、法制度は特定の思想や信条を保護することを目的として立法してはならない。
それをした場合には憲法20条1項後段・89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
そのため、「同性愛」という思想や信条に着目して法制度を立法することは違憲となる。
そのことから、そのような内容を持つ制度を婚姻制度としても、ここでいう「別の制度」としても立法することはできない。
また、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないから、「異性愛」や「同性愛」の思想や信条についても、区別して取扱いをしているという事実はない。
そのため、法制度上において「異性愛者」を称する者も「同性愛者」を称する者も、その他の「性愛」を有すると称する者も、そのような分類を用いない者も、「キリスト教徒」も「イスラム教徒」も「仏教徒」も「神道を信じる者」も「武士道を重んじる者」も「無宗教の者」も区別して取扱われている事実はなく、差別は存在しない。
むしろ、婚姻制度が「性愛(性的指向)」を保護することを目的として立法されていると考えて、婚姻制度が「男女二人一組」であることは、「異性愛」を保護するものであるという誤った理解こそが、「異性愛」を優越した思想や信条であるとする価値観に結び付くことになり、その他の「性愛」に対する「差別」を引き起こす原因となるものである。
婚姻制度と「性愛(性的指向)」の間に直接的な関係がないことを理解することこそが、「性愛(性的指向)」という思想や信条の在り方の間に優劣はないことを明らかにし、特定の価値観の優劣を争い合うことから生じる「差別」を解消することに繋がることになる。
それにもかかわらず、この判決は婚姻制度は「異性愛」の思想や信条を抱く「異性愛者」のための制度であるかのような前提で論じたり、その他の「性愛」の思想や信条を抱く者を別の制度によって保護することを提案することは、そもそも個々人の内心に属する思想や信条によって区別取扱いを行うものであるから、憲法20条1項・89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となるし、制度と特定の価値観を結び付けて考える者の主張に与し、特定の価値観の優劣を争い合うことから生じる「差別」を助長する原因となるものである。
この判決では「差別が助長されるとは必ずしもいえない。」と述べるのであるが、法制度と個々人の内心における思想や信条を結び付けて考えているこの判決の立場こそが、「差別」を「助長」する原因となるものである。
「我が国においても近年地方公共団体の登録パートナーシップ制度が増加しているが、原告らの主張によっても、これらの制度によって同性カップルに対する差別や偏見は解消されつつあるというのである。」との記載がある。
まず、憲法20条1項・3項、89条には「政教分離原則」が定められており、「同性愛」という特定の思想や信条を保護することを目的として制度を立法することは違憲となる。
また、特定の思想や信条を保護することは、他の思想や信条との間で憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
他にも、個々人の抱く思想や信条によって区別取扱いをすることは、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
そのことから、「地方公共団体の登録パートナーシップ制度」が「同性愛」という思想や信条に着目して分類された「同性愛者」にあたる者を対象とした制度となっていれば、違憲となる。
よって、「これらの制度によって同性カップルに対する差別や偏見は解消されつつある」との意味が、「同性愛者」を対象とした制度となっていることにより、「同性愛者」に対する「差別や偏見」が「解消されつつある」と述べているのであれば、そもそもその法制度は違憲である。
法制度は思想や信条に対して中立的でなければならず、特定の思想や信条を取り上げて制度化したり、その制度を利用する者に対して一定の優遇措置を設けていること自体が違憲となるからである。
「差別や偏見の真の意味での解消は、むしろ民主的過程における自由な議論を経た上で制度が構築されることによって実現されるものと考えられる。」との記載がある。
しかし、「差別や偏見」を「真の意味」で「解消」するためには、法制度に特定の思想や信条を持ち込むような形で立法してはならないことを理解し、法解釈においても特定の思想や信条を反映した法制度が存在することを許してはならないことを理解することである。
これを前提とせずに、婚姻制度が「異性愛」という特定の思想や信条を保護することを目的とした制度として存在していたとしても、それが許されるかのような理解をしていることは、特定の思想や信条に与することになるのであり、このような理解こそが「差別や偏見」を招くものである。
婚姻制度の立法目的は、下記の要素が考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
これらの立法目的を達成するための手段として、制度の枠組みが定められているのであり、「異性愛」という思想や信条を保護することを目的とする制度ではない。
この点を理解しなければ、婚姻制度の立法目的に「性愛(性的指向)」が関わっているかのように誤解をしていることを原因として、それら特定の思想や信条の優劣を争い合おうとする者の間で生じる「差別や偏見」を「真の意味」で「解消」することにたどり着くことはできない。
以上のとおりであるから、同性カップルの公認に係る利益の実現のためには、現行法上の婚姻制度そのものを適用する方法のみならず婚姻類似の制度を含めた幅広い検討がされるべきで、同性愛者らの中でもなお様々な意見があることにも照らすと、原告らが希望していないという理由だけで、婚姻類似の制度を構築するという選択肢を検討する余地がおよそなくなるとはいえない。
【論点番号】
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること
【筆者】
「同性カップルの公認に係る利益の実現のためには、現行法上の婚姻制度そのものを適用する方法のみならず婚姻類似の制度を含めた幅広い検討がされるべきで、」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は立法目的に従って、それを達成するための手段としての枠組みが設けられ、対象となる者(人的結合関係)を選び出している制度である。
そのため、その対象となる者について婚姻制度による「利益」を得ることができ、対象とならない者については婚姻制度による「利益」を得ることができないという差異が生じることは、立法段階で当然に予定されていることである。
そのため、婚姻制度の対象となっていない者に対して、婚姻制度による「利益」を与えなければならないということにはならない。
また、ここでいう「公認に係る利益」であるが、これは「婚姻制度を利用する者」が「婚姻している者(既婚者)」として認知されていることを意味するものであるが、「婚姻していない者(独身者)」についても「婚姻していない者(独身者)」として認知されているのであるから、「婚姻している者(既婚者)」だけが特別に得ている「利益」というわけではない。
日本国憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定しているのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態として扱われており、その地位に何らの不足もないのである。
さらに、もし「婚姻している者(既婚者)」だけに何らかの「利益」があるとしても、それは婚姻制度の立法目的に従って、それを達成するための手段として設けられた「利益」なのであり、その立法目的の達成に沿わない関係に対しても同様にその「利益」を与えなければならないということにはならない。
制度の対象外の者に対して、その制度の立法目的とそれを達成するための手段の枠組みの当否の問題を離れて、同様の「利益」を与えなければならないとの前提が、そもそも制度の目的を逸脱した考え方である。
これは、法制度が予定しておらず、もともと存在しない利益を、裁判官個人の動機によって「利益」を与えるべきと考えて新たな法制度を立法するように促そうとするものであるから、裁判官個人の政治的な動機や恣意的な動機が含まれているように思われる。
他にも、ここでは「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて「公認に係る利益」の実現を検討するべきと述べるのであるが、婚姻制度の中に含まれない人的結合関係を取り上げるのであれば、「近親者との人的結合関係」や「三人以上の人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」など、他の人的結合関係についても同様に取り上げて「公認に係る利益」の実現を検討するべきと論じる必要がある。
これらの人的結合関係を差し置いて、「カップル」という「二人一組」の関係だけに着目して比較対象として取り上げようとすることは「カップル信仰論」に陥っていることになる。
「現行法上の婚姻制度そのものを適用する方法のみならず婚姻類似の制度を含めた幅広い検討がされるべきで、」との部分について検討する。
婚姻制度は立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが定められており、その立法目的の達成に沿わない人的結合関係については、婚姻制度の中に入れることはできない。
このような差異は、もともと「婚姻」自体が政策目的を実現するための手段として形成されている制度である以上は当然のことである。
また、婚姻制度は「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、その人的結合関係の中で抽象的・定型的に自然生殖を想定することができない場合には、「婚姻」として扱うことができないという場合もある。
これは、「婚姻」という概念自体の存在意義を保つための一線を損なった場合には、他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念自体が成り立たなくなり、雲散霧消してしまうからである。
これは、他の様々な人的結合関係とは区別する形で枠づけられた「婚姻」という概念そのものが内在的に有している限界である。
よって、ここは、ここでいう「同性カップル」という同性間の人的結合関係を「現行法上の婚姻制度そのもの」の中に組み入れることが可能であるかのように論じるのであるが、「現行法上の婚姻制度そのもの」には組み入れることができないとも考えられる。
また、「婚姻類似の制度」についても、そもそも婚姻制度を基準として考えている時点で、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害するような人的結合関係に対して制度を設けることはできないという限界が含まれているのであり、同性間の人的結合関係を「婚姻類似の制度」の中で扱うことはできない場合もあり得る。
また、「婚姻類似の制度」を創設した場合には、その「婚姻類似の制度」を利用することに安住する者が増えることよって、国民に対して婚姻制度を利用するように働きかけるインセンティブを損ない、婚姻制度を利用する者が減少し、婚姻制度が達成しようとしている立法目的を達成できない事態に陥ることがある。
そのため、そもそも婚姻制度の立法政策を実現するためには「婚姻類似の制度」を創設することはできないという結論が導かれることもあるのであり、「婚姻類似の制度」を創設することが可能であることを前提として論じていることも、結論を先取りしようとするものであり、妥当でない。
「同性愛者らの中でもなお様々な意見があることにも照らすと、」との部分について検討する。
まず、法律上は個々の自然人がどのような思想や信条、感情を有しているのかを審査していないのであるから、特定の思想や信条、感情を有している者を取り上げて、区別して論じるべきではない。
法律上は、「権利能力」を有する法主体としての地位を認められている者(あるいは法人)を、どのような法律関係で結び付けるかという視点から見る必要があり、ここでいう「同性愛者」などと、思想や信条、感情を入り混ぜる形で取り上げることはできない。
また、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、婚姻制度を利用する者が「異性愛者」であると考えていることも誤りである。
婚姻制度を利用する者が「異性愛者」であると考えてしまっていること自体が偏見であるし、「異性愛」や「同性愛」という思想や信条、感情によって分断や差別を生み出す原因となっているものである。
もともと婚姻制度が「性愛(性的指向)」を保護するための制度ではなく、婚姻制度を利用する者が「異性愛者」であると考えてしまっていることが誤解であることを認識すれば、最初から「異性愛」も「同性愛」もその他の「性愛」も法制度とは直接的な関係がないのであり、これらを取り上げて論じていること自体が法律論として妥当でないことが明らかとなる。
よって、法制度を論じる際に、特定の思想や信条、感情を結び付けることは誤りである。
また、特定の思想や信条を保護することを目的として法制度を立法した場合には、憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。他の思想や信条、感情との間でも、14条の「平等原則」に反して違憲となる。
そのため、「異性愛」や「同性愛」などの特定の思想や信条を取り上げて、婚姻制度や「婚姻類似の制度」などの法制度を立法することができるかのような前提で考えてしまっていることも誤りとなる。
「同性カップルの公認に係る利益の実現のためには、……(略)………婚姻類似の制度を構築するという選択肢を検討する余地がおよそなくなるとはいえない。」との論旨を検討する。
婚姻制度から得られる「利益」は、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられているものであり、その立法目的とそれを達成するための手段の当否の問題を越えて、制度の対象外の者に対して、「利益」を与えなければならないということにはならない。
よって、ここでいう「同性カップル」という同性間の人的結合関係に対して、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の枠組みの当否の問題を離れて、婚姻制度を利用することによって得られる「利益」(ここでいう『公認に係る利益』にあたるもの)を与えなければならないということにはならない。
この判決は、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段である枠組みが憲法に違反しないと結論付けているにもかかわらず、婚姻制度の対象外の者に対して婚姻制度の有している「利益」(ここでいう『公認に係る利益』にあたるもの)を与える必要があるかのような論じ方をしている点で、誤っている。
このような主張は、憲法やその他の法令に違反するか否かしか判断することができない司法権の範囲を越えて、立法裁量(憲法に抵触する場合には立法裁量がないこともある)に関わる問題について、特定の政治的な立場に与する形で論じようとするものであり、越権行為であると考えられる。
また、同性間の人的結合関係に対して婚姻制度から得られる「利益」を与えることは、婚姻制度の立法目的を達成することを阻害すること、他の婚姻できない人的結合関係との間で整合性がとれなくなることがあること、「婚姻」という概念に許容できる人的結合関係に内在的な限界があること、などの観点からできない可能性がある。
よって、婚姻制度の趣旨目的を引き継ぐことを意味する「婚姻類似の制度」によって、婚姻制度から得られる「利益」を与えることはできないという結論が導かれる余地がおよそなくなるとはいえない。
これらの検討をせずに、「現行法上の婚姻制度そのものを適用する方法」や「婚姻類似の制度」の創設が可能であるとする結論を先取りする形で論じている点で、妥当でない。
また、そもそも憲法に違反しない事柄であるにもかかわらず、立法政策(憲法に抵触する場合には立法裁量の余地もないことに注意)に口出ししようとしている点でも、司法権によって判断できる範囲を越えている。
(カ) さらに、原告らは、同性愛者は少数者であるから、その保護のための制度の構築を立法過程に期待することはできないと主張し、このような場合には、司法が、少数者の権利保護の観点から積極的に違憲審査を行い、本件諸規定の違憲を宣言することにより同性愛者を救済すべきである旨をいう。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
「原告らは、同性愛者は少数者であるから、その保護のための制度の構築を立法過程に期待することはできないと主張し、」との部分について検討する。
「同性愛者は少数者であるから、」との部分であるが、「同性愛」の思想や信条、感情を抱く「同性愛者」を称する者も、その内心は憲法19条の「思想良心の自由」によって完全に
保障されている。
そのため、そのような思想や信条、感情を抱く者が「少数者」であるとしても、その内心を侵すことはできず、もしそれを侵すような立法がなされた場合には、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となる。
「その保護のための制度の構築を立法過程に期待することはできない」との部分であるが、憲法19条で「思想良心の自由」が定められているのであるから、その内心そのものは既に保障されているということができる。
「同性愛」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的とした法律を立法することについては、憲法20条1項前段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、「同性愛」という特定の思想や信条・感情を保護することを目的とした法律を立法することは、他の思想や信条・感情との間で憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「司法が、少数者の権利保護の観点から積極的に違憲審査を行い、本件諸規定の違憲を宣言することにより同性愛者を救済すべきである旨をいう。」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は「異性愛者」や「同性愛者」やそれ以外の「性愛」を有するものであるのか、そのような分類を用いていない者なのかなど、個々人の内心を審査して区別取扱いをしているわけではないことから、「同性愛者」を称する者も、婚姻制度を利用する「権利」そのものは平等に有している。
そのため、ここでは「少数者の権利保護」と述べられているが、「同性愛者」を称する者も婚姻制度を利用する「権利」そのものは平等に有しているのであるから、これを制限されている者には該当せず、「少数者」とはいえず、大多数の国民と同様であるから、多数派ということができる。
そのことから、「少数者の権利」と考えようとしていることは理解を誤っている。
「同性愛者を救済すべき」の部分であるが、「同性愛」という思想や信条、感情を抱くことを法律の規定によって禁じられている場合には、憲法19条の「思想良心の自由」によって「同性愛」という思想や信条、感情を抱く「同性愛者」を称する者を救済するべき場合は考えられる。
しかし、この事例では、「同性愛者」を称する者も婚姻制度を利用することは可能であるため、「権利」が制限されているという性質のものではない。
また、婚姻制度は「国の立法目的」として「性愛」を保護することを目的とした制度ではないから、婚姻制度を利用する際に「個々人の利用目的」として「性愛」を満たすことを目的とするかどうかは個人の価値観によるものに過ぎない。
よって、法律論として婚姻制度が「同性愛者」と称する者であることを理由として利用の可否を区別しているものではないことから、「同性愛者」と称する者であることを理由として「救済すべき」とする憲法上の自由や権利があるわけではない。
このような主張について、国(行政府)は下記のように考えている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本件規定の憲法14条1項適合性の判断においては、現行の婚姻制度(異性婚)に加えて同性婚を認める法制度を創設しないことが問題となること
同性間の人的結合関係について「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれが妨げられないという意味における「婚姻をするについての自由」が憲法24条1項により保障されているとの前提をとり得ないことは、前記第2の1において述べたとおりである。そして、原告らが「婚姻の自由」として主張するものの内実は、「個人の尊厳」及び「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の婚姻制度の枠を超えて、同性問の人的結合関係についても婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならないのであって、国家からの自由を本質とするものということもできない。この点については、仮に本件規定が違憲無効であると判断されたとしても、現行の法律婚制度が違憲無効となるだけで、直ちに本件規定の下で同性婚が法律上可能となるものではないことをも加味すると、より一層明らかである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF (P10)
(これは大阪地裁ではなく、福岡地裁における国〔行政府〕の主張である。)
しかし、同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえない以上、同性間の婚姻が認められないことを憲法上保障された少数者の基本的人権が侵害されている場合と同等に考えることはできない。加えて、同性カップルの婚姻又は婚姻類似の制度を実現することと異性カップルの婚姻をするについての自由は利益が相反する関係にもないことなどからすれば、同性間の婚姻等の制度の構築に向けた立法が多数決の原理の下においては期待できないとは必ずしもいえない。実際、近年の調査によれば、同性カップルに婚姻等の法的保護の制度を認めるべきだとの回答をしている者が相当程度にまで増加してきている旨の結果も示されている。このように、民主的過程での議論の余地がある以上、これを措いて、現時点において司法が積極的に本件諸規定の違憲を宣言すべき状況にあるということはできない。
【論点番号】
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
【筆者】
「同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえない以上、同性間の婚姻が認められないことを憲法上保障された少数者の基本的人権が侵害されている場合と同等に考えることはできない。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを立法目的とはしていないし、「性愛」を満たすことを目的として「婚姻」することを求めるものでも、勧めるものでもない。
また、婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められ、その枠組みに当てはまる場合には制度を利用することができ、その枠組みに当てはまらない場合には制度を利用できないとしているだけである。
この婚姻制度の対象となるか否かを定める要件は、個々人の「性愛」がどのようなものであるかを審査して区別取扱いをするものではない。
よって、ここで「少数者」と述べている者は、一段落前の文の続きから「同性愛者」と称する者のことを指していると考えられるが、「同性愛者」と称する者も婚姻制度の要件に当てはまる形で婚姻制度を利用することができるのであるから、婚姻制度を利用するか否かの自由(婚姻をするについての自由)を有していることになる。
この意味で、「男女二人一組」の婚姻制度についての「婚姻をするについての自由」は「同性愛者」と称する者にも等しく与えられているのであり、「同性愛者」を称する者は「少数者」には該当しないし、「基本的人権が侵害されている」とも言えない。
よって、この文は、あたかも婚姻制度が「性愛」を保護することを目的として立法された制度であるかのように理解した上で、その中でも「異性愛」という思想や信条、感情を満たすための異性間の「婚姻をするについての自由」(婚姻制度を利用するか否かの自由)が憲法上保障されているが、「同性愛」という思想や信条、感情を満たすための「同性間で婚姻をするについての自由」については「憲法上保障されているとまではいえない」として、「同性間の婚姻が認められないことを憲法上保障された少数者の基本的人権が侵害されている場合と同等に考えることはできない。」と考えるものとなっているが、そもそも婚姻制度そのものが特定の思想や信条、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の思想や心情、感情に対して中立的な内容であることを理解しないものであり、結論を導くまでの判断の過程を誤っている。
「同性カップルの婚姻又は婚姻類似の制度を実現することと異性カップルの婚姻をするについての自由は利益が相反する関係にもないことなどからすれば、同性間の婚姻等の制度の構築に向けた立法が多数決の原理の下においては期待できないとは必ずしもいえない。」との記載がある。
ここでいう「同性カップル」と「異性カップル」を取り上げて「カップル」という単位を基にして比較をしようとするものであるが、「カップル間不平等論」の誤りがある。
婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みを定め、制度の対象者を選び出しているのであり、婚姻制度を構築する以前の段階には「二人一組」でなければならないとの前提は存在しないのである。
そのため、現在の「男女二人一組」の婚姻制度の枠組みに当てはまらない形の人的結合関係に対して何らかの制度を構築するか否かを検討する際には、「カップル」という「二人一組」の形に限られるもではなく、「三人以上の組み合わせ」についても同様に検討することが必要である。
それにもかかわらず、勝手に「カップル」という「二人一組」の単位を取り上げて、それを前提として比較対象としようとしている点で、なぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥っている。
結局、「カップル」という「二人一組」を前提としていること自体が、現在の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、それを真似るものとして何らかの制度を形成しようとするものに過ぎないのであり、その時点で、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として枠組みを設けていることの当否の問題を避けることはできないのである。
そして、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段には、下記が考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
この立法目的の達成を阻害することになる人的結合関係については、「婚姻又は婚姻類似の制度」を整備することはできない。
ここでは、「利益が相反する関係にもないことなどからすれば、」と述べられているが、「利益が相反する関係にもない」と言い切ることはできないと思われる。
現在の婚姻制度が「近親婚」や「重婚」、「複婚」を認めていないことは、これによって発生する社会的な不都合を抑制するためである。
そのため、「近親婚」や「重婚」、「複婚」を求める者と、それが含まれない婚姻制度を求める者との間には「利益が相反する関係」にあることになる。
同様に、同性間の婚姻を求める者と、それが含まれない婚姻制度を求める者との間には「利益が相反する関係」にあることも当然に考えられる。
そのため、「利益が相反する関係にもない」と断定することはできない。
「同性間の婚姻等の制度の構築に向けた立法が多数決の原理の下においては期待できないとは必ずしもいえない。」との部分について検討する。
婚姻制度の立法目的を達成することを阻害する関係に対しては、婚姻制度の対象者とすることはできないのであり、同性間の「婚姻」が可能となるかのような前提で論じることは結論を先取りしようとしているように見えるため適切ではない。
「民主的過程での議論の余地がある以上、これを措いて、現時点において司法が積極的に本件諸規定の違憲を宣言すべき状況にあるということはできない。」
━━24条2項の論点━━
24条2項の論点については、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」で詳述している。
確かに、我が国では、前記のとおり憲法24条1項が同性間の婚姻又は婚姻類似の制度の創設を禁止していないにもかかわらず、同性愛者らに対し、婚姻どころか、婚姻類似の別の制度の構築の動きでさえ本格化していないこともうかがわれる。しかし、同性間の婚姻について国会において議論されるようになったのは平成27年に至ってからであり(甲A11、12、60~62、312、318。なお、平成27年より前にこれに言及されたことはあったものの、議論された形跡は見当たらない。)、同性間の婚姻や同性カップルの法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民が今もなお少なからず存在している(平成27年の調査では、20代や30代など若年層においては上記に対する法的保護に肯定的な意見が多数を占めるものの、60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めているし、全年代で「無回答」も相当程度存在する。令和元年の調査では肯定的な意見が更に増加してはいるものの、60歳以上では、肯定的な意見が約47%であるのに対しなお約43%余の者が否定的な意見を有しており、無回答も一定程度存在している(認定事実(6))。さらに、「同性婚」や「同性同士の結婚」に賛成とする意見が多い旨のアンケートの結果も存在するものの(認定事実(6))、既に述べたように、これらの調査において「同性婚」等の意味が各回答者において統一的に捉えられていたとは必ずしもいい難い。)。これらの事情に照らせば、我が国において、同性愛についての理解が深まり、同性愛者にも婚姻と同等の法的保護を与えるべきとの機運は高まっているとはいえるものの、少なくともその方法についての議論はまだその途上にある。そうすると、現時点で法改正や新たな制度を設けることの具体的な検討がされていないからといって、必ずしも同性愛者の婚姻に関する権利が少数者の人権であるがために、その検討が遅れているとまではいえず、国会における今後の議論がおよそ期待できないということはできない。
【論点番号】
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
【筆者】
「憲法24条1項が同性間の婚姻又は婚姻類似の制度の創設を禁止していないにもかかわらず、」との記載がある。
━━24条1項の論点━━
(上記で既に解説済み)
24条1項の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるか否かについては、「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。
「同性愛者らに対し、婚姻どころか、婚姻類似の別の制度の構築の動きでさえ本格化していないこともうかがわれる。」との記載がある。
まず、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、制度を利用するにあたって、特定の「性愛(性的指向)」を有してることを求めたり、勧めたりする制度ではない。
そのため、「同性愛者」を称する者も「婚姻」することは可能である。「婚姻」する際に「性愛(性的指向)」に比重を置いて考えるかどうかは、個々人の価値観の問題ということである。
同時に複数人に対して「性愛」の感情を抱く者であったとしても、「男女二人一組」の形の婚姻制度を利用することはできるのであり、個々人の内心の問題と法制度を利用できるか否かという問題には直接的な関係はないのである。(不倫の事例を見れば明らかである。)
よって、「同性愛者らに対し、婚姻どころか、婚姻類似の別の制度の構築の動きでさえ本格化していない」というように、「同性愛者」を称する者が婚姻制度を利用することができないかのような前提で論じている部分は、誤りとなる。
また、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護するための制度ではないから、婚姻制度は「異性愛者」を対象とした制度として構築されているわけでもない。
そのため、婚姻制度が「異性愛者」のために構築された制度であることを前提として、それに対する形で「同性愛者ら」に対して「婚姻」や「婚姻類似の別の制度」を構築することが必要となるのではないかとの主張も、そもそも前提を誤っている。
ここでいう「同性愛者ら」と称する者について、「同性間の人的結合関係を『婚姻』とする法制度を立法することを希望する者」という意味に置き換えて考えたとしても、婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているのであり、その合理性や政策的な当否の問題を離れて、「同性間の人的結合関係を『婚姻』とする法制度を立法することを希望する者」に制度上の利益を与えなければならないということにはならない。
「同性間の婚姻や同性カップルの法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民が今もなお少なからず存在している」との記載がある。
しかし、「今もなお」というように、「同性間の婚姻や同性カップルの法的保護」は必ず認められるべきものであることを前提とし、時間が進めば必ず「否定的な意見や価値観」が消えてなくなるかのような形で、特定の政治的な立場に肩入れして論じるべきではないと考える。
このような論じ方によれば、「近親婚」や「重婚」、「婚姻適齢に満たない者との婚姻」についても同様に「否定的な意見や価値観を有する国民が今もなお少なからず存在している」と論じることも可能となってしまうのである。
婚姻制度の立法目的とその達成手段の当否の問題を越えて、勝手に「同性間の婚姻や同性カップルの法的保護」が正しいものであると決めつけて、「否定的な意見や価値観を有する国民」の立場を軽んじるような態度は控えるべきであると考える。
裁判所は司法権の行使に際して、特定の政治的な立場や価値観に与するべきではない。
「我が国において、同性愛についての理解が深まり、同性愛者にも婚姻と同等の法的保護を与えるべきとの機運は高まっているとはいえるものの、少なくともその方法についての議論はまだその途上にある。」との記載がある。
「同性愛者にも婚姻と同等の法的保護を与えるべきとの機運は高まっているとはいえるものの、」との部分であるが、そもそも婚姻制度は「同性愛者」と「異性愛者」について区別取扱いをしていないのであるから、「同性愛者」を称する者も婚姻制度を利用することができるのであり婚姻制度による「法的保護」は同等に得ることができている。
そのため、これを得ることができないという区別取扱いが存在することを前提として論じることは誤りである。
また、これを得ることができないかのような前提で、「婚姻と同等の法的保護を与えるべき」と論じていることからすると、「性愛(性的指向)」を満たすために「婚姻」することが正しい価値観であるとする裁判官個人の思想を露顕しているものとなっている。
このような考えは、「性愛(性的指向)」を満たすことを目的とせずに婚姻制度を利用している者の立場を不当に貶めるものであり、妥当ではない。
法制度は、制度を利用する者の思想や信条、感情、価値観に対して中立的でなければならない。法解釈においても同じである。
「必ずしも同性愛者の婚姻に関する権利が少数者の人権であるがために、その検討が遅れているとまではいえず、国会における今後の議論がおよそ期待できないということはできない。」との記載がある。
「同性愛者の婚姻に関する権利が少数者の人権であるがために」との部分について検討する。
まず、法律論上は「同性愛者」というように個人の思想や信条・感情に基づいて区別取扱いをしてはならないのであり、「同性愛者」という形で自然人を指し示してはならない。
このような形で個人の思想や信条・感情に基づいて区別取扱いをすることは、憲法19条の「思想良心の自由」や14条の「平等原則」に反して違憲となる。
また、「同性愛者」を称する者も現在の婚姻制度の枠組みに従う形で婚姻制度を利用することは可能であり、「同性愛者」を称する者が「婚姻に関する権利」を有していないわけではない。
「同性愛」の思想や信条・感情を抱く「同性愛者」を称する者であるとしても、婚姻制度は個々人がどのような「性愛(性的指向)」を抱くかを審査して区別取扱いをしていないし、そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とする制度でもないから、「同性愛者」を称する者も「婚姻に関する権利」の全部を有しているのである。
その現在の婚姻制度に従った「婚姻」を望むか否かの問題であり、望まないというのであれば、「婚姻に関する権利」は有しているが、個人の意思によって利用していないというだけである。
そのため、「同性愛者の婚姻に関する権利が少数者の人権であるがために」などと、「同性愛者」を称する者が「婚姻に関する権利」を有していないことを前提として説明していることは誤りである。
また、「同性愛者」を称する者も、婚姻要件を満たす他のすべての者と同様に「婚姻に関する権利」を有しているのであり、「少数者の人権」という性質のものではない。
次に、「同性愛者」であるか否かにかかわらず、「同性間」で「婚姻」を希望する場合についてであるが、これはこの判決の「2(3)イ(カ)」の部分で、「同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえない以上、同性間の婚姻が認められないことを憲法上保障された少数者の基本的人権が侵害されている場合と同等に考えることはできない。」と述べている通り、「憲法上保障された少数者の基本的人権」とはいえないのであるから、この意味でも「少数者の人権」という性質のものではない。
よって、「少数者の人権であるがために」というように「少数者の人権」との理解の下に論じようとしていることは誤りである。
以上によれば、今後の社会状況の変化によっては、同性間の婚姻等の制度の導入について何ら法的措置がとられていないことの立法不作為が、将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性はあるとしても、本件諸規定自体が同項で認められている立法裁量の範囲を逸脱しているとはいえない。
【論点番号】
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「今後の社会状況の変化によっては、同性間の婚姻等の制度の導入について何ら法的措置がとられていないことの立法不作為が、将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性はあるとしても、」との部分について検討する。
まず、「同性間の婚姻」については、既に「2(3)イ(エ)」の部分で「同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障された権利とまではいえない以上、同性間の婚姻が認められていないというだけで直ちに本件諸規定が憲法24条2項で認められている裁量の範囲を逸脱しているということはできない。」と述べているのであるから、24条2項に違反しないはずであり、「将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性はある」と述べている部分は判断枠組みとして論理に矛盾が存在し、誤っている。
次に、「……等の制度」であるが、24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される規定であり、同性間の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」「兄弟」「姉妹」などに当てはまらないのであれば、法律上の「家族」でもないため、24条2項が適用される事例ではないのであり、「将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性はある」と述べていることは誤りとなる。
「憲法24条2項に違反するものとして違憲になる」との表現があるが、文の意味が適切ではない。
「違憲」という言葉は、「憲法違反」の略である。
既に「憲法……に違反する」の文言が登場しているのであるから、そこに重ねて「違憲になる」と述べることは、「憲法……に違反するものとして『憲法違反』になる」と述べていることになるのであり、意味が重複している。
そのため、下記の(かっこ)に示した部分は不要である。
「将来的に憲法24条2項に違反する(ものとして違憲になる)可能性はあるとしても、」
判決文を書く際には、この点も厳密に考えて文言を整理していくべきである。
「本件諸規定自体が同項で認められている立法裁量の範囲を逸脱しているとはいえない。」との記載がある。
24条2項は「婚姻及び家族に関するその他の事項」について「個人の尊厳」と「両性本質的平等」に立脚した法律を制定することを求める規定であり、「立法裁量の範囲を逸脱している」場合とは、「婚姻及び家族に関するその他の事項」が「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を満たさない場合のことである。
しかし、「同性間」の人的結合関係については、「婚姻」ではないし、「婚姻」という制度の立法目的の実現を阻害しない範囲で規律される枠組みである「家族」の中の「親子」「兄弟」「姉妹」などにも当てはまらないのであれば、法律上の「家族」でもないのであり、「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含まれない。
そのため、そもそも24条2項が適用される事例ではなく、24条2項が適用されることを前提としてその「立法裁量の範囲を逸脱している」か否かを論じる場面ではない。
そのことから、24条2項が適用されることを前提として「同項で認められている立法裁量の範囲を逸脱しているとはいえない。」と論じている部分は、前提を誤っている。
3 本件諸規定が憲法14条1項に違反するかについて(争点(1)関係)
(1) 本件諸規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻は定めていないものである。そこで、原告らは、本件諸規定により、異性愛者は婚姻をすることができるのに対して同性愛者はこれをすることができず、婚姻の効果を享受できないという別異の取扱い(以下「本件区別取扱い」という。)が生じているとして、このことが憲法14条1項に違反する旨主張する。
【論点番号】
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
④ 区別取扱いが存在しないこと
【筆者】
「本件諸規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻は定めていないものである。」との記載がある。
その通り、婚姻制度は「男女二人一組」のみを定め、それ以外については定めていないものである。
「相手や仲間のいない一人だけ」や「同性だけの二人以上の組み合わせ」、「男女を含む三人以上の組み合わせ」については、「婚姻」としては定めていない。
また、「近親者」や「婚姻適齢に満たない者」との間でも「婚姻」としては定めていない。
この「男女二人一組」という枠組みは、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として定められているものである。
婚姻制度の目的は、下記が考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するための手段として「男女二人一組」の形とすることに合理性が認められるため、「男女二人一組」としているものである。
これらの立法目的と、それを達成するための手段としての整合性を離れて、勝手に「二人一組」という枠組みが根拠もなく存在するわけではない。
そのため、ここでは「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」のように、「二人一組」の形だけを比較する形で論じているが、現在の法制度に存在しない組み合わせを取り上げて比較するのであれば、「二人一組」に限らず、「三人一組」や「四人一組」などの様々な人的結合関係との比較も同様に行う必要がある。
そうでなければ、14条の適合性審査を行う余地があるとしても(24条で『男女二人一組』〔一夫一婦制〕に限られており、14条適合性を審査できない可能性がある)、立法目的の合理性と、それを達成するための手段の合理性を審査する際に、網羅的な検討を行ったことにはならないからである。
「異性間の婚姻」と「同性間の婚姻」のように、「二人一組」だけを取り上げて論じようとすることは、「カップル信仰論」に陥るため注意が必要である。
「原告らは、本件諸規定により、異性愛者は婚姻をすることができるのに対して同性愛者はこれをすることができず、婚姻の効果を享受できないという別異の取扱い(以下「本件区別取扱い」という。)が生じているとして、このことが憲法14条1項に違反する旨主張する。」との記載がある。
まず、法律上は「異性愛者」であるのか「同性愛者」であるのか、その他の「性愛」を有する者なのかを審査して、分類している事実はない。
また、特定の思想や感情を有する者の「婚姻」を制限しておらず、特定の「性愛(性的指向)」を有する者の「婚姻」を制限するしている事実もない。
そのため、「異性愛者は婚姻をすることができるのに対して同性愛者はこれをすることができず、」との理解は誤りである。
また、婚姻制度は下記の立法目的を達成するための手段として枠組みが定められていると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するための手段として設けられた枠組みに当てはまれば「婚姻」することができ、当てはまらなければ「婚姻」することができないというだけである。
そのため、婚姻制度は特定の思想や感情を有する形で利用することを求めるものではなく、「性愛(性的指向)」に従う形で「婚姻」することに価値がある考えるかどうかは、個々人の価値観によるものに過ぎない。
「婚姻の効果を享受できないという別異の取扱い(以下「本件区別取扱い」という。)が生じているとして、」との記載がある。
しかし、上に挙げたように、法律上は「異性愛者」であるのか「同性愛者」であるのかを審査して区別している事実はないのであるから、「別異の取り扱い」は存在しない。
ここで「(以下「本件区別取扱い」という。)」として、これを「区別取扱い」するものであることを前提として論じようとしているが、そもそも「区別取扱い」が存在しないため、前提を誤っている。
「異性愛者」を称する者も、「同性愛者」を称する者も、「その他の性愛を有する」と称する者も、「性愛を持たない」と称する者も、そのような分類を用いない者も、すべて「婚姻の効果を享受」することが可能である。
「このことが憲法14条1項に違反する旨主張する。」との記載がある。
しかし、もともと「区別取扱い」が存在しないのであるから、14条によって「法の下に平等」であるかを審査する前提を欠いている。
憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第1472 号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁、最高裁平成25年(オ)第1079号同27月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁等)。前記2(3)アのとおり、同法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきとの要請、指針を示すことによって裁量の限界を画したものであるから、婚姻制度に関わる本件諸規定が、国会に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合に、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当であるというべきである(最高裁平成24年(ク)第984号、第985号同25年9月4日大法廷決定・民集67巻6号1320頁参照)。
【筆者】
「前記2(3)アのとおり、」との部分であるが、その「2(3)ア」に記載されているのは夫婦別姓訴訟の判決(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集第69巻8号2586頁参照)である。
また、この夫婦別姓訴訟の判決が述べているのは、基本的にあらゆる法制度については13条の「個人の尊重」や14条の「平等原則」を満たすものとなることが当然に求められているのであるが、その中でも24条2項に「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」が記されていることは、「婚姻及び家族に関する事項」についてはより意識して憲法上の統制を行うべきであるということである。
下記で確認する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PDF (夫婦別姓訴訟・上記のリンクのPDF版)
この点、上記の夫婦別姓訴訟では、「婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否か」と記載されており、13条、14条の統制よりも、24条の統制の方が厳格である(審査密度が高い)旨を示している。
また、国(行政府)の引用する資料でも、その旨が示されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(イ) この点,再婚禁止期間違憲判決においても,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法適合性の判断に当たっては,憲法14条1項適合性判断の枠組みにおける検討がされているとともに,その検討に当たり併せて憲法24条の趣旨及び意義が考慮されており,同条2項にいう「両性の本質的平等」違反の有無に関する立法府の立法裁量の範囲を逸脱していないかの審査も同時に行われている(加本・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕685ページ)。
また,憲法14条1項適合性と憲法24条2項適合性との関係について,「憲法24条2項にいう『両性の本質的平等』については,同項により立法に当たっての要請,指針が示されていることから,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法14条1項の形式的平等を害していない場合であっても,実質的平等の観点から憲法24条2項に違反するとの判断はあり得ると解されるが,同規定が憲法14条1項に違反する場合には,同時に憲法24条2項にも違反するとの結論が導かれることとなるであろう」(加本・前掲解説民事編平成27年度〔下〕684及び685ページ)と説明されているとおり,憲法14条1項適合性については,憲法24条2 項の解釈と整合的に判断する必要があることが明らかにされている。
さらに,平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決については,「憲法14条1項の『平等』が,少なくとも裁判規範としては基本的に形式的な平等をいうものであることを示し」ており,「実質的平等の観点は,憲法14条1項適合性の判断において直ちに裁判規範とはなるものではないものの,(中略)憲法24条に関連し,(中略)考慮すべき事項のーつとしたものであ」る(畑・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕746及び747ページ)との理解がされている。
(ウ)以上のとおり,婚姻及び家族に関する事項の立法行為又は立法不作為の憲法14条1項適合性については,憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要があるというべきである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年8月24日 PDF (P9)
この国(行政府)の主張で、最後に「婚姻及び家族に関する事項の立法行為又は立法不作為の憲法14条1項適合性については,憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要がある」と述べられているが、これは、「婚姻及び家族に関する事項」については、24条2項によって14条よりも厳格に審査されることになるから、「婚姻及び家族に関する事項」について14条の適合性を審査する場合には、より厳格な24条2項の適合性審査が既になされているはずであるから、「憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要がある」とするものである。
国(行政府)がこのように述べているのは、同性婚訴訟の札幌地裁判決の内容が、同性間の人的結合関係について「婚姻及び家族に関する事項」に属する問題であるという前提を置きながら(注:筆者はこの前提は成り立たず、札幌地裁の判断は誤っていると考えている。)、より厳格な(審査密度が高い)24条2項に違反しないとしながら、14条1項に違反すると結論付けることは、「再婚禁止期間違憲判決」や「夫婦別姓訴訟最高裁判決」で示された判断手法に沿わないと考えるからである。
【参考】【東京二次・第5回】被告第3準備書面 PDF
【参考】【札幌・第2回】被控訴人第1準備書面 PDF
ただ、筆者は同性婚訴訟の札幌地裁判決については、「区別取扱い」が存在しないものを「区別取扱い」があるかのような前提で憲法適合性審査を行おうとしていたり、比較対象の選択を誤って「カップル間不平等論」に陥っている部分があるため、14条1項の適合性を24条2項の解釈と整合的に判断するかどうかという論点以前の問題によって排斥されるべき主張であると考えている。
また、筆者は24条が「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」を定めている理由は、「婚姻」を中心として構成される「婚姻及び家族に関するその他の事項」については、「生殖」に関わる問題が含まれており、これは自らの身体で子を産むことができるか否かという観点などから、男女間でもともと鮮明な違いがあるため、「生殖と子の養育」に関わる法制度を立法する際にも、その違いに基づいて男女間で差異を生じさせる不平等な立法が行われやすいことが懸念されているという背景によるものと考えている。
それに対して、「組合」「雇用」「会社」「宗教団体」「学校」「地方自治体」などについては、「生殖」に直接的に関わることのない人的結合関係であるため、男女間で鮮明な差異が意識される場面が少なく、ここでいう特別の懸念が生じにくいため、24条2項の「両性の本質的平等」にあたる規定を置かなくとも、14条1項の「平等原則」によって十分に統制できることを予定していると考えている。
そのため、24条2項の「両性の本質的平等」については、「生殖」に関わる問題について、男女間で鮮明な違いがあるため、法制度を立法する際にも男女間の差異が許容されやすいという懸念に起因して、特に注意的に定められているだけであるから、この24条2項の「両性の本質的平等」が、14条1項の「平等原則」に比べてより厳格な(審査密度が高い)ものというわけではないと考えている。
つまり、筆者は法律上の「婚姻及び家族に関する事項」に対する憲法適合性の審査においては、14条1項の「平等原則」についても、24条2項の「両性の本質的平等」についても、厳格さ(審査密度)は同じであると考えている。
(注意したいのは、24条2項は『婚姻及び家族に関する事項』の内部の者同士を比較する場合においてしか規律できないことに対して、14条1項は『婚姻及び家族に関する事項』の内部の者と外部の者との間の差異についても合理性を審査して規律できる点で14条1項の方が審査できる比較対象の範囲が広いと考える。例えば、『婚姻している者(既婚者)』と『婚姻していない者(独身者)』の間の差異は、24条2項では審査することはできないが、14条1項で審査することが可能である。詳しくは、このページの上記の『「平等」の審査方法』の項目で解説している。)
このような14条1項と24条2項の関係の理解に対して、この大阪地裁判決では「同法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、…(略)…裁量の限界を画したものであるから、婚姻制度に関わる本件諸規定が、…(略)…そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合に、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当であるというべきである」と説明しており、意味が分からない。
まず、24条2項については、「婚姻及び家族に関する事項」のみを規律しており、「婚姻及び家族に関する事項」の内容が「両性の本質的平等」に違反する場合には、24条2項に違反する場合は考えられる。
次に、「婚姻及び家族に関する事項」について定めた法律に対しても、14条1項の「平等原則」が及ぶから、「婚姻及び家族に関する事項」の差異が不合理な内容であれば、14条1項の「平等原則」に違反することも考えられる。
しかし、この大阪地裁判決が述べるように、24条2項が「婚姻及び家族に関する事項」に対して「裁量の限界を画したもの」であることを理由として、「婚姻及び家族に関する事項」における区別について合理的根拠が認められない場合に、突然14条1項に違反するという判断枠組みを定めようとすることは、24条2項の規定と14条1項の規定を無用に連結しているものとなっており、論理的に飛躍している。
この大阪地裁判決は、国(行政府)が同性婚訴訟の札幌地裁判決の判断手法について、最高裁判決の判断手法に照らして「特異」であることを示す文脈の中で「婚姻及び家族に関する事項の立法行為又は立法不作為の憲法14条1項適合性については,憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要がある」と述べている意味を読み誤り、「婚姻及び家族に関する事項」については、24条2項の規定によって独立して判断するべきものではなく、あたかも「婚姻及び家族に関する事項」はすべて14条1項の中に吸収する形でこれ違反するか否かのみを判断すればよいと考えてしまっているように見受けられる。
また、この大阪地裁判決の述べている24条2項と14条1項の関係の部分について、「非嫡出子法定相続分違憲判決」の中にそのような判断枠組みが示されているかのように「参照」を記載しているが、「非嫡出子法定相続分違憲判決」の内容を読み解いても、そのような判断枠組みは示されていない。
「非嫡出子法定相続分違憲判決」が14条1項に違反するか否かという観点から判断している理由は、「婚姻及び家族に関する事項」という婚姻関係にある者の下で生まれた「嫡出子」と、その外で生まれた「非嫡出子」の間を比較対象としているからである。
「婚姻及び家族に関する事項」の内部に関しては、24条2項の統制が及ぶが、「婚姻及び家族に関する事項」の内部の者と「婚姻及び家族に関する事項」の外部の者との間では、24条2項による統制が及ばないので、14条1項の「平等原則」が用いられているのである。(詳しくは、当ページの上記『「平等」の審査方法』の項目の図の『法の下の平等(E)』のパターンで示している。)
「婚姻及び家族に関する事項」に含まれる事柄であれば、24条2項によって統制できるのであり、前提として24条2項の下での「裁量の限界」に触れながら、突然14条1項に違反するか否かに話が移るのは不自然である。
反対に、「婚姻及び家族に関する事項」に含まれない事柄であれば、そもそも最初から14条1項違反か否かを審査すればよいのであり、24条2項が持ち出されて「婚姻及び家族に関する事項」との整合性を検討するような形で説明されていることは不自然である。
よって、この大阪地裁判決は、14条1項と24条2項の判断枠組みに対する解釈を誤っている。
また、「非嫡出子法定相続分違憲判決」の判決を引用しているように示しているものの、「非嫡出子法定相続分違憲判決」の示している判断枠組みに対する理解も誤っている。
このことから、この大阪地裁判決が示すような判断枠組みそのものが成り立たず、これによって婚姻制度についての憲法適合性を審査することはできない。
(2) このような観点から、本件諸規定が憲法14条1項に違反するかを検討する。
ア この点について、被告は、本件諸規定は、客観的に同性愛者であるか異性愛者であるかによって婚姻制度の利用の可否について取扱いを区別するものではないから、同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができない結果が生じているのは、本件諸規定から生ずる事実上の結果にすぎないとし、それゆえ立法裁量がより広範になる旨主張する。確かに、本件諸規定は、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めるものではなく、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁止するものでもないから、その趣旨、内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえない。しかし、婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。
【論点番号】
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
④ 区別取扱いが存在しないこと
【筆者】
「被告は、本件諸規定は、客観的に同性愛者であるか異性愛者であるかによって婚姻制度の利用の可否について取扱いを区別するものではないから、同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができない結果が生じているのは、本件諸規定から生ずる事実上の結果にすぎないとし、それゆえ立法裁量がより広範になる旨主張する。」との記載がある。
この「客観的に同性愛者であるか異性愛者であるかによって婚姻制度の利用の可否について取扱いを区別するものではない」との部分について、その通りである。
婚姻制度は利用者個々人の内心の問題には立ち入っていないのであるから、「異性愛者」を称する者も、「同性愛者」を称する者も、「全性愛者」「多性愛者」「無性愛者」を称する者も、「キリスト教徒」「ユダヤ教徒」「イスラム教徒」「仏教徒」「神道を信じる者」「武士道を重んじる者」も、「飛行機マニア」「建築マニア」、「精神病を持つと名乗る者」「他者から精神病とではないかと疑われている者」なども、すべて「取扱いを区別するものではない」ということができる。
また、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的とする制度ではないことから、「性愛(性的指向)」が合致することを正しい価値観であることを前提とする制度というわけでもない。
そのため、「性愛(性的指向)」を満たすことを目的とする「婚姻」を望む者に対して、その「性愛(性的指向)」に応じる形で等しく婚姻制度を与えなければならないとの前提も存在しない。
このことから、この「同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができない結果が生じているのは、本件諸規定から生ずる事実上の結果にすぎない」との記載があるが、「事実上の結果にすぎない」どころか、そもそも「性愛」が満たされることと「婚姻」という制度そのものとの間には直接的な関係がないのであり、「異性愛者」や「同性愛者」などの「性愛(性的指向)」という思想や感情に基づいた分類の問題と、制度の問題は切り離して考えることが必要である。
「それゆえ立法裁量がより広範になる」の部分についても、そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを立法目的とはしていないことから、もともと保護を与えなければならないとの前提が存在しないことも押さえる必要がある。
また、憲法24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言が「男女二人一組」に限定する形で立法裁量の限界を画している場合には、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできないため、「立法裁量」も存在しない場合もあることに注意が必要である。
さらに、「性愛(性的指向)」という特定の思想や感情、価値観を保護することを目的として法律を立法することは、それ以外の思想との間で14条1項の「平等原則」に抵触して違憲となるし、19条の「思想良心の自由」や、20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となると考えられる。
「確かに、」の文は、その通りである。
「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。」との記載がある。
「婚姻の本質」の論点については、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」で詳述している。
かえって、本件区別取扱いは、上記のとおり、性的指向という本人の意思や努力によっては変えることのできない事柄によって、婚姻という個人の尊厳に関わる制度を実質的に利用できるか否かについて区別取扱いをするものであることからすると、本件区別取扱いの憲法適合性については、このような事柄の性質を考慮して、より慎重に検討される必要がある。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること
② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
「本件区別取扱いは、」との部分であるが、そもそも法律は「異性愛者」であるのか「同性愛者」であるのか、「その他の性愛」を有する者なのか、「性愛を有しない者」なのかを審査しておらず、法律論上の「区別取扱い」そのものが存在しない。
「性的指向という本人の意思や努力によっては変えることのできない事柄によって、婚姻という個人の尊厳に関わる制度を実質的に利用できるか否かについて区別取扱いをするものであることからすると、」との記載がある。
しかし、婚姻制度は下記の立法目的を達成するための手段として枠組みが定められた制度と考えられ、その枠組みに当てはまる場合には婚姻制度を利用することができ、その枠組みに当てはまらない場合には婚姻制度を利用できないというだけのものである。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
そのため、「性的指向」に基づいて婚姻制度の対象者を選別しているという事実はないため、「性的指向」によって「区別取扱い」をしているとの事実はない。
また、婚姻制度は特定の「性的指向」を保護することを目的として立法された制度ではないし、「性的指向」に従って婚姻制度を利用することこそが正しい価値観であると定めているものでもない。
このような法律論としての「区別取扱い」が存在しない中で、この判決が「区別取扱い」があると論じることは、単に「性愛(性的指向)」を満たすことを目的とした婚姻こそが正しい価値観であるという特定の価値観を優越するものと位置づけようとする意味を持つのであり、法律論として正当化することはできない。
「性愛(性的指向)」は「内心の自由」の問題であり、法の関知しないものである。
裁判所が法律論を論じる際に、「性愛(性的指向)」に基づいた「婚姻」こそが正当であり、正しい価値観であるかのような言説を持ち出すべきではないと考える。
「性愛(性的指向)」を有しない者も婚姻制度を利用することはあるし、「同性愛者」と称する者も「男女二人一組」の婚姻制度を利用している場合もある。
「性愛(性的指向)」にどの程度の価値があると考えるかは、まったく個々人の価値観の問題である。
この判決のように「性的指向」によって「区別取扱い」があるとする前提をもって論じることは、「性的指向」によって「婚姻」に至ることが正しい価値観であるとする特定の価値観を正当化しようとする主張に過ぎないのであり、婚姻制度そのものを論じたものとはいえず、法律論として正当化することはできない。
さらに、婚姻制度は「性的指向」を保護することを目的として立法された制度ではないし、このような特定の価値観を保護することを目的として法律を立法することは、20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。
また、法制度が特定の思想や信条を取り上げて制度を設け、それ以外の思想や信条に対して制度を設けないことになれば、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。
「婚姻という個人の尊厳に関わる制度を」との部分について検討する。
憲法の「個人の尊厳」の原理とは、「個人主義」の下に各々が「自律的な個人」として生存していくことを予定していることをいうのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で、既に完全な状態として認められていることを示すものである。
そのため、「婚姻」しなければ「個人の尊厳」が満たされないという性質のものではない。
また、自然人が法律関係を形成する際には、法主体としての地位を有することが必要であり、この「個人の尊厳」とはその地位を指す言葉でもある。
そのため、法律関係を形成する場合には、あらゆる法制度において「個人の尊厳」が関わるということもでき、「個人の尊厳」に関わる制度と、関わらない制度を切り分けて論じることはできないように思われる。
他にも、憲法は「個人の尊厳」の原理に裏付けられているが、24条2項に記された「個人の尊厳」は、24条2項の示している「婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用されるものである。
そして、どのような「性的指向」を有する者も、法律上の要件によって婚姻制度を利用することが制限されているという事実はないのであるから、どのような「性的指向」を有しようとも「婚姻という個人の尊厳に関わる制度」を利用することができる。
よって、「個人の尊厳」の観点から見ても、「区別取扱い」をしているという事実はない。
この判決は「婚姻という個人の尊厳に関わる制度」と述べるのであるが、このような論じ方は、「婚姻している者(既婚者)」を「個人の尊厳」を認められた価値ある存在であり、「婚姻していない者(独身者)」は「個人の尊厳」を認められていない価値のない存在であるかのように扱うような前提認識を持っているように見受けられる。
このような認識に基づいて論じることは、むしろ、個人で既に完全な状態として取り扱われることを意味する「個人の尊厳」の原理に反する理解である。
「個人の尊厳」とは、「個人主義」に根差すことをいうのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全であることを示すものである。
「本件区別取扱いの憲法適合性については、このような事柄の性質を考慮して、より慎重に検討される必要がある。」との記載がある。
しかし、そもそも「区別取扱い」は存在しないため、「憲法適合性」を審査することはできない。
また、「個人の尊厳」の原理の理解も誤っている部分があり、「このような事柄の性質を考慮して、」の部分も、「事柄の性質」を的確に捉えることができていない。
「より慎重に検討される必要がある。」との部分であるが、それ以前にこの「区別取扱い」が存在しない事案に対して、「区別取扱い」が存在するかのように論じている部分を「より慎重に検討」する必要がある。
「このような事柄の性質を考慮」した後の部分を「より慎重に検討」するのではなく、「このような事柄の性質」と考えている部分の認識を「より慎重に検討」する必要がある。
誤った前提の下に、「より慎重に検討」したところで、適切な解を導き出すことはできない。
イ そこで検討すると、本件諸規定は、憲法24条2項が、異性間の婚姻についてのみ明文で婚姻制度を立法化するよう要請していることに応じ、個人の尊厳や両性の本質的平等に配慮した異性間の婚姻制度を構築したものと認められ、その趣旨目的は、憲法の予定する秩序に沿うもので、合理性を有していることは既に述べたとおりである。そして、本件諸規定が同性間の婚姻制度については何ら定めていないために本件区別取扱いが生じているものの、このことも、同条1項は、異性間の婚姻については明文で婚姻をするについての自由を定めている一方、同性間の婚姻については、これを禁止するものではないとはいえ、何らの定めもしていない以上、異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえないことからすると、上記立法目的との関連において合理性を欠くとはいえない。したがって、本件諸規定に同性間の婚姻制度が規定されていないこと自体が立法裁量の範囲を超えるものとして憲法14条1項に違反するとはいえない。
【論点番号】
⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと
【筆者】
「本件諸規定は、憲法24条2項が、異性間の婚姻についてのみ明文で婚姻制度を立法化するよう要請していることに応じ、個人の尊厳や両性の本質的平等に配慮した異性間の婚姻制度を構築したものと認められ、その趣旨目的は、憲法の予定する秩序に沿うもので、合理性を有していることは既に述べたとおりである。」との記載がある。
ここでは、憲法24条2項が「異性間の婚姻」(男女二人一組)の婚姻制度を立法するように要請しているとしている。
そして、その「本件諸規定」である法律上の婚姻制度が「異性間の婚姻」(男女二人一組)であることについての「趣旨目的は、憲法の予定する秩序に沿うもの」としている。
このことから、憲法24条の「婚姻」についても、その「趣旨目的」は「2(3)イ(ア)」の部分で示されているように「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、このような男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるもの」であると述べていることになる。
そして、その「趣旨目的」は「合理性を有している」としている。
このように、法律上の婚姻制度が「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定していることの「趣旨目的」に「合理性」があるということは、憲法24条の「婚姻」についても、「婚姻」の趣旨そのものや、「両性」「夫婦」「相互」の文言により「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定して立法裁量の限界を画する意味を有しているとしても、その「趣旨目的」には「合理性」があると認めていることになる。
この大阪地裁判決は「2(2)ア(ウ)」の部分等で、24条1項が「同性間の婚姻」を「同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べているが、憲法24条1項が「婚姻」について「両性」「夫婦」「相互」の文言を設けて「男女二人一組」の形に限定し、立法裁量の限界を画し、これを満たさない形の「婚姻」を立法してはならないという意味で禁止する趣旨である場合にも、その「趣旨目的」の「合理性」は認めることができるということである。
そうなると、法律上の立法政策として「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定していることに「合理性」があると考えているのであるから、憲法上の立法政策として「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定している場合でも「合理性」があると考えていることになるのであり、憲法24条が「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定している趣旨ではない(この判決のいう『積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。』)と考えるのであれば、その立法政策としての「合理性」を上回る何らかの根拠を示す必要があるはずである。
これを乗り越えることなく、法律上の立法政策が「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定していることの「合理性」を認めながら、憲法上の立法政策として「異性間の婚姻」(男女二人一組)に限定している意味を有しないと断定することは、解釈の一貫性を欠き、他の解釈を退けるだけの説得的な根拠を示しているとはいえない。
このような一貫性を欠く解釈を行いながら、それを裏付ける根拠を十分に説明しないようでは、解釈の客観性が保たれておらず、正しい解釈をめぐって紛争を招くことになり、法的安定性を損なうことになる。
「本件諸規定が同性間の婚姻制度については何ら定めていないために本件区別取扱いが生じているものの、このことも、同条1項は、異性間の婚姻については明文で婚姻をするについての自由を定めている一方、同性間の婚姻については、これを禁止するものではないとはいえ、何らの定めもしていない以上、異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえないことからすると、上記立法目的との関連において合理性を欠くとはいえない。」との記載がある。
まず「本件諸規定が同性間の婚姻制度については何ら定めていないために本件区別取扱いが生じているものの、」の部分を検討する。
「本件区別取扱い」とは、「3(1)」の部分で示された「本件諸規定により、異性愛者は婚姻をすることができるのに対して同性愛者はこれをすることができず、婚姻の効果を享受できないという別異の取扱い」のことであるが、そもそも法律は「異性愛者」であるのか「同性愛者」であるのか、それ以外の「性愛」を有するものであるのか、「性愛」を有しないのかなど、一切関知しておらず、このような思想や感情に基づいて自然人を区別して取扱っているという事実はない。
そのため、どのような思想や感情を有する者も婚姻制度は利用することができる。
このことから、「本件区別取扱いが生じているものの、」との認識は誤りである。
また、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを立法目的とする制度ではないことから、婚姻制度を整備することによって特定の「性愛(性的指向)」を有するものを優遇しようとする意図も含まれていない。
さらに、特定の思想や信条を保護するために法律を立法することは、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条を有する者との間で憲法14条の「平等原則」に反して違憲となる。
これにより、この判決の内容は、もともと「区別取扱い」は存在しないものを「区別取扱い」が存在すると考える誤りがあるし、この判決が婚姻制度について自然人の「内心の自由」に属する「性愛(性的指向)」を基にして「区別取扱い」を行っている制度として扱おうとしている前提そのものが、自然人の「思想良心の自由(19条)」に反するし、特定の思想や信条を優遇することになるから「政教分離原則(20条1項・3項、89条)」に抵触して違憲となるし、他の思想や信条を有する者との間で「平等原則(14条)」に反して違憲となる。
「同条1項は、…(略)…同性間の婚姻については、これを禁止するものではないとはいえ、何らの定めもしていない以上、異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえないことからすると、」との部分について検討する。
「禁止するものではない」とあるが、そもそも「婚姻」の趣旨そのものによって、また「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」という成立条件によって、さらに「夫婦」の文言によって、「同性間」(同性同士の組み合わせ)については「婚姻」として成立しないことも考えられる。
24条1項の規定の意味が「禁止するものではない」としても(この意味は『義務文・否定文による禁止』ではないという意味)、もともと「婚姻」として成立しない場合については、「婚姻」として成立することが認められることにはならない。
この点の論理についても明確に描き出すように検討を重ねていかなければ、客観性のある論理的な過程によって誰もが共通認識を持つことができるものとはならず、法解釈として論争を招き続けることになる。そうなれば、法的紛争を法に従って適切に解決していることにはならず、「この判決がそう言っている」「あの判決がそう言っている」というような、裁判官がむやみな断定をしているだけの人治主義の世界となり、法治主義を逸脱することになる。
「異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえない」とあるが、そもそも「同性間の婚姻」については「何らの定めもしていない」し、24条1項の保障の対象ではないのであるから、「同程度」どころか、まったく保障はないはずである。「同程度に」などと含みを持たせるような書き方は、論理の世界ではない。
また、ここでは「同性間の婚姻」のように「二人一組」を前提として考えているようであるが、現在の法制度に存在しない人的結合関係について論じるのであれば、同じく現在の法制度に存在しない「三人一組」や「四人一組」など、「三人以上の人的結合関係」についても同様に論じる必要がある。
これを検討することなく、勝手に「二人一組」だけを取り上げて比較対象となるものは「二人一組」だけであるかのような前提を有しているのであれば、なぜ「二人一組」であるのかという根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥ることになる。
そのことから、この判決が「同性間」について「異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえない」と述べるのであれば、同様に「三人以上の組み合わせ」についても「異性間の婚姻と同程度に保障しているとまではいえない」と述べることができることも押さえる必要がある。
「上記立法目的との関連において合理性を欠くとはいえない。」との部分を検討する。
「上記立法目的」とは、「2(3)イ(ア)」に記載された「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、このような男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるもの」のことである。
これを「立法目的」であると考えているのであれば、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないことを自ら理解しているはずである。
よって、婚姻制度が個々の自然人がどのような「性愛(性的指向)」を有しているかを審査して「区別取扱い」を行っているわけではないことについても、自ら理解していることになるはずである。
婚姻制度は「性愛(性的指向)」に着目して「区別取扱い」を行っている制度ではないことを自ら理解しているにもかかわらず、「本件区別取扱いが生じている」と論じていることは論理が矛盾していることになる。
結局、国(行政府)の主張が正しいことになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他方,原告らの主張が,個々の国民という個人を主体とする法令上の区別をいうものと解したとしても,被告第2準備書面第3の3 (1)イ(21ページ)で述べたとおり,本件規定は,制度を利用することができるか否かの基準を,具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく,本件規定の文言上,同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから,この点に法令上の区別は存在しない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF
この「本件諸規定が」~「合理性を欠くとはいえない。」までの一文は文脈が読み取りにくいものとなっているが、要するに、「本件諸規定が同性間の婚姻制度については何ら定めていないために本件区別取扱いが生じているものの、」、24条1項が「異性間の婚姻」(男女二人一組)を定めていることの「立法目的」は「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係として捉え、このような男女が共同生活を営み子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるもの」であるから、その「本件諸規定」の「区別取扱い」は「立法目的との関連において合理性を欠くとはいえない。」というものである。
ただ、この意味を検討するとしても、そもそもここでいう「区別取扱い」とは「性愛(性的指向)」に着目した「区別取扱い」をいうものであるが、そのような「区別取扱い」は存在しないし、憲法24条の「婚姻」の趣旨を先ほど挙げられたような意味で理解しているのであれば、当然、24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言によって、「男女二人一組」の形に限定して立法裁量の限界を画し、一夫一婦制とすることを要請する意味を有する規定であるとしても、この憲法上の立法政策についても同様に「合理性を欠くとはいえない。」と論じることが可能である。
そうなると、この判決は24条1項が「同性間の婚姻」を「禁止するものではない」と述べているが、そのように論じるためには、法律上の立法政策としての「婚姻」の枠組みと、憲法上の立法政策としての「婚姻」の枠組みとの間にどのような違いがあるのかについて明確な根拠を必要とするのであり、これを示さないままに24条1項が「同性間の婚姻」を「禁止するものではない」と言い切ることには、説得的な根拠が示されているとはいえない。
説得的な根拠が示されていないのであれば、裁判官個人による人治主義に陥るのであり、法治主義が求められる裁判所の役割を果たしたとはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。
解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)
㊥ 「したがって、本件諸規定に同性間の婚姻制度が規定されていないこと自体が立法裁量の範囲を超えるものとして憲法14条1項に違反するとはいえない。」
ウ 確かに、現時点の我が国においては、同性愛者には、同性間の婚姻制度どころか、これに類似した法制度さえ存しないのが現実であり、その結果、同性愛者は、前記のとおり、婚姻によって異性愛者が享受している種々の法的保護、特に公認に係る利益のような重要な人格的利益を享受することができない状況にある。したがって、このような同性愛者と異性愛者との間に存在する、自らが望む相手との人格的結合関係について享受し得る利益の差異の程度が、憲法14条1項の許容する合理的な立法裁量の範囲を超えるものではないかについてはなお慎重に検討すべきということができる。
【論点番号】
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
【筆者】
「現時点の我が国においては、同性愛者には、同性間の婚姻制度どころか、これに類似した法制度さえ存しないのが現実であり、」との記載がある。
まず、「同性愛者」を称する者でも、現在の「男女二人一組」の婚姻制度を利用することが可能である。婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛(性的指向)」に従って「婚姻」することを求めるものでもない。婚姻制度そのものと「性愛(性的指向)」が満たされるか否か別問題であり、「性愛(性的指向)」を満たすことを目的として「婚姻」することに価値があると考えるか否かは、個々人の価値観によるものである。実際、「同性愛者」を称する者であっても、婚姻制度を利用していることはある。「性愛(性的指向)」は思想や感情の一つに過ぎず、それにどの程度の価値を見出すかは個々人の価値観の問題である。
また、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために「生殖と子の養育」の観点から、他の人的結合関係とは区別する形で設けられた制度であり、この立法目的を達成するための手段としての枠組みに当てはまる者には一定の優遇措置を与え、その枠組みに当てはまらない者についてはそれらの優遇措置を得られないことは当然のことであり、この差異によって婚姻制度の政策目的を達成しようとしているものである。
よって、ここには「同性間の婚姻制度どころか、」のように、「同性間」の人的結合関係を婚姻制度の中に組み入れるべきであるかのような論じ方をしているが、そもそも婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みを定め、その対象とならない人的結合関係については意図的に婚姻制度の中に含めていないのであるから、その立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題を論じずに、「同性間」の人的結合関係を婚姻制度の中に含めるべきであるとの結論を導き出すことはできない。
「これに類似した法制度さえ存しないのが現実であり、」との部分についても、「同性間」の人的結合関係について、「婚姻」に「類似した法制度」を創設するべきであるにもかかわらず創設されていないという立場から論じるものとなっている。しかし、そもそも婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために国家の政策の手段として設けられている背景からは、この目的を達成することを阻害するような影響のある制度を設けることはできないのであり、「婚姻」に「類似した法制度」についても、婚姻制度との関係で意図的に設けられていないという場合がある。そのため、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段の当否を論じることなく、「婚姻」に「類似した法制度」を創設することが正しい価値観であるかのような前提を含める形で論じるべきではない。
「同性愛者は、前記のとおり、婚姻によって異性愛者が享受している種々の法的保護、特に公認に係る利益のような重要な人格的利益を享受することができない状況にある。」との記載がある。
まず、法律論としては個々人の思想や信条、感情によって区別して取扱ってはならないのであり、「同性愛者」と「異性愛者」に区別して論じてはならない。
また、ここでいう「同性愛者」というものも、法律論として取り扱うことのできる形に整理して理解すれば、「『同性間の人的結合関係』を『婚姻』とする新たな法制度を立法することを希望する者」ということである。
これについては、国(行政府)が下記のように理解している者である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……(略)……原告らが本件諸規定により侵害されていると主張する権利又は利益は、憲法24条2 項の要請に基づき、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻について具体的な内容として定められた権利又は利益であり、結局のところ、これらが侵害されたとする原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大阪・第12回】被告第6準備書面 令和4年2月21日 PDF (P12)
よって、ここで法律論としての視点で考えるのであれば、もともとの「『同性愛』と称する思想や信条、感情を有する者」という意味での「同性愛者」かどうかではなく、単に「同性間の人的結合関係について新たな法制度の創設を国家に対して求める者」という意味で読み取ることが妥当となる。
「婚姻によって異性愛者が享受している」との部分であるが、婚姻している者がすべて「異性愛者」であると考えていることは、裁判官個人の思い込みによる偏見である。
このような論じ方をするのであれば、「婚姻している者(既婚者)」がすべて「異性愛者」であることを証明する必要がある。
また、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、「異性愛者」と称する者を対象とした制度ではないし、「性愛(性的指向)」という思想や信条、感情に従って「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。
婚姻制度を利用する者が「性愛(性的指向)」の思想や信条、感情を満たすために婚姻している者もいるだろうし、そうでない者もいるのである。
「性愛(性的指向)」を満たすために婚姻することに価値があると考えるか否かは、個々人の価値観によるものである。
あたかも「性愛(性的指向)」を目的とする「婚姻」こそが正しい価値観であるかのような前提で論じるべきではない。
「種々の法的保護、特に公認に係る利益のような重要な人格的利益を享受することができない状況にある。」との部分について検討する。
まず、婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、その対象となる場合は制度を利用することができ、その対象とならない場合には制度を利用することができないという差異が生まれることは、当然に予定されているものである。
また、憲法は「個人の尊厳」の原理により「個人主義」を採用しており「自律的な個人」として生存していくことが予定されている。
そのため、「婚姻制度を利用しない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であり、「婚姻」による「法的保護」や「利益」を受けていない状態でも、何ら不合理な差別的な扱いを受けているわけではない。その状態が基準(スタンダード)である。
その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成して共同生活を行うことも自由である。それが普通の状態であり、基準(スタンダード)である。
そのような前提の中、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する形で婚姻制度が設けられている。
これは立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているものであるから、その対象となる場合には制度を利用することによって「法的保護」や「利益」を受けることができることになる。
これらの「法的保護」や「利益」を受けることを希望するのであれば、制度の枠組みに従って制度を利用すればよいというだけである。
婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、「性愛(性的指向)」に従って制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないから、どのような「性愛(性的指向)」を有しているとしても利用することができるのであり、「異性愛者」や「同性愛者」、その他の「性愛」を有すると称する者も、同様に利用することが可能である。
よって、制度の要件に当てはまる者は、制度の枠組みに従って制度を利用することができるのであるから「婚姻」による「法的保護」や「利益」を「享受することができない状況にある。」と考えていることは誤りである。
「公認に係る利益」との部分であるが、「婚姻制度を利用する者(既婚者)」は「婚姻している者(既婚者)」として認識されており、「婚姻制度を利用しない者(独身者)」は「婚姻していない者(独身者)」として認識されているのであり、ここに優劣が存在するわけではなく、法律論上の違いはない。
「婚姻していない者(独身者)」も、「公認」はされているということができるのである。
あたかも「婚姻」していることが素晴らしいものであると考える価値観を有している者が社会の中に一定数存在しており、その者たちから称えられるというような意味で「公認に係る利益」と論じているのかもしれないが、それは法律論上の利益ではない。
これは、「婚姻」していることに優越した価値があると考えている宗教団体があるとして、その団体の信者に称えられている状態に過ぎないのであり、法制度上の「利益」とは何らの関係もないことである。
また、そもそも婚姻制度を利用していることによる利益を婚姻制度を利用していない者にも与えるべきと考えることは、制度が制度として成り立つための境界線を破壊することになるのであり、制度が成り立たなくなる。
例えば、「弁護士」の資格を有する者が、この判決のいう「公認に係る利益」を有しているとして、この「弁護士」が得ている「利益」を「弁護士」でない者に対しても与えなければならないということにはならない。
「弁護士」という資格を形成している立法目的とその達成手段としての枠組みの当否の問題を越えて、「弁護士」が得ている「利益」を「弁護士」でない者に対して与えるようなことをすれば、制度そのものが成り立たなくなるからである。
この点でも、制度の対象外の者に対して「利益」を与えなければならないという論旨は、妥当とはいえない。
「このような同性愛者と異性愛者との間に存在する、自らが望む相手との人格的結合関係について享受し得る利益の差異の程度が、憲法14条1項の許容する合理的な立法裁量の範囲を超えるものではないかについてはなお慎重に検討すべきということができる。」との記載がある。
まず、法制度は個々人の内心に基づいて区別取扱いをしてはならないのであり、「同性愛者」や「異性愛者」というように、個々人の内心を取り上げて区別取扱いをすることは、違憲になる。
そのため、法制度が「同性愛者」と「異性愛者」に区別して取扱いをしている場合には、そのこと自体が違憲無効となる。
そして、婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするための制度でもないことから、「同性愛者」を称する者も、「異性愛者」を称する者も、その他の者も、同様に制度を利用することができる。
よって、婚姻制度を利用することにより「享受し得る利益」については、「同性愛者」を称する者も、「異性愛者」を称する者も、その他の者との間でも、「差異」は存在しない。
これにより、もともと「差異」の生じていないものについて、憲法14条1項の「平等原則」による審査はできないのであり、「差異」があることを前提として「憲法14条1項の許容する合理的な立法裁量の範囲を超えるものではないか」について「検討すべき」と述べていることは誤りとなる。
次に、「自らが望む相手との」との部分であるが、自然人は社会生活において必ず「自らが望む相手との人格的結合関係」を形成しなければならないという義務が課せられているわけではないのであり、「自らが望む相手との人格的結合関係」を形成するか否かは自由である。
また、婚姻制度を利用することを希望するのであれば、婚姻制度の要件に当てはまる形で「自らが望む相手」を選択し、相手からも「合意(憲法24条1項)」が得られた場合には、婚姻制度を利用することができるというだけである。
この婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として設けられている枠組みを超えて、単に「自らが望む相手との人格的結合関係」を形成している者に対して「利益」を与えなければならないという前提がそもそも存在しないのであり、「自らが望む相手との人格的結合関係について享受し得る利益の差異」などと、「自らが望む相手との人格的結合関係」を形成しているというだけで「利益」を得られると考えて「差異」の存否を論じようとしていることそのものが誤りである。
さらに、「同性愛者」を称する者も、「異性愛者」を称する者も、その他の者を称する者も、婚姻制度の枠組みに沿う形で存在する選択肢の中で、その中でもなお「自らが望む相手」が存在した場合に、相手方との「合意」を得た場合に婚姻制度を利用できるというだけのものである。
「近親者」や「婚姻適齢に満たない者」、「同性間」など、婚姻制度の要件に沿わないのであれば、そもそも「自らが望む相手」がいたとしても、相手方からの「合意」が得られたとしても、婚姻制度は利用できないのは当然である。
「自らが望む相手との人格的結合関係」を形成すれば、何らかの「利益」が得られるはずであると考えている前提そのものが誤っている。
「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を受けている場合においては、「婚姻していない者(独身者)」との間で憲法14条の「平等原則」が審査され、違憲となる場合は考えられる。
これは、「人的結合関係」を単位として比較するのではなく、常に「婚姻している者(既婚者)」と「婚姻していない者(独身者)」との間の比較である。
そして、もともと「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準であるから、「婚姻している者(既婚者)」が婚姻制度の目的達成のために不必要に過大な優遇措置を得ているとされた場合には、その不必要に過大な優遇措置を与える根拠となっている規定が個別に失効することによりその「差異」が解消されることになる。
これは、「婚姻している者(既婚者)」の得ている「利益」の方を基準と考えて、「婚姻していない者(独身者)」に対しても同様の「利益」を与えるという措置ではなく、「婚姻していない者(独身者)」の方を基準と考えて、「婚姻している者(既婚者)」の「利益」の方を是正するものであることを押さえる必要がある。
しかし、前記2(3)イのとおり、異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度であるのに対し、同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについては前記のとおりなお議論の過程にあること、同性愛者であっても望む相手と親密な関係を築く自由は何ら制約されておらず、それ以外の不利益も、民法上の他の制度(契約、遺言等)を用いることによって相当程度解消ないし軽減されていること、法制度としては存在しないものの、多くの地方公共団体において登録パートナーシップ制度を創設する動きが広がっており、国民の理解も進んでいるなど上記の差異は一定の範囲では緩和されつつあるといえること等(前記2(3)イ(イ))からすると、現状の差異が、憲法14条1項の許容する国会の合理的な立法裁量の範囲を超えたものであるとは直ちにはいい難い。
【論点番号】
⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
【筆者】
「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度であるのに対し、同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについては前記のとおりなお議論の過程にあること、」との記載がある。
「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により」としているのであるから、婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にする制度ではないことを自ら明らかにしていることになる。
また、婚姻制度はこの目的を達成するための手段として枠組みが定められているだけであり、その枠組みに当てはまる場合には制度を利用することができ、その枠組みに当てはまらない場合には制度を利用することができないというだけであるから、個々人の「性愛(性的指向)」に着目して区別取扱いをする制度ではないことも明らかである。
よって、この論旨は、「3(2)ア」で述べているような「本件区別取扱いは、上記のとおり、性的指向という本人の意思や努力によっては変えることのできない事柄によって、婚姻という個人の尊厳に関わる制度を実質的に利用できるか否かについて区別取扱いをするものである」との理解とは矛盾するものとなる。
婚姻制度があたかも「性愛(性的指向)」(その中でも特に『異性愛』)を保護することを目的として立法されているかのような主張は成り立たない。
この判決は、立法目的の中に存在しない「内心の自由」に属する思想や信条、感情、価値観を取り上げたり、あるいは社会の中で形成された文化的な差異に着目して、法律上の区別取扱いが存在するかのように論じようとしていることになるが、法律論でない話を持ち出している点で誤りである。
また、この判決は、下記のようにも述べている。
2(3)イ(ア)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
…(略)…取り分け、近年は家族の形態や夫婦の在り方が多様化しており、人々の意識においても、婚姻を、子の養育のためではなく個人の自己実現あるいは幸福追求に資するためのものとして位置付けようとする傾向が高まっている。しかし、そのような価値観の変化があるとしても、現在でもなお、男女が安定した関係の下で共同生活をしながらその間に生まれた子を養育することを保護する婚姻の目的の意義は何ら失われているわけではないし、このような目的と、個人の自己実現等の手段としての婚姻とは矛盾するものではなく、互いに両立し得るものである。そうすると、このような趣旨や目的自体が、歴史的、社会的意味を失っているとはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これは、要するに、婚姻制度についての「国の立法目的」と「個々人の利用目的」は「矛盾するものではなく、互いに両立し得る」と述べるものである。
そうであれば、「性愛(性的指向)」に基づいて「婚姻」することに価値があると考えるかどうかというのも、この判決の言う「個人の自己実現等の手段」としての価値観の一つに過ぎないという位置づけになる。
それなのに、あたかも婚姻制度が「性愛(性的指向)」を保護することが立法目的であるかのような話を取り上げながら、14条の「平等原則」の審査を試みようとしている部分は妥当でない。
自身の主張の中で食い違いが生じていることになる。
「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により」としているのであるから、憲法24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言によって「男女二人一組」の形に限定して立法裁量の限界を画する意味を有しているとしても、そのこと自体には「合理的な目的」があると論じることが可能である。
この判決は24条1項について「同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べているが、法律上の立法政策として「男女二人一組」に限定することが「合理的」であれば、憲法上の立法政策として「男女二人一組」に限定しているとしても「合理的」ということができるのであり、24条1項の解釈としてその他の解釈方法を排斥するだけの説得的な根拠が示されているとはいえない。
「歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度である」との部分については、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みが妥当であり、合理性を有していることが人々の間で承認され、「歴史的、伝統的に完全に社会に定着した」ことを示すものである。
ここでは婚姻制度の目的として「男女が子を産み育てる関係を社会が保護する」としているが、その「男女が子を産み育てる関係」という枠組みが設定されるまでの、それ以前の立法目的として下記の要素があると考えられる。
・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
・母体を保護すること
これらの目的を達成するための手段として「生殖と子の養育」の観点から枠組みを定め、「男女二人一組」の関係を「婚姻」として扱い、一定の優遇措置を与えているわけである。
これらの立法目的の合理性と、それを達成するための手段の合理性が人々に認められ、受け入れられていることにより、「歴史的、伝統的に完全に社会に定着した」ということである。
また、この立法目的と、それを達成するための手段の枠組みの中に合わない関係については、優遇措置を行う必要はないし、もし優遇措置を行った場合には、これらの目的の達成を阻害することになるため、妥当でなく、そのような制度は不合理であるから、「歴史的、伝統的に完全に社会に定着」することはないと思われる。
「同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについては前記のとおりなお議論の過程にあること」との部分について検討する。
この判決文は、「同性間の人的結合関係」について、何らの保護も与えられていないことを前提として「どのような保護を与えるか」を論じているように見受けられる。
しかし、「同性間の人的結合関係」についても、憲法12条、13条の「公共の福祉」や、民法90条の「公序良俗」、その他の法律の規定に違反しないのであれば、憲法21条の「結社の自由」によって保障されている。
そのため、法的に何らの保護も与えらていないと考えているのであれば、それは誤解である。
また、婚姻制度は立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが定められているのであり、その制度が形成されている段階で、既にその対象とならない人的結合関係については、「婚姻」という形で「保護」されることがないことは当然に予定されている。
これは婚姻制度に限らず、法律上のあらゆる制度を立法する際に共通する事柄である。
制度の対象者は「保護」されるが、制度の対象でない者については、その制度によって「保護」されることはないという差異は、法制度が政策の手段として定められたものである以上は当然のことである。
【動画】シンポジウム 国葬を考える【The Burning Issues vol.27】 2022/09/25
さらに、「同性間の人的結合関係」を取り上げて論じるのであれば、「三人以上の人的結合関係」や「近親者との人的結合関係」、「婚姻適齢に満たない者との人的結合関係」についても同様に取り上げて「どのような保護を与えるか」を論じる必要がある。
それを取り上げずに特定の「二人一組」を取り上げて比較しようとすることは「カップル信仰論」に陥るし、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みとの整合性を保てなくなるため妥当でない。
他にも、「同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるか」との認識についても、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいて定められており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されている。
そのため、その「自律的な個人」はその状態で既に完全な状態ということができ、それに対して「どのような保護を与えるか」というような、「保護」を与えなければならないという前提は存在しない。
制度を創設する際には、常に立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みが定められるのであり、その「立法目的」が存在しないのであれば、もともと「保護」を与えるような制度も必要ないのである。
そして、裁判所が自分の受け持った法的紛争を解決する際には、現行の法令に従って解決する必要があるし、三権分立の制度の下では、司法権しか有しない裁判所の立場で、国会の立法権に踏み込むことになってもいけない。
現在存在する婚姻制度は、その立法目的に従う形で枠組みが定められているものである。
この婚姻制度の範囲に含まれない人的結合関係に対して何らかの「保護」を与えることを希望する者は、その立法目的の達成を国会を通して実現するべき課題ということができる。
その検討の過程の中では、他の制度の政策効果を阻害することにならないかどうかや、他の法令との整合性が議論されることになる。
この過程を差し置いて、裁判所が司法権を行使する枠組みの中で、立法目的が未だ定まっておらず、それを達成するための手段となる枠組みも明確でないにもかかわらず、政治的な議論のある課題の特定の立場に肩入れするような形で「どのような保護を与えるか」などと「保護を与える」ことを前提とする立場で論じることは、司法権の範囲を越えた立法府に対する脅しの意味を有することになる。
一切の政治的な立場から独立することによってしか、司法権の正当性を保つことができないことを認識する必要がある。
「同性愛者であっても望む相手と親密な関係を築く自由は何ら制約されておらず、それ以外の不利益も、民法上の他の制度(契約、遺言等)を用いることによって相当程度解消ないし軽減されていること」との記載がある。
「同性愛者であっても望む相手と親密な関係を築く自由は何ら制約されておらず、」との部分について検討する。
まず、法律上は個人の内心を審査していないのであるから、個々人の心理特性を取り上げて「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して論じるようなことをしてはならない。
このような形で個々の自然人をその内心に基づいて区別して論じようとすることは、「思想良心の自由(19条)」に違反するし、「平等原則(14条)」にも違反することになる。
また、「同性愛者」と称する者でも、「婚姻」することはできるし、実際に「婚姻」している者もいる。
そのため、法律が「同性愛者」と「その他の者」を区別して、「同性愛者」に対して婚姻制度の利用を制限しているかのような前提で、「同性愛者であっても望む相手と親密な関係を築く自由は何ら制約されておらず、」と論じることは、誤りとなる。
また、この判決では「異性愛者」と「同性愛者」の二分論を用いているが、その他にも様々な分類が持ち出されることもあるのであり、このような個人の思想や信条に属する分類の一部の「異性愛者」と「同性愛者」の二分論のみを取り上げて論じることも妥当でない。
さらに、「同性愛者であっても望む相手と親密な関係を築く自由は何ら制約されておらず、」などと論じることは、あたかも「婚姻している者(既婚者)」を基準として考え、「婚姻していない者(独身者)」かつ「同性愛者」を称する者の立場を、「成年者」を基準とした考え方である「未成年者」(制限行為能力者)であるかのような位置づけで考えようとしていることになり、「婚姻していない者(独身者)」かつ「同性愛者」を称する者の地位を不当に格下げする意味を有するものとなる。
法律論として、「同性愛者であっても」などと個人の内心の問題である思想や信条を取り上げて、その地位を不当に格下げするかのような物言いをするべきではない。
いたずらに「同性愛者」を理由として論じること自体がそもそも不当である。
個人の内心に基づいて区別取扱いを行う姿勢であり、この姿勢そのものが憲法19条の「思想良心の自由」を侵すものであるし、憲法14条の「平等権」に違反するものとなる。
そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の内心を審査して区別取扱いをしている事実はないし、法律論として個々人の思想や信条に立ち入るような形で論じることもしてはならない。
そのため、「婚姻している者(既婚者)」との比較をする際には、「同性愛者」という取り上げ方をするのではなく、単に「婚姻していない者(独身者)」として考える必要がある。
「それ以外の不利益も、民法上の他の制度(契約、遺言等)を用いることによって相当程度解消ないし軽減されていること」の部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理により、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことが予定されているのであり、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態である。
そのため、その完全な状態の「婚姻していない者(独身者)」に「不利益」があるかのような前提で論じている点で誤りである。
婚姻制度は、「生殖」に関わって発生する社会的な不都合を解消するために国家の政策の手段として定められた制度であり、その制度の対象となる場合には制度を利用することができ、その制度の対象とならない場合には制度を利用することができないという差異が生じることは当然に予定されている。
また、そもそも「婚姻していない者(独身者)」の状態が基準(スタンダード)であるから、その「婚姻していない者(独身者)」が「結社の自由(21条)」によって人的結合関係を形成したり、民法上の「契約、遺言等」を用いながら生活している状態が基準(スタンダード)である。
よって、「婚姻していない者(独身者)」が不完全で「不利益」を受けているかのような前提認識を持ち、それが別の手段で「相当程度解消ないし軽減されている」などと論じようとしていることは、基準の採り方を誤っている。
このような「婚姻していない者(独身者)」が「不利益」を受けている存在であるかのように考えることは、憲法が「個人の尊厳」の原理に基づいていることを理解しないものであり、「個人主義」が確立されておらず、「自律的な個人」として扱われておらず、あたかも戦前の家を中心とする「家制度的な家族観」の現れた理解の仕方である。
この判決でも、下記のように「憲法の個人主義的家族観に沿うものに改めるべく」と述べているのであるから、この意味を読み取り、憲法の「個人主義」の意味を正確に捉え、「婚姻していない者(独身者)」を基準(スタンダード)として考えるように理解を構築し直す必要がある。
1(2)イ(ウ)a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a 起草過程
明治民法は、家を中心とする家族主義の観念から、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻も、戸主や親の同意を要件とし、当事者間の合意のみによってすることのできないものとし、夫の妻に対する優位も認めていた(前記(ア)参照)。昭和22年民法改正は、このような明治民法を、憲法の個人主義的家族観に沿うものに改めるべく、家制度を廃止するほか、未成年者以外における父母や、継父母・嫡母の婚姻同意に関する規定を廃止し、戸主の婚姻同意権も廃止して婚姻の自主性を宣言したものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法制度としては存在しないものの、多くの地方公共団体において登録パートナーシップ制度を創設する動きが広がっており、国民の理解も進んでいるなど上記の差異は一定の範囲では緩和されつつあるといえること」 との記載がある。
しかし、「地方公共団体」の「登録パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度に抵触する場合には違法となる。
婚姻制度は下記の立法目的に応じて、それを達成するための手段として枠組みが定められていると考えられる。
〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること
(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)
〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること
(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)
〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと
(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)
〇 母体を保護すること
(→ 達成手段:婚姻適齢)
「登録パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。
また、憲法は14条で「平等原則」、19条で「思想良心の自由」、20条1項・3項、89条で「政教分離原則」を定めており、特定の思想や信条に着目して法制度を整備し、何らかの優遇措置を与えることは違憲となる。
これらの論点について、具体的には、「2(3)イ(ウ)」の第二段落の解説部分や、当サイト「パートナーシップ制度」のページで解説している。
「国民の理解も進んでいるなど」との部分であるが、多くの国民は今ある制度をそういうものだと思って受け止めているだけであり、その制度の内容についての婚姻制度との矛盾・抵触の有無や憲法適合性についてまで検討できているわけではないと思われる。
そのため、「登録パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度や憲法に違反していないかどうかの検討をしないままに、「国民の理解も進んでいる」などと示すような形で、制度を正当化するべきではない。
例えば、自動車を運転する際に、スピード違反を行うことについて一定数の「国民の理解」が進んでしまったとしても、スピード違反が違法であることに変わりはないのである。「国民の理解」が進めば、違法な制度が合法になるという性質のものではないことに注意する必要がある。
「上記の差異は一定の範囲では緩和されつつあるといえる」との部分について検討する。
憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、「個人主義」の下、各々「自律的な個人」として生存していくことが基本となっている。
そのため、何らの人的結合関係も形成していない「婚姻していない者(独身者)」を基準(スタンダード)として捉える必要がある。
そして、その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成したり、契約や遺言等を用いて生活していくことが通常の状態である。
よって、この「婚姻していない者(独身者)」には何ら不利に扱われているわけではないのであり、それが普通の状態であるから、そこに「緩和」しなければならないような不利益が存在するわけではない。
そのため、「婚姻していない者(独身者)」について「緩和」しなければならないような「差異」が生じているかのような前提で論じている部分は誤りである。
また、「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻していない者(独身者)」と比べて、婚姻制度の立法目的を達成するための手段としては不必要に過大な優遇措置を得ている場合には、憲法14条によってその優遇措置に関する規定が個別に違憲・無効となる。
そのため、「差異」を解消する必要のある問題が存在する場合でも、婚姻制度における優遇措置に関する規定が違憲となるのであり、「婚姻していない者(独身者)」の利用する制度の方を変更して是正するという性質のものではない。
この点で、この判決の立場は、基準(スタンダード)の採り方を誤っている。
㊥ 「現状の差異が、憲法14条1項の許容する国会の合理的な立法裁量の範囲を超えたものであるとは直ちにはいい難い。」
また、仮に上記の差異の程度が小さいとはいえないとしても、その差異は、既に述べたように、本件諸規定の下においても、婚姻類似の制度やその他の個別的な立法上の手当てをすることによって更に緩和することも可能であるから、国会に与えられた裁量権に照らし、そのような区別に直ちに合理的な根拠が認められないことにはならない。
【論点番号】
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
③ 「婚姻している者(既婚者)」との比較対象は「婚姻していない者(独身者)」であること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
㊥ 「仮に上記の差異の程度が小さいとはいえないとしても、その差異は、既に述べたように、本件諸規定の下においても、婚姻類似の制度やその他の個別的な立法上の手当てをすることによって更に緩和することも可能であるから、」
㊥ 「国会に与えられた裁量権に照らし、そのような区別に直ちに合理的な根拠が認められないことにはならない。」
以上のとおりであるから、本件区別取扱いが憲法14条1項に違反すると認めることはできない。
【論点番号】
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
【筆者】
㊥ ここでいう「本件区別取扱い」とは、「3ア(2)」で述べられている「本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、」の部分に対応する意味である。
4 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるかについて(争点(2)関係)
(1) 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7 号1512頁、最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁、最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)
(2) これを本件についてみると、前記2、3で説示したとおり、本件諸規定は、国会の合理的な立法裁量の範囲内にあり、憲法の規定に違反するものではないから、本件諸規定を改廃しないことが上記の例外的場合に当たると解すべきとはいえない。よって、本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
第4 結語
以上によれば、原告らの請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第11民事部
裁判長裁判官 土井文美
裁判官 神谷善英
裁判官 関尭熙
「2(2)(ウ)」の部分で、「憲法24条1項が両性の合意のみに基づいて婚姻が成立する旨規定している趣旨は、婚姻の要件として戸主等の同意を求める明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から、婚姻が、当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意のみに委ねられることを明らかにする点にあったものと解される。」ことから、「『両性』という文言がある以上、憲法24条1項が異性間の婚姻を対象にしているということは否定できないとしても、このことをもって直ちに、同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」としている。
しかし、24条1項の規定に「婚姻の要件として戸主等の同意を求める明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から、婚姻が、当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意のみに委ねられることを明らかにする」趣旨があったとしても、そもそも「婚姻」という制度を設ける趣旨・目的そのものはこのことによって何らかの影響を受けるものではない。
そのため、これをもって直ちに「両性」「夫婦」「相互」の文言によって一夫一妻制(男女二人一組)を定めている24条の下で「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるとする理由にはならない。
【参考】Twitter
判決の誤りを継承する解説
【同性婚訴訟】伝統>人権? 司法の責務は 2022年6月22日
上記の記事は、下記の点で誤っている。
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
『大阪地裁、合憲の判決。司法判断が分かれる同性婚』 2022.06.23
上記の記事は、下記の点を認識できていない。
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること
・ 婚姻制度についての「国の立法目的」と「個々人の利用目的」は異なること
大阪地裁R4.6.20判決に対する違和感 2022年6月26日
上記の記事は、下記の点を認識できていない。
③ 「婚姻している者(既婚者)」との比較対象は「婚姻していない者(独身者)」であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
「同性婚を認めない」のは「憲法違反ではない」とした、大阪地裁判決との戦い方 伊藤建(弁護士) 2022.07.19
上記の記事は、下記の点で誤っている。
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと
同性婚をめぐる憲法論━2つの地裁判決をもとに考える━ 専修大学 内藤光博 2022年8月1日
(同性婚をめぐる憲法論━2つの地裁判決をもとに考える━ 専修大学 内藤光博 2022年8月1日)
上記の記事は、下記の点で誤っている。
① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること
④ 区別取扱いが存在しないこと
⑤ 「カップル信仰論」になっていること
⑥ 「カップル間不平等論」になっていること
⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること
⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと
⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること
長文、お読みいただきありがとうございました。